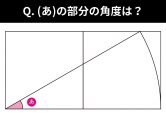総合・推薦入試を成功させるカギは志望理由書! 合格を引き寄せる3つの視点

「推薦入試で大学に入学する学生が増えているいま、思いつきやその場しのぎでは合格は難しくなっており、ハードルは上がっていると言えるかもしれません」
そう語るのは、推薦入試のプロ、和田圭史さん。総合・推薦入試のカギとなる書類「志望理由書」とは?
キャリアコンサルタントの眞下みのりさんとの共著『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』より、「志望理由書」の書き方のコツを紹介します。
※本稿は、和田圭史/眞下みのり著『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』(Gakken)より一部抜粋、編集したものです。
GOAL:3つの観点から「志望理由書とは何か」を説明できるようにしよう

志望理由書は、総合型選抜・学校推薦型選抜の合否のカギを握る書類です。なぜそう言えるのかを理解してもらうために、志望理由書とは何かを3つの観点から説明します。
「したい」「なりたい」「学びたい」を伝える書類
読んで字のごとく、志望理由書は「受験する大学をなぜ志望するのか」を伝える書類です。しかし、理由なら何でもよいというわけではありません。「校舎が新しくてかっこいいから」「自宅と同じ沿線にあるし、駅から徒歩5分の立地も気に入ったから」なども志望の理由といえばその通りです。
見た目の印象、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスの良さも進学先を検討する際に大事なポイントであることは否定しません。とはいっても、志望理由書にそれを書くのは見当違いです。
志望理由書は、志望大学に向けて書くものです。志望する大学・学部・学科の先生があなたの志望理由書に目を通したときに、「うん、ぜひウチの学科の学生として迎えたいね」と思わせるような内容にまとめ上げなければなりません。そのためには、何を書くとよいでしょうか。
志望理由書に書くテーマは、大まかに分けると次の3つなります。
●将来(大学を卒業したら)~をしたい。
●将来(大学を卒業したら)~になりたい。
●将来(のために大学で)~を学びたい。
志望大学・学部・学科に進学したい理由は、この「したい」「なりたい」「学びたい」を実現するためであると、はっきり示すことが良い志望理由書を書くための第一歩になります。まずはこの点を押さえましょう。
出願時に提出する書類
志望理由書は願書と一緒に提出する書類です。試験場で決められた時間内にテスト形式で書くものではありません。つまり、出願期間中に提出できれば、仕上げるまでにいくら時間をかけてもよいのです。
ですから、よく考えながら何度も書き直し、丁寧に清書して提出したいものです。しかし、出願直前に集中して取り組めばなんとかなると思っている受験生は少なくありません。
これは、決して志望理由書を甘く見ているというわけでなく、他科目の勉強などに追われて、ついつい後回しになってしまうケースが多いからのようです。
とはいえ、短時間で慌てて仕上げたものは、やはり出来としては今ひとつのものになってしまいます。その点は書いた本人も自覚していて、少し自信のないものを提出する羽目になりがちです。
実際に私も、出願前の志望理由書の指導をしながら、「もう少し時間をかけていれば自信を持って送り出せたのになあ」と思うケースは少なくありません。
本書を手に取っている読者のあなたには、悔いの残らない書類を提出できるように、なるべく早めに着手することを強く勧めます。出願期間の2か月ぐらい前から、本腰を入れて取り組むのがよいでしょう。
また、一度書いただけで終わらせず、書いたものを誰かに見てもらい、添削を受けたり、コメントをもらったりと、何かしらのフィードバックを受けましょう。フィードバックを踏まえて何度も書き直しながら仕上げてください。
文章で自己アピールする出願書類は、志望理由書の他に自己推薦書・活動報告書・学修計画書・課題レポートなどがあります。
書類は1つだけなのか、それとも複数の書類を提出するのかは、各大学・学部・学科、選抜方法によってまちまちです。
しかし、ほとんどのケースで、志望理由書の提出は必ず求められます。名称が「自己推薦書」となっていたとしても、指示内容を読むと志望理由を求められているようなケースもあります。
また、複数の提出を求められる場合には、軸となるのは志望理由書と考えてください。志望理由書の説得力が増すように他の書類を書くことができれば、全体の評価を高められるでしょう。
志望理由書は、努力が報われる書類です。じっくり時間をかけて仕上げましょう。
面接の「台本」
願書と一緒に提出した志望理由書は、それ自体に点数の付く場合が増えています。ある大学の学校推薦型選抜では、出願時に志望理由書の提出があり、試験として小論文と面接がありますが、全体の配点を志望理由書20点、小論文40点、面接40点としています。
100点中の20点ということは全体の2割になりますので、合否への影響は決して少なくありません。また、大学によっては配点がもっと大きい場合もあります。そのため、合格に少しでも近づけるように、良い志望理由書に仕上げる努力と工夫をしてほしいと思います。
志望理由書自体で点数を稼ぐことも大切ですが、実は志望理由書にはもう1つの役割があります。それは面接試験の「台本」としての役割です。
総合型選抜・学校推薦型選抜では、ほとんどの場合、面接試験があります。面接で何を聞かれるかというと、実は出願時に提出した書類の中身について、あれやこれやと質問をされることが多いのです。
大学の先生は、提出された書類を眺めながら、この受験生には「こんなことを聞いてみよう」「この点を詳しく説明してもらおう」などと、あれこれ考えます。
このように、一人ひとりの受験生に何を質問するのかを検討するための資料にするのです。だからこそ、志望理由書は面接官にとっては、目安となる「台本」と言えるのです。
志望理由書が面接の「台本」としての役割を果たすのは、面接官の側だけではありません。志望理由書は、受験生にとっても面接の「台本」になります。
大学の先生は志望理由書等の提出書類を眺めながら面接の「台本」を考えるわけですから、面接を受ける側も提出した志望理由書を元に「どんなことを聞かれるだろうか」「この点は具体例を示すように言われるだろうな」などと、聞かれそうな質問を想定して回答準備をするのが得策でしょう。
このように、志望理由書は、面接官にとっての「台本」であるとともに、面接を受ける受験生にとっての「台本」でもあると心得ておきましょう。先に志望理由書・小論文・面接の配点が20点・40点・40点とする大学があると紹介しましたが、この場合に「志望理由書+面接」の配点は60点になります。
つまり、志望理由書の仕上がり次第で、全体の60%の点数に影響を与えることになります。総合型選抜・学校推薦型選抜における志望理由書の影響力の大きさがわかっていただけたでしょうか。
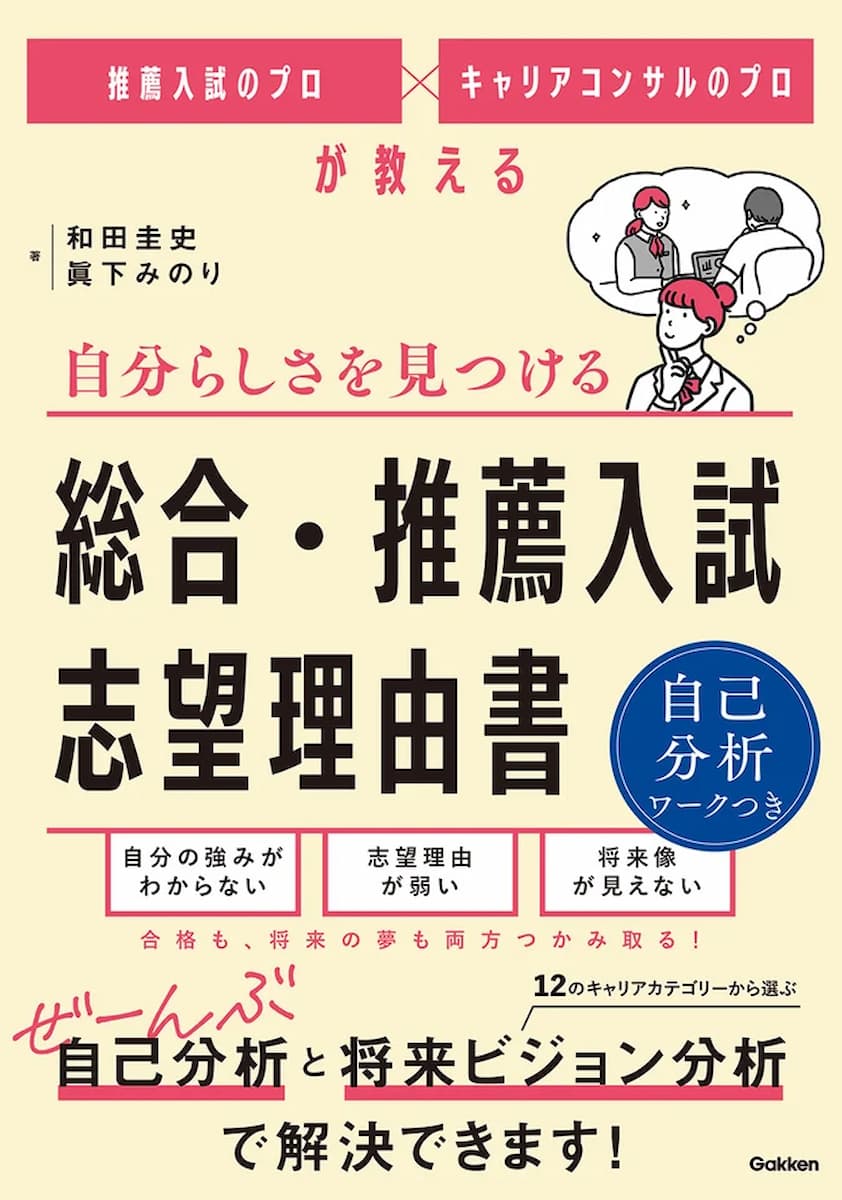
『推薦入試のプロ×キャリアコンサルのプロが教える 自分らしさを見つける 総合・推薦入試 志望理由書』(Gakken刊/和田圭史・眞下みのり著)
10万部突破の推薦入試のプロと、相談実績1000回超のキャリアコンサルのプロがタッグを組み、「自己分析」と「将来ビジョン分析」という今までにない切り口で推薦入試対策を解説します。
「自分の強みがわからない」「志望理由が弱い」「将来像が見えない」などの悩みを解決し、“自分らしい”志望理由書を書く方法がわかります。
自己分析と将来ビジョン分析を掛け合わせた一冊で、“合格”も”将来の夢”も両方つかみ取りましょう!将来や受験に悩む高校生必読。