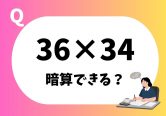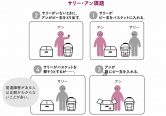親がかける言葉で、 子どもの人生が変わる

親が普段何気なくかけている言葉は、子どもの人格形成、思考パターンにおいて、どのような影響を与えるのでしょうか。
※本稿は『PHPのびのび子育て』2016年7月号に掲載されたものを一部抜粋・編集したものです
【著者紹介】榎本博明(えのもと・ひろあき)
1955年生まれ。東京大学教育心理学科卒。東芝市場調査課勤務の後、東京都立大学大学院心理学専攻博士課程中退。カリフォルニア大学客員研究員、大阪大学大学院助教授等を経て、現在、MP人間科学研究所代表。主な著書に、『伸びる子どもは○○がすごい』『勉強できる子は○○がすごい』(以上、日経プレミアシリーズ)、『教育現場は困ってる』(平凡社新書)、『〈自分らしさ〉って何だろう?』『「さみしさ」の力』(以上、ちくまプリマ―新書)『「やさしさ」過剰社会』(PHP新書)などがある。
親の言葉が、子どもの人生の土台になる
私たちの自己イメージがどのようにつくられてきたのか、ちょっと考えてみましょう。たとえば、あなたが「私はだらしない」という自己イメージをもつとしたら、きっと幼い頃から「あなたはほんとにだらしないわね」というような言葉を投げかけられていたはずです。
とくに親から投げかけられた言葉や親の口ぐせは、自己観や人生観の土台になります。「どうせムリ」と諦めぐせを身につけている子、すぐに「めんどくさい」といってラクをしたがる子も、親の口ぐせの影響を受けているものです。
子どもは、無意識のうちに親の口ぐせを真似るようになります。それは、親の口ぐせになっている言葉が子どもの心の中に定着している証拠です。心の中で繰り返される言葉は、ものの見方や考え方に影響します。こうして親の口ぐせが子どもの人生を方向づけていくのです。
子育てにおける「口ぐせ」のプラス&マイナススパイラル

お子さんは、普段どんな言葉をよく使いますか? 一度チェックしてみてください。言葉から、前向き思考が育っているかが見えてきます。
□「いい言葉」をかけられ続けていると…
周りの子が諦めかけていても、「大丈夫、なんとかなるよ」「がんばろう」とみんなを鼓舞して粘り強くがんばろうとする子がいます。そのような子は、「大丈夫、なんとかなる」といった親の口ぐせや、「がんばらなくちゃ」といった親の口ぐせを無意識のうちに心の中に取り込み、自分自身の口ぐせにしているのです。
親が前向きの口ぐせを身につけていると、子どもは人生に対して前向きの姿勢を身につけていきます。そのことを肝に銘じて、できるだけ前向きの口ぐせを身につけ、言葉を投げかけるようにしましょう。
□「悪い言葉」をかけられ続けていると…
何かにつけて「どうせムリ」「きっとダメだよ」と言って、すぐに諦めてしまう子がいます。そのような子は、「どうせムリ」という親の口ぐせや、「もう、ほんとにダメなんだから」という親の口ぐせを無意識のうちに心の中に取り込み、自分の口ぐせにしているのです。
「あー、めんどくさい」「もう、やだ」「ほんとにイライラする」といった口ぐせも同じです。こういった後ろ向きの口ぐせを親が身につけていると、子どもは人生に対して後ろ向きの姿勢を身につけていきます。子どもの前では、マイナスの言葉はできるだけ口にしないことが大切なのです。