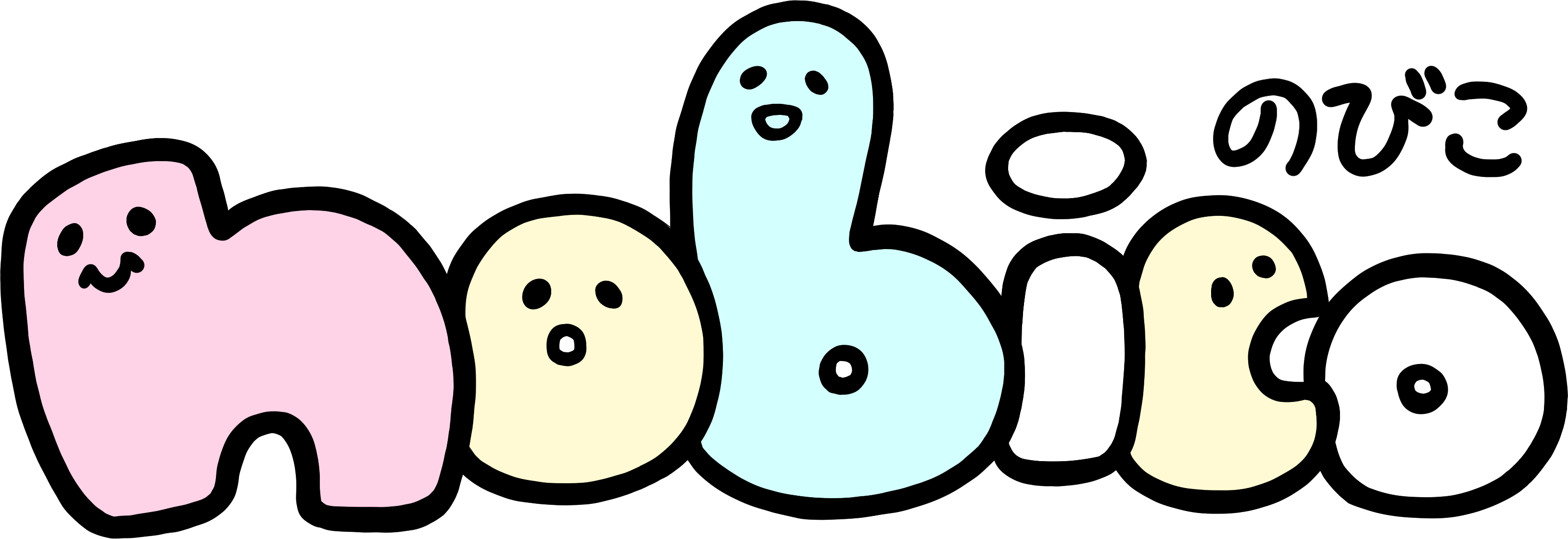「東大合格するための3つの方法」小倉優子さんの受験を支えた人の逆転理論
「東大生になれる人」の演技

師匠はさらに話を続けた。
「人間は、『人の間』と書く。『間』というのは、周りの目線だ。その人がどういう人間かよりも、周りがその人をどのように見るのかの方が、実は重要なのさ」
この話には抵抗感がある。本当の自分より、周りが思う自分の方が重要だなんて。
「この実験の面白いところは」
師匠の声が、僕の思考を一瞬止めた。
「実際に、やってみせたということだ。命令させるだけじゃなくて、行動させた」
「行動?」
そうだ、と師匠は首を大きく縦に振った。
「人間は、どう思ったかより、どう行動したかの方が重要だ。何を考えていても、その行動を取った時点で、そういう人間になる」
「例えば、善行をした人間は、みんな善者だってことですかね」
「そう、よくわかってるじゃないか。善行をする人間は善者だ。その心の中で何を思っていたとしても、いい行いをしているのであれば、それはどんな人間であれ、偽善者ではない。それと同じように、看守の行動を取らせたら、看守になるんだ。それがどんな人間であれ、な」
まあ、善者と偽善者の話はわからなくはない。確かにその二つは、見分けがつかない。だが、本当にそういうものなのだろうか?
「前に伝統の話をしたよな? 伝統を疑わない奴は、猿だ。『前もそうだったから』という理由だけでその伝統や環境を疑わずにいる、猿と同じような奴がこの社会にはたくさんいる」
「身をもって、体験しましたよ」
「だが、奴等だって本当は、その伝統や環境が疑わしいことだって知っているんだ」
「そうなんですか?」
「知っているけれど、逆らったら面倒臭い。他の猿から攻撃される。だから納得したフリをする。肯定したフリをする。猿の真似をするんだ」
「でも、本当はその人たちは、猿ではないんですよね?」
疑わしいと思っているということは、少なくとも、猿ではないのではないか。
「いいや、奴等は猿だ。最初は猿の真似をしていただけだった。でも、猿の真似をするうちに、自分が猿だったのか人間だったのかなんてわからなくなるんだ。わからなくなって、誰かのことを攻撃しだす」
師匠は笑った。笑ったが、それは楽しそうな笑いではなく、苦しそうな笑いだった。
「人間は、演技をしているうちに、演技をしているという事実を忘れる。だからあんなに、『猿』が多いのさ。猿の大半は、そう演技をしているうちにそうなってしまった人間でしかないのさ」
確かに納得できる話ではある。明らかにおかしいことでも、「周りがそう言っているから」という理由で、疑わずにいることもあるのだと思う。
「だから、演技をすればいい、ってことですか?」
優等生の演技を。東大生になれる人間の演技を。中身なんて関係ない。外見を取り繕えば、いつかはそうなれると言いたいのだろうか。
「そうだ」
東大合格者の誰もが行っている勉強法

師匠は黒板に3つの項目を書いた。
1 数字にこだわって勉強する
2 東大に行くのだと、周りに公言する
3 他の人の質問を積極的に受けて、時には教える
「いいか西岡、この3ヶ条を守れ」
師匠は言った。
「まずは数字だ。勉強時間でも、模試の点数でも偏差値でも学校の順位でもなんでもいい。とにかく、いい数字を取れ。どんなに些細なことでも、小テストでも定期テストでも関係なく、1位上を、1点上を目指せ」
「まずは1科目でいい。1科目でいいから、偏差値70を目指せ」
「はい」
「次は東大に行くと公言しろ。今までは恥ずかしがっていたかもしれないが、とにかく周りに言い続けるんだ」
「は、はい」
正直、それは、ハードルが高いなと思った。元々いじめられっ子の僕だ。笑われるのではないかという思いが強い。
「大丈夫だ。数字さえあれば、周りの大人は必ず納得する」
「そういうものでしょうか」
「結果が伴っていることを否定できる人は少ない。言われたら、結果で返事をしてやれ」
だとすると、僕が東大に行くと言ったら笑われそうなのは、結果がないからだ。結果さえあれば、周りは僕のことを「東大に行けるかもしれない人」と思ってくれるのかもしれない。
「そっか、そうですね。頑張ります」
そして3番目を師匠は指差す。
「最後に、他の人の質問を積極的に受けて、お前が人に教える立場になるんだ」
そんなこと、できるのか? 僕は口下手だし、人に何かを教えられるとも思えない。
「西岡、東大生が誰でもやっている勉強法が、これなんだ」
「へっ?」
僕は素っ頓狂な声を出した。
「自分がインプットしたことを、他人に対してアウトプットする。東大生は自分で誰かに教えたり、周りの子と勉強したことを議論する場合が多い。東大合格者が多い学校では、毎回授業ごとに誰かが授業の内容を嚙み砕いて他の子に説明したり、みんなで授業を元に問題を作ったり、考えを共有しあったりすることが多いんだ」
「本当ですか?」
ガリガリ机に向かうことの方が多いと思っていたのだが、そうではないのか。
「本当だぞ。それにこれは学力面以外のことでもメリットがある。周りがお前のことを、頭がいいと認識するんだ」
「はあ」
今度は気の抜けた返事をする。それ、本当にメリットなんだろうか? そしてそんなことってあり得るのだろうか?
「優等生というのはみんな、小さい頃からずっと『頭がいい』と言われ続けていた人間がなるもんだ。優等生になることを求められ、もし順位を落としたら笑われ、優等生じゃなくなるかもしれないというプレッシャーがあって、その演技をし続けている人のことだ」
そう言われてみると、そうかもしれない。確かに僕の周りの優等生は、学年をまたいでもずっと変わらず優等生だった。いきなりぽっと出で優等生になる人はいなかった。
「だからお前は、優等生という仮面をかぶれ。周りから、勉強において頼られるくらいに、優等生だという演技をし続けろ。それこそ、女にモテるくらいにな!」
「まだ言うんですね」
「当たり前だ。あながちバカにもできないだろ?」
まあ、確かにそうだが。
「大丈夫だ、この3つをやり続ければ、成績も上がるしモテるようにもなるさ」
いいや、もう突っ込まない。そう決めて、僕はノートにその三つを写す。

それでも僕は東大に合格したかった
話題の現役東大生作家が自身の受験経験を描く、感動ドキュメント・ノベル。日曜劇場『ドラゴン桜』の脚本監修者、累計40万部突破『東大読書』シリーズで知られる著者のリアルな原点。