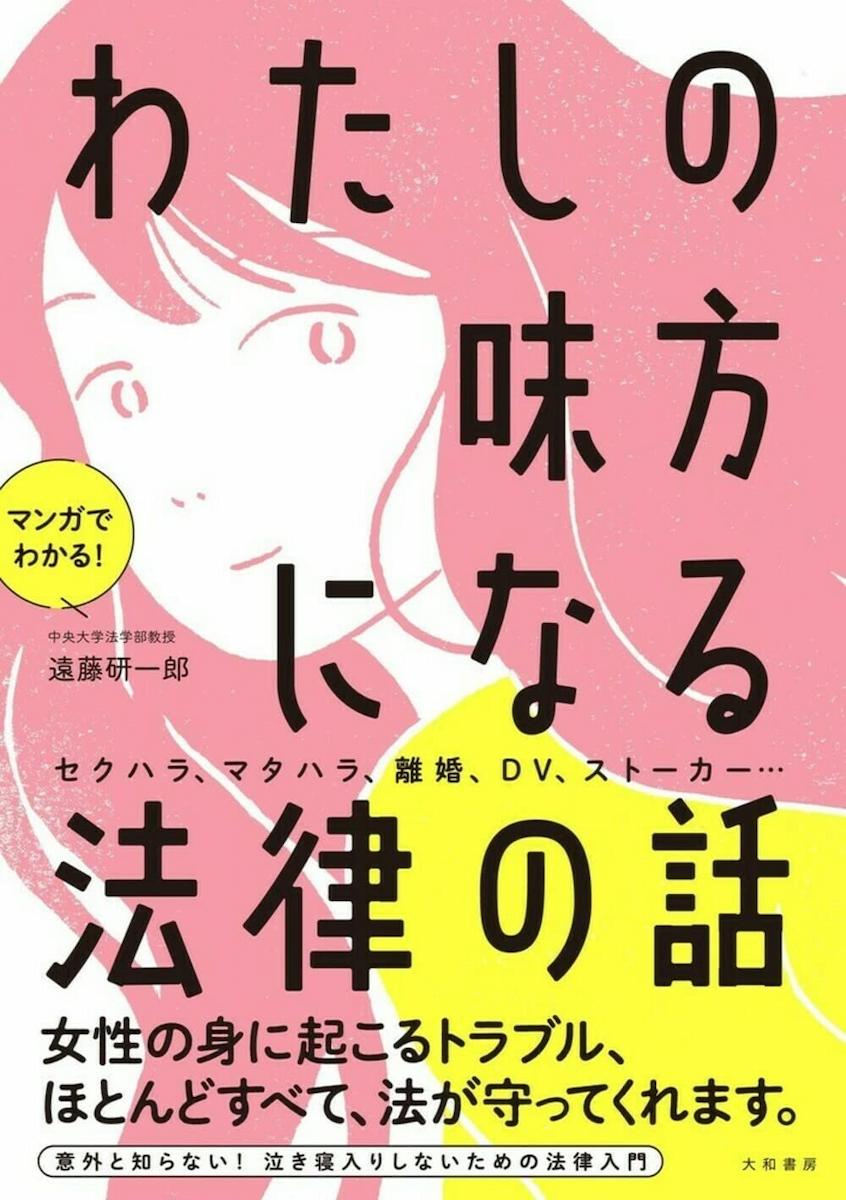子どもを叩いてしまいそう…児童虐待を防ぐために知っておくべき法律の話
子育てにイライラはつきもの。時には子どもを叩いてしまいそうになってハッとしたことがある人もいるかもしれません。
「子どもを叩いたりしてしまったらどうしよう」と悩んだらどうしたらいいのでしょうか?
子どもを大切にするためには、親はまず自分を大切にすることが大事なのだそうです。
児童虐待や児童相談所についての法律の話を、中央大学法学部教授の遠藤研一郎著『マンガでわかる! わたしの味方になる法律の話』から紹介します。
※本稿は、遠藤研一郎著『マンガでわかる! わたしの味方になる法律の話』(大和書房)から一部抜粋・編集したものです。
子どもを叩いてしまいそう
ルリさん、夫が育児に協力的でないことから、子育てに悩んでいるようですね。いつか、自分は子どもに手を上げてしまうのではないかと心配しています。
児童虐待に関するニュースがたびたび報じられますが、虐待は特別な状況に限った話ではありません。たとえば、育児のストレスから「子どもを叩いたりしてしまったらどうしよう」と悩むお母さんも少なくないのです。
「19万件」、これは、児童相談所が児童虐待に関する相談を受け、指導や措置をした件数です(令和元年度中、厚生労働省しらべ)(※1)。みなさんは、この数字を見てどのように感じるでしょうか?
そもそも周囲が「この子は虐待を受けているのでは?」と気づくきっかけには、いろいろなものがあります。たとえば、子どもの泣き声がひんぱんにすることを近所の住民が気にかけたり、学校の身体検査で児童に不自然なあざや傷があることがわかったり、警察が子どもを保護するなかで子どもから「親から虐待を受けている」と相談されたり……。そういった場合、必要に応じて、児童相談所に通告がなされます。
通告を受けた児童相談所は、保護者から事情を聞くなど必要な調査をします。その件数が、年間19万件に上る、ということです。
なかには、虐待を原因とした死亡事件も起こっています。実の親が幼いわが子を殺害するという痛ましい事件も、たびたびニュースなどで伝えられますね。
なぜ、児童虐待は起きてしまうんでしょうか。そして、それを防ぐためのしくみとしてどんなものがあるのでしょうか。
(※1)令和4年度中の児童相談所の児童虐待相談対応件数は、214,843件です(約21万件。本書を書いた時の最新の数値よりも、大幅に増加しています)。
虐待でもっとも多いのは“心理的虐待“
愛情にはいろんな形や表現のしかたがありますが、ほとんどの親は、わが子に対して、自分なりの愛情をたくさん注いでいます。子どもも親からの愛情を受けることによって、自分は守られているという安心感をもちます。
でも同時に、子どもに愛情を注ぐのがむずかしくなってしまう親もいるのが現実です。それは時として、「虐待」という形であらわれます。
そもそも、児童虐待とは、なんでしょうか?
一般的には、「子どもの体や心を傷つけて、子どもの成長や人格形成に大きな影響を与えること」をいいます。具体的には、「児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)」2条のなかで、次の図のような4つが児童虐待であると定義されています。
このなかで、とくに件数として多いのは「心理的虐待」です。
「あんたなんか、産まなきゃよかった!」と子どもに暴言をぶつけたり、酒に酔って子どもの前で激しい夫婦げんかをしたりするなど、子どもを精神的に追いつめてしまういろいろな例が報告されています。
世界中の子どもがもつ権利
ところで、みなさんは、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」というものを知っていますか?
“世界中のすべての子どもたちがもつ権利“について定めた条約です。1989年に国連で採択され、翌年に発効されています。
たくさんの国がこの条約を結んでいて、日本も1994年に結ぶことになりました。児童虐待が社会問題として考えられるようになるきっかけになった、大切な条約です。
この条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するためにつくられたもので、全部で54の条文で構成されています。とくに、次のような内容が柱となっています。
◯生きる権利……すべての子どもの命が守られること。病気やケガをしたときに、きちんと治療が受けられること。
◯育つ権利……心や体がすこやかに成長できるために必要な、医療や教育、生活への支援を受けること。休んだり、遊んだりすること。
◯守られる権利……暴力や搾取、有害な労働などから守られること。また、子どもたちのプライバシーが守られること。また、虐待や放任から守られること。
◯参加する権利……知りたいことを知ることができること。また、自由に自分の意見を言ったりすること。
この条約からもわかるとおり、“児童虐待は、子どもが当然にもっているはずの権利を侵害する行為“です。決して許されるものではありません(児童虐待防止法3条)。
虐待をした親は……
虐待をしてしまうと、親とはいえ、刑事的責任に問われる可能性があります。
たとえば、「保護責任者遺棄罪(刑法218条)」、「遺棄等致死罪(刑法219条)」、「重過失致死罪(刑法211条)」、「傷害罪(刑法204条)」、「傷害致死罪(刑法205条)」など、さまざまな犯罪にあたるおそれがあります。
また、民事上だとどうでしょうか?
親は通常「親権」をもっていますが、親の言動が子どもの監護・教育にふさわしくないときには、子どもを保護するため、子ども本人を含む特定の人からの申し立てによって、親から親権をうばう制度(親権喪失・停止。民法834条、834条の2)があります。
なぜ、児童虐待は起こるの?
では、どうして児童虐待が起こってしまうんでしょうか。むずかしい問題ですが、ちょっと考えてみたいと思います。
一般的には、身体的、精神的、社会的、経済的な要因が複雑にからみ合って起こるといわれていて、一概に原因を断定することはできません。ただ、よく指摘されるものとしては、次のようなものがあります。
たとえば、親側の要因として、育児に対する不安や、疲れによるストレスなどがあると、虐待に結びつきやすいといわれています。毎日、何があるかわからない子育ては、緊張の連続ですからね。
また、親自身が子どものころに虐待を受けて育つと、自分の子どもを虐待してしまう場合があることも指摘されています。自分では、どうしてもコントロールがむずかしい部分があるのかもしれません。
それから、子ども側の要因として、子どもに発達の遅れや障がいなどがあったりするときに、親が将来への不安を感じたり、余裕がなくなったりして虐待に走ってしまうケースがあるといわれています。
また、夫婦間の不和や経済的な困窮、失業など、家庭内のストレスが虐待のきっかけになってしまうこともあれば、子どもへの過度な期待から、度をこえた要求をしてしまうこと、そして、子連れ再婚や内縁関係のなかで虐待が起こることもあります。
最近では、社会からの孤立という視点も指摘されています。親族や近隣とのつながりが弱くなるなかで、子育てについて相談できる相手がおらず、親が孤立してしまうことで、虐待の危険性が高まる、というわけです。
いずれにしても、児童虐待は、特殊な環境に限った話ではなく、どこの家庭にも起こりうる問題です。今回の事例でも、ルリさんを責めることなどできませんよね。それよりも、社会全体で、子育て世帯をサポートしていくことが重要です。
虐待かも? と感じたら
では、みなさんの近くで、「もしかしてこれは虐待では?」と疑われる子どもを発見したときは、どうしたらいいでしょうか。
ご近所やママ友に意見をするなんて、なかなかできないことだと思います。ほかの家の育児に口をはさむのは簡単ではありませんし、人間関係が壊れてしまうかもしれません。
でも、できることもあります。可能であれば、匿名で、「児童相談所」などに相談してみてください。
通報した人がだれなのかについての秘密は、固く守られています。また、虐待かどうかは児童相談所が判断しますから、たとえ虐待でなかったとしても、相談した人が責められることはありません。
ところで、「児童相談所」って? みなさんは、児童相談所について、どんなイメージがあるでしょうか。
児童相談所は、児童福祉法という法律にもとづき、“児童虐待への対応の中核を担う行政機関“として、都道府県に設置されているものです。
児童相談所が虐待の通告を受けると、このあと詳しく説明するようなものも含めて、適切な措置をとることになります。
最近は、子どもの安全確認・安全確保のために、積極的な介入が期待されています。子どもの命にかかわる緊急性のあるケースが少なくないためです。
また、児童相談所はほかにも、児童や保護者へのさまざまな支援をおこなっています。子どもの発育についての相談、障がい・非行・不登校などの相談・支援など、いろいろです。
子どもを保護する
では、児童虐待について児童相談所がおこなう措置には、具体的にどんなものがあるんでしょうか。
まず重要なものとして、「一時保護制度」があります。これは何かというと、緊急に子どもを家庭から一時的に引き離す必要があるときに用いられるものです。親などの意思に反しておこなうことができる、すごく強い制度です。
また、必要であれば、「児童養護施設」に子どもを入所させる判断もします。
「児童養護施設」とは、災害や事故、親の離婚や病気、または不適切な養育を受けているなどいろんな事情によって、家族による養育がむずかしい子どもたちが暮らすための施設です。現在、全国各地の施設に約3万人が暮らしています。それぞれの自立目標に合わせた支援計画をもとに、児童指導員、保育士などの専門職の人たちが、子どもたちの養育をおこなっています。
児童相談所の葛藤
ところで、児童相談所にも“葛藤“があるんです。
というのも、児童相談所は、「虐待している親から子どもを保護するために離す」という役割をもつとともに、「子育てに悩む親を支援する」という役割も担っています。たとえば……。
―― Aちゃんのお母さんBさんを、児童相談所の児童福祉士として支援していたCさん。ふだんからBさんはCさんに子育ての悩みなどを 打ち明けていて、関係は良好でした。しかしあるとき、Aちゃんから、「お母さんに叩かれる」という訴えが……。児童相談所は、いろいろ慎重に調査をした結果、最終的に一時保護を決断。Bさんに通知文書を手渡すと、Bさんはその場で泣きくずれてしまいました。――
昨日まで、育児の相談をするなかで「一緒にがんばりましょう!」と声をかけてくれていた組織から、突然、一時保護の通知を受けたら? ずっと味方だと信じていた存在から「裏切られた」と感じるかもしれません。また、「子どもを奪われた」とも感じるかもしれません。実際に、児童相談所の職員に対して「このまま死んでやる」といったり、強い敵意をもって待ち伏せをしたりする人もいるんです。
さらに、一時保護したあとでも、子どもをふたたび家庭に帰すことができるかどうかを検討しなければいけませんよね。そのためには、保護者とじっくり話し合わなければなりませんが、一度崩れてしまった関係を修復するのは、とてもむずかしいことです。
児童相談所は、葛藤を抱えながらも、「介入」と「支援」という相反する役割を同時にこなして奮闘しています。
子どものためにも、親はまず自分を大切に
子育てをしていると、いろんな不安や、いろんな心配や、いろんなイライラが、たくさんあると思います。
そんなときは、とにかく、だれかに話してみてほしいのです。行政も、民間団体も、地域も、きっと助けてくれるはずです。
その一方で、子どもの命に危険がおよんでいて一刻を争う深刻な虐待もあります。その場合、まわりの人は、必要だと感じたら迷わず、児童相談所に相談してみてほしいのです。この世に希望とともに生まれてきた子どもの、かけがえのない未来のためです。
『マンガでわかる! わたしの味方になる法律の話』(遠藤研一郎著/大和書房)
しんどいとき、あなたを守る法律があります。
結婚、妊娠、DV、子育て……日常の中で女性が直面しがちなトラブルと、そのとき味方になってくれる法律をマンガ入りでわかりやすく解説。