偏差値40台の学校を目指す意味とは?「上位校に受かるだけが成功ではない」と気づいた母の中受体験記
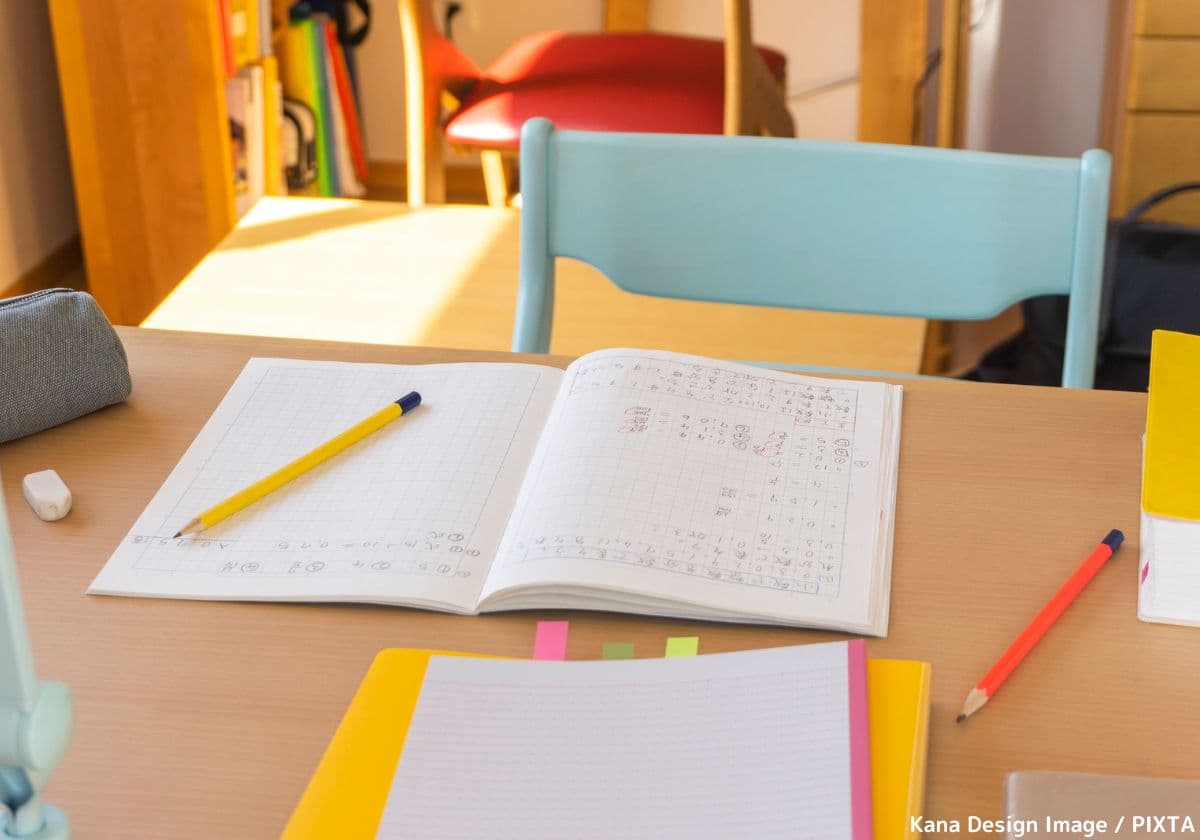
こうして受験を続けることは決めたものの、サピックスは難関校を狙う塾だ。ちょっと努力したところで成績はそうそう上がらない。下のランクというレッテルを貼られた状態で通っても、よい影響はないのでは─母親がそう考え始めたとき、父親の信介さん(仮名)が、隣駅にある塾の情報をもってきた。
会社の同僚の子が通っていたというそこは、少人数指導で手厚く見てもらえるのが評判の塾だという。美佐子さんはさっそく、来夢さんを誘い、体験授業を受けに行った。地域密着の個人経営の塾で、この校舎の先生は3人ほど。1クラスの人数も10人前後と少なめだ。男子が多いものの、来夢さんもこの塾が気に入ったようだった。ここなら、学んだことの定着が遅い娘でも、丁寧に見てもらえるかもしれない。そう思った美佐子さんは、サピックスをやめ、転塾させることにした。
すでに5年生の秋、志望校選びも始まった。姉のときとは偏差値帯も違うため、見る学校も変わってくる。
娘の良い部分を見て、伸ばしてくれる学校はないか。中学受験をあきらめずに、毎日机に向かい頑張る娘を応援したい。「娘に合う学校を見つけよう」と、通学圏内の学校をくまなく探した美佐子さん。見学した学校は2校にも上った。このうち、来夢さんと訪れたのは16校。6年生になってからは、コロナの影響でオンライン説明会となった学校もあった。
「オンラインでは実際の雰囲気がわからない部分もありました。でも、説明会は日程がかぶることも多かったので、オンラインだと移動もなく、多くの説明会に参加できるというメリットもありました」
通学時間や現在の成績を考慮して、姉の通う学校などをチャレンジ校に定め、本命校として偏差値40ほどの学校を据え、勉強を進めていくことを決めた。
転塾した先でも、来夢さんは決して成績がよいほうではなかった。しかし、ここには仲間がいた。「ずっこけ3人組」。塾の先生からそう名付けられた3人は、いずれも似たような成績だった。愛嬌たっぷりにそう呼んで目をかけてくれる先生。熱心な指導は続いたが、成績はあまり伸びず、最高でも偏差値40がやっとだった。
「毎日やっているのになんで成績が上がらないの!」
自分に対するいらだちや、やるせなさからなのか、来夢さんは塾に行くことを考えると、吐き気をもよおすようになった。そしてある日、来夢さんは逃亡した。
自宅の電話が鳴ったのは、夕方のことだった。
「来夢さん、塾に来ていません」
先生の言葉に美佐子さんは青ざめた。塾に行くと言って出た来夢さんが、突然いなくなったのだ。近所を探したが見つからない。部屋を見ると、パジャマがないことに気がついた。いったいどこへ行ったのか。携帯電話にかけても一向に出てくれない。携帯電話をなくした時に使う機能を使って居場所を探すと、表示されたのはなんと新宿駅だった。 何度も電話をして、やっと娘と繫がった。
「お母さん、どうすればいい……」
困ったような声が聞こえてきた。
聞くと、埼玉に住む女子大生のいとこの家に行こうと新宿まできたものの、そこからどうやったら行けるのかがわからなくなったという。
「とにかく一度、帰っておいで」
無事がわかってほっとした美佐子さんは、優しくそう呼びかけた。そして「そんなに苦しいなら、中学受験、もうやめよう」と、娘に語りかけた。

帰宅後、落ち込んだ様子の来夢さんを自室に誘ったのは、高校生の姉だった。
「お姉ちゃんは中学受験を頑張らなかったこと、少し後悔しているの。幼なじみの雪ちゃんは、大学付属校に入れたから、大学受験もなく、自由に過ごしているようなの。私は付属校じゃないからもう、大学受験を考えなくちゃいけなくて、今、すごく苦しい。こんなに苦労するくらいなら、あのとき、もっと本気で勉強して、第一志望校に受かっていたらよかったのにと、何度も思った。あんたは今ならまだ間に合うんだよ。頑張れるんだよ」
涙ながらに話す姉。姉の言葉が来夢さんの心を動かしたのか、翌日からは何事もなかったかのように、再び塾に通い始めた。 塾では「ずっこけ3人組」に向けての指導が本格化していた。3人まとめて合格させるぞ! という講師陣の気迫が明らかに感じられた。
当初、別の学校を第一志望にしていた来夢さんだが、ほかの2人が目指す学校がいつしか来夢さんの第一志望校となった。3人で、同じ学校に合格しよう!
お互いにそう励ましあって小6の後半を過ごした。
12月に行われた直前の4教科模試の偏差値は35。直前の模試で合格圏内に入れず、来夢さんは不安なまま受験当日を迎えた。だが、最後の最後で桜は咲いた。来夢さんはその第一志望の合格を見事に手に入れたのだ。偏差値40台後半、彼女が精一杯頑張ってやっと手が届くかどうかという学校だ。
偏差値上位校に入ることこそが“受験の成功“と思っている人にとっては、来夢さんのこの合格に価値は感じられないかもしれない。しかし彼女には、まぎれもなく価値ある勝利だった。3年以上、受験勉強生活で抱え続けた劣等感を払拭することができたようだ、と美佐子さんは感慨深そうに振り返る。
それだけではない。一度は“逃亡“までしながらも踏みとどまり、自らの意志で頑張り抜くという粘り強さ。それによって目標に到達できたという大きな自信を、彼女は手に入れたのだ。できないことに背を向けず、自分の力で目標までたどり着いたという達成感は、きっと、これからも彼女の支えになることだろう。
最後に、美佐子さんはこう語ってくれた。
「偏差値底辺で頑張っている家族の方々へのエールになればと思って、今回お話しさせていただこうと、取材に応募しました。二人の娘の中学受験を通じて感じたのは、偏差値上位校に受かることだけが成功ではない、ということです。自分で頑張り抜くという経験ができたこと、子どもにとって大切なのは、間違いなくそのことだったとはっきり言えます」
偏差値の高低という他人との比較ではなく、自分自身で決めた目標にどう立ち向かったか。受験の目的と評価について、そうした認識を親子で共有できれば、大変な受験も、前向きな思いと共に記憶に残るのではないだろうか。
これはきれいごとではまったくない。中学受験は人生のゴールではなく、人生の勝敗は、中学受験で決まるものでもない。まだまだ成長の途上にある子どもたち。中学受験という体験を、親子でどういう記憶にしていくかが、その後の子どもの糧となる。上位校に入学することだけが勝ちではない。中学受験を終えたすべての子どもたちに、あらためて拍手を送りたい。

宮本さおり著『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)
急増する中学受験生、「全落ち」などの厳しい現実…。
「合格体験記」には書かれないドラマを追って、15組の親子を取材したノンフィクション。
首都圏の中学受験者数は2023年、過去最高を記録した。東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県では、18パーセントの子どもたちが受験を経験し、熱は地方にも波及している。中・高一貫校への人気が高まり、子どものために移住するケースもみられる。一方、第一志望校に合格する子どもの数はわずか3割。負け戦とわかっていても中学受験へと向かわずにはいられない親子。まだ幼さの残る小学生の彼らが立ち向かう受験という魔物。
「全落ち」を経験する子どもは立ち直れるのか? 親のエゴや塾の実績づくりで志望校を決めていいのか? 偏差値では測れない、子どもに合った学校とは? 中学受験に挑んだ親子を5年間追い続けたルポルタージュには、きれい事では終わらない中学受験のリアルがある。































