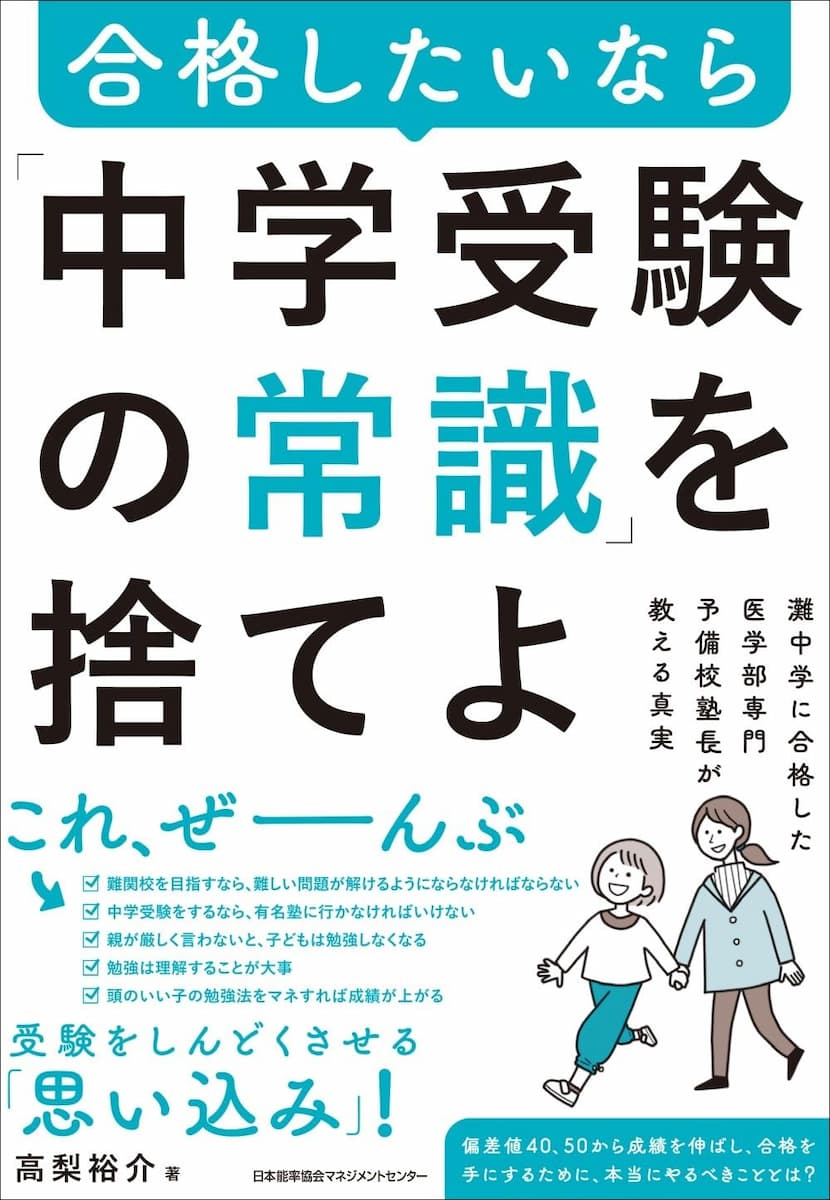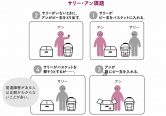「難問特訓」は逆効果? 中学受験で子どもの力を伸ばす本当の学び方
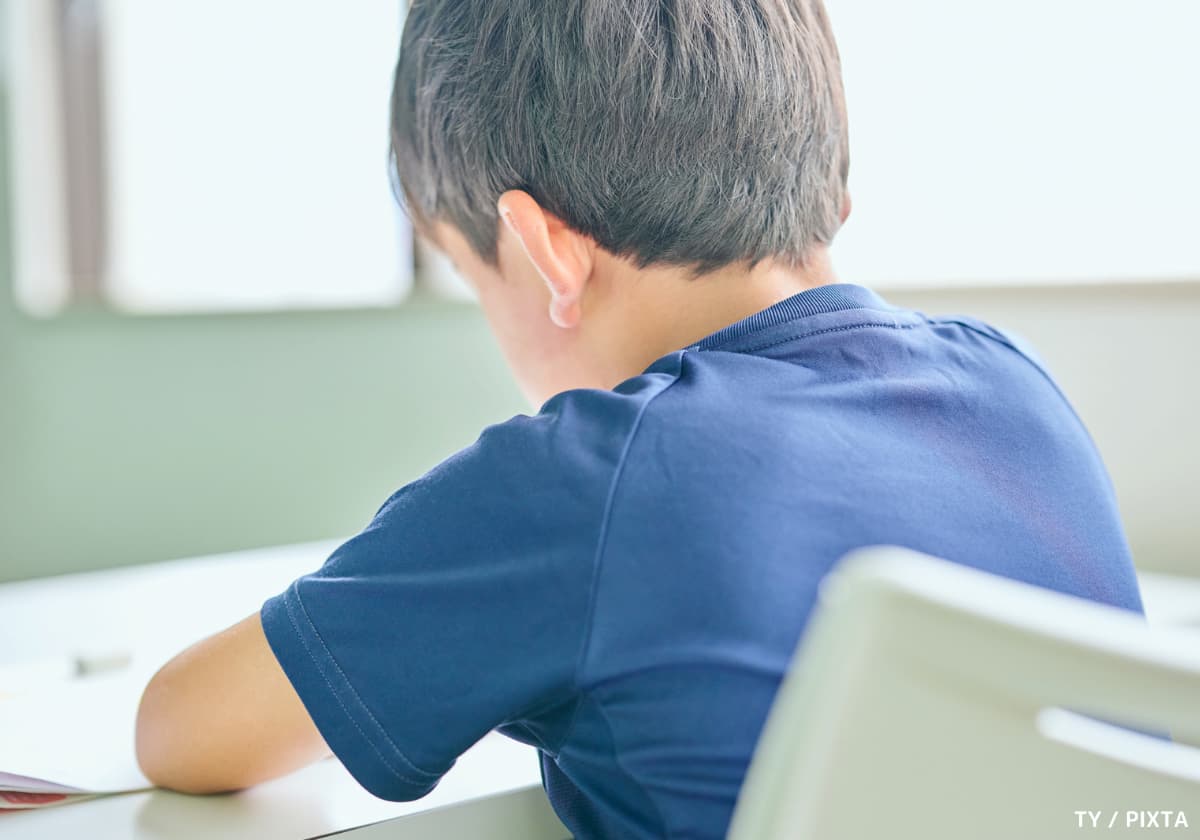
子どものためにと選んだ中学受験の道。しかし、本人の実力に見合わない勉強を無理やりさせてしまうと、子どもが勉強嫌いになってしまう事もありえます。
基礎が身についていないのに難問に挑むのは、泳げない子をプールに突き落とすようなもの。理解できないまま苦手意識を持ち、勉強そのものが嫌いになってしまうこともあります。
では、子どもが自信を持ち、学ぶ楽しさを感じながら成績を伸ばすにはどうすればいいのか? 本記事では、無理のない学習法と親のサポートのコツをお伝えします。
※本稿は、高梨裕介 (著) 『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(日本能率協会マネジメントセンター)から一部抜粋・編集したものです。
×難しい問題をたくさんやれば頭がどんどんよくなる
〇基礎力がない子に難しい問題をやらせるのは、泳げない子をプールに突き落とすようなもの
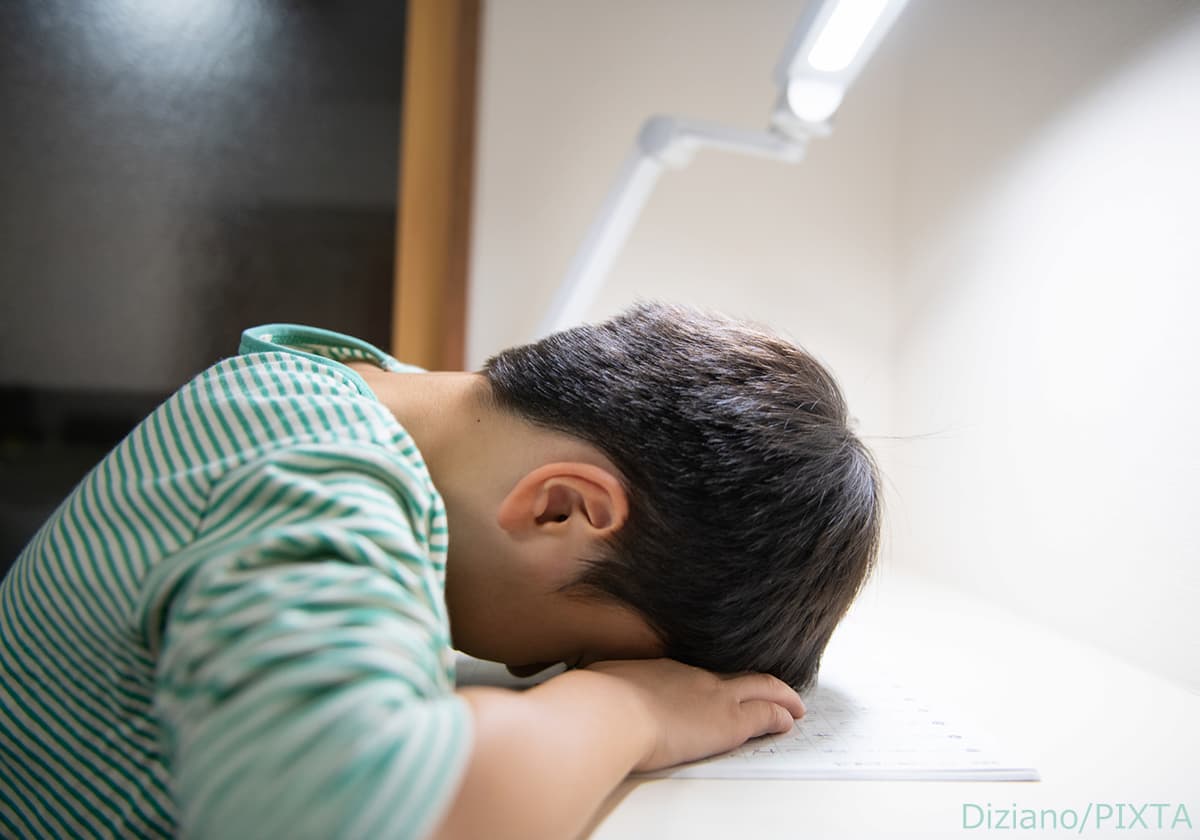
「中学受験の勉強は、小学校の授業で習う内容よりもはるかに難しいらしい」 中学受験をしんどいものにしてしまっている元凶は、すべてこの思い込みから始まっています。
だから、難しい問題を教えてくれる塾に通わなければいけないし、塾のカリキュラムについていくためには、親が必死になって子どもに勉強を教えなければいけない、そう思い込んでしまうのです。
でも、基礎がまったくできていないのに、難しい問題を教える塾に入れたところで、理解できっこないんです。
これはスポーツで喩たとえるなら、泳げない子をプールに突き落とすようなもの。 または、何も練習をしていないのに、いきなりプロサッカー選手の試合に放り込むようなものです。
つまり、命の危険に関わるような、めちゃくちゃ怖いことをしている、ということです。
プールだったら溺れてしまいます。
かわいいわが子にそんなことをさせる親はいないでしょう。
ところが、こと勉強になると、そうは思わない。それはなぜか――?
勉強だと、見た目ではケガをしないからです。
でも、本当は命にかかわるくらいの大事故が起きているのです。
いくら頑張ってみてもちんぷんかんな授業を、苦痛に耐えながら何時間も座って聞き、難しくて解けない山のような宿題を持ち帰る。
そして、家に帰れば親御さんが鬼のような顔をして、「なんで解けないの?」「ちゃんと授業を聞いてきたの?」とガミガミ叱る。
こんな状態では、心身ともにクタクタです。もはや、教育虐待の域に入っていると言っても過言ではありません。
だけど、小学生の子どもにとって、親は絶対的な存在。
敵に回せば、ご飯にありつけなくなる、心安らかに暮らせなくなる、それこそ生命の危機です。
だから、仕方なくやる。またはやっているふりをするしかないのです。
そうやってムリにムリを重ねて、中学受験では合格できたとしても、入学後に燃え尽き症候群になってまったく勉強をしなくなってしまったり、「本当は○○(子どもの好きなこと)をやりたかったのに、あのとき、親にムリやり勉強をさせられた」という不満が残り、あとあとまで親子関係に響いてしまったりすることがあります。
「わが子の幸せのために」と選択した中学受験で、そのようなことになってしまっては本末転倒です。
×子どもが難しい問題を解けないと叱る
〇子どもが解ける問題を解かせ、自信をつけさせる

そうは言っても、まわりの子がみんな塾に通っているのに、うちの子だけ塾に入れないなんてことはできない。
そうおっしゃる親御さんはたくさんいます。
誤解しないでいただきたいのは、私は「塾」=「悪者」にしたいわけではありません。
私自身、小学生時代に通っていた塾はとても楽しかったし、友達と切磋琢磨し合うことで、よい刺激をもらいました。
でも、そう思うことができたのは、私はもともと成績がよかったので塾のカリキュラムと自分の学力がたまたま合っていたからです。
もし合っていなかったら、同じようには感じていなかったはず。
中学受験をしんどいものにさせているのは、お子さんのレベルと合っていない難しい問題を、塾や親御さんがムリに教えて、理解させようとするから。
結局、子どもが勉強をイヤがっているときというのは、その問題がその子にとって難しいからなのです。
それなのに、「何度教えたら分かるの?」「このくらいの問題が解けなきゃ、どこにも行けないよ」と、親御さんに叱られる。
困っている状態のところに、さらに無理難題を突きつけられるから、ダブルパンチできついのです。
「いや、こんな問題、基礎でしょ?」
と、親御さんたちはおっしゃいますが、お子さんのいまの学力レベルから見ると「全然基礎じゃない」ということは多々あります。
まずは、お子さんが「これなら絶対に解ける」と思えるくらいの基礎の基礎に戻って、そこからスタートしてみましょう。
分かる問題はスイスイ解けて気持ちがいいし、ちょっと頑張れば解けそうな問題が解けたときはめちゃくちゃ嬉しい。
そうやってお子さんが気持ちよく解ける問題に取り組ませて、まずは自信をつけさせることが先決。
そして、いちばん大事なのが、「このくらいの問題は解けて当たり前」ではなく、「こんなにスラスラ解けてすごいね!」「毎日ちゃんとドリルをやってえらいね」と褒めてあげることです。
大人でもそうですが、どんな些細なことでも褒められれば嬉しいもの。
よほどのひねくれ者でない限り、嬉しくない人なんていません。
褒められたら気分が上がるし、もっと頑張ってみたくなる。
これがごく自然な感情。
だからこそ、親御さんには、お子さんをたくさん褒めてあげていただきたいのです。
×「受験生は勉強するのが当たり前」
〇当たり前ができていたら、積極的に褒める
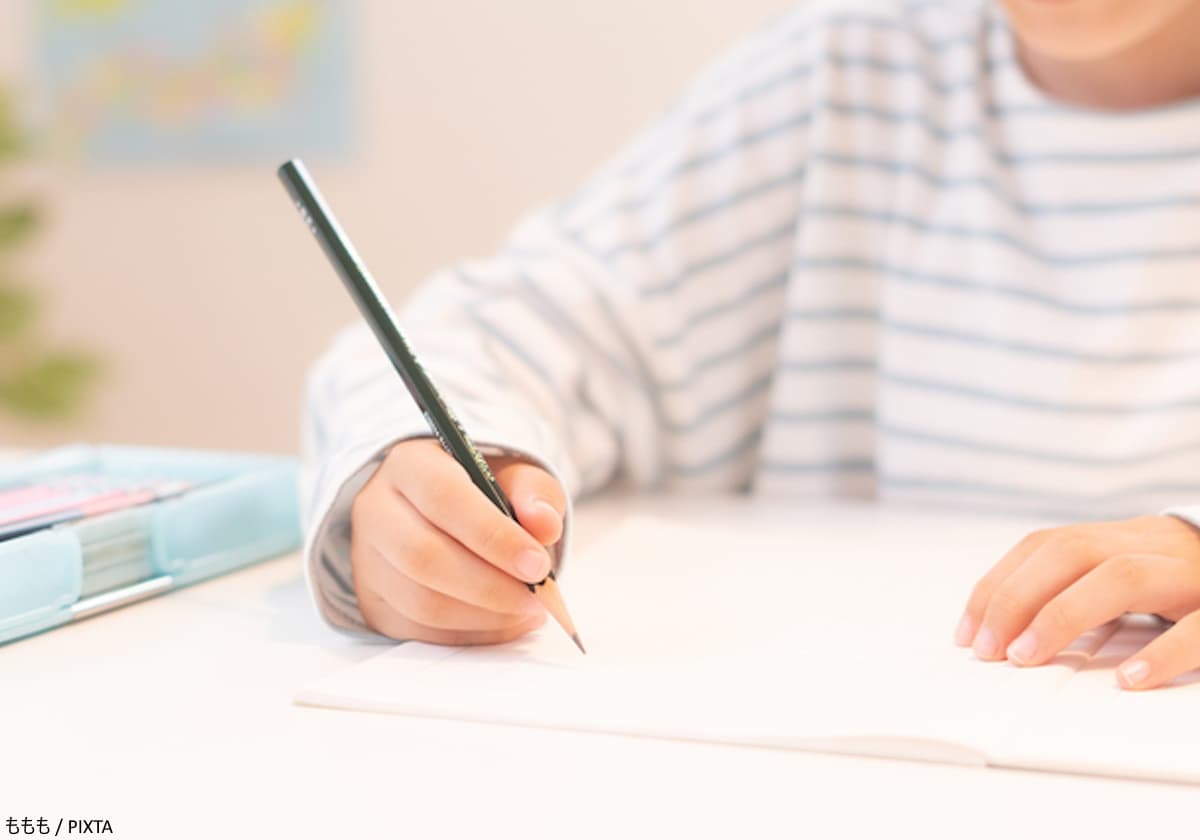
「子どもが勉強するのは当たり前」、と考えている親御さんは多いでしょう。
しかし、好きでもないことを毎日やり続けるというのは、子どもにとってはもちろんのこと、大人にだってつらいことです。
例えば、走るのが嫌いな人が上司から「毎日10 分走れ!」と命令されたら、誰だってイヤな気持ちになると思います。
10分間走る。時間としては短いし、距離もそれほどないから、「しんどい」まではいかないレベルです。
これを基礎学習に当てはめて考えてみてください。
基礎学習は1回やって終わりではありません。
私が言う「基礎の徹底」は、たとえば教科書ワークをやるのであれば、1冊を3〜5周やり込むくらいの勉強を指します。
つまり、毎日欠かさず取り組む、ということです。
1回の勉強は、基礎的な内容ですし、それほど大変ではないでしょう。
でも、それを365日、毎日取り組むとしたらどうでしょう? なかなかしんどいと思いませんか?
実は基礎を徹底することって、めちゃくちゃしんどいんです。
なぜなら、毎日継続してやらなければいけないから。
10分なら誰だってできます。
でも、それを毎日やるのが大変なのです。
だから、それができて当たり前ではないし、ちゃんとできたなら、めちゃくちゃ褒めるべきなのです。
10分間、雨の日も、風の日も、酷暑の日も走って、「それが当たり前」と言われたらどうでしょう?
「じゃあ、あなたがやってみなさいよ!」とブチ切れそうになりますよね。
それと同じことを、親御さんたちは平然とやってしまっているのです。
基礎を徹底するには、毎日必ず取り組む。
そして、1冊の問題集を何周もする。
それでようやく頭のなかにたたき込まれる。
その大変さが分かっていれば、おのずとお子さんにかける言葉も変わってくるでしょう。
「毎日頑張って勉強してえらいね」。
心からそう言えるようになるはずです。
『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(高梨裕介 著/日本能率協会マネジメントセンター)
今までの「中学受験の常識」が合格を遠ざけている?!
高偏差値の大学に進学するには幼い頃から中高一貫校に入り、常に難問に挑み続けなければならないと思い込んでいる人が多くいます。
競争を煽る塾、甘やかしは悪とする親、管理至上主義……これらはすべて子どもの生きる力を奪います。
そんな負のスパイラルを断ち切るには、180度の意識改革が必要です。
実際、著者は毎年100 名以上の医学部合格者を輩出する医学部受験の専門予備校「エースアカデミー」を運営していますが、多くの受験生と面談すると、「しんどい」と深刻に悩んでいる相談のうち 6〜7割が親子関係の悩みだということがわかりました。
そこで子どもたちを悩ませる「親」の対応を改善するためには、間違った思い込みを正し、親が実施すべきサポートを体系化して伝える必要があるのでは、と感じるようになりました。
情報過多の現代社会においては、自分の子どもにあった学習方法よりも、世間一般によしとされている学習方法を盲信し、それが唯一の正解だと思い込んでいる親が多いのが現状です。
間違った学習方法や子どもへのかかわり方では、子どもの学力が向上しないばかりか、親からのプレッシャーで長年苦しむ子どもが増えるばかり。
本書では、受験生の親がすべきこと、すべきでないことを確認し、親が強いるのではなく、子ども自らが勉強に取り組むようになる行動変容を促すことで、受験を通して子どもたちが「自分軸」で生きていくベースを築き、かつ確かな学力向上につながる親の考え方と姿勢を提示します。