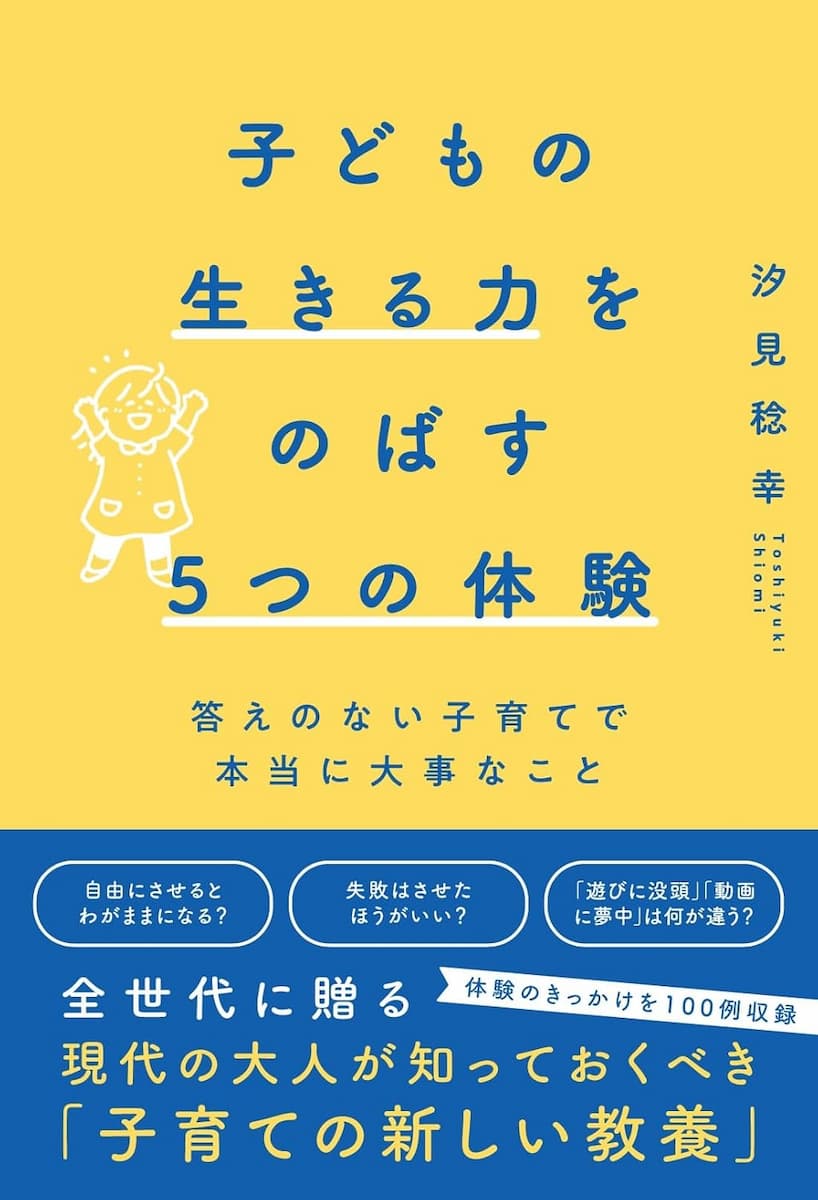土遊びが子どもの腸を育てる?「自然の中の子育て」がもたらす驚きの効果

さまざまな「偶然」に見舞われる自然と触れ合う体験が、子どもの育ちに必要と考える人は多いのではないでしょうか?でも、その理由をじっくり考えたことありますか?意外な効果含め、教育の第一人者である汐見稔幸の著書、『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』よりご紹介します。
※本稿は汐見稔幸著『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』(辰巳出版刊)より一部抜粋・編集したものです
土に触れて腸内環境を形成する

自然体験は、人間のさまざまな感覚を育ててくれます。人間はいわゆる五感以外にもたくさんの感覚を持っていると言われていて、それらは自然の中にいて、自然から来るさまざまな情報に接し、その情報を処理しようと体が動くことで研ぎ澄まされていきます。
中でも重要なのは「腸」です。腸には脳と同じような感覚神経があり、脳からの指令がなくても、独自の情報処理や判断をしていることがわかってきました。
また、腸と脳は迷走神経で深くつながっていて、お互いに感知した情報を交換し合っているのです。これを「脳腸相関」と言います。強いストレスがかかるとお腹を壊したり、逆に便秘になったりするのは多くの人が身に覚えがありますよね。
腸には、腸内細菌と呼ばれる細菌が約100兆個棲んでいると言われており、ビフィズス菌や乳酸菌など種類も数千いるだろうと言われています。たくさんの種類の腸内細菌がバランスよく活発にはたらきながら腸内に生息していることが、人間の健康にもかかわっています。
腸内細菌の存在は免疫力にも関係があり、数が減ったりバランスが悪くなったりすると病気にかかりやすくなります。免疫細胞の多くは大腸でつくられているのだそうです。
この腸内細菌、お母さんのおなかの中にいる赤ちゃんの腸には存在していません。産道を通って生まれてくるとき、また出生後に母乳を飲んだり、お母さんや産院の看護師さんにお世話をされたりする中で種々の細菌を獲得し、それが腸までいって増殖する。
そして腸内細菌は5歳頃までに種類やバランスが決まり、それからは新しい腸内細菌が入ってきてもあまり定着しないと言われています。5歳までにバランスよく、できるだけたくさんの種類の腸内細菌を増やすのによいと言われているのが、子どもが自然の中で接する活動です。例えば泥んこ遊び。
フィンランドで行われた調査では、土を入れて植物を植えたプランターを園庭に置いて土遊びをした園と、毎日森に遊びに行った園の園児は、自然のない園の園児にくらべて、皮膚の表面にいる細菌や腸内細菌の多様性が高まっていたそうです。土に触れて遊ぶ自然体験は腸内細菌の種類を増やすためにも大切なのです。
自然環境は親子関係も変えてくれる

今は親世代でも、子どもの頃に野山を駆け回って遊んだ経験のない人がめずらしくないかもしれません。「親子で自然と触れ合いましょう」という話をすると「汚れるからイヤです!」と拒否する保護者もいます。
子どもと自然豊かな場所に出かけても、自分自身が楽しみ方やふるまい方を教えることができないからと尻込みしてしまい、自然学校による体験プログラムなどプロに委ねる方もいるでしょう。
それがいけないことではありませんが、少し考えを柔軟に持てたらと思います。「子どもにこういった自然体験をさせないといけない」という決まりはありません。
近くの公園に出かけて親子で遊ぶだけでも自然を感じる経験になります。大人も興味を持てるのなら、キャンプに出かけてみるのもいいですね。
自然体験に興味を持っている保護者は決して少なくはないと感じます。ある保育所では「今度の土日に親子で自然学校に遊びに行きませんか?」と声をかけると結構な人数が集まるといいます。
私が知っている山梨の自然学校では、自然の中での活動に慣れていない親子でも楽しめるようなプログラムを考えていて、最初は楽しく遊ぶことから始めます。
やがて子どもたちはプロに引率してもらいながら自然の中のコースの散歩などに発展していくのですが、子どもたちが戻ってくるのを待っている間、保護者に「たき火を囲んで何か焼いて食べてみませんか?」と声をかけると、「ビールを持って来てもいいですか?」「こんなものも焼いていいですか?」と、それぞれのスタイルで自然を楽しむようになっていくそうです。
自然の中で遊んだことがないという人であっても、人間の遺伝子の中には、自然に囲まれて生活をしていた頃の記憶が残っているはずなのです。肩ひじを張らず、自然の中で楽しくすごしていると、やがて遺伝子に組み込まれた本能が活性化していき、「やっぱり自然っていいものだな」と思えてくるものです。
親がそうして自然と共鳴していくと、やがて子育てに対する価値観も変わっていきます。そうすると、社会の中で生き抜くために必要な力を育てなければいけないと意気込み、認知能力や偏差値など数値化しやすい力をのばすことに目を向けていた保護者が、人間にとって最も大切なことはなんだろう、子どもが本当にやりたいことはなんだろうと考えるようになることもめずらしくありません。
自然の中でイキイキと力いっぱい遊ぶ子どもの姿を見ていると、偏差値を上げるために「勉強しなさい!」と追い立てるよりも、こんなふうに目を輝かせて取り組める物事を見つける手伝いをするほうが、よほど大切ではないかと思えてくるのでしょう。自然体験は、親の教育観や人生観も大きく揺さぶってくれるのです。
子どもの生きる力をのばす5つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと(汐見稔幸 著/辰巳出版)
子どもを育てるときに、本当に大事なこと─それは豊かな経験をたくさんさせてあげることです。なぜなら、子どもの将来の育ちに影響が出てくる非認知能力は「体験」をすることによって育つからです。子どもが情報だらけの社会の中で上手に考え、判断できる人間に育てるにはどうすればいいのか。「体験」の豊かさがどんな影響を及ぼすのか。誰も教えてくれない、けれど、親が知っておくべき「子育てで本当に大事なこと」をまとめた一冊です。