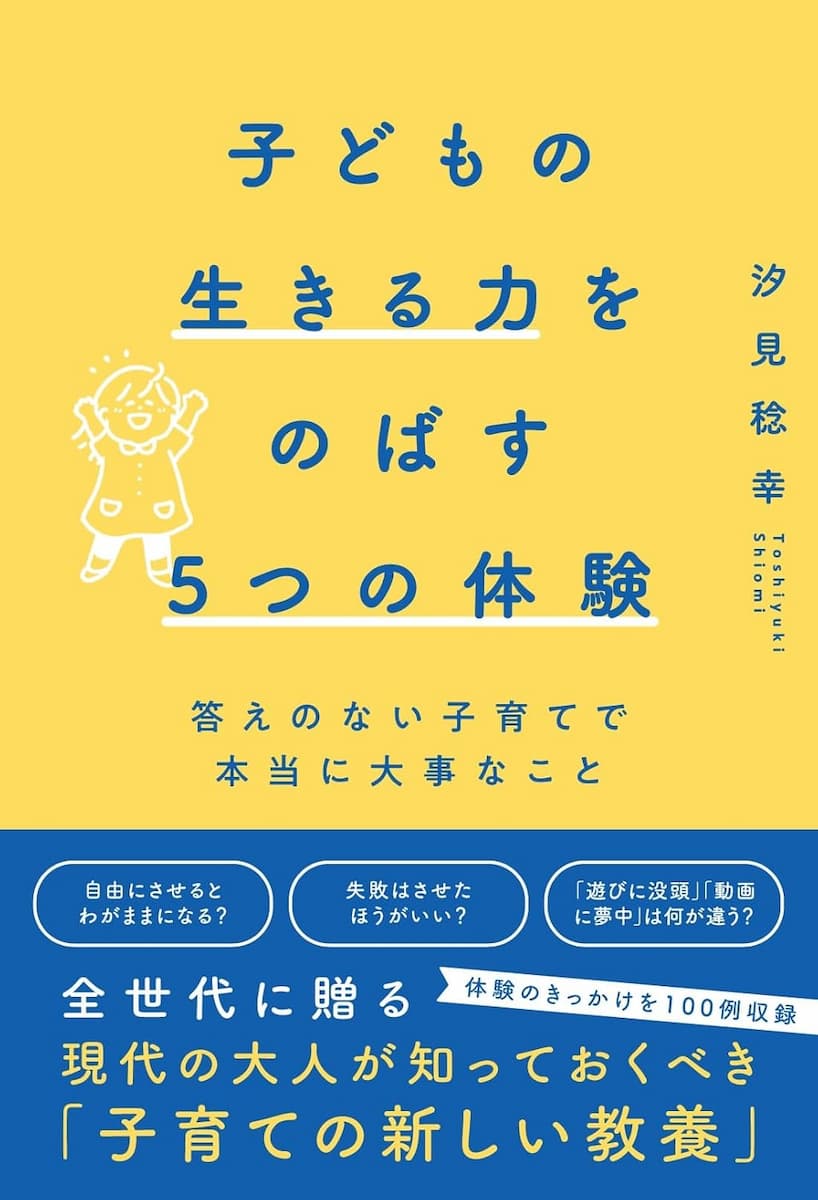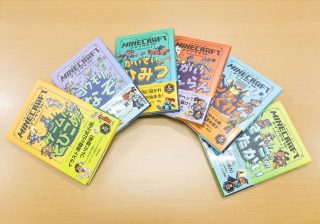走り出す友達を大人しく歩かせる2歳児 その方法は? 大人も見習いたい「見極めの力」

正解を求めがちの子育てですが、教育関係者や子どもを育てた親からは「子育てに正解はない」という声をよく耳にします。正解のない子育てで子どもの力をのばすために親ができることとはなんなのでしょうか?現代の大人が知っておくべき「子育ての新しい教養」を、幼児教育の第一人者である汐見稔幸の著書、『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』よりご紹介します。
※本稿は汐見稔幸著『子どもの生きる力をのばす5 つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと』(辰巳出版刊)より一部抜粋・編集したものです
子どもの興味関心・タイプを見極める

じっくりと「聞く」ことも、子どもの個性や興味関心を知ることにつながりますが、これは何も大人にしかできないことではありません。子どもだって相手を観察し、分析し、見極めることができます。
ある保育所に、衝動的な行動をよくする2歳児がいました。ここではAちゃんと言っておきます。
散歩中もいきなり走り出してしまうことがあり、保育士さんたちは手が離せずにいたそうです。でもお友達のBちゃんとだけは手をつないで歩くことができ、Bちゃんと手をつないでいるときは衝動的に走り出すことがありませんでした。
不思議に思い、Bちゃんに「どうしてAちゃんはBちゃんと手をつないでいるときは一緒に歩けるのかな?」と聞いてみると、Bちゃんからこんな答えが返ってきたのだそうです。
「Aちゃんはキラキラしたものを見つけるとそっちに行っちゃうから、わたしが先にキラキラしたものを見つけて、そのときはAちゃんの手をぎゅっとにぎってニコッとしてあげるの。そうするとAちゃんはキラキラしたものを見ないから、まっすぐ歩けるんだよ」とーー。
ふたりとも2歳児です。2歳でもそれだけ友達のことを観察してクセを見極めることができ、その対処法までわかっているのです。
これは色眼鏡で見ない子どもだからこそ気づけることかもしれません。親やまわりの大人は「いい子になってほしい」という色眼鏡で子どもを見てしまうことがしばしばあります。「いい子」だと認められる行動だけは評価をして、その枠からはみ出たときには叱責して矯正しようとする。
でも、色眼鏡を外してみると、「何かに一生懸命になって遊んでいる面白い子だな」「あんなに長い時間ぼーっとしていられるなんてすごいな」と思えるようになるはずです。子どもはそうした大人の前でこそ、その子らしく育つのです。
苦手も弱さも、そのままを受け止める

人間には、誰にも苦手なことや弱点があるものです。克服できることもあれば、できないこともあります。私はそれが悪いことだとは思いません。
わが家には子どもが3人いますが、一番下の息子は子どもの頃から感情コントロールがうまくできず、一度機嫌が悪くなると、ずっとそれを引きずってしまう子どもでした。家族の中では「あいつの機嫌が悪いときには近づくな」と言われていたほどです。
その子が小学生のときに「今、自分でも機嫌が悪くて困ってるんだろう?」と聞いたら、「うん」と言うんです。
自分の機嫌が悪いこと、それを自分でうまくコントロールできなくて、ずっと機嫌が悪い状態が続いてしまっている、それをどうしていいか悩んでいる、と言ってくれたわけです。
息子がそういう弱点を自分でちゃんとわかっていると知って、私は安心しました。自分の苦手や弱点をわかっている人は、ほかの人の苦手や弱点に対しても厳しい態度をとらないと思うのです。
「自分もそうなんだから、そういう人もいる」と思える。つまり、息子は弱者に対してやさしくなれる人間だとそのとき感じたのです。
子どもの苦手や弱さに気づくと、そればかりが目についてしまい、直さなければと思ってしまうかもしれません。でも、自分に苦手や弱さがあることで、まわりの人に共感できたり、やさしくできたりするのであれば、それは子どもにとっての強みです。
また、自分にやさしくしてくれる人に出会ったときには「自分のことを理解してくれているんだな」と感謝することもできます。
「弱さ」を弱点と見るのではなく、それも含めて私がある。それも含めてその人があると考え、それを私の大事な一部と思うこと、これが本当の個性だと思います。苦手や弱さをマイナスに見て、子どもの可能性を摘んでしまうことがないようにしたいものですね。
子どもの生きる力をのばす5つの体験 答えのない子育てで本当に大事なこと(汐見稔幸 著/辰巳出版)
子どもを育てるときに、本当に大事なこと─それは豊かな経験をたくさんさせてあげることです。なぜなら、子どもの将来の育ちに影響が出てくる非認知能力は「体験」をすることによって育つからです。子どもが情報だらけの社会の中で上手に考え、判断できる人間に育てるにはどうすればいいのか。「体験」の豊かさがどんな影響を及ぼすのか。誰も教えてくれない、けれど、親が知っておくべき「子育てで本当に大事なこと」をまとめた一冊です。