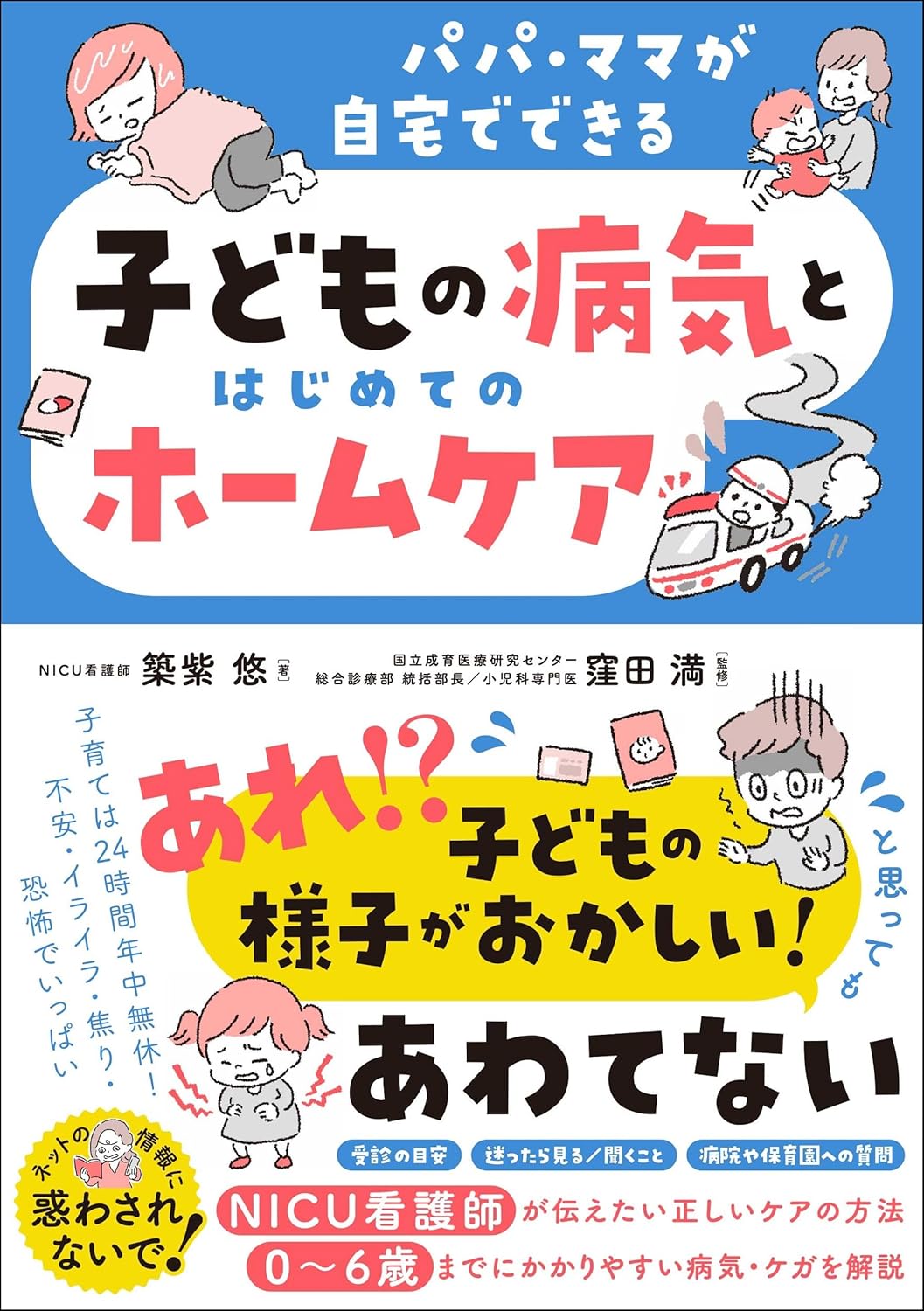ネットと小児科の先生、正しいのはどっち? 親が受診で感じる「モヤモヤ」の解決法
「診断名を言われなかった」「様子を見るだけでいいの?」「ネットでは違うことが書かれてた…」。
子どもの通院時に、こんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
受診で疑問が残るとき、親が安心して医療に向き合うための解決策を、看護師・築紫悠さんの著書より紹介します。
※本稿は、築紫悠(著),窪田満(監修)『子どもの病気とはじめてのホームケア』(総合法令出版)より一部抜粋・編集したものです。
「診断名」を言われなかったら
「咳が出る」から病院を受診したら、「咳を鎮め、痰を切れやすくするお薬で様子を見ましょう」と言われたり。
「腕がかゆい」と伝えたら、「かゆみ止めを塗って様子を見ましょう」と対応されたり。
このように、具体的な診断名が告げられないまま症状を緩和する薬が処方されるケースは珍しくありません。
私自身「あれ? ただの風邪ってことでいいのかな?」「このかゆみの原因は何だったのかな?」と疑問に思うことがありました。
しかし、よく考えてみると、処方された薬が効いたかどうかを確認したり、様子を見たりすることで症状の改善が見込まれる場合が多かったなと振り返っています。
それでも不安なら、質問する診断名が言われず不安な場合は、次のように質問してみてください。
・「咳が出ていますが、これは喘息の可能性はありますか?」
・「このかゆみはアトピー性皮膚炎ではないかと気になっていますが、どうでしょうか?」
「今の症状」と「心配な病名」に代えて聞いてみてください。こうした質問をすることで、医師が考えている可能性や方針を教えてもらえることが多いです。具体的に診断名を知りたい気持ちがある場合、その旨を率直に伝えてみても問題ありません。
「様子を見ましょう」と言われたら
診察の終わりに医師から「様子を見ましょう」と言われることがあります。
その言葉を聞いて、「これで本当に大丈夫なのかな?」「様子を見るだけでいいの?」と不安を感じた経験がある方も多いと思います。
「様子を見る」という判断には、改善の見込みがある、あるいは処方された薬が効果を発揮する可能性が高いという意味が含まれています。
「様子を見てください」と言われても、改善しない場合や悪化する場合にはどうすればいいのか気になるもの。
そんなときは、次のポイントを確認すると安心できます。
・「どのくらい様子を見ればいいですか?」
(例:2〜3日程度なのか、1週間程度なのか)
・「症状がどうなったら再受診したほうがいいですか?」
(例:熱が下がらない、咳が強まる、など)
これらの質問をしておけば、次に取るべき行動がわかります。
様子を見ることは「放置」ではなく、子どもの自然な回復力に期待しつつ、適切な判断をするためのプロセス。そう理解すると、安心感が得られるはずです。
「ネットと先生、どっちを信じたらいいの?」と思ったら
今では医療に関する情報も簡単に手に入るようになりました。
SNS、パパやママたちの会話の中でも専門的な言葉が飛び交い、「医療従事者ではないのに、詳しいことをよく知っているな」と驚くことがあります。
その反面「抗菌薬は体に良くないみたいだけど、病院で処方された」「ステロイドは怖い薬なのでは?」といった不安や疑問をよく耳にします。
しかし、ネットの情報はすべてが正しいとは限りません。
情報の出所や根拠が不確かなものも多いため、参考程度にとどめることが重要です。一番聞いておきたいのは、直接お子さんに触れている医師の意見。医師もあなたの不安を解消することが治療の一環だと考えています。
心配な場合は、次のように質問してみてください。
・「抗菌薬を内服すると下痢になるという記事を目にして不安に思ったのですが、先生のお話を伺えると安心できます」
・「ステロイドを使うのが心配なのですが、副作用について教えてください」
「このサイトにはこう書いてありましたが、これはどうなのでしょうか?」と医師に直接サイトを見せるのも有効です。医師に「どんな情報によって不安を感じているか」が伝わり、より的確なアドバイスがもらえるでしょう。
【著者紹介】
築紫悠
看護師/寄り添い疲れの人専門コーチ
北海道在住。看護専門学校卒業後、JA北海道厚生連帯広厚生病院に入職し産婦人科、新生児集中治療室(NICU)を経験。
退職後、内科、整形外科に勤務。看護師として13年、延べ2万人以上の患者と家族に寄り添ってきた。
20代でがんと診断された夫を12年間支え続けるうちに、自己犠牲による心身の消耗を痛感。自身の「寄り添い疲れ」をきっかけに、患者本人に「寄り添う言葉」が自分自身を守るものでもあるべきだと気づく。
現在は、病気の家族や介護に寄り添い続けて疲れた人に向けに、本当の自分を取り戻し、再び自分らしい人生を歩めるようフルサポートするサービスを提供中。
オンラインサロン「リトリートスペース」主宰。働きながら娘を育てる母。
窪田満(監修)
国立成育医療研究センター 総合診療部 統括部長
小児科専門医。医学博士。北海道大学医学部卒業後、埼玉県立小児医療センターなどを経て、2018年より現職。
専門は、先天代謝異常症、小児消化器病、小児総合診療(成人移行支援や小児在宅医療など)。
日本小児科学会、日本先天代謝異常学会、日本マススクリーニング学会の理事、日本小児突然死予防医学会 評議員も務める。
『パパ・ママが自宅でできる 子どもの病気とはじめてのホームケア』(築紫悠著,窪田満監修/総合法令出版)
本書は、子どもの病気やケガ・気持ちに悩まされるパパ・ママに向けて、NICU(新生児集中治療室)看護師で一児の母である著者が正しいホームケアの方法を解説します。
さらに、病院に行くか判断するために子どもの「どこ」を見るのか・「何」を聞くのか、病院や薬局で話す・聞くべき項目も掲載。
病院に行くか悩んで検索・自己判断する前に、「こんなとき、どうしたら?」と思ったら本書を見てください。