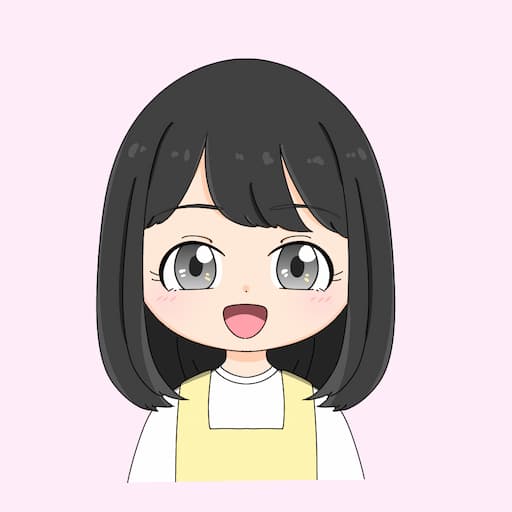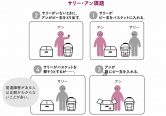2回目の発達検査も発達指数に変化はなく…それでも心理士さんの言葉に安心できた理由(もしかしてうちの子、発達障害!? 第11話)

私は、3人の子ども(小学3年生の男の子・年長の女の子・年少の男の子)を育てる保育士ライターです。小学3年生の長男は軽度発達障害で、今は支援級に在籍しています。今回は「療育のスタッフさんが見た息子の園での様子と2回目の発達検査」についてお伝えします。(連載「もしかしてうちの子、発達障害!?」第11回/写真はすべてイメージです)
療育スタッフが見た息子の園での様子

療育では年に2回「モニタリング」という個人面談が行われます。面談で園での様子を聞かれた際、保育園の個人面談がまだだったため「集団から外れることはなくなったと思いますが、配慮なしでは過ごしていないと思います」と伝えました。
するとスタッフさんが「息子くんの保育園訪問をしてみましょう」と提案してくださり、園訪問が実現しました。
訪問後の報告では、息子はきちんと集団で過ごせているものの、話が長くなると集中力がなくなり、視線が別の場所に向かってしまうとのことでした。この日は制作活動で、途中から作り方が分からなくなり周りを見ながら取り組み、最終的には先生と1対1で教えてもらって完成させていました。
配慮は必要ですが、集団にしっかり参加し、苦手な制作も周りを見ながら自分なりに取り組んでいる様子から、息子なりに頑張って過ごしていることが分かりました。
初めての療育手帳更新と2回目の発達検査
関連記事

編集部おすすめ