子どもの「噛まずに飲み込む」を改善するには? 急がない食べ方を身につける習慣
朝の忙しい時間、食事中の子どもについつい、「急いでー」といった言葉をかけていませんか?時間に余裕をもった上で、よくかむ正しい食べ方を日頃から意識してもらうには?
早食い防止の重要性や正しい食べ方を取得できるコツを、歯科医・生澤右子さんの著書(医師・脳生理学者の有田秀穂さん監修)より紹介します。
※本稿は、生澤右子(著)有田秀穂(監修)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)から一部抜粋・編集したものです。
急がない食べ方を身につける
私は大学院と研修先の病院で、昼休みは頑張って早く食べるようにしていました。
というのも、大学院では研究グループのみんなで生協食堂に行くのですが、男性ばかりで食べるのがとても早く、最初からどんどん食べていても、最後にみんなを待たせてしまいます。そのときは話を聞きながら、黙々と食べるようにしていました。
病院では、手術・集中治療部の所属で毎日のように手術室で全身麻酔を担当していました。
子どもの病院だったので、夏休みなどの時期は手術室のスケジュールはパンパンです。扁
桃腺の手術など短いものも何人も連続で行われるので、準備・手術・片づけ・準備・手術・片づけ……となかなかハードなのです。
手術中に昼食をとるときは、代わりに入ってもらっているので、できるだけ早く食べ終わる必要があり、必死に食べました(お弁当を5分で食べるのはなかなか大変でした)。
と、私の早食い時代のお話をしましたが、急がない食べ方は、この全く反対を実践すればよいわけです(笑)。
「早食い」を防止する習慣
まず、環境としては、楽しく会話しながら、時間をしっかり確保して、ゆったり食べるということです。大人が見本を見せることも重要です。
ですから、朝食をお子さんに出して、こちらは支度をしながら、「急いでー!!」と叫ぶというのは、やはりよくはないですよね。朝食を食べないというのは、もっとよくないですが……。
また、テレビを消したり、おもちゃが目に入らないようにしたりして、食事に集中できる環境を作ります。
その次に、口へ運ぶ習慣について考えてみましょう。つまり、ひと口の量と運ぶ頻度です。
急がない食べ方は、ひと口の量を減らして、口に詰め込まないことです。
ひと口の量は、スプーンの大きさや、お箸の太さなどで決まります。
口の中で扱いやすい量は、徐々に自分でわかってくるものですが、最初から口をパンパンに膨らませた状態に慣れてしまうのは問題です。
離乳食でも、自分で口に運ぶようになる段階で、ひと口の量をとりすぎだというときは、適量はこれくらいだと教えてあげましょう。
ちょうどよいひと口の量がわかってきたら、しっかりかむように伝えます。「すぐに飲み込まないで、お食事を味わってね」と。
口に食事を運ぶ頻度については、「口の中が空っぽになったら次を入れる」「ゴックンしたら次を入れる」というように、連続で口の中に入れないように習慣づけましょう。
大人では、お箸を置いて会話をしたり、周りを見渡したりということもお伝えします。
急がない食べ方を身につけると、満腹感を感じやすく、肥満防止にも役立ちます。
ここで水分の話になりますが、食事のときに水やお茶は積極的には飲ませないようにすることも大切です。かまないで水分で流し込むような食べ方をするようになってしまうからです(お味噌汁やスープは別です)。
これでは、正しい食べ方が身につきません。
本来は、かんでよく唾液を出すことで、口の中でまとめて飲み込むのです。どれも筋肉を使っている動きです。
つまり、味が濃いものをよくかまずに水分で流し込むような食べ方が、最も身につけてほしくない食べ方なのです。
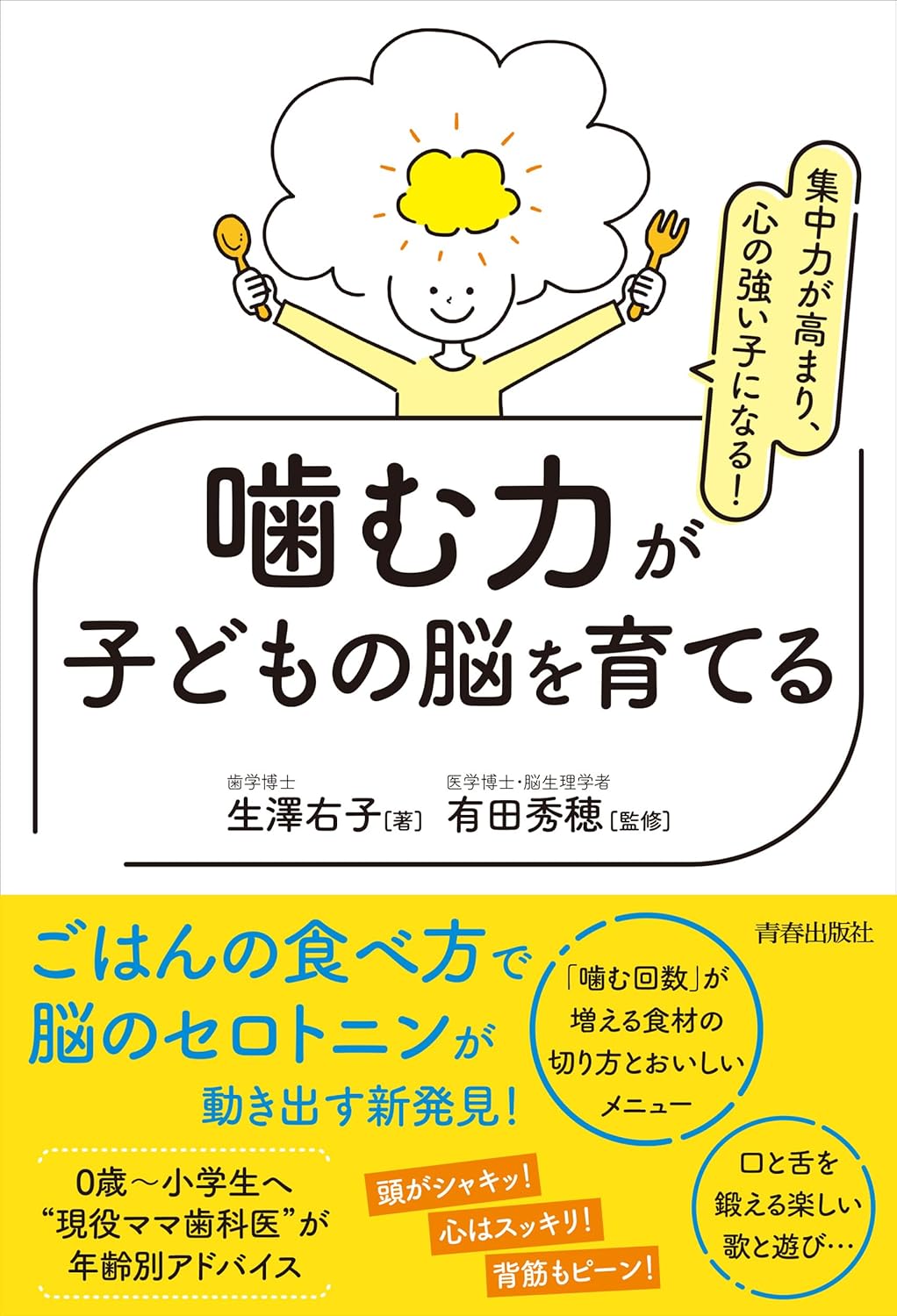
生澤右子/有田秀穂(著)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)
「かむ」から始める「食育」といつもの「生活習慣」をちょっと変えれば、幸せホルモン・セロトニンがどんどん脳で作られるという新発見 !
「噛む回数」が増える食材の切り方とおいしいメニュー 、口と舌を鍛える楽しい歌と遊び……など、0歳~小学生へ 歯と口のママドクターが年齢別にアドバイス。子どもの脳がぐんぐん育つ食育と生活習慣を伝授する一冊。