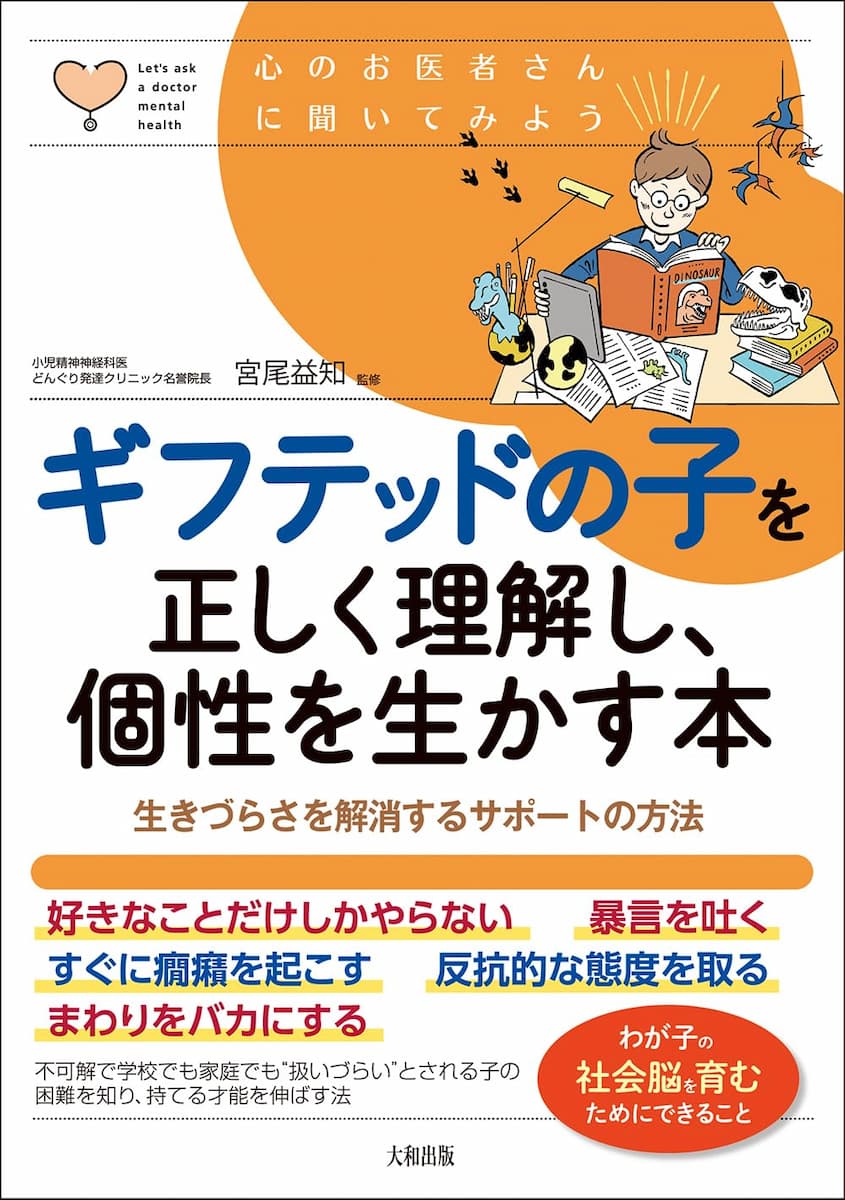高IQでも生きにくいギフテッド 子ども時代に才能を上手に伸ばすには?
高い知能や創造性をもつギフテッドの子どもたち。しかし、IQの高さだけでは才能を十分に伸ばし切れず、社会での生きづらさに直面することも少なくありません。日本では専門的な支援や教育環境がまだ整っていない現状があり、親や周囲の大人の理解とサポートが欠かせません。
本稿では、ギフテッドの才能を育むために必要な教育のあり方と支援のポイントについて、小児精神神経科医の宮尾益知先生の解説をご紹介します。
※本稿は、宮尾益知 (監修)『ギフテッドの子を正しく理解し、個性を生かす本』(大和出版)より一部抜粋、編集したものです。
高い知能、創造性、やり抜く力がそろうことで能力が花開く
ギフテッド教育の専門家ジョセフ・レンズーリ博士は、ギフテッドネス(卓越した才能や行動)には3つの要素があるとして「三輪概念(Three-Ring Conception of Giftedness)」を提唱しました。
ギフテッド教育に必要な3つの輪
ギフテッドの三輪概念は「高い知能」「創造性」「課題へのコミットメント(やり抜く力)」の3つです。
高い知能とはIQや論理的思考力、問題解決能力です。学業成績に限らず幅広い分野における優れた能力が含まれます。
創造性とは、枠にはまらない柔軟な発想、思考の柔軟性、新しいアイデアや方法を確立する力です。独自の視点や発想の豊かさを重視します。課題へのコミットメント(やり抜く力)は、目標や課題に対して強い集中力をもち、困難があっても粘り強くがんばる力です。努力や忍耐力、モチベーションの高さなどが含まれます。
ギフテッドネスはこれら3つの要素が重なり合って初めて発現します。3つの要素は先天的なものに限らず教育や経験でも成長するため、博士はギフテッドを「発展しながら形成されていくもの」と定義しています。この考え方は現代のギフテッド教育の基盤となっています。
日本では大人のサポートが欠かせない
ギフテッドを育てるには専門的プログラムが必要です。欧米ではSELやSTEAMなどが開発されていますが、日本ではまだ整っていません。同じ知的レベルの友だちが皆無だと刺激が得られず孤立してしまいます。私立の進学校に進んだほうがよい場合もあります。NPOのフリースクールや個別対応の支援級を活用するのもおすすめです。
環境になじめず不登校になるギフテッド児は大勢います。でも、社会脳を育てるには集団生活が不可欠です。無理に学校に行かせる必要はありませんが、学校に代わる居場所は探してあげましょう。
どんなに能力が高くても、ギフテッドの成長には親や周囲の大人のサポートが必要です。家庭や医療でできることはたくさんあります。注意深く見守りながら対応し、ギフテッドネスを伸ばしてあげてください。
知識だけでない、非認知能力を重視するSEL教育&STEAM教育
ギフテッド児向けの教育は、欧米を中心に盛んです。日本では民間団体主導で、数も少ないのが現状。指導者の育成が急務です。
適した学びの場が必要
ギフテッド児は多様な分野に興味をもち探究を深めていきますが、ASDの子のように特定の事柄に執着するわけではなく、最先端の知識を求めながら興味が移り変わっていきます。
彼らは本やインターネットを駆使して知的好奇心を満たそうとしますが、ネットには不正確な情報もあふれており、必ずしも精度の高い最先端情報が見つかるとは限りません。
大人は彼らの知識欲を満たすため、適切な学びの場を考慮する必要があります。
日本ではギフテッドのための教育環境はまだあまり整っておらず、専門機関の支援も不足しています。
非認知能力が重要視される
一方米国ではギフテッド専門プログラムや学校が充実し、同じ能力の子ども同士で学べる環境が整っています。スタンフォード大学では自宅で学べるホームスクーリングもあります。
子どもたちが知的探究心を伸ばすために期待されているのがSTEAM教育です。
STEAMとは、理数教育と創造的学習を教科横断的に学ぶシステムです。子どもは主体的・創造的に課題に向き合うことができ、知的探究心が刺激されます。
またSEL教育もギフテッド児に有効な教育法として注目されています。SELは心のIQともいわれるEQを重視。自己理解、自己統制、他者理解、人間関係のスキル、責任ある意思決定という5つの能力を育み、社会性を伸ばすことを目標としています。
STEAMもSELも、感情抑制や他者との協同作業など非認知能力を重視しています。また、新たな課題を他者と対話しながら解決する「21世紀型スキル」の習得も目指しています。
学びの場は学校に限らない
現在、日本では米国ほどの教育は整っていません。しかし、学校以外の場所には学びの場が生まれています。
たとえばオンラインでは経済産業省のSTEAMライブラリーをはじめSTEAM教育のためのツールや教材が提供されています。今後はこうした知のプラットフォームを活用しながら自分のペースで学び、かつ集団のなかで共に探究を深めていけるような環境づくりも求められるでしょう。またギフテッドや2Eの子の社会性を育み、集団のなかで生きる力をつけることを目的としたフリースクールなども生まれつつあります。
子どもの学びの場は多様化しており、選択肢も増えています。ただし学校や団体を選ぶ際は専門家とよく相談し、お子さんの向き不向きを見極めながら慎重に判断してください。
宮尾益知 (監修)『ギフテッドの子を正しく理解し、個性を生かす本』(大和出版)
「好きなことだけしかやらない」
「すぐに癇癪を起こす」
「反抗的な態度を取る」
「まわりをバカにする」
「暴言を吐く」
親は手を焼き、先生は対応しきれず、クラスでは浮いてしまう。IQが高いのになぜ問題児になってしまうのだろう? どうしたら持てる才能を伸ばせるか?
認知脳に比べ、社会脳の発達が遅れているギフテッド児は社会の中で他人の心を想像し、自分に引きつけて考え、行動することが苦手なため、集団で協力しあって行う学習にもついていけなくなる。IQが高くても、知識を活用して考えを深め、新たなことを発見・創造するまでには至らないのだ。持てる才能の芽を摘まずに個性を伸ばしていくには、適した学びの場や親のサポートが必要なのである。
不可解で学校でも家庭でも“扱いづらい”とされる子の困難を知り、上手に寄り添い援助する法。