お金をかけずに東大進学は可能? 年収300万円台家庭に生まれた秀才の教育費
世帯年収300万円台の家庭に生まれた斎藤さん。彼女が東京大学に入学するまでの道のり、そして教育費の総額は? 西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』から紹介します。
※本稿は、西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』(笠間書院)から一部抜粋・編集したものです。
イントロダクション
東京都内世帯年収300万円台の家庭に生まれた斎藤さんは、お金はなくとも親から無償の愛を注がれ続け、幸せに育てられました。
小さな頃から勉強は得意で、通った公立小中では常にトップの成績を維持。順調に都内有数の公立進学校へ歩みを進めます。もちろんここでもトップを取り続けましたが、その裏には秀才ならではの苦悩もあったようです。
彼女が東京大学に合格するまでを、彼女の本音とともに振り返っていきましょう。
小学校・中学校とも公立を選択
「共働きだから延長保育の可能性があった」。保育園に通った理由を振り返れば、忙しそうに働く両親の姿がありました。幼稚園も見たけれど、お金がかかるし、ママ友付き合いに参加する時間も気力もありません。家から近い保育園が最適解でした。
もちろん、小学校受験なんて考えるべくもありません。当時からお金の余裕はなかったそうですが、両親はお金がないなりに子どもに楽しんでもらおうと、児童館や図書館に足しげく通い、イベントがあれば欠かさず出向きました。
小学校は地域の公立小学校へ進学。保育園の子たちとは学区が異なり離れ離れとなりましたが、新しく友達を増やしたかった斎藤さんは、むしろこの状況を楽しんでいたといいます。当時は苦労することもなく、いい成績を取り続けました。
本人曰く「普通にやって、普通に90点以上」。高得点が取れないとショックを受けたのだとか。
勉強自体は好きでしたが、特別に自習をしたわけでもありません。年度の終わりには両親が「まとめドリル」を買ってきたそうですが、学校のテストよりも内容が難しく、心が折れかけたと語ってくれました。
ただ、当時の先生から出されていた「自主学習ノート」が印象的だったといいます。「何をやってもいいので、見開き2ページを埋めて先生に提出する」試みで、創作が大好きだった彼女は、教科学習に加え、写真を貼ったり詩を書いたり、物語を作ったりして、楽しみながらこなしました。
中学受験については、そもそも存在すら知らなかったといいます。仮に存在を知っていたら選択したかと尋ねたところ、「今から振り返っても、やりたくなかったでしょう。みんなと遊んでいるほうが楽しいと感じたはず」とのこと。
中学校は学区の公立中学校を選択。学区で指定された学校でしたが、当時は建て替え直後で非常にきれいであり、「ここしか考えられなかった。最高だった」と振り返ります。部活でダンス部があったこと、制服がかわいかったことも決め手でした。
推薦で都内トップクラスの公立高校に
中学に入ってからも塾には通いませんでした。通いたいとも考えなかったそうで、「塾に対するアンチだった」そうです。その理由について「力を貸すという建前で、実際は搾取されている気がしたから」と述べました。
そもそも、先生の献身的なサポートがあれば自力でできることを、わざわざ塾にお金を払って教えてもらう必要なんてありませんでした。逆に、塾通いを自慢してくるクラスメートに、うっとうしさを感じる時期も。「周りの人がみんな頭がよさそうだった。点数を取れるか心配だった」そうです。
しかし、それでも中学時代の成績はずっと1番。塾なしでもトップが取れることを証明しました。これはいいことばかりではなく、「斎藤はまじめで勉強ができる」と周囲から期待され、その通りに結果を出さなくてはならない息苦しさを感じた時期もあったといいます。1位の裏には、そのための必死の努力がありました。
中学校2年生の冬頃から受験を意識し、立地、偏差値、経済的条件などを考慮した結果、毎年東大合格者を輩出する都内でもトップクラスの公立高校を第一希望に。
春休みに見に行った時に、校舎が非常に魅力的で、ホームページで確認したよりも開放的な雰囲気を感じて一目ぼれ。その高校しか考えられなくなったそうです。
受験方法は推薦を選択し、合格。推薦入試の内容は、集団討論、面接、小論文、自己PRの4つ。作文コンクールでもらった賞など、全てを書けたのがよかったそうです。
塾に通わない戦略で東大合格
ついに高校に入学し、1発目の定期テスト。周りは受験を勝ち抜いてきた首都圏でも屈指の秀才ばかり。どうなるかと思われましたが、蓋を開ければクラス1位。
思った以上に勉強は順調に進みました。結局、3年生になって順位が非開示になるまで、つねにクラス1位か2位をキープし続けます。そのためか、高校1年生の時点で先生から東大を勧められました
それまでは大学には行かず専門学校に進学しようと考えていた斎藤さん。「みんなと一緒の進路を選びたくない」ためでした。担任の勧めを本気にせず、当時は受け流していました。
大学に行かず、違う進路を選ぶには、「どんな進路があるか」を知る必要があります。地元の図書館に通い、色々な本を読み漁るうちに、「私は探究活動がやりたいのだ」と気付きます。
教科書に出てこないような知の探究が叶う場所として入学後の選択肢の多い東大から目が離せなくなっていきます。
どうせあと2年は高校で勉強を頑張るのだから、それなら最大の努力をしてみよう。妥協しないで東大を目指してみよう。心が決まりました。
この頃は塾通いを検討したこともあり、無料体験会にも行ったそうです。しかし、授業の内容に無駄を感じる場面が多く、自ら要不要を判断しコントロールできない環境にストレスを感じ、受験戦略として塾に通わない選択をしました。
受験校は東京大学文科三類のみ。どうせ東大しか行かないつもりで、万が一落ちたら自宅で浪人の覚悟でした。推薦入試は論文や受賞歴などわかりやすい経歴がなく、苦戦すると判断したそうです。結果は、見事現役での合格でした。
大学に入学するまでの合計金額
彼女の大学入学までの教育費用合計は、212万円です。内訳は、私立保育園が40万(年間雑費20万円×2年間)、公立小学校が72万円、公立中学校が50万円、公立高校が50万円。
彼女は塾や習い事を一切せず、小学校から高校まですべて公立に通ったので、非常に安く東大進学を果たしています。
また、高校で補助が出ており、授業料が一部減免になったほか、月1万円の奨学金を支給されたそうなので、実際には212万円よりもずっと少ない金額での進学と考えられます。
やはり、お金をかけずに一流大学へ進学するならば、都道府県内トップの公立高校へ進学するのが最良なのでしょう。
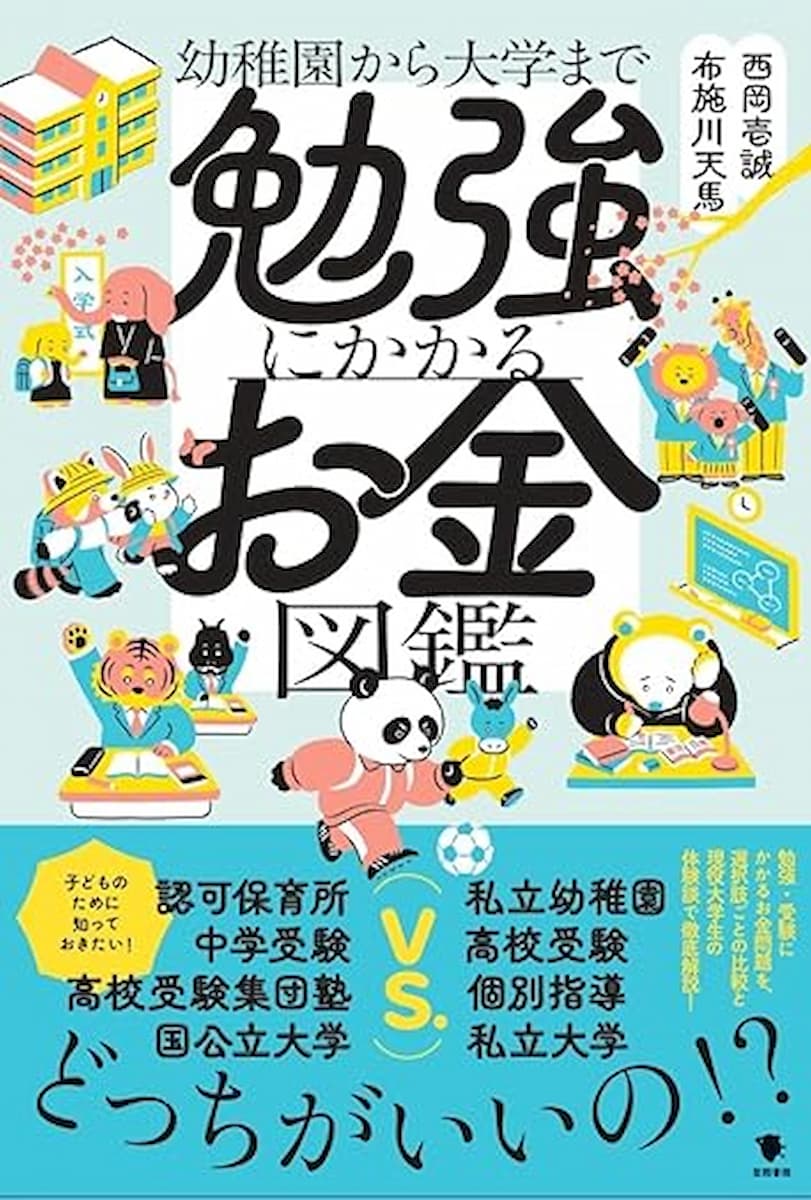
西岡壱誠(著)布施川天馬(著)『幼稚園から大学まで 勉強にかかるお金図鑑』(笠間書院)
塾・家庭教師・受験料・入学金……子どもの勉強や受験にはお金がかかります。本書は、累計50万部「東大シリーズ」著者で東大カルペ・ディエム代表・西岡壱誠と、貧しい家庭に生まれながら東大合格を果たした著者・布施川天馬が、「子どもの勉強・受験にかかるお金」の問題に特化し、経験と膨大なデータをもとにまとめた一冊です。