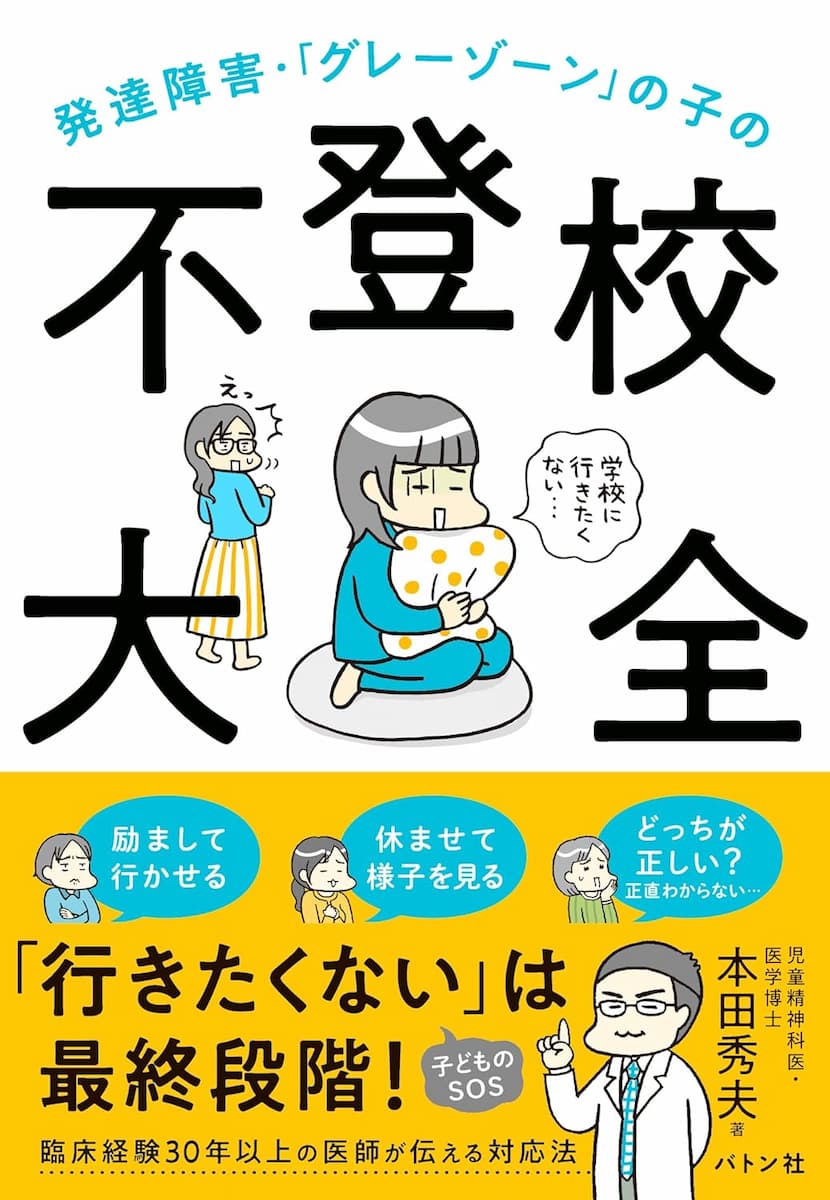どうして学校に行けなくなるの? 発達に特性ある4人が不登校になった理由
ある日突然、「学校に行きたくない」と言い出す子どもたち。
理由がわからず戸惑う親御さんも多いですが、子どもが不登校に至るまでには、それぞれに積み重ねられた背景があります。
この記事では、発達に特性のある小学生4人が、どのような経緯で「学校に行けなくなったのか」を、精神科医・本田秀夫先生の著書よりご紹介します。
※本稿は本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)より一部抜粋、編集したものです。
イラスト(マンガ):フクチマミ
子どもはどんなときに不登校になるの?
「学校に行きたくない」というのは、親御さんからすると「問題の始まり」に見えますが、お子さんからすると“ 学校に行く自分” を捨てた「最終段階」と言えます。大人が思っている以上に、子どもは問題を抱え込んだり一生懸命にふるまったりしているのです。
親や教師と子どもとの「すれ違い」を防ぎたい
小・中学生のお子さんが不登校になっていく経緯は、その子によって違います。「友だちづき合い」や「部活動」といったきっかけがはっきりして対応しやすい場合もあれば、発達特性があって、本人の悩んでいるポイントが親御さんや学校の先生方になかなか理解されないこともあります。その場合、不登校が長期にわたって続くこともあります。
子どもが不登校になるまでの経緯を紹介
「発達障害と不登校の関係」を解説することで、親子や教師との子どものすれ違いを防ぎ、不登校に苦しむ子どもを減らしたいと考えています。
取り上げる例は、発達特性のある小学生の相談例ですが、特性の詳細については
触れません。
まずは「子どもがどのような状況で不登校になるのか」を知ってもらえればと思います。
①腹痛で休んでから、学校に行けなくなった子
小学3年生 女子の場合
最初のケースは、小学3年生・女の子のエピソードです。このお子さんは、ある朝突然「学校に行きたくない」と言いました。親御さんが理由を聞いても「わからない」と答え、顔色が悪かったので学校を休ませました。その日は動画を見たりゲームをしたりのんびり過ごしたところ、翌日は登校したので親御さんは安心しました。
しかし、数日後の朝、彼女はまた「行きたくない」と言い出しました。今度は「お腹が痛い」と訴えたため小児科に連れていきましたが、診察では異常は見つかりませんでした。
お子さんは、夜になると少し元気になって、次の日にはまた学校に行きましたが、その後は学校に行けない日が少しずつ増えていきました。朝になるとお子さんが「お腹が痛い」「頭が痛い」と言うのです。最初のうちは、親が励ますと登校できることもありましたが、そんなやりとりを続けていたある日、お子さんに変化が現れました。
玄関で靴を履いているときに、ランドセルを背負ったまま泣き出し、動けなくなってしまったのです。それ以来まったく登校できなくなり、親子で相談に来られました。
仮病ではなく、本当にお腹や頭が痛くなることも
小学校、中学年くらいのお子さんは、「学校に行きたくない」という気持ちは言えても、その理由は説明できないことが多いです。学校の何かが嫌なのだけれど、それを言語化できない。だから理由を聞いても「わからない」と答えるわけです。
モヤモヤしたものが体の不調となって現れることもあります。それで「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えるのです。このケースのように病院で「異常ありません」と言われると、お子さんの仮病を疑ってしまう瞬間もあると思いますが、特に病気の兆候がなくても、お腹や頭が痛くなることはあります。
保護者の方としては「理由を知りたい」「何ができるかを考えたい」と思うかもしれませんが、不登校になったときには、対応の糸口がすぐには見えてこないこともあります。その場合には解決を焦らずに、じっくり対応していきましょう。お子さんの話をゆっくり受け止めていくなかで、理由がわかってくる場合もあります。
②立ち歩いて叱られ、先生を怖がるようになった子
小学1年生 男子の場合
続いて、小学1年生の男の子です。このお子さんの場合は、不登校の理由が比較的はっきりしています。先生に叱られるのが怖くて登校するのが嫌になってしまったケースです。
このお子さんは勉強が苦手で、授業についていくことに苦労していました。先生の話を聞こうとするのですが、教科書のどこを読んでいるのかわからなくなり、集中が切れてしまいます。そのとき周囲に気になるものがあると、ふと立ち歩いたりするのです。先生は子どもを注意し、そこで彼がおとなしく座ることもあれば、かんしゃくを起こすこともありました。そのため、先生からは「問題児」とみなされていました。やがて授業以外でも叱られる場面が多くなり、本人が先生を怖がって、登校をしぶるようになったのです。
保護者の方は担任の先生に連絡をとり、対策を相談したのですが、先生から授業中の様子を聞いて、「家でもよく言い聞かせなければ」と思ったそうです。そしてお子さんに「授業中はちゃんと座っていなさい」「先生の話をよく聞いて!」などと伝えたそうですが、その後も状況は改善せず、お子さんが学校を休む日は増えていきました。
立ち歩く行動を叱る前に、まず必要なこと
発達特性がある子は、このケースのように「行動の問題」を何度も叱責され、次第に登校できなくなっていくことがあります。授業中に立ち歩くのは確かに問題ですが、このようなケースでは「どうして立ち歩くのか?」を大人たちが考え、対応していく必要があります。
例えば、立ち歩く理由として、集中力の欠如や不安感、周囲の刺激による混乱などが考えられます。こうした行動の背景には発達障害の特性が影響していることがあり、それを理解することで適切な支援につながります。
近年では、お子さんの離席が目立つ場合に、保護者の方や学校の先生が発達障害の可能性を考え、医療機関などに相談することも増えています。しかしこのお子さんのように、不登校になってから相談に来られるケースもあります。私はもっと早い段階でお子さんを支援することが大切だと考えています。
③「授業がつまらない」と言って、登校しなくなった子
小学4年生 男子の場合
次は相談例②とは対照的な例で、勉強が得意なお子さんのエピソードです。このお子さんも男子です。彼は小学4年生のときに「授業がつまらない」と言って、登校をしぶるようになりました。最初は保護者の方が「そんなこと言わないで」と声をかけて登校させていたのですが、本人の気持ちはその後も変わらず、そのうち毎朝親子で口論をするようになっていきました。結局不登校になり、親子で相談に来られました。
このお子さんは学力が高く、一度教科書を読めば内容をだいたい理解できてしまうそうです。本をよく読むので、まだ習っていない漢字も知っています。しかし、担任の先生からは「習っていない漢字は使ってはダメ」と言われ、不満に思っていたそうです。
彼はもっと多くのことを知りたいのですが、学校の授業はその学年の標準的なペースで進んでいくので、彼にとっては「つまらない」というわけです。本人は、同級生と話が合わないのも「つまらない」と言いました。このお子さんは口も達者なので、小学校・中学年の段階で、自分がなぜ学校に行きたくないのかを、しっかり説明できたのです。
学校以外に「社会参加する場所」を見つけよう
彼は好きなことをとことん調べて、ノートにまとめたりするのですが、それを担任の先生に見せたら「習っていない漢字を使ってはいけません」と言われたそうです。ほかにも自分の得意なやり方で勉強しているときに、先生から「普通のやり方にしなさい」と注意されることもありました。その結果、学校に行くのが嫌になってしまったのです。
保護者の方は「授業に出なくても勉強はできるから」と言って学校を休ませ、お子さんを個人学習塾に通わせていました。ほかにも習い事の教室やフリースクールも見学したそうですが、活動が多くなるとお子さんが混乱してしまうため、学習塾だけにしているということでした。
学校が居場所にならない場合には、別の居場所を探す必要があります。子どもには「社会参加する場所」が必要です。居心地のいい場所で、自然と社会性を身につけていくような時間も持っておきたいのです。
④担任との相性が合わず、登校をしぶるようになった子
小学5年生 女子の場合
小学校・高学年の女子の例です。このお子さんは、小学4年生までは学校生活を楽しんでいたのですが、5年生になり学校へ行けなくなりました。親御さんが理由を聞くと、彼女は「担任の先生が嫌い」だと答えたそうです。親御さんは本人の気持ちを大事にしたいと考え、ひとまず休ませましたが、先生に「うちの子が先生を嫌がっています」とは言えず、困って相談に来られました。
その後、本人の話を聞いていくと、担任の先生がとても細かい人だということがわかってきました。先生は学習方法などにルールを設定したがり、それを杓子定規に守らせようとするのです。一方、このお子さんはコツコツやるのが苦手でした。授業中、気が散ってしまうこともあるけれど、最後には帳尻を合わせてどうにかするというタイプなのです。
先生は管理主義的。お子さんはマイペース。相性がとても悪かったわけです。このお子さんは自分なりのやり方で頑張っていたのですが、何か一つ抜けるたびに先生から注意され、「ルールをよく見て!」「やればできるよ!」と言われていました。
担任以外の第三者に相談する
先生に注意されたとき、友だちに「また怒られちゃった」などと愚痴を言える子もいます。そして一緒に遊んで気持ちを切り替え、また次の日も学校に行ったりするわけですが、発達障害の子のなかには、友だちづき合いを通じてストレスを解消するのが苦手な子もいます。モヤモヤした気持ちを一人で抱え込み、しんどくなってしまう子もいるのです。
人間関係には相性があります。この例のように、子どもと担任の先生との相性が悪くて不登校になっていくパターンは、けっして少なくありません。なかには「自分は叱られていないけど、友だちがいつも叱られていて、それを見ているのがつらい」と言って、登校を嫌がるようになる子もいます。
しかし現在の教育制度のもとでは、担任の先生との相性が悪いからと言って、一人だけクラス替えをしてもらうわけにもいきません。保護者の方が第三者(スクールカウンセラー、学校管理職など)に相談しながら、なんらかの手立てを考えていく必要があります。
本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)
「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍
子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。
休ませて様子を見たほうがいいのか。
それとも、励まして登校させたほうがいいのか。
保護者の方からそのように聞かれることがあります。
学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。
この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。
<中略>
私は、不登校になっているお子さんもみてきましたが、発達障害や知的障害があっても登校できているお子さんもみてきました。ですから「学校に行けるお子さんは、どうして行けているのか」を知っています。何がポイントなのかをお伝えすることができます。
主には発達特性がある子を対象とする話ですが、この本の内容の多くは、特性が目立たない子にも通用します。お子さんの不登校に悩んでいる保護者の方や学校の先生方、子育て・教育に関わっている支援者の方々に、ぜひ読んでいただきたいと思います。
(「はじめに」より)