2030年導入決定…研究で見えた『デジタル教科書』の問題点とは? 言語学者が考察する紙との差
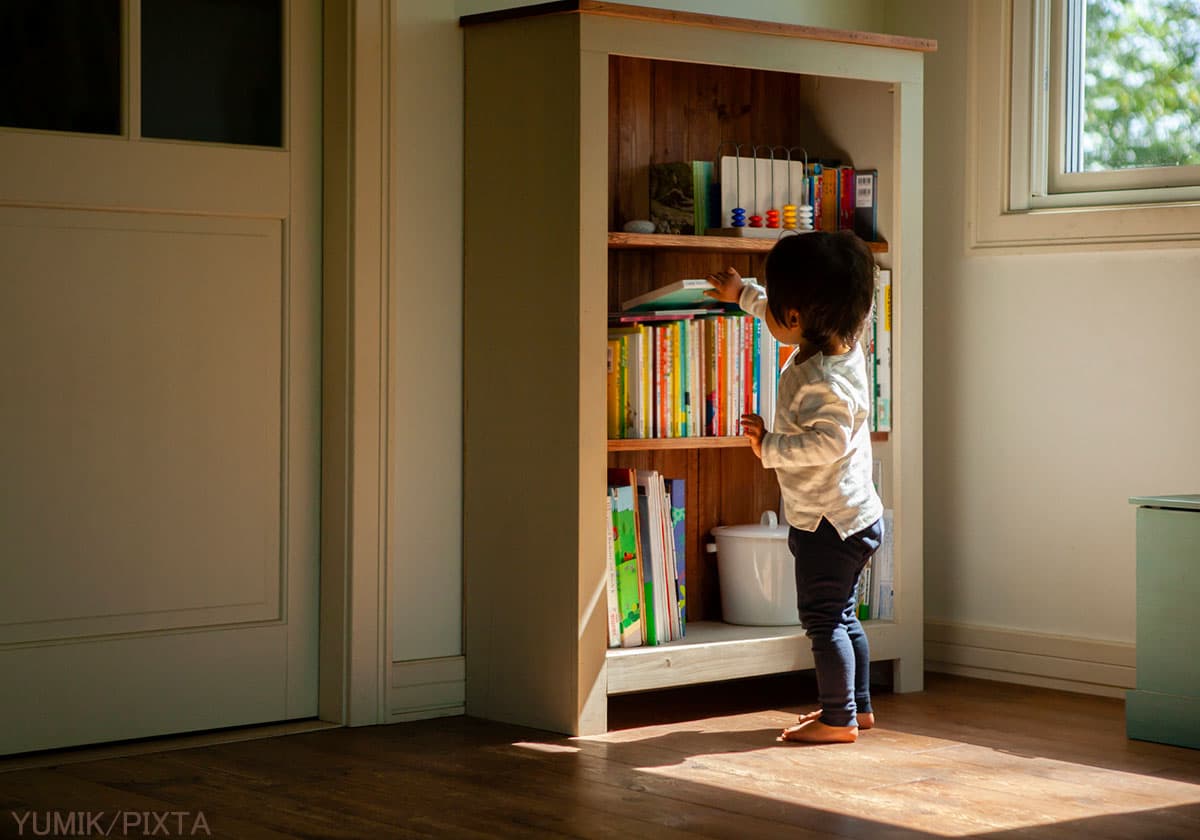
2025年9月24日、中央教育審議会(文部科学相の諮問機関)の作業部会は、デジタル教科書を正式な教科書と位置づけ、2030年度から導入することを了承しました。教育現場は大きな転換点を迎えていますが、「やっぱり紙の方が頭に入るのでは?」と不安に思う保護者も多いはずです。
では、紙とデジタル、それぞれの強みや弱点はどこにあるのでしょうか。言語学者で明治大学教授の堀田秀吾先生に、研究データをもとに詳しく伺いました。(文・吉澤恵理)
読解の深さと記憶定着、紙とデジタルの違いは?

――紙とデジタルで、理解のしやすさに違いはあるのでしょうか?
はい。ノースダコタ大学のクリントン氏が2019年に33件の研究を分析した結果、特に説明的な文章や学術的な長文では紙の方が理解度が高いと報告されています。
――なぜ紙の方が理解しやすいのですか?
































