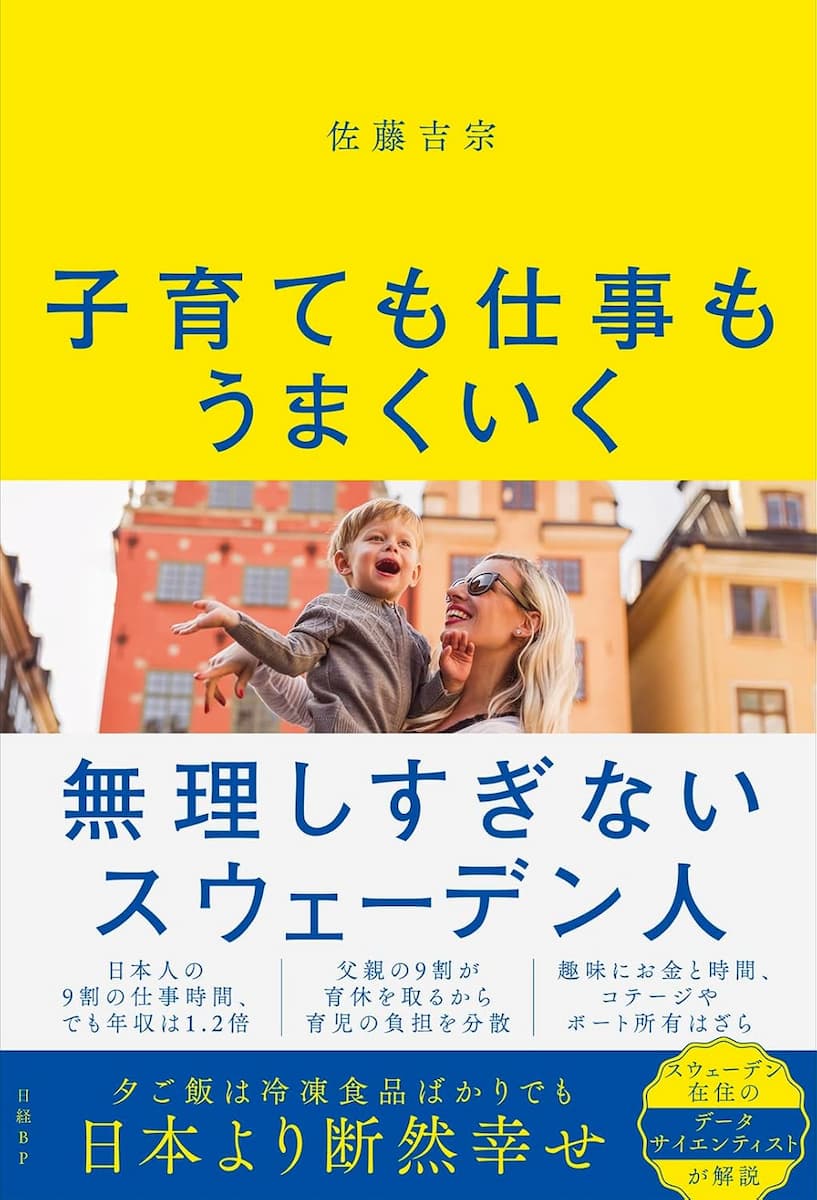父親の育休はプラス評価されるべき? スウェーデン25年在住2児のパパに学ぶ共働き術
男性の育休取得の重要性が語られる時代になりましたが、父親の育休が日本の職場で“当たり前”に実施されているとは、まだ言い難いのが現状です。
スウェーデンに25年暮らす日本人データサイエンティストで、2児の父親でもある佐藤吉宗さん。スウェーデンで知り合った日本人パートナーと共働きで子育てをしています。
自身の経験を交えながら、スウェーデン社会に根づく育休制度を解説します。パパもママも子どももハッピーになれる育休取得のヒントとは?
※本稿は佐藤吉宗著『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。
育休のキャリアへの影響「心配は全くなかった」
スウェーデンの大手銀行の課長職に就いている私の同僚、グスタフは38歳。彼は第2子が1歳になったときに、それまで育児休業を取っていたパートナーとバトンタッチする形で8カ月間の育児休業を取った。
彼の育休復帰後のある午後、彼と職場でお茶をする時間(フィーカ)があったので詳しく聞いてみた。第1子が生まれたときは別の金融機関で働いており、そのときも同じようにパートナーがまず1年間の育児休業を取り、その後、彼が8カ月取ったのだという。
「最初の娘が生まれた後の子育てで、授乳という形で娘と絆を着実に築きつつあったパートナーを見て、自分は蚊帳の外に置かれた気が少しした。授乳がだいたい終わり、自分でも離乳食をあげることができるようになったとき、今度は自分が娘との関係を築いていく番だと感じた」という。
日本の男性が育児休業をあまり取ろうとしない理由の一つは、キャリアに与える悪影響への懸念だというが、彼はそんな心配はしたのだろうか。聞いてみた。
すると、「心配は全くなかったよ。スウェーデンでは育児休業がキャリアに影響するとは思わないな。むしろ、会社からはプラスに評価されると思う」という答えが返ってきた。それは、職場が親としての経験を評価しているということなのだろうか?
育休で家庭と仕事のバランスが取れる人間だと見られる
「そう、それもあるし、会社は私のことを、親の役目をしっかり果たそうという責任感があり、家庭と仕事とのバランスをうまく取れる人間だと見てくれていると思うよ。
課長職に就いて複数の部下を持つ今の自分が言っているんだから、この考え方は間違いじゃないよ(笑)。
もし自分のチームの誰かが育児休業を取るならば、その人はきっと自分に自信があるんだと私は考えるよ。半年以上も職場を離れる勇気があるということだからね」
収入についても聞いてみた。育児休業を取れば働いているときよりも収入が減ることになるわけだが、心配はなかったのだろうか。
「確かに減るけれど、それでも給与の90%近くがもらえるから、それが育児休業の取得に影響を与えることはなかった」
日本と異なる雇用慣行
このように、職場を一定期間離れることに関しては日本人が持つような心配はないようだ。ここには日本とスウェーデンの雇用慣行の違いも影響しているかもしれない。
新卒採用で入社して、ジョブローテーションによりさまざまな経験を積み、同期入社の同僚と競い合い比較されながら、成果を認められて昇進を目指していく。
そんな日本特有の職場では、確かに数カ月も職場を離れることによって同僚にキャリアの面で大きな後れを取ってしまうことになりかねない。
一方、スウェーデンでの雇用形態は基本的に「ジョブ型雇用」であり、社内異動や転勤は原則としてなく、転職も頻繁だ。
一人ひとりが自分のキャリアプランを描いていて、今の職場よりも良い条件の職場があれば次々と転職し、経験を積んでいく。
管理職になりたいと思えば、今働いている会社の内外を問わず、自分で空きポストを見つけて応募する。現時点での自分の生き方には非管理職が合っていると思えば、今のポストに居続けることもできる。
キャリアは会社が決めてくれるものではなく、自分で積極的に築いていくものなのだ。そのような働き方においては、半年から1年に及ぶ育児休業も大きなマイナスとはならない。
育児に理解を示さない職場からは人材が流出する?
これに関連して付け加えるならば、転職が一般的で流動的な労働市場であるため、従業員の育児に理解を示さないような職場からは人材が流出してしまうことになる。
優秀な人材を引きつけたり、今いる従業員にとどまってほしいと思えば、育児休業を取りたい従業員には、男女を問わず積極的に取らせる必要がある。
そして、育児を通じてその人が培った経験や考え方を職場でも活用していければ、職場にとってもプラスとなる。
育児を分担しない男性には女性がついてこない
また、スウェーデンでは男女を問わず、自分の希望する仕事に就いてキャリアを積むことを当然と考えているので、育児を分担しようとしない男性には女性がついてこない。
私が以前、スウェーデンの大学で研究職に就いているとき、子どもがいる同世代のスウェーデン人の同僚男性に、なぜ育児休業を取るのか尋ねたことがある。
彼の答えは至ってシンプルで単刀直入だった。「子どもを持つということは子育ての責任も自分で引き受けるということ。それができないなら、子どもは持たないほうがいい」
ある日本人経営者の発言に感じたギャップ
もう10年ほど前のことだが、日本の経営者の団体がスウェーデンに視察に来た。私はそれ以前に『スウェーデン・パラドックス 高福祉、高競争力経済の真実』(日本経済新聞出版)を共著で出版していた。
スウェーデンの経済や税制・社会保障についてまとめた本であり、男女平等や育児支援の制度などについても幅広く触れていた。この著書に目を通していた視察団の方々は、私にレクチャーを依頼した。
レクチャー後の質疑応答の中で、視察団長と思われる年配の男性経営者の方がこう発言した。
「佐藤さんの本を読んで、男女平等がスウェーデンでは大事だということは分かったのですが、私には今一つピンときません。
私の会社で育児休業を取りたいと言い出す男性従業員がいたなら、私は言ってやりたいですよ。
『お前は仕事に打ち込む気がないのか。自分のキャリアを真面目に考えているのか』と」
その時点で10年以上スウェーデンで暮らしていた私は、正直、発言の意味が全く分からなかった。じゃあ、誰が育児をするんですか? 父親がしないとなれば結局、母親がせざるを得ない。
では、母親のキャリアはどうなるんですか? 彼女のキャリアを真面目に考えなくてもよいのですか? というのがとっさに私の頭に浮かんだ反応だったが、せっかく私のレクチャーを聞きに来てくれたこともあり、攻撃的にならないように柔らかく応答したことを覚えている。
日本人が持ちがちな「育休は余暇」という思い込み
後でその発言を何度も思い起こしてみて、少し気づいたことがある。
その方の発言の背景には、会社のために自分を犠牲にしてバリバリ働く人が良い社員、という高度成長期の体育会系・精神主義的な考え、それから、育児休業イコール「余暇・休み・怠け」という思い込みがあるのではないかということだ。
会社の経営者ということで、もしかしたら育児には直接関わってこなかったのかもしれない。育児を実際に知っていれば、それが決して楽な余暇などではないことは分かると思う。
残念ながら、このような偏見は日本ではこの方に限ったことではないようだ。育児をしたことのある男性が社会の中で増えていけば、育児に対する理解も進み、育児休業をより取りやすくなっていくに違いない
佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)
子育てしやすい国として知られるスウェーデン。しかし、実は30年前は子育てしながら働くための制度は整いつつあるものの「男性が働き、子育ては女性がするもの」という男女の性別分業が根深く残っていました。
そんなスウェーデンの社会はどのように変化してきたのでしょう?
現在のスウェーデン人の共働き子育てスタイルについて、スウェーデンに25年にわたって暮らす日本人データサイエンティストが、自身の子育て経験も交えて解説。
日本人が「無理しすぎず」共働き子育てをする手掛かりがつかめるはずです。