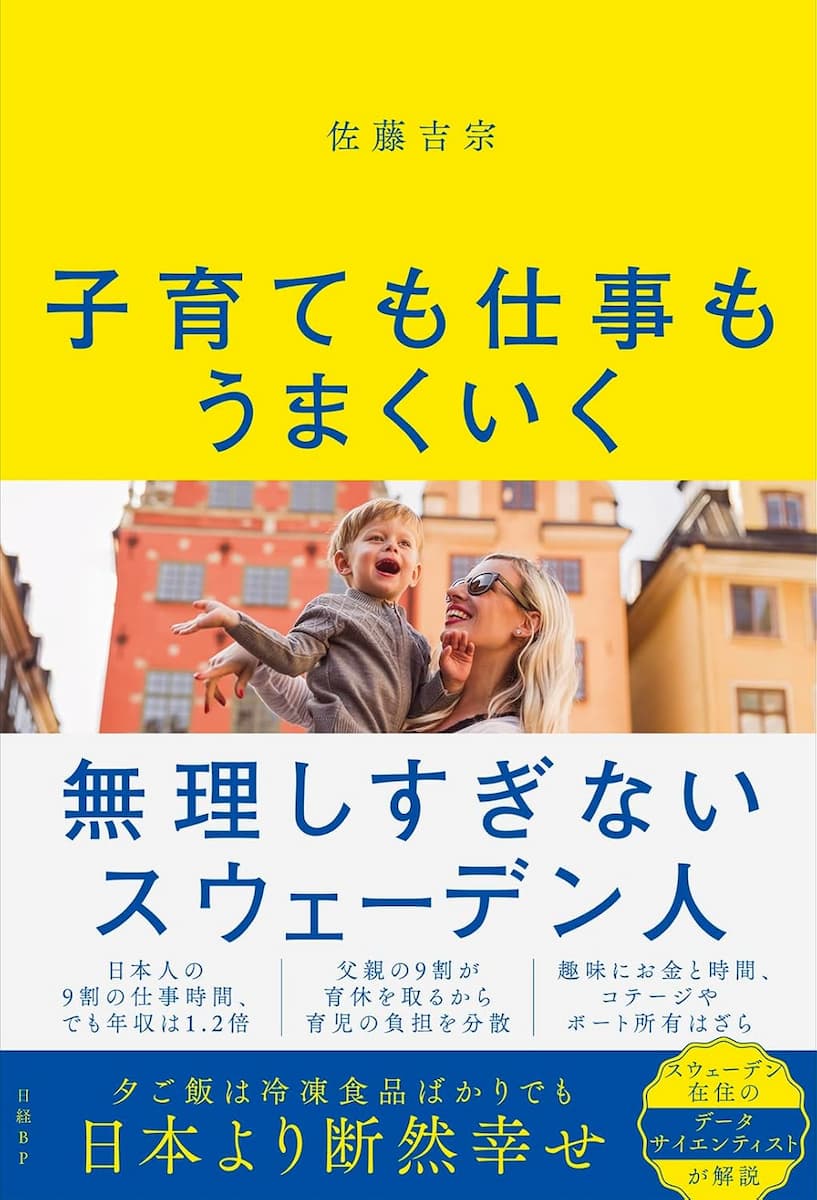「自然教育」「言葉遊び」で育む好奇心…スウェーデン保育が重視する幼少期の体験や学習とは?

「三つ子の魂百まで」ということわざのとおり、幼少期の体験や経験は子どもの好奇心を刺激し、学びの扉を開くきっかけになります。
「自然教育」や「言葉遊び」など、スウェーデンの保育所での取り組みを通じて、幼少期で重要な体験や経験とは何かを考えます。
現地に25年暮らす日本人データサイエンティストで2児の父・佐藤吉宗さんの著書『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)から紹介します。
※本稿は佐藤吉宗著『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。
転園も迅速、申し込みから約3週間

年が明けてからの慣らし保育は私とパートナーと1日ずつ交代で付き添った。一筋縄ではいかなかったが、1週間ほどすると親の姿が見えなくなった途端に泣きやむなど切り替えが早くなってきた。
家で使ってきた薄いブランケットがあると安心するので、保育所でも肌身離さず持っていた。夕方に迎えに行くと、息子はブランケットを首に巻き、端を上着のシャツの下にきれいに入れて落ちにくくした状態で砂場で遊んでいることがよくあった。保育士がやってくれたのだと思うが、その巧みな巻き方に感心した。
その保育所に特に不満があるわけではなかったが、自宅からの方向が駅とは逆なので通勤途中に預けようとすると遠回りになってしまうのが面倒だった。
保育所までたった200mなのでずいぶんぜいたくな悩みなのかもしれないが、息子を保育所に預け始めてから8カ月後、ダメもとで自宅前の保育所への変更を市に申し込んでみた。
すると、今度は1週間で返事が来た。その保育所に空きがあるという。そして、早くもその2週間後には息子はそこで新たな保育所生活を始めた。
保育所はスウェーデン語をしっかり教える
保育所での生活や保育の内容についてはここで詳しく書くスペースがないが、特に印象に残ったのは、言葉とコミュニケーションに重きを置いていることだった。
スウェーデンには私たちのように外国からの移住者がたくさんいる。数多くの難民も受け入れてきた。そのようなバックグラウンドの異なる人々が一つの社会をつくっていくための重要な鍵は、スウェーデン語と民主主義という価値観だ。
だから、スウェーデン語は小さいときからしっかり教える。身の回りにあるものの名前や遊びの中で使うものの名前や概念を一つ一つ確認し、もやもやした自分の感情にも一つ一つ呼び方があることを教えて、何がうれしいのか、どうして悲しいのかを、自分で言葉として表現できるように教えていた。
それから韻を踏む言葉遊びをよくやっていた。katt(猫)とhatt(帽子)、bok(本)とlok(機関車)といった言葉の後半の母音・子音とリズムが似た言葉だ。単語の発音を子どもに意識させたり、ボキャブラリーを増やしたりしていく上で役立つそうだ。
そういえば、スウェーデンでは絵本にある物語でも歌の歌詞でも、よく見たり聞いたりするとリズミカルに韻を踏んでいるものがたくさんある。
また、毎日必ず1回は外遊びをさせていた。保育所の周りにはフェンスで囲まれた大きな庭が広がり、滑り台やブランコ、砂場などの遊具がある。
スウェーデンでは土砂降りの雨が降ることはまれで、降るときはたいてい小雨程度なので、雨が降っても外で遊ばせていた。
冬も同様で、寒くても気温がマイナス10度を下回らない限りは厚手のオーバーオールと冬用ブーツを着せて遊ばせていた。
週に一度は森や公園に遠足

週に少なくとも一度は、近くの森や公園に遠足に出かけていた。私たちの住む住宅地周辺にはたくさんの公園や森、草原が広がっている。自然の中で花木や虫、鳥を観察しながら四季の移り変わりを感じたり、のびのびと遊んだりする。
「自然教育」とか「環境教育」などと大々的に銘打っているわけではないが、身近にある自然を教材にしながら自然の大切さや面白さを学ばせていた。森や公園の所定の場所で火をおこして、ソーセージを焼いてランチを食べることもあった。
遠足の次の日は、遠足で見たものを教室でみんなと確認したり、本で調べたり、拾ってきた枝や葉っぱで工作をしたりしていた。
息子はそのようなやり取りの中で鳥の名前をたくさん覚えたらしく、私と一緒に散歩しているときも「あの鳥はsädesärla(タイリクハクセキレイ)っていうんだよ」「あっちの黒い鳥はkoltrast(クロウタドリ)だよ」と私に教えてくれるくらい、いつの間にか鳥に詳しくなっていた。
保育園教諭と保育士の違い
スウェーデンの保育所では、子どもの教育に直接携わる職種として、保育園教諭と保育士の2種類がある。
保育園教諭は全体の学習計画を立ててそれに基づいた教育を主導する役割を持ち、3年の大学課程を修了して資格を得る。
一方で、保育士は保育園教諭を補佐する役割を担っており、資格はないものの高校や自治体などが提供する成人向け高校の教育課程で学ぶのが望ましいとされている。
このように職種に違いはあるものの、現場で子どもたちと日常的に接する役目であることに変わりはなく、日々協力しながら仕事をしている。
職員が休んだときのための臨時保育士
私たちは2つの保育所を経験したが、どちらもクラスが5つあり、1クラスが20~23人ほど。3歳以下だと1クラスの子どもの数が12人くらいだろうか。
1つのクラスを保育園教諭と保育士合わせて3人が担当しており、日中の活動では基本的にはその3人がついている。
保育所は朝7時から夕方17時まで開いており、出勤が早い家庭では、保育所で子どもに朝食を食べさせることができる。ただ、早朝と夕方の時間帯は子どもの数が少ないので、複数のクラスをまとめることで必要な人員数を減らしていた。
朝早くから勤務を始めた職員は早めに仕事を終え、遅く始めた人は最後までいるというようなシフトだ。
また、正規の教諭や保育士が自身の病気や子どもの看病で休んだときのために臨時保育士が登録されており、特に風邪がはやる季節にはそのような臨時保育士が穴埋めをしていた。
スウェーデンの保育所で聞かれる親からの不満
一般的に保育所に対する不満として親からよく聞かれるのは、子どもを夕方迎えに行っても別のクラスの教諭・保育士か臨時の保育士だけしかおらず、その日の子どもの様子がどうだったのか、尋ねてもよく分からないというものだ。
だから、私たちの保育所も情報の引き継ぎには気を使っていたように感じた。
また、教諭・保育士の中にはスウェーデン語が流ちょうではない人もいるが、子どもがスウェーデン語をきちんと学べるように、息子の保育所では1つのクラスに2人はスウェーデン語を母国語とする、あるいはネイティブ並みに話せる保育士を配置させていた。
私たちの息子は2つ目の市立保育所に4年間通い、23年6月に無事卒園した。新型コロナウイルス禍の混乱した時期もあったが、しっかりと息子の保育と教育をしてくれ、息子も仲の良い友達やたくさんの楽しい思い出ができたようだ。
佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』(日経BP)
子育てしやすい国として知られるスウェーデン。しかし、実は30年前は子育てしながら働くための制度は整いつつあるものの「男性が働き、子育ては女性がするもの」という男女の性別分業が根深く残っていました。
そんなスウェーデンの社会はどのように変化してきたのでしょう?
現在のスウェーデン人の共働き子育てスタイルについて、スウェーデンに25年にわたって暮らす日本人データサイエンティストが、自身の子育て経験も交えて解説。
日本人が「無理しすぎず」共働き子育てをする手掛かりがつかめるはずです。