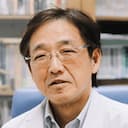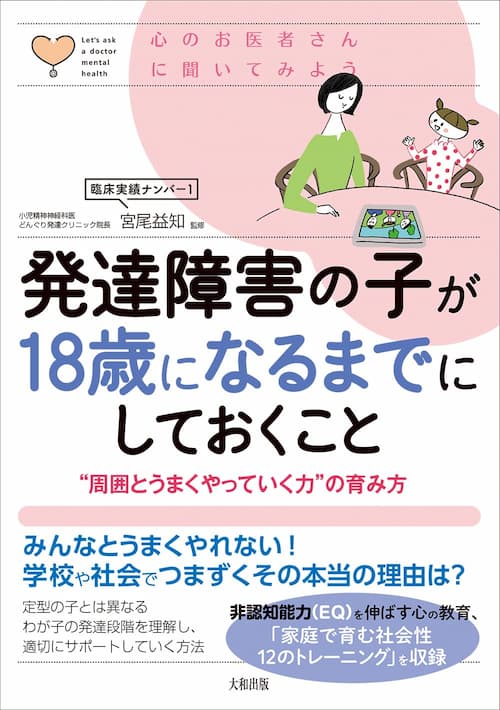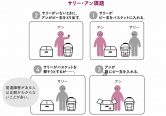子どもの「できない」原因が発達障害だと分かったら 親子の傷を癒やすための言葉
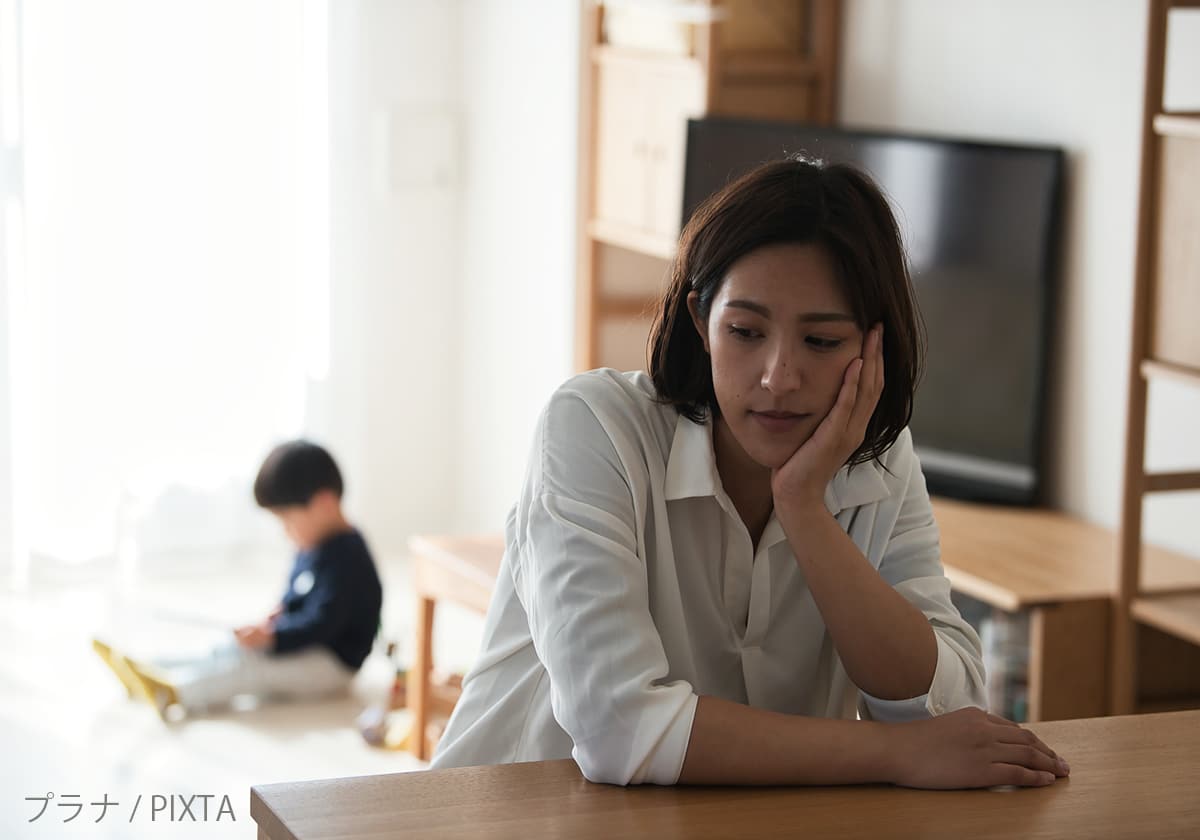
「どうしてできないの?」と厳しく接していたら、のちに子どもの発達障害が判明した……というケースは少なくありません。
子どもにかけた言葉はなかったことにできません。しかし、子どもとの関係を修復し、よい関係を築くためにできることはあります。 その具体的なプロセスを、書籍『発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと』よりご紹介します。
※本稿は、 宮尾益知著「発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと」(大和出版)から一部抜粋・編集したものです。
もし親が誤った対応をし、 信頼の基盤が壊れていたら
子どもに発達の問題があることになかなか気づけない親御さんもたくさんいます。「みんなと同じようにできない」と子どもを厳しく叱りつづけ、その結果として自己有能感がもてなくなるということも。
間違った対応をしていたら、子どもに謝罪と説明を

とくにADHDの子の場合、落ち着きがなく、片づけられない、忘れものや遅刻をしてしまう、勝手に行動する……といった行動が見られます。「なぜこんなことをするの?」「何度も言っているのにどうしてできないの?」と声を荒らげてしまいたくなるのも無理はありません。
でも、特性が招く行動なので、子どもが自分だけで改善できるものではありません。こうしたことがつづき、小学校中学年くらいになると、自分を「ダメな子」「できない子」と言うようになります。
発達障害である、またその傾向があるとわかったときに、「知らずに叱ってばかりいた……」「とりかえしのつかないことをした」と、いままでの育て方を後悔する親御さんが多くいます。子どもとの関係を修復し、よい関係を築くにはどうすればよいのか、相談に来る方もいます。
ひとつの方法は、「親が謝って言語的に理解させる」ことです。してしまったことを「なかったこと」にはできません。言葉による説明と謝罪で、子どものなかのわるい記憶を上書きするのです。
「あなたによかれと思ってやってしまったけど、あなたの特性や心を考えていなかった。私が間違っていたことがわかった」と、自分の非を認め、そのうえで、「私はあなたのことを本当に愛している。あのときは、そうするのがあなたにとってよいと思っていた。私の思いはわかってほしい」と、その行為の意味を説明します。
怒鳴られたという身体的記憶はもう書き換えられません。でも言語的に理解させ、その意味を上書きすることはできるかもしれません。
本人も自分の言葉で親に伝える

親だけでなく、子ども自身が自分の思いを言葉で明らかにして親に伝えることも大事です。
ADHDの場合、認知特性から記憶を鮮明に記憶していることがあります。親に対してネガティブな感情をもつできごとがあるなら、それを自分の言葉で話してもらいます。親はそれを否定せず、まず本人の思いをただ聞いてまるごと受けとめてください。子どもがすべての思いを吐き出したら、親はそれについて誠実に謝罪し、自分の思いを伝えます。
子どもは自分の思いを伝えられると、満足感や達成感が生まれます。それがあって初めて親の思いを冷静に聞く気持ちになれます。
発達障害の家族関係の治療を行っていると、当事者から「親も苦しかったんだ。私と同じ思いを子ども時代にしていたんだ。だから私を見ると過去の自分を見るようでつらかったんだとわかり、親を許す気持ちになった」という声を聞くことがあります。親子間でこうしたやりとりをするのは、困難なことかもしれません。主治医や第三者があいだに入って行うとよいかもしれません。
ただし、なかには視覚優位という特性をもつ子もいます。視覚優位の子は記憶が映像として鮮明に残ることがあります。そうなると、過去の記憶がまるでいま起きているように感じるタイムスリップ現象が起き、生々しい感情が呼び起こされて苦しみます。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの症状を引き起こすこともあります。そのときは主治医と相談し、発達障害とは別に専門の治療を受けるケースもあります。
発達障害の子が18歳になるまでにしておくこと (大和出版)
ASD、ギフテッド、ADHD…、それぞれ異なる発達段階がある。定型に合わせるのではなく、自分を理解し、好きになり、周囲とうまくやっていく――。社会性を育むために、発達の段階を踏まえてわが子をサポートしていく方法。