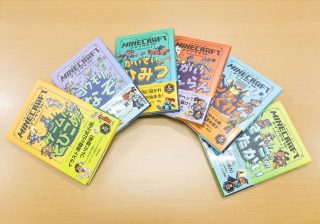偏差値38からの大逆転で「まさか受かるとは思わなかった」 親も驚いた息子の“中受“への情熱
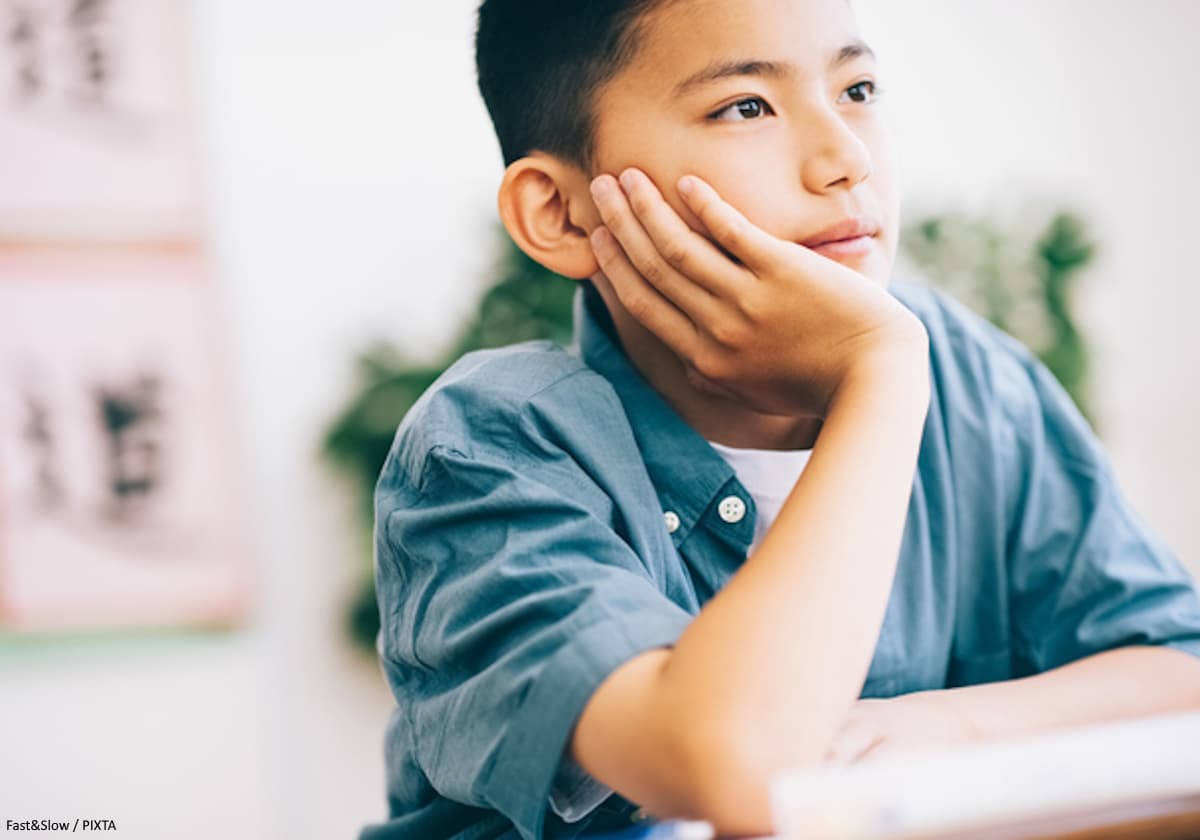
最近は、都立中高一貫校志望者の滑り止め校としての役割を担おうとする私立もある。これらの多くの学校では、適性検査型入試を導入している。偏差値だけを見れば、中堅から下という学校が多いため、“肩慣らし“のために受けるという人が多いのが実情だ。とはいえ、都立に落ちて、こちらに入学する子もいる。ある学校の関係者は「適性検査型入試でうちに入った生徒をみると、入学後によい成績を取る子が多い」と漏らしていた。それだけ力がある生徒が多く、積極的に取りたいということだ。
村田夫妻のモヤモヤした気分はしばらくしても収まらなかった。温子さんがたまらず塾に話してみると、塾は引きとめてきたという。都立を第一志望にしたまま、近隣で併願できそうな私立中を受けることを勧めてきたのだ。
「ここなら、今の成績で間違いなく受かります」
塾の担当者はそう語りかけたが、夫妻は「そんな保証はどこにもない」と感じていた。
そこで、他の意見も聞いてみようと、当初候補から外した早稲田アカデミーを訪れた。
突きつけられたのは厳しい現実だった。1年とはいえ、中学受験の準備はしてきた。近くの大学付属校はどうだろうと、希望を伝えると、応対した講師から「今からでは厳しいです」という言葉が返ってきたのだ。
この講師の話では、都立中高一貫校と私立の受験では、取り組む勉強が違うという。すでに6年生クラスともなれば「理科と社会が追いつかない」というのが担当者の意見だった。となるとますます、都立に落ちたときのことが不安になる。その気持ちを正直に、通塾中のエナの塾長に話すと、なんとこれまでの担当者とはまったく違う答えが返ってきた。
「翔馬君の場合、正直、私立の入試のほうが向いていると思います」
適性検査型入試では答えだけでなく、答えを求めるプロセスにも重きがおかれる問題がある。だが、私立入試の場合、答えだけを書かせる学校も多くある。翔馬君は授業でも、
「どうやったら簡単にこの答えを導きだせるのかを教えて欲しい」
と聞くことが多いため、答えだけを書かせ、スピードを求められるような入試の学校のほうが向いているのではないかというのが、塾長の考えだった
だが、今の塾では私立に向けての対策をすることは難しいと判断。6年生の5月、村田家は思い切って私立にも対応できる早稲田アカデミーへの転塾を決めた。
“厳しい“と聞いていた言葉のとおり、転塾後の成績は散々なものだった。転塾後の最初の模擬試験の結果はどの教科も目を疑う数字が並んだ。偏差値は38、成績順で決まるクラス分けではいちばん下のクラスとなった。
「こんなに厳しい道なのかと、正直驚きました」(慎吾さん)

しかし、本人は前向きだった。父親から「お前は私立の入試に向いている」と言われると、「自分でもそう思う」と、志望校選びを進んでするようになっていった。
覚悟していた“塾弁“も始まった。温子さんの両親が週に1度は手伝いに来てくれた。それまでも家の掃除を頼んでいたシルバー人材センターの人には、塾弁用にご飯を炊いてもらうことも追加で依頼した。おかずは朝お弁当箱に詰めて冷蔵庫で保存、午後6時半、帰宅した温子さんはシルバーさんがセットしてくれた炊きたてのご飯を弁当箱に詰め、ダッシュで塾に届ける毎日だった。
だが、どうしても間に合わずにコンビニで買った食事を届けたこともある。
「働いていると大変ですね」
同じ塾に通わせる専業主婦の母親が、ねぎらいのつもりでかけたであろう言葉も、かえって温子さんを憂鬱にさせた。「共働きだからって、侘しい思いはさせたくない」できるかぎり、手作りのお弁当を届けるように頑張った。厳しい夏の講習を乗り切ると、塾のクラスも上がり始めた。そんな中、翔馬君が志望校として提示してきたのが、今通う中学校だった。
翔馬君の偏差値はというと、正直まったく届いていなかった。親にしてみれば、無謀な挑戦とも思えたが、2年間勉強を頑張ってきたのは翔馬君だ。本人の希望を通し、この学校を含め、出願校を決めた。
目標が定まってからの翔馬君はそれまで以上に頑張った。学校から帰宅するとすぐに塾に向かい、受講のない日も夜10時近くまで自習室で勉強した。
しかし、親としては不安だった。本人が本命に据えた学校は偏差値50台後半。6年生の5月に偏差値38だったわが子の成績、この頃少し上がってきているとはいえ手は届きそうにない。
現実的に受かりそうな別の学校も視野に入れて、1月入試の大宮開成中学校を含め、6校に願書を出して、入試本番を迎えた。初日の大宮開成は無事合格、その後、親はここが本命校と思っていた明治大学の付属校も合格する。これで十分、両親はそう思っていたが、息子からは頼もしい言葉が返ってきた。
「俺、本気で第一志望に合格しようと思ってるから、ここでつまずくわけないじゃん」
両親は“難しいだろうな“と心の中では思っていた。悔し涙を見る覚悟をしつつ「そうだね」と頷き、息子の背中を見守るしかなかった。
いよいよ第一志望校の受験当日がやってきた。会場から出てきた翔馬君の顔は、それほど明るいものではなかった。
「できたと思うけれど、今までの学校ほど、“できた“という自信がない……」
弱気な言葉を漏らすのは初めてだった。第一志望校は“憧れ校“だ。落ちても無理もない。落ちたときにどう声をかけようか、本人には悟られぬように、両親はそんなことを考えていた。そして、迎えた合格発表。そこにはなんと、翔馬君の番号が書かれていた。
「受かった!」
まだまだ小さいと思っていた息子の背中が大きく見えた瞬間だった。受験後、翔馬君の部屋から出てきたのは、冬期講習中、毎日頭に巻いていたハチマキだった。
「絶対合格するぞ!」
翔馬君の力強い文字を見た両親の頰に涙がつたった。
「こんなに強く思っていたなんて、ぜんぜん知りませんでした」
振り返って話す父親の慎吾さんの目は、涙でにじんでいた。自分の可能性を信じて勉強を続けた翔馬君と、無謀と思える挑戦にも、出すぎることなく後ろから支えた両親。第一志望校の合格は間違いなく、3人で勝ちとった合格だろう。
「こうやって親を乗り越えていくんですね」
努力が無駄にならないという経験はおそらく、翔馬君にとって、一生の宝となることだろう。

宮本さおり著『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)
急増する中学受験生、「全落ち」などの厳しい現実…。
「合格体験記」には書かれないドラマを追って、15組の親子を取材したノンフィクション。
首都圏の中学受験者数は2023年、過去最高を記録した。東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県では、18パーセントの子どもたちが受験を経験し、熱は地方にも波及している。中・高一貫校への人気が高まり、子どものために移住するケースもみられる。一方、第一志望校に合格する子どもの数はわずか3割。負け戦とわかっていても中学受験へと向かわずにはいられない親子。まだ幼さの残る小学生の彼らが立ち向かう受験という魔物。
「全落ち」を経験する子どもは立ち直れるのか? 親のエゴや塾の実績づくりで志望校を決めていいのか? 偏差値では測れない、子どもに合った学校とは? 中学受験に挑んだ親子を5年間追い続けたルポルタージュには、きれい事では終わらない中学受験のリアルがある。