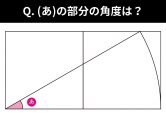「慶応以外認めない親」に耐えかね、入試当日に受験拒否…大人になった今思うことは

「一族みんな慶應」という家に生まれ育ち、当たり前のように慶應への入学を両親から期待された明子さん。自分の意志と関係なく始まった受験勉強の中で、違和感がぬぐい切れない日々を送ります。
親の望みで始まった中学受験の、その先に待っていた結末とは?
ジャーナリストの宮本さおりさんが取材した、中受当事者の生の声をご紹介します。
※本稿は宮本さおり著『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)から一部抜粋・編集したものです。
一族みんな慶應という家に生まれてしまった少女
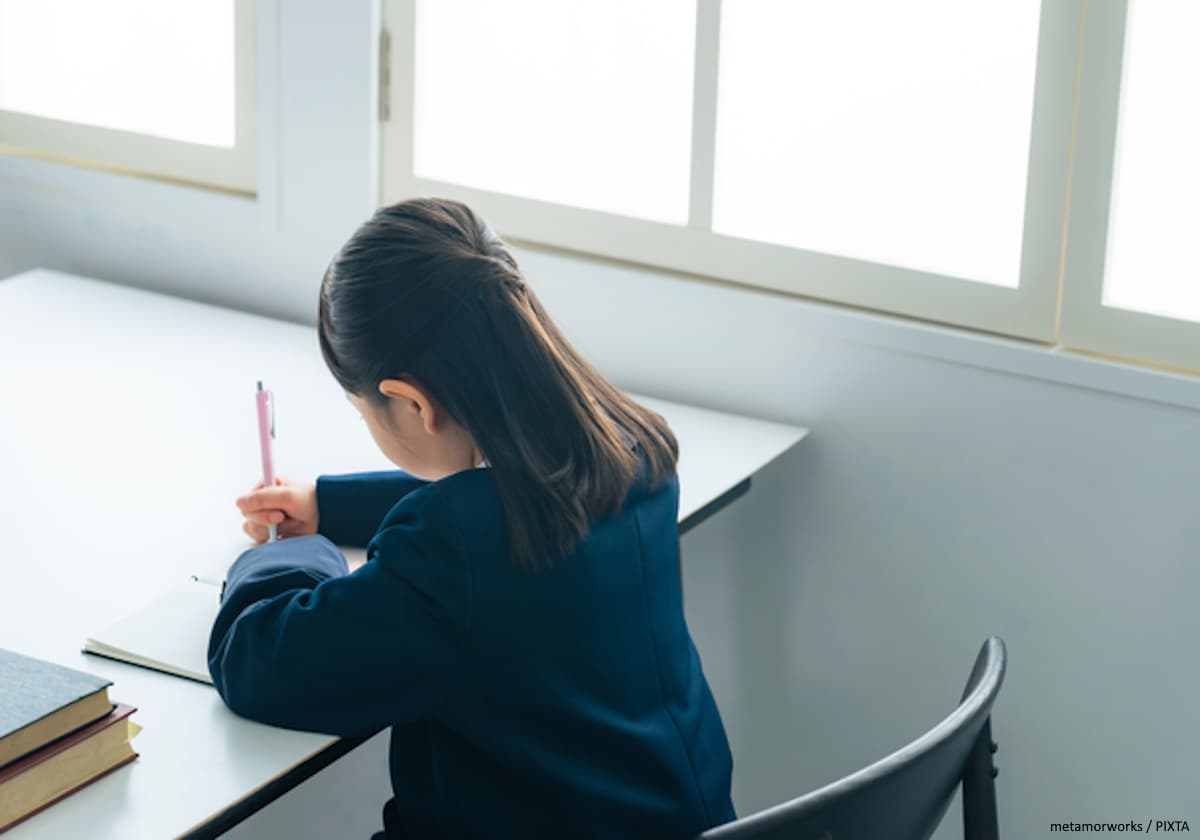
「大人になってからの人脈の広がりもありますから、入学できた人にとっては幸福なのだと思いますが、私はそこには行けなかった側なので……」
そう話してくれたのは、両親、兄、父方の祖父、いとこまで、そろいもそろって全員が慶應義塾幼稚舎(小学校)から慶應義塾大学への持ち上がりだという島崎明子さん(仮名・当時 30代)。一族みんな慶應出身の彼女には、そもそも受験以外の選択肢は用意されていなかった。小学校受験で不合格となっても中学受験で志望校を選ぶ余地はなく、これが波乱の青春時代の幕開けとなる。
塾通いが始まったのはもちろん幼稚園の頃だった。2歳上の兄も幼稚舎を受験、なんなく合格して入学したため、明子さんの母親は、なんの疑問もなく明子さんを小学校受験のための「お教室」へと入れたのだ。
「兄とまったく同じ幼稚園と塾に通いました。幼稚園を選んだ基準はおそらく、小学校受験をする子が多い幼稚園だったからだと思います」
毎週連れて行かれるお教室では、自分の描いた絵を使い、物語を発表したり、工作をしたりといったお稽古が繰り広げられていた。活発に手を上げ、ハキハキと楽しそうに発言していく子どもがいる中、明子さんはというと、まったく面白さを感じなかった。
「人前で話すとか、そういうことがとにかく苦手なタイプでした。小学校受験には向いていなかったと思います」
早生まれの明子さんは小柄で、幼稚園ではいつも友達から赤ちゃん扱いを受け、おままごとで遊ぶときなども、役を率先して決めるようなリーダータイプではなかった。
「兄は私とは正反対の性格で、何でもキビキビとやっていける子でした。だから、私は幼稚舎に落ちて当然だったと思います」
卒業生の家族は合格しやすいなどという噂も聞くが、明子さんのケースをみるに、噂は噂でしかないなと思わされる。
「幼稚舎以外の学校なんてありえない」
そう考えていた両親が小学校受験の志望校に据えたのはもちろん幼稚舎だけだった。
「まさか落ちるとは思っていなかったのだと思います」
ところが結果は不合格。父方の家系では祖母を除いて一族で唯一、公立の小学校に進むことになった明子さん。親族が集まる席で慶應にまつわる話が出ないときはなかった。
“私だけが幼稚舎出身ではない“。いつからか、疎外感のようなものを抱くようになったという。そして、その後も両親の「慶應に」という思いは続いていった。「慶應」という世界で育ち、その教育の素晴らしさを感じていたからだろうが、それが明子さんにしてみれば、重荷でしかなかったのだ。
「次は中学受験で入ればいい」 という両親の考えで、再び通塾を始める。受験前に通っていたのは地元の子が多く通う塾だった。
「実は一度転塾をしました。塾については親から何か言われることはなかったんです。大手の塾に通っていたのですが、地元の塾のほうが学校の友達がたくさんいたので、私の希望で転塾しました。多分、慶應に入れるのならば親はどこの塾でもよかったんだと思います」
集団指導とは別に個別指導も受けていたが、成績は伸び悩み、とうとう最後まで慶應を受けられるレベルには達しなかった。
「6年生の時点で偏差値的に10くらい開きがありましたから、どう考えても無理だろうと。でも、親は慶應しか頭になくて、兄が通っていたこともありますが、文化祭などの見学は慶應しか連れて行ってくれませんでした」
受かるわけがない受験をなぜまたしなければならないのか、学校見学に連れて行かれても明子さんの心の中は複雑だった。自分の希望する学校がないままで迎えた出願校決定時期、明子さんは、
「慶應は受けない」
と自分の意思を口にするようになっていた。
「母は取り合いませんでしたね。塾の先生にも私に慶應を受けるように勧めてくれと頼んでいたようでした」

偏差値も気持ちも乗らないまま中学受験は始まった。今回は滑り止めの学校も用意された。
「滑り止めの学校を決めたのもすべて母だったと記憶しています。塾が勧めてくれた学校の中から選んだのだと思いますが、見学に行ったのは1校だけだった気がします。おそらく、滑り止めも慶應大学に入学する人数が多い学校を選んだのだと思います」
親はしきりに「慶應に」と言うけれど、いくら勉強してもそこには届かないやるせなさ。通塾や個人指導などお金をかけての教育は十分すぎるほど与えられたが、本人の気持ちはまったく乗らない。それよりも、むしろ親の期待に応えることができないという気持ちばかりが増していた。
「よく、“家ではお父さんが一緒に問題を解いてくれました“というような受験エピソードを見かけますけど、うちはそんなサポートはまったくなかったです。なにせ両親は幼稚舎出身で小学校のお受験以外の受験経験はありませんから」
モヤモヤした気持ちを引きずりながら慶應義塾中等部の入試当日を迎えた。
「私、受験しないから」
朝起きた明子さんは、なんと受験をエスケープ、ランドセルを背負いそのまま小学校に登校したのだった。
「名前を書くだけでもいいから受けに行って」
懇願する母親の声を背に、明子さんは、
「名前を書いただけで合格できるとでもいうの? 何のために行くのよ!」
と言い放ち、玄関から出て行った。
結局、合格をもらっていた滑り止めの学校に入学を決めた。
中学受験が終われば受験に追われずほっとできる─。
そう思った明子さんのそんな気持ちは、またしても打ち砕かれる。そこは人気の難関女子校で、慶應大学も十分に目指せるレベルの進学校だったのだ。コツコツ勉強できる子にはとてもフィットする学校だ。だが、これで受験は終わりで小休止できると思って中学受験を終えた明子さんにとっては過酷な学校生活のスタートとなる。