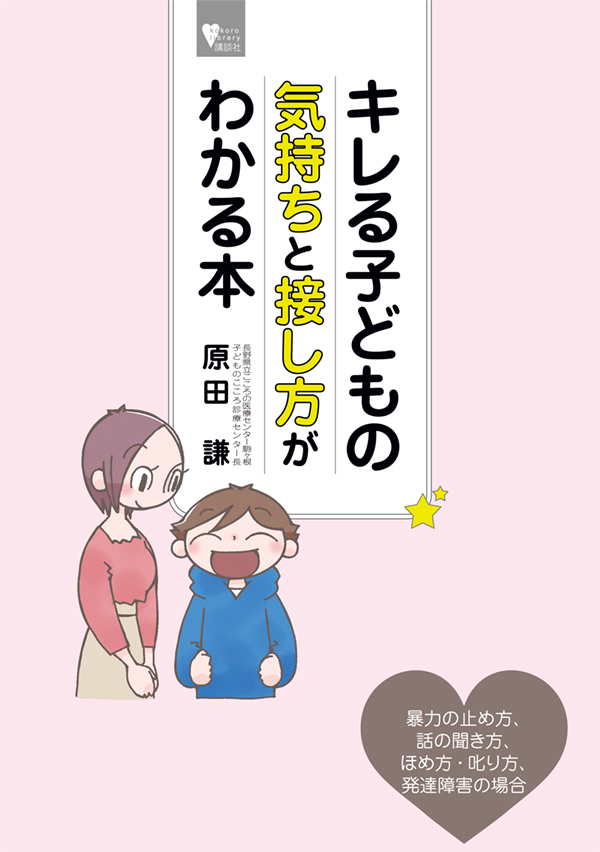子どもの暴力はどこからが問題? 専門家に相談する前に知っておきたいこと

今、多くの親御さんが「キレる子ども」の悩みを抱えています。エスカレートすると、やがて暴力へと発展してしまうことも。悩みが深刻な場合、どのタイミングで専門家に相談すべきなのでしょうか? また、相談するときに気をつけるべきポイントは?
『キレる子どもの気持ちと接し方がわかる本』(講談社)の著者で、児童精神科医の原田謙先生に、子どもの暴力への向き合いかたについてお話を伺いました。
キレる子の暴力 深刻なのは?

――子どものキレ方がエスカレートすると、家族や友達に暴力をふるうこともあると思います。そうなる前に、周りの大人が気付くべきサインはありますか?
おとなしかった子が突然キレるようになるパターンもあるにはあるんですが、そんなに多くないんですよね。暴力的だったり反抗的だったりする態度は、小さい頃から徐々に積み重なってきていることが多いです。突然何かが起こるのではなく、だんだんエスカレートしていくケースがほとんどです。
年齢が上がると、行動が派手になったりすることはありますが、子どもの性格や質は急に変わるわけではありません。
――未就学児だと、思い通りにならないと泣いたり、かんしゃくを起こす子も多いですが、年齢が上がれば落ち着くのでしょうか?それとも、エスカレートする可能性もあるのでしょうか?
世間で言われる「イヤイヤ期」などは、自我が育ち始める時期です。だんだんいろいろなことを言うようになり、感情を表現することが増えますよね。
学校に上がる前の年齢であれば、例えば下の子を押したり、親を蹴飛ばしたりすることがあっても、それは問題ないことが多いです。その年齢では、気持ちを上手に表現できず、他の子どもを叩いてしまうこともありますからね。
――小学校に上がってしばらくしても友達を叩いてしまう場合は、注意したほうがいいですか?
例えば、学校で子どもが先生などの大人に対して暴力を振るうようなことがあれば、注意して見守る必要がありますね。友達への暴力については、どのくらい頻繁に起こるかが大切なポイントです。頻繁に叩いてしまうようであれば、少し深刻に考えたほうがいいかもしれません。
家の中での問題より、学校など社会の中で暴力が出ることのほうが心配です。子どもにも社会性があり、「外ではこうこう振る舞わなきゃいけない」といった考えもあるので、外で暴力が見られる場合は注意深く見守ることが大切です。
もし家の中だけで暴力が見られるなら、まだ少し安心できる部分もありますが、やはり頻度には気をつけたいところです。例えば、毎日のように下の子をいじめるようなことがあれば心配ですが、たまに起こる程度なら様子を見て大丈夫だと思います。
専門家に相談するときのポイントは

――悩みが深刻化し、専門家への相談を検討する親御さんもいると思います。たとえば児童精神科を受診するのに、ベストなタイミングはいつなんでしょうか。
『キレる子どもの気持ちと接し方がわかる本』(講談社)の中で「悩みを抱えた段階ですぐに相談していい」と書きましたが、実際に相談できる場所を見つけるのは難しいこともあると思います。
親御さんはまず学校の先生に相談されると思うのですが、そこで解決しない場合、次はどこに相談すべきか悩みますよね。市町村の子育て相談にハードルの高さを感じる親御さんもいらっしゃると思いますが、児童精神科への相談となるとさらにハードルが上がってしまいます。
医師としては、早い段階で気軽に相談してほしいのですが、ご存じの通り児童精神科は患者さんが殺到しており、初診の待機期間が数ヶ月ということも珍しくありません。そのため、なかなか「気軽に来て」と言いにくいんですね。
タイミングとしては、学校や地域で解決できない場合に、最終的に児童精神科へ相談するという流れが現実的だと思います。
――信頼できる相談先の探し方について、なにかアドバイスがあればぜひお聞かせください。
これはなかなか難しいですね(笑)。私は親御さんに「自分を責めないで」と強くお伝えしたいのですが、時には親御さんに対して厳しい言い方をする専門家もいます。「お母さんのこれが悪い、愛情が足りない」といった短絡的な意見を言う専門家は今は少ないと思いますが、それでも相性が合わない場合、相談したことで逆に親御さんが落ち込んでしまうこともあります。
――相談先との相性が大事ですね。
そうですね。私も相談を受ける時は気をつけています。でも時には、どうしても親御さんのニーズとずれてしまうこともあります。
例えば、不登校の子どもに「学校へ行ってほしい」と考えている親御さんがいる場合、私たちの立場としては、学校に行くことがすべてではないという考え方をすることがあります。それが「先生は子どもを学校に行かせることに協力してくれない」と捉えられ「病院に行く意味がない」と思われてしまったり……。なかなか難しいですね。
ちなみに、皆さんはどうやって病院を探しているのでしょう?
――ネットのレビューなどを参考にしつつも、どこまで信頼していいのか悩んでいる方も多いと思います。
うちの病院も、時々ひどいレビューを書かれることがありますよ(笑)。でも、今は結局、ネットのレビューが主流ですよね。病院の公式サイトにはいいことしか書いていませんから。
もし実際にその病院に行った方から直接話を聞けるなら、それがベストかもしれませんね。信頼できる相談先探しについては、知人の口コミが一番頼りになると思います。
――いざ児童精神科を受診する際に、親が事前に準備しておいた方がいい事や、特に伝えるべき重要な情報があったら教えていただけますか。
特に「これを用意しなければならない」というものはありませんが、小さい頃から現在に至るまでの経過や、相談に至った経緯について質問させていただきたいです。たとえば、どんな家庭環境で育ってきたのか、子どもの心が傷つくような大きな出来事はなかったか、きょうだいが生まれたときにどんな反応を示したかなどです。
また、子どもが困ったり苦しかったときに、親にどのように話を持ち掛け、助けを求めてきたか、つまり「アタッチメント」(愛着)についてもお聞きしたいです。
――ありがとうございます。最後に、この記事を読んでいる方や、先生の著書を手に取られた読者の方に、メッセージをいただけますか。
まずは、自分を褒めてあげてほしいです。 日々努力して子どもと向き合って、記事を読んだり、本を手に取って「頑張ろう」と思ってる自分を、褒めてほしいっていうのが一番ですね。
(取材・文:nobico編集部 中野セコリ)