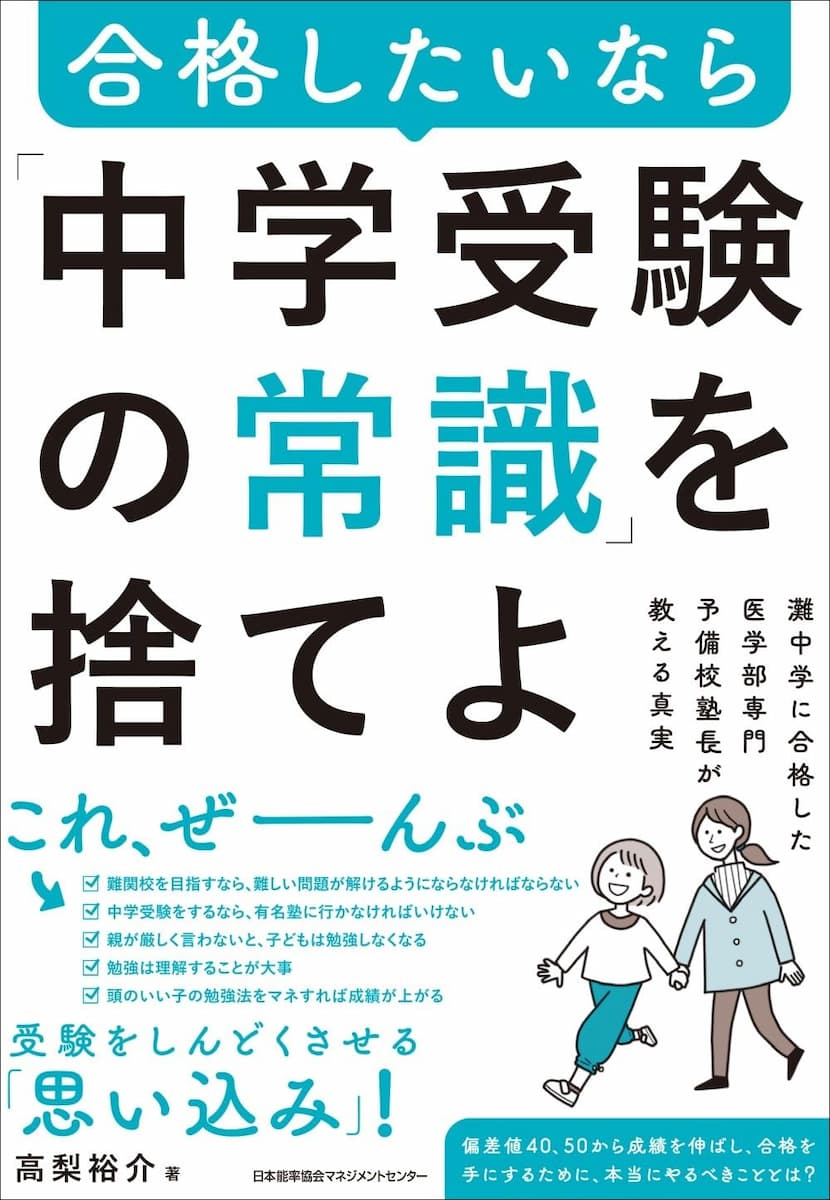「授業をまじめに聞く」だけではNG! 医学部専門予備校の塾長が語る、成績を伸ばす唯一の方法
中学受験
「授業はちゃんと聞いているのに、なぜか成績が伸びない…」 そんな悩みを抱えているなら、“暗記”と“習得”が足りていないのかもしれません。
どれだけ理解しても、試験本番でスラスラ解けなければ意味がありません。成績を伸ばすために本当に必要なのは、知識を“暗記”し、何度も繰り返して“習得”すること。
では、具体的にどんな勉強法が効果的なのか? 本記事では、効率よく知識を定着させる方法と、親ができるサポートのポイントを解説します。
※本稿は、高梨裕介 (著) 『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(日本能率協会マネジメントセンター)から一部抜粋・編集したものです。
×難しい問題が解けるようになることが大事
〇基礎を徹底的に習得することが大事
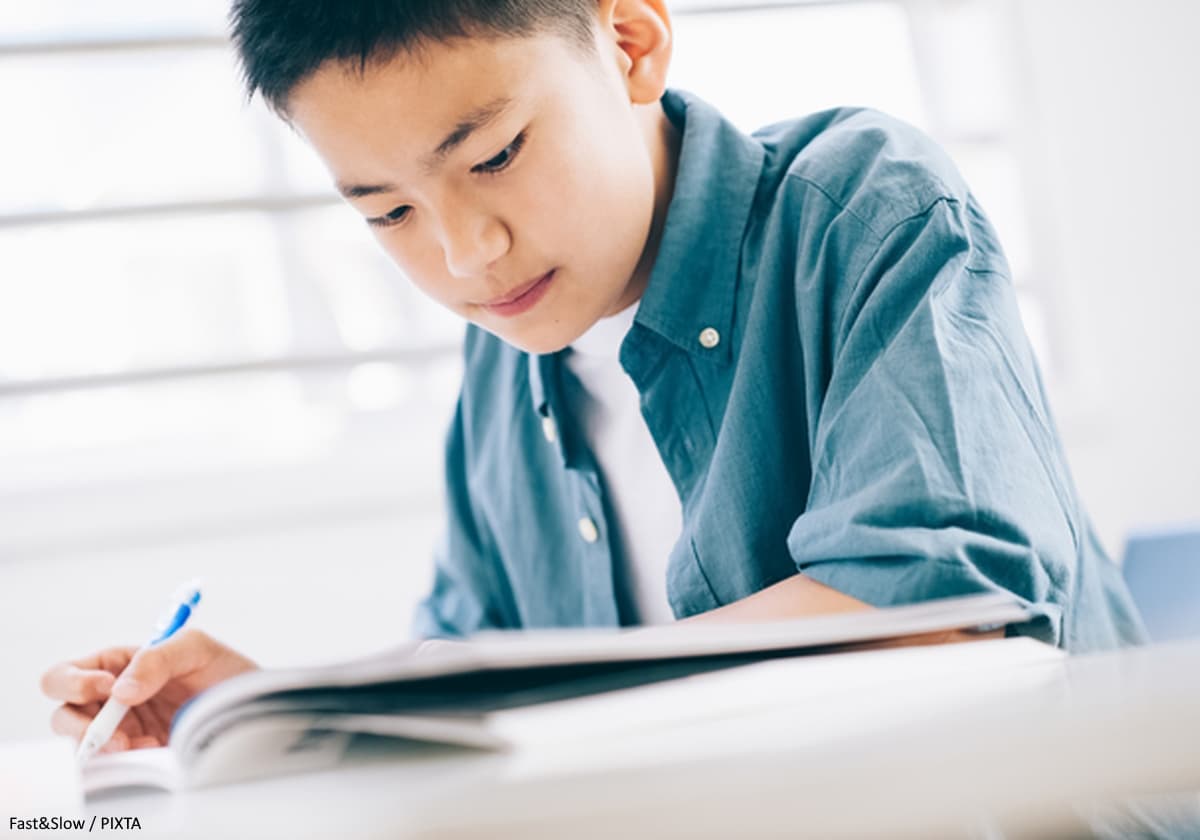
成績を伸ばす唯一の方法は、基礎の習得と暗記です。
しかし、基礎ができていないのにもかかわらず、難しい問題の演習に力を入れてしまい、失敗してしまう受験生がとても多いです。
エースアカデミーでは、数年前から「エースアカデミーこども支援」という企画を実施しています。
夏休みや冬休みなどの長期休みの小中学生を対象に、エースアカデミーの講師である現役の医学生が「無料で勉強を教える」プロジェクト。
オンラインでの指導なので、全国どこからでも参加でき、好評を得ています。
ある親御さんは、お子さんを小学1年生のときから進学塾に入れ、難関中学受験を目指させていました。
その方から、小学3年生の段階で塾では難しい問題を教えていて、それが理解できなくて困っている、というご相談を受けました。
問題を見せてもらうと、たしかに難しく、担当した医学生でも分からないほど。 と同時に、こんな難しい問題を解く必要なんてないのに、と思いました。
それよりも、そもそも基礎はできているのだろうか、そっちのほうが気になり、教科書ワークを勧めてみました。
親御さんとしては、「いまさらそんな基礎問題をやって、本当に効果があるのか」と不思議に思われたはずです。
しかし数日後、その親御さんから連絡が入りました。
「先生、すみません! 私が間違っていました。3年生の教科書ワークをやらせてみたら、あの子、基礎すら全然できていなかったんです」
親御さんとしては衝撃だったことでしょう。
お子さんも「こんなの知っているよ。学校で習ったし」と見下していたところがあったと思います。
でも実際は、それすらできていなかったのです。
この状況は、このお子さんに限ったことではありません。
実は中学受験塾に通う多くの子がこの状態なのです。
基礎すら身についていないのに、難しい問題を解こうとしているのです。
基礎が身についていない状態で難しい問題を解こうとしても、上滑りを起こしてしまい、成績は伸びません。
基礎をきちんと習得することで、はじめて成績は伸びていきます。
ただし、「基礎の習得」は思ったほど簡単なことではありません。
この章では、具体的な勉強方法について解説します。
×基礎学習はラクな勉強
〇基礎の継続はとても大変
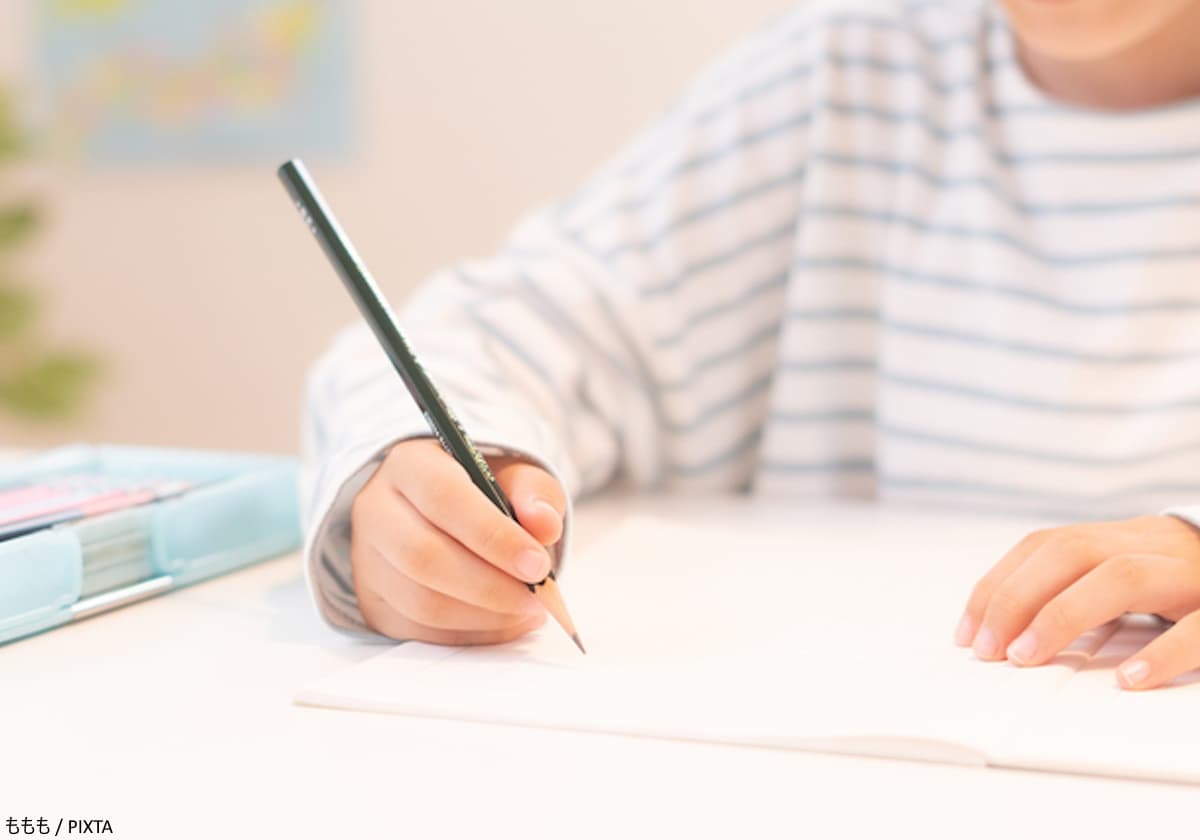
基礎を盤石にするには、どんな学習法が有効なのでしょうか。
私がおすすめするのは、教科書ワークを徹底的に習得することです。
教科書ワークはいろいろな出版社から出ていますが、「基本の解説」→「基本の ワーク」→「練習(応用)のワーク」→「まとめ」の四つで構成されていることがほとんどです。
私がおすすめするのは、解説やまとめが丁寧に書かれている教科書ワークです。
それを読めば、子ども自身でおおよそ理解できるというのが理想です。
教科書ワークを習得するために大事なことは、1冊のワークを何周も繰り返すことです。
教科書ワークは1回やったら終わりではありません。
人間は時間が経つと忘れる生き物です。
そのときは「分かったつもり」でも、少し経ってやってみたら「忘れていた」「抜けていた」なんてことはしょっちゅうあります。
だから、繰り返し取り組む必要があります。
一度やったくらいでは当然忘れてしまうので、2周、3周……と繰り返すことで、ようやく定着するのです。
ここで一つ大事なのが「定着」の定義です。
「定着」の定義は、「テスト中の短い時間で、素早く正確にスラスラ解けること」です。
これができなければ、いくら知識を持っていても正解にはならず、合格することはできません。
だから、何度も覚えて、アウトプットを積み重ねていくことが大事。
基礎学習というと「ラクな勉強」と思っている親御さんは少なくありませんが、実はものすごく大変なことです。
基礎学習は基本的に自分で進めていくしかありません。
それを遊びたい盛りの小学生の子どもが、毎日欠かさず続けるのですから、塾の授業をぼんやり聞いているよりもよっぽど大変なのです。
×理解に時間をかける
〇理解より「暗記」「習得」に時間をかける

学校でも塾でも言えることですが、授業をまじめに聞いている生徒は、「あの子はいつも頑張っている」と高評価を得やすいものです。
また、多くの親御さんはお子さんが難しい問題を前に、ああでもない、こうでもないと考えている様子を見て、「よしよし、ちゃんと勉強しているな」と安心します。
しかし、私からするとこれらの勉強は、めちゃくちゃ「ラクな勉強」だと思います。
なぜなら、授業を受け身で聞き、「勉強しているふう」なパフォーマンスをしているだけに過ぎないからです。
実際に、授業を聞くという勉強方法は、学習効果が非常に低いという研究結果も出ています。
成績を伸ばすために重要なことは、「理解」ではなく、「暗記」と「習得」に時間をかけることです。
では、この「暗記」と「習得」、具体的に何をどうやればよいのか――?
中学受験では「漢字」「植物の種類」「歴史の年号」というように、暗記しなければならない事項が山ほどあります。それらを抜けなく習得することは簡単なことではなく、時間もかかります。
新しい知識をまずは覚える。そして、忘れないように繰り返し復習する。
思考力や記述力が重要のように言われている昨今の中学受験ですが、入試の半分以上の問題はこの暗記で乗り越えられます。
「暗記」を甘く見ず、しっかりと時間を使うことが大切です。
一方、算数や理科の水溶液や重さの問題は、一見「暗記とは別物」のように感じますが、「解法を覚える」という点では同じ「暗記」です。
まず、「こういう問題のときは、この解法で解く」ということを覚える。
そこで、なぜその解き方をするか深掘りさせようとする講師がいますが、私はここで深掘りする必要はないと思っています。
授業で解説を聞いて一時的に「理解したつもり」になったとしても、試験本番で自分の力で解けるようにはなりません。
試験本番に自力で正解するためには、自分で何度も問題を解いて、解法を習得するしかありません。
授業を聞かずとも、問題集を繰り返し解くなかで、「気がついたら解法を選ぶ理由が自力で理解できるようになっていた」というケースがほとんどです。
さらに、入試には制限時間があるため、処理能力を上げること、つまり、短い時間で素早く正確に解く力を身につける必要があります。
塾の授業をなんとなく聞いている子と、自分で問題集を何周も繰り返し習得した子。
どちらの成績が伸びていくかは、ご想像いただけるかと思います。
『灘中学に合格した医学部専門予備校塾長が教える真実 合格したいなら「中学受験の常識」を捨てよ』(高梨裕介 著/日本能率協会マネジメントセンター)
今までの「中学受験の常識」が合格を遠ざけている?!
高偏差値の大学に進学するには幼い頃から中高一貫校に入り、常に難問に挑み続けなければならないと思い込んでいる人が多くいます。
競争を煽る塾、甘やかしは悪とする親、管理至上主義……これらはすべて子どもの生きる力を奪います。
そんな負のスパイラルを断ち切るには、180度の意識改革が必要です。
実際、著者は毎年100 名以上の医学部合格者を輩出する医学部受験の専門予備校「エースアカデミー」を運営していますが、多くの受験生と面談すると、「しんどい」と深刻に悩んでいる相談のうち 6〜7割が親子関係の悩みだということがわかりました。
そこで子どもたちを悩ませる「親」の対応を改善するためには、間違った思い込みを正し、親が実施すべきサポートを体系化して伝える必要があるのでは、と感じるようになりました。
情報過多の現代社会においては、自分の子どもにあった学習方法よりも、世間一般によしとされている学習方法を盲信し、それが唯一の正解だと思い込んでいる親が多いのが現状です。
間違った学習方法や子どもへのかかわり方では、子どもの学力が向上しないばかりか、親からのプレッシャーで長年苦しむ子どもが増えるばかり。
本書では、受験生の親がすべきこと、すべきでないことを確認し、親が強いるのではなく、子ども自らが勉強に取り組むようになる行動変容を促すことで、受験を通して子どもたちが「自分軸」で生きていくベースを築き、かつ確かな学力向上につながる親の考え方と姿勢を提示します。