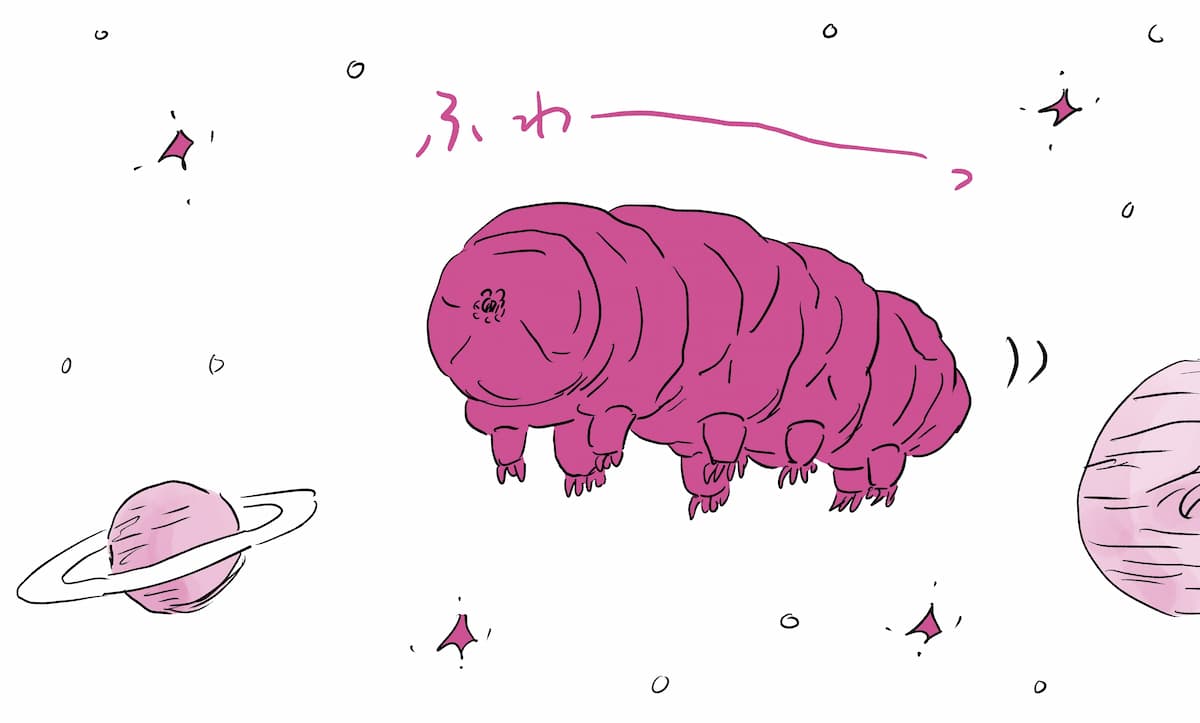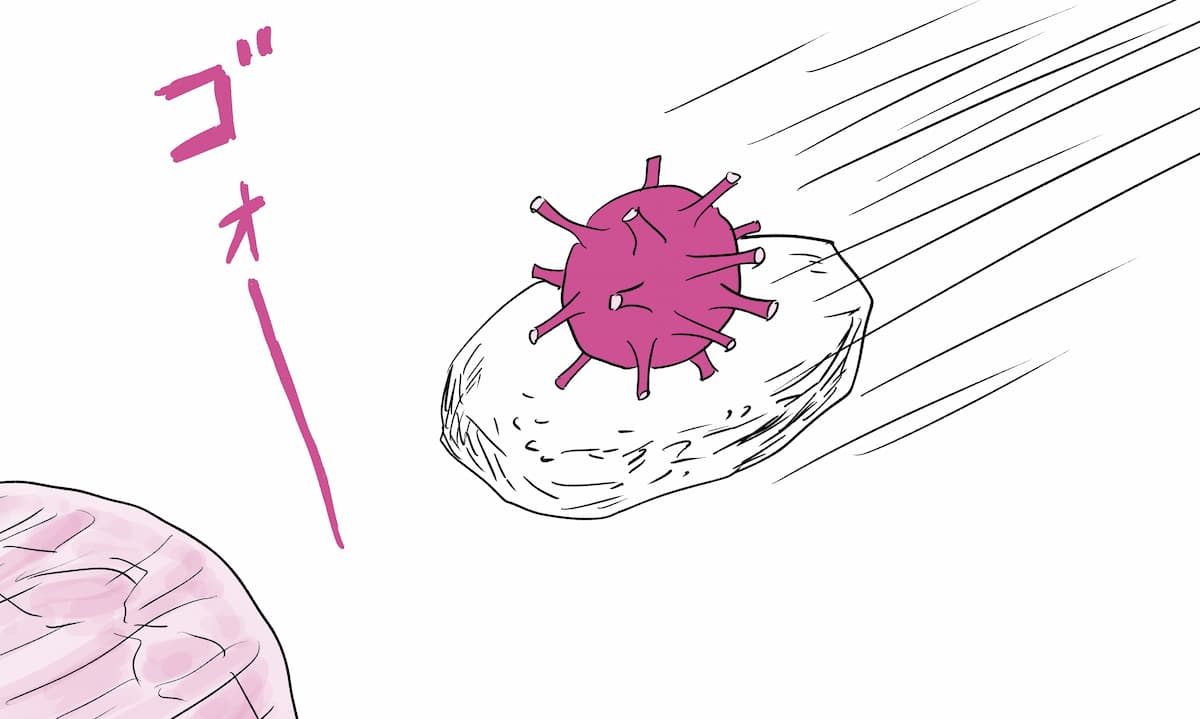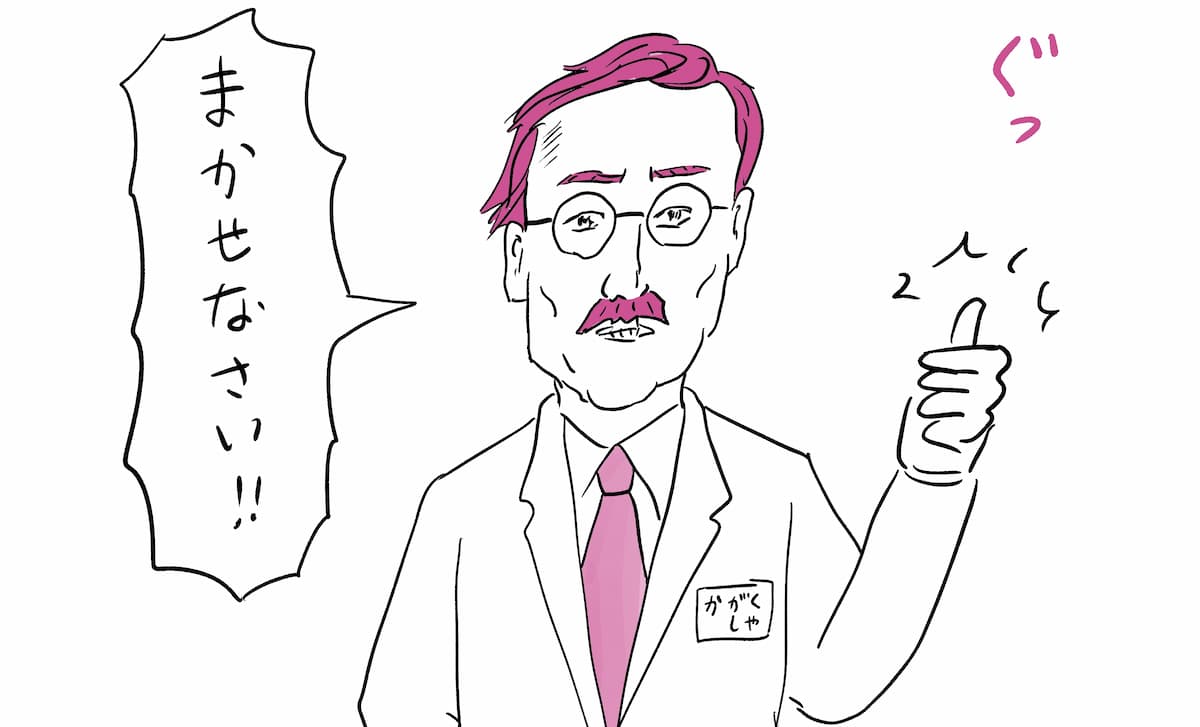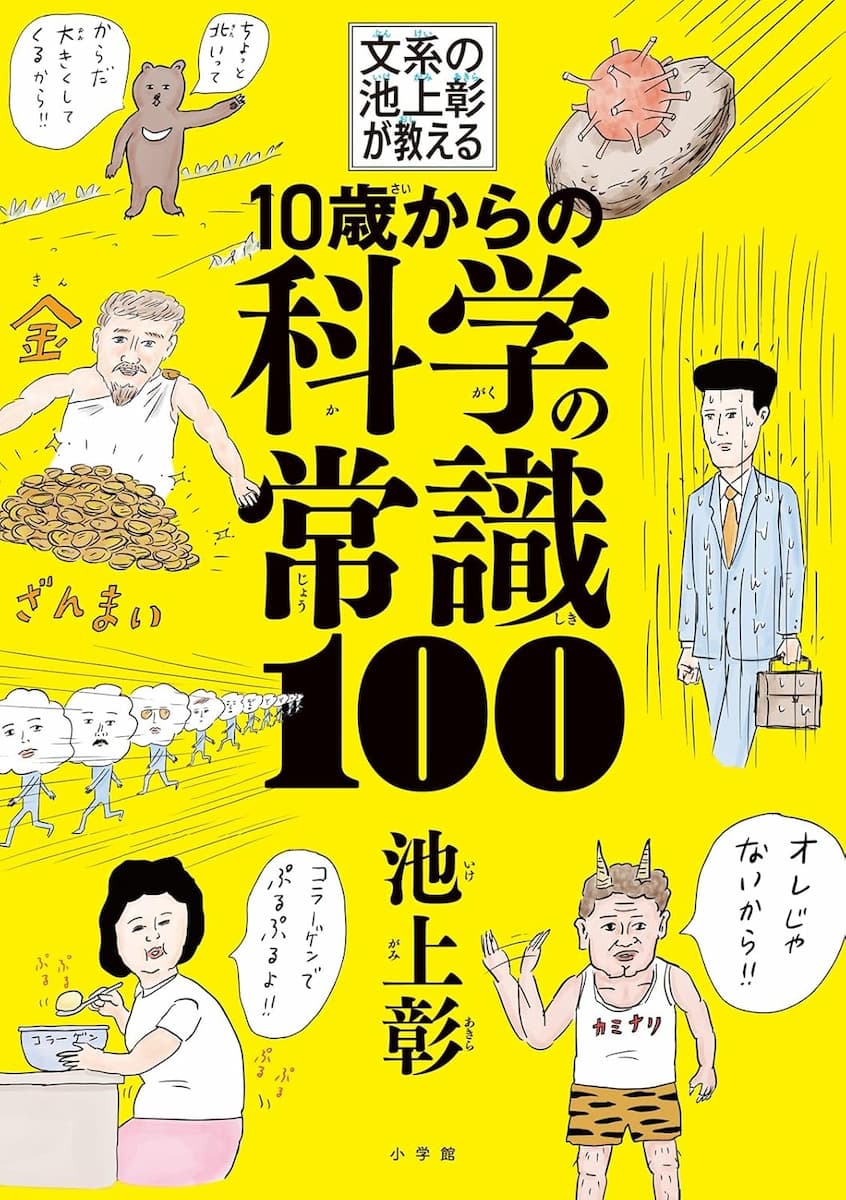コラーゲンを食べても肌はぷるぷるにならない!? 子どもがハマって知識が身につく「生物」クイズ
「コラーゲンを食べると肌がぷるぷるになる」──そう思っている人は多いですが、実はそれは「うそ」! ほかにも、「人間を最も多く殺した生きもの」「宇宙でも生きられる生物」「地球の生命が宇宙から来た可能性」など、生物の世界には驚きの事実がいっぱい! 「生物」を学ぶことで、ただ知識を増やすだけでなく、「本当に正しいことは何か」を考える力が育ちます。楽しく学んで、世の中の意外なしくみを知るきっかけにしませんか?
※本稿は、池上彰・著『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(小学館)から一部抜粋・編集したものです。
イラスト/和田ラヂヲ
生物クイズ1:コラーゲンを食べると肌がぷるぷるになる。本当? うそ?
大人たちが、「コラーゲンを食べたらお肌がぷるぷる」なんていっているのを聞いたことはありませんか? しかし、残念ながら、コラーゲンを食べても肌はぷるぷるになりません。答えは「うそ」です。
コラーゲンとは、人間をふくむ、ほ乳類が体内にもっているタンパク質の一種。タンパク質は、皮ふや筋肉、骨や血管などをつくる上で大切なものです。また、コラーゲンというタンパク質の働きは、体のいろいろな組織を強く保つことです。細胞が新しくなるのをサポートしたり、皮ふに弾力を与えたり、臓器を守ったりします。そのためコラーゲン自体がお肌にいいのは事実です。しかし食べたコラーゲンが直接皮ふに作用することはありません。
コラーゲンを摂取すると、体内で分解されてアミノ酸になります。そのアミノ酸が、体内に必要なタンパク質の材料になるのです。つまり、コラーゲンというタンパク質に組み立てられたブロックおもちゃがあって、それが体内でバラバラのブロック(アミノ酸)になり、そのブロックが新たに組み立てられてさまざまな種類のタンパク質になるのです。新たにできたタンパク質がコラーゲンとは限りません。
つまり、コラーゲンに限らず、食べたタンパク質がそのまま人間の体をつくるわけではなく、一旦アミノ酸に分解されて、体内でつくり出すタンパク質のパーツとして使われるということ。
もし、「コラーゲンをたくさん食べたから肌のつやがよくなった!」という人がいたら、「気のせいですよ」といってあげてください。何事も、過剰摂取には気をつけましょう
生物クイズ2:人間をもっとも多く殺した生きものは何?

①蚊 ②人間 ③クマ
なんだか物騒な質問ですが……。ヒントは、「殺した」というよりも「命をうばうきっかけをつくった」というイメージですね。答えは「①蚊」です。
蚊は、主に亜熱帯・熱帯地域で発生する「マラリア」という病気を運ぶことで、これまで数多くの人間を死にいたらしめました。
マラリアは感染症の一つで、マラリアを運ぶハマダラカという蚊に刺されて感染すると、1〜4週間ほど体内にひそみます。やがて発症すると、発熱や頭痛、吐き気や関節痛などの症状が出て、それがひどくなると死にいたります。
第二次世界大戦のとき、東南アジアの戦地では多くの日本人が亡くなりました。もちろん、戦いの中で命を落とした人もいますが、それ以上に食料不足で餓死した人や、マラリアにかかって亡くなった人の方が多かったとみられています。
蚊は、マラリアだけでなく、ジカ熱やデング熱などの感染症も運びます。蚊による感染症で亡くなる人は、世界で年間約72万5000人もいるといわれています。日本では、2014年にデング熱の感染者が国内で見つかりました。命に関わることもあるので、気をつけたいですね。
蚊の栄養源は、花の蜜などの糖分。人の血を吸うのは産卵をするメスだけです。蚊は、人が発する微量のガスやにおい、体温を感知して近づいてきます。一度に吸うことのできる血は、ほぼ蚊の体重くらいだそう。血を吸うと体重が倍になるので、血を吸った直後は体が重くてフラフラしていることが多いようですよ。
生物クイズ3:宇宙空間でも生きられる生きものは、いる? いない?
宇宙は真空で、生物が生きられる環境にはありません。ですが、生きのびるものがいるのです! 答えは「いる」です!
それは「クマムシ」です。体長1㎜ほどですが、「最強の生物」といわれます。クマムシといっても虫(昆虫)ではありません。分類としては「緩歩動物」というもので、今のところ緩歩動物に属するのはクマムシだけです。水の中やコケのあるところなど湿った場所に生息しているのですが、なぜか泳げず、クマのようにゆっくりと歩いて移動することから緩歩動物となったそう。肉眼では見えません。クマムシは多くの種があり、現在確認されているものだけでも約1200種存在しています。クマムシの最大の特徴は、「乾眠状態」になること。これは「乾いて眠る」という言葉通り、水のないところでは、通常85%ほどある体内水分量を3%まで落として乾いた状態になり、みずから代謝を止めて仮死状態になるのです。
その特徴がいかんなく発揮されたのが、宇宙空間。2007年9月、クマムシは人工衛星に乗って宇宙に飛び立ちました。特別につくられたケースに入ったクマムシは、たった一人(?)で宇宙に10日ほど滞在し、見事に地球に生還。宇宙にいる間は乾眠状態で、地球に帰った後は元通りの姿に戻りました。クマムシの多くは、水のない場所で生きることができません。そんなクマムシがどんな状況になっても生きのびるために身につけた能力が乾眠なのです。周囲が乾いてきたら、自分で自分を乾燥させて生命活動を止める。そしてまた水のあるところに行ったら、元に戻る。生きものの力ってすごいですね。
生物クイズ4:地球上の生命は宇宙からやってきた可能性が、ある? ない?
私たち人間のように命ある生きものは、どのように生まれたのでしょうか。
宇宙からやってきたというと、「祖先は宇宙人なの⁉」と思うかもしれませんが、そういう話ではありません。生命の源が宇宙からやってきた可能性があるかどうか、ということで、答えは「ある」です。
生命の源についてのもっとも古い説は、紀元前4世紀ごろ、ギリシャの哲学者アリストテレスによる「自然発生説」です。生命は、どろやごみなどの無生物(生命をもたないもの)から自然に生まれたとする説です。現在の新しい説は「化学パンスペルミア説」といって、生命の元になるものが宇宙から運ばれてきたとする説です。
宇宙空間から落ちてくる物体を「隕石」といいます。1969年にオーストラリアに落下した「マーチソン隕石」を調べたところ、アミノ酸がふくまれていました。アミノ酸は生命をつくるための重要な材料です。
さらに、この隕石にふくまれるアミノ酸は地球上のものとは異なり、宇宙でつくられたものだったのです。宇宙でも、生命活動とは異なる化学反応でアミノ酸が合成される可能性が出てきたのです。また、2020年に宇宙探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」からもち帰った石や砂からもアミノ酸が見つかりました。
これらは、生命の源が宇宙から地球にやってきたという「パンスペルミア説」を支持する証拠の一つといえます。つまり、宇宙が生命の種をまく役割をしている可能性があるのです。
生物クイズ5:遺伝子組換え食品は安全?
①安全ではない ②科学者は安全性を確認している
「遺伝子組換え食品」というと、人工的に手を加えた危険なものという印象があるかもしれません。遺伝子組換え食品は危険だという声高な意見もあり、見極めがむずかしいところでしょう。
私が生命科学の専門家に聞いたところ、「②科学者は安全性を確認している」という答えでした。それには根拠があります。まず、私たちが食べたものは、すべて胃や腸で分解されます。タンパク質はアミノ酸に分解されます。遺伝子組換え食品とは、特定の遺伝子を組換えて特定のタンパク質をつくったものなので、体の中でアミノ酸にまで分解されたら、組換えだろうがそうでなかろうが同じアミノ酸、ということ。食品のパッケージに「遺伝子組換え食品は使用していません」と表示されていることがありますが、食べて消化することについてはどちらでも問題ないのです。
遺伝子組換え食品については、適切な規制の下で販売されており、組換えによってつくられたタンパク質の安全性や、その遺伝子が人体に害を与えないことが、現時点で、世界中の科学者たちによって確認されているのです。
もともと遺伝子組換え食品は、人間にとってプラスになるために開発されたものです。たとえば、トウモロコシの遺伝子を組換えることによって、除草剤に強いトウモロコシをつくりました。それによって、邪魔な雑草を枯らすための除草剤をまいてもトウモロコシは枯れず、無事に育つというわけです。しかし、生態系への影響については、今後も見ていく必要があります。
『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(池上彰 著/小学館)
「朝食を食べる子は学力が高い?」「南海トラフ地震は30年以内に起こる?」「地震雲は科学的根拠がある?」「コラーゲンを食べると肌がぷるぷるに?」
――気になる現代の科学知識を池上彰がスッキリ解説!
文系出身ながら、科学にも強い池上彰が、理系の「むずかしい」を文系にも「わかる!」に変換します。科学的考え方、気象、地学、物理、化学、生物、環境問題…子どもが興味をもつ現代的な7つの科学ジャンルをクイズ形式で楽しく紹介。読むことで、理系ジャンルに強くなるだけでなく、論理的思考も養われ、国際情勢や国内ニュースに対して、自分の頭で深くで考える力が身につきます。