子どもが「平均」から外れると焦る・・・“常識的な親“が陥りがちな思い込みの罠
周りの子とわが子を比べて、つい焦ってしまう…。そんな経験はありませんか? 「子どもが“平均”から外れると不安になる」という気持ちは、多くの親御さんが抱くものです。 しかし、そもそも「平均的な子」とはどのような子なのでしょうか?
本記事では、「平均」や「常識」にとらわれがちな親御さんに向けて、石田勝紀先生の言葉を、著書より抜粋してご紹介します。
※本稿は、石田勝紀著『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(大和書房)から一部抜粋・編集したものです。
「平均」「常識」という言葉の罠 ― 特性のある子、不登校
妊娠すると母子手帳を手にします。そこには身体発育曲線や年齢ごとの平均的な発達の様子が書かれています。するとどうしても自分の子どもと比較すると思います。平均ラインに乗っていれば安心し、外れていると少し不安になったりします。
また、ネットで検索すれば膨大な数の情報が出てきます。そこに書かれている内容は専門的なことから個人の意見まで、またフェイクも交じっています。しかし、見ているうちに書かれていることが常識であると勘違いしてしまう人もいます。
このように平均、常識という呪縛が始まり、いつしかそこから外れていることは悪いことだから正さないといけないと焦りの気持ちが出てきます。しかし、よくよく考えてみると、平均とはすべてのデータを足し算して、データ数で割ると出てくる数字です。例えば、4人のテストの点数が50、50、50 、50だとします。するとこの4人の平均点は(50+50+50+50)÷4=50。平均は50点です。
では4人の点数が0、0、100、100だとしたらどうでしょうか。(0+0+100+100)÷4=50。これも平均は50点です。50点を取った人が1人もいないのに平均としては50点となります。このように、実態としては平均値の人が存在しないにもかかわらず、平均でないと心配になるというのはよく起こる現象です。
また、常識という言葉も怪しい言葉です。道徳的、倫理的に考えることは大切ですが、ときに親は世間の見えない空気感を常識と勘違いすることがあります。例えば、中学受験。
特に首都圏では中学受験が盛んであるように見えます。マスコミでも取り上げられますし、塾の宣伝等を目にすると、中学受験することが当然のような空気が流れています。しかし実態を調べてみると、日本全体で最も受験率および私立中学に進学する割合が高い東京都ですら、20パーセントです。つまり、東京都の80パーセントの小6は公立中学に進学しているということです。中央区、港区は50パーセント近い数字を出していますが、全体では20パーセント程度なのです。ついで、高知県が13パーセント、大阪府や神奈川県では11パーセント程度であり、全国平均では7・7パーセント。全国の10人に9人以上が公立中学に進学しています。 肌感覚とは異なるような印象があります。
もうひとつ事例をあげておきましょう。高齢者が運転する車の事故が多いという印象を持っていませんか。しかし、実際は若者の運転する事故件数の方が圧倒的に多いということが統計データで出ています。また若年者による凶悪事件の件数も年々増えているのではと思う人もいるかもしれませんが、実際は大幅に減っています。このように、自分が認知していることが事実とは異なる「認知バイアス」はたくさんあります。
世間の空気感より大切なこと
子育てにおいても同じです。周囲のお友達と異なるからという理由で我が子を心配することがあります。
例えば、我が子が友達と外で遊ばないことを心配するケースです。子どもが遊びたいと思っていないのだから心配する必要は一切ないのですが、「もっと外で遊んでおいで」とか「友達と遊ぶ約束とかないの?」など余計なことを子どもに言ってしまう場合もあるようです。これは子どもから見たら大きなお世話なのですが、親は「○歳ぐらいの子は外で遊ぶもの」という“常識“にハマってしまっている典型例です。
Mama Café(全国で開催するカフェスタイルの勉強会)でも平均、常識に関わる相談がたびたびあります。不登校や発達障がい(グレーゾーン含め)の相談です。割合はかなり高く、5人のうち1人あるいは2人がそれらの相談であるときもあります。
不登校については、近年増加の一途を辿っており、特に2020年から2023年のコロナ禍で急増しました。少子化にもかかわらず不登校者数が増えているということは、相当の割合となっているということです。不登校は子どもには一ミリも問題はなく、現代の学校教育システムが子どもたちに合っていないという問題であると私は考えています。もちろん、学校に行くのが本来の姿であるので、そこから外れていることで心配になるのは当然のことです。
親世代が子どもの頃はそのような状況ではなかったため、どうしても不登校を受け入れることができず、社会のはみ出し者になってしまうのではないかと強い不安感を抱く人もいます。しかし、学校に行くことが常識である一方で、行かない選択もありということが徐々に“新しい常識“へと変わってきています。
発達に特性がある子の相談もたくさんあります。私は、発達障がいという概念を好まないため、便宜上、説明の際にわかりやすいためその言葉を使うことがありますが、通常は使いません。なぜなら、発達特性は誰にでもあると考えているからです。その特性の幅が広いか狭いかの違いがあり、狭ければ世間の常識内、平均内に収まりますが、そうでなければはみ出ているように見えるというだけの話だと思っています。つまり、その子の特性に合わせて対応すればいいだけであり、無理に平均や常識という枠の中に閉じ込めようとすることは、その子にとって良いことではないのです。
もしかしたら平均、常識の枠に入っている子も、無理して枠に入っているだけかもしれません。そうするとやがてストレスが溜まり、それを解放できないと、いずれどこかで歪みが出ることもあります。
本来、どのような子も平均という枠には収まらず、その子らしい生き方、あり方をしていくことが大切です。その中で、子どもが知らないことは教えてあげます。時には今の常識について話をすることもあるでしょう。しかし、本人が常識通りにやるかどうかはケース・バイ・ケースだと思います。
平均とか常識という言葉は、参考にすることはあっても、それに必ず従わなければならないというものではありません。世間が作った空気感に子どもを合わせると考えるよりも、その子にとって何が望ましいのか、何が成長につながるのかという視点で子育てをされるとよいかと思います。
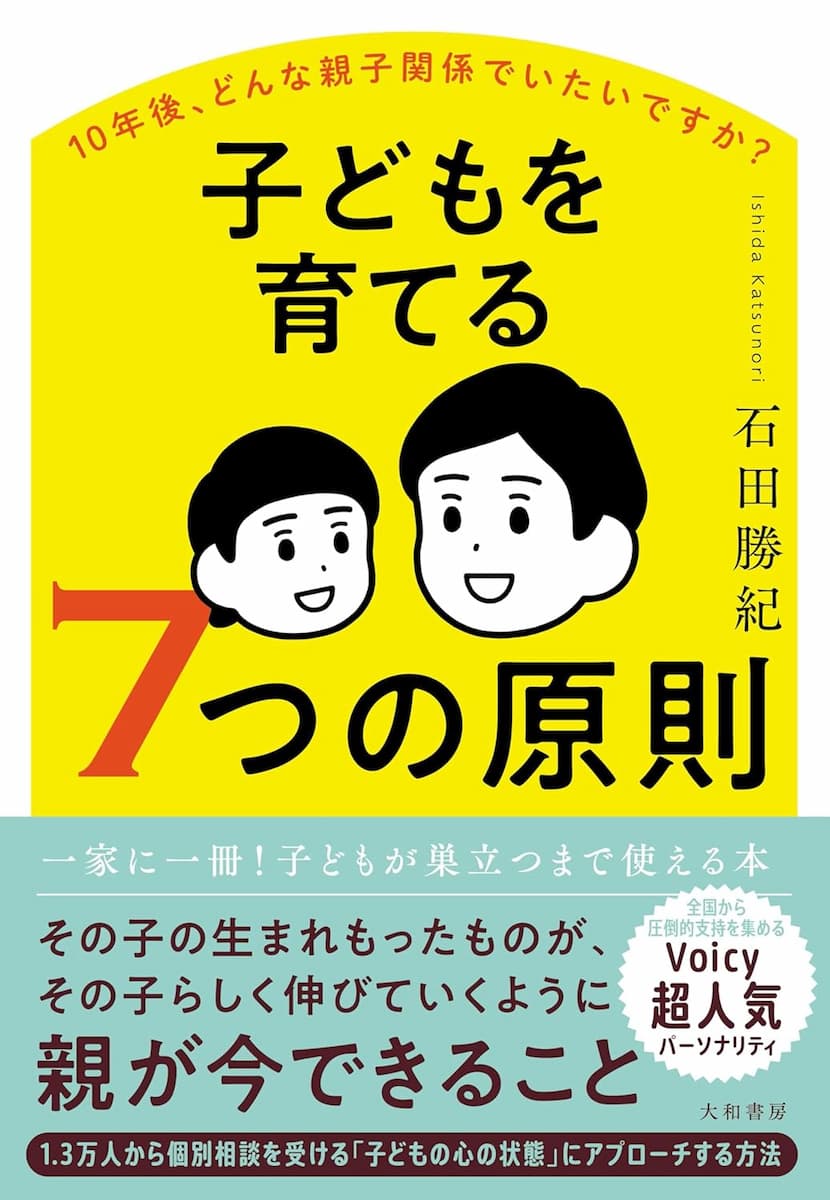
『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(石田勝紀 著/大和書房)
子育てには正解は存在しません。その子に合ったアプローチがあるだけです。
子どもが反発してくる、勉強しない。ゲームばかり…と行動面でやきもきしたり、友達と遊ばなくて心配、頑固で相手するのが疲れる、すぐプンプンする…と性格面を気にしたり。
そんなふうに心配事はバラバラで、子どもも親も性格は多様なので、万人に当てはまるノウハウは存在しません。 ただし、子どもを育てるには原則があります。その原則さえ押さえれば、わが子に合ったアプローチを親が自分で編み出すことができます。