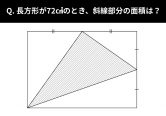起伏が激しい子の対処法は「感情に巻き込まれないこと」 受け流すためのコツとは

激しい感情を抑えきれず、親に当たってしまう子ども。そんなとき、親が一緒になって感情的になるのはNGです。大切なのは「感情に巻き込まれないこと」だと、石田勝紀先生は解説しています。
今回は、石田先生の著書より、上手に対応するためのヒントをご紹介します。
※本稿は、石田勝紀著『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(大和書房)から一部抜粋・編集したものです。
子どものマイナス感情に巻き込まれない

感情は伝播します。楽しそうな人と一緒にいると楽しくなり、悲しそうな人と一緒にいれば悲しくなりますよね。当たり前と言ってしまえば当たり前のことですが、日常生活においてはそれが意識されないことが多いものです。
つまり、親がイライラしているとその感情が子どもに伝わり、子どもが癇癪を起こすとその感情が親に伝播し親もイライラするという現象が起きているということです。親が楽しそうにしていれば子どももその感情を受け取り、子どもが楽しそうにしていれば親も楽しい気持ちになります。
これが日常生活で繰り広げられているわけです。日々、楽しくしたいのは誰しも同じでしょうが、実際はなかなか難しいものです。そこで、日々の心がけとしては次のことを意識しておいてください。
子どものネガティブな言動には反応せず、スルーする(※中学生以上の場合)

つまり、「子どものマイナス感情に巻き込まれないようにしましょう」ということです。筆者がパーソナリティをしている音声配信「Voicy」で、プンプンして当たってくる子(プンプン丸)についてリスナーさんに聞いてみたところ、「我が家にもプンプン丸がいます」とコメントが続出しました。一例を挙げると次のようなものです。
「娘にはマイルールがあり、その数はめちゃくちゃ多いです。それがうまくいかないとプンプンしています」
「次女は1歳の頃からジェットコースターのような気性。それが小3の今も続いています」
「振り返ると、自分も小さいときはプンプン丸でした。理想と現実の差にどう対応していいかわからず、それが怒りになって出ていたと思います」
コメント全体からは、女子が相対的に多く、またしっかりとやる気持ちがあるのにできない状態のとき「プンプン化」するケースが多数見受けられました。
子どものプンプンに頻繁に接していると、親も精神的に参ってしまうことが少なくないようです。コメント欄にはそのような嘆きの声も同時にたくさん書かれていました。私は、子どもがマイナス的なことを言ってきたときは、基本的に次のようにしてくださいと言っています。
「子どものネガティブには反応せず、スルーする」
子どもの感情に巻き込まれないように注意しないと、余計な反応をして火に油を注ぎ、親子ゲンカに発展することがあるからです。
ただし、ポジティブには積極的に反応しましょう。親の反応を求めている子は、このように対応することでネガティブ発言が徐々に減っていきます。そしてポジティブな発言が増えていきます。
実は、この方法は子どもが中学生以上の場合に効果がある方法で、子どもが小学生であれば、これだけでは対応が難しくなります。
例えば中学生以上で、ゲームをしながらブツブツ文句を言っていたり、テストや宿題に対してネガティブな発言を連発したりするときには、親はいちいち反応せずスルーするのがベターですが、小学生の場合はそうはいきません。小学生でも特に低学年となると、スルーだけだと次の2つの問題が起こることがあります。
・子どもが「お母さん! 聞いているの‼」と子どもがさらにまくし立ててくる
・スルーされることで、子どもは自分の話を聞いてもらえない、気持ちを理解してもらえていないと感じ、いつしか親を信頼できない存在と思ってしまうことがある
そこで小学生までの子どもに対しては、次の3つの手順を試してみてください。
【共感】→【提案】→【スルー】 (※小学生の場合)

ステップ1 共感
子どもの話をしっかりと聞いてあげることから入ります。共感の重要性は、カウンセリングやコーチングでも言われています。
子どもは実際に、何か問題を感じているからプンプンしているわけであり、それを「話す」ことで「放す」に変わることがあります。
ただし、プンプン状態ですから、かなり感情がエキサイトしています。その強い感情に親が引っ張られてしまうと、共感ができなくなってしまいます。
共感とは「相手が今どういう気持ちか理解している状態」で、同じ感情になっているわけではありません。ですから、親も一緒になってイライラしたり、怒ったりしている場合は、共感ではなく同感状態になってしまっていると言えます。
相手の感情に巻き込まれないコツのひとつとして「相手のペースに合わせない」という方法があります。例えば、「相手の話す速度に合わせず、ゆっくりとしたペースで低い声で話をする」などです。人は感情が高ぶっているとき、早口で声が高くなる傾向にあるため、そこから外すということです。
ステップ2 提案
話を聞き、子どもの気持ちを理解した後に、「こういう方法もあるよ」と提案をしていきます。例えば、勉強の場面であれば、「今やらずに、ご飯の後でやる方法もあるよ」「時間を分けてやっていく方法もあるよ」と提案してみます。
この提案は、ほとんどの場合、受け入れられないと思います。でも、それで問題ありません。なぜなら、親が提案した方法を子どもが実行することが目的ではなく、「方法はいくつもある」と伝えることが目的だからです。
提案したことを子どもが実行すると期待していると、親は「お母さんが言ったようにやらないから、またプンプンするんでしょ!」と言ってしまうなどして、事態が悪化することがあります。
ステップ3 スルー
最後のステップはスルーです。「共感→提案」ステップでも、まだプンプンしていることもあります。その後で、ようやくスルーになります。
これまでのプロセスで、子どもの感情は相当程度解放されていると思われますが、まだ〝種火〞が残っていることもあります。そのとき再度、「共感→提案」ステップを取っても問題ありませんが、親の気持ちがそこまで続かず、参ってしまうこともあります。その場合は、スルーしていくことを試してみてください。つまりネガティブには反応しないということです。
以上のように、子どもがまだ小さいときは、スルーの前に必要な段階を経ていく必要があります。特に大切なことは、ステップ1の「共感」でしっかり話を聞いてあげることです。ここをしっかりおさえておくことで、子どもの内面深くにある感情は徐々に解放へと向かうと思います。
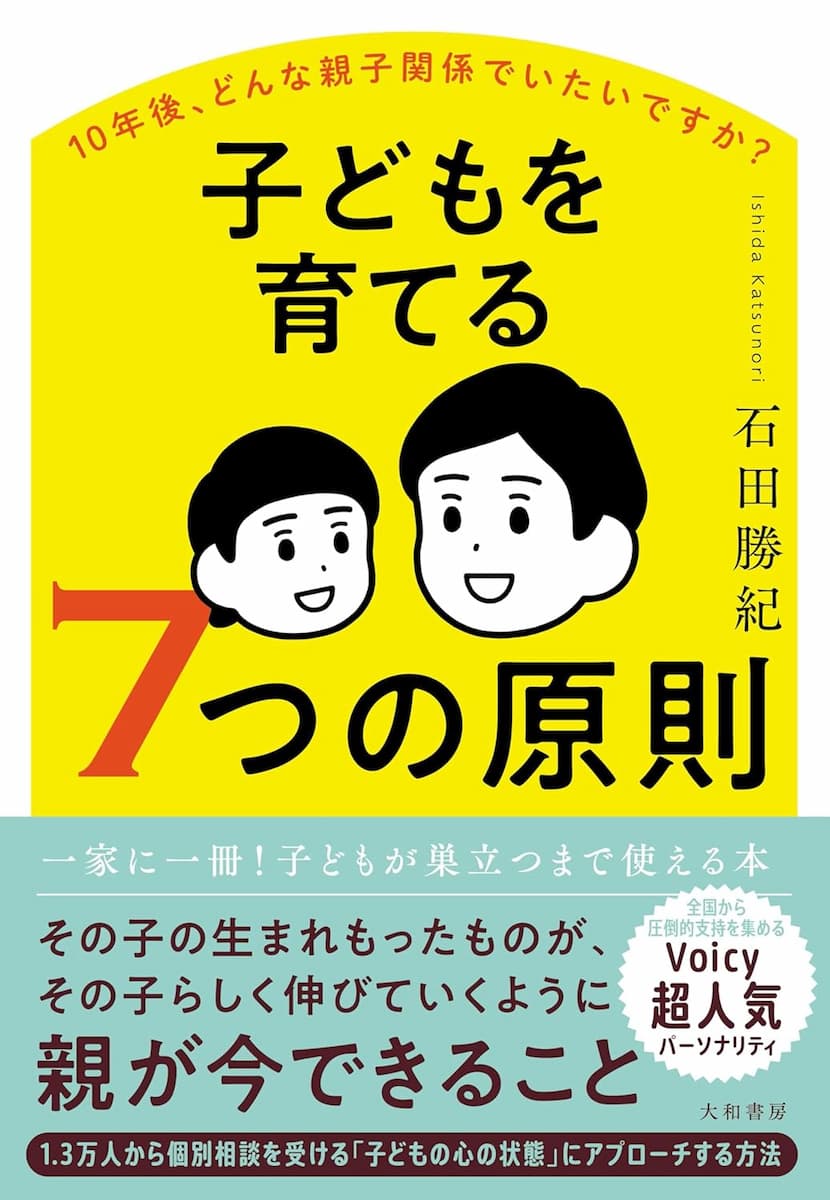
『10年後、どんな親子関係でいたいですか?子どもを育てる7つの原則』(石田勝紀 著/大和書房)
子育てには正解は存在しません。その子に合ったアプローチがあるだけです。
子どもが反発してくる、勉強しない。ゲームばかり…と行動面でやきもきしたり、友達と遊ばなくて心配、頑固で相手するのが疲れる、すぐプンプンする…と性格面を気にしたり。
そんなふうに心配事はバラバラで、子どもも親も性格は多様なので、万人に当てはまるノウハウは存在しません。 ただし、子どもを育てるには原則があります。その原則さえ押さえれば、わが子に合ったアプローチを親が自分で編み出すことができます。