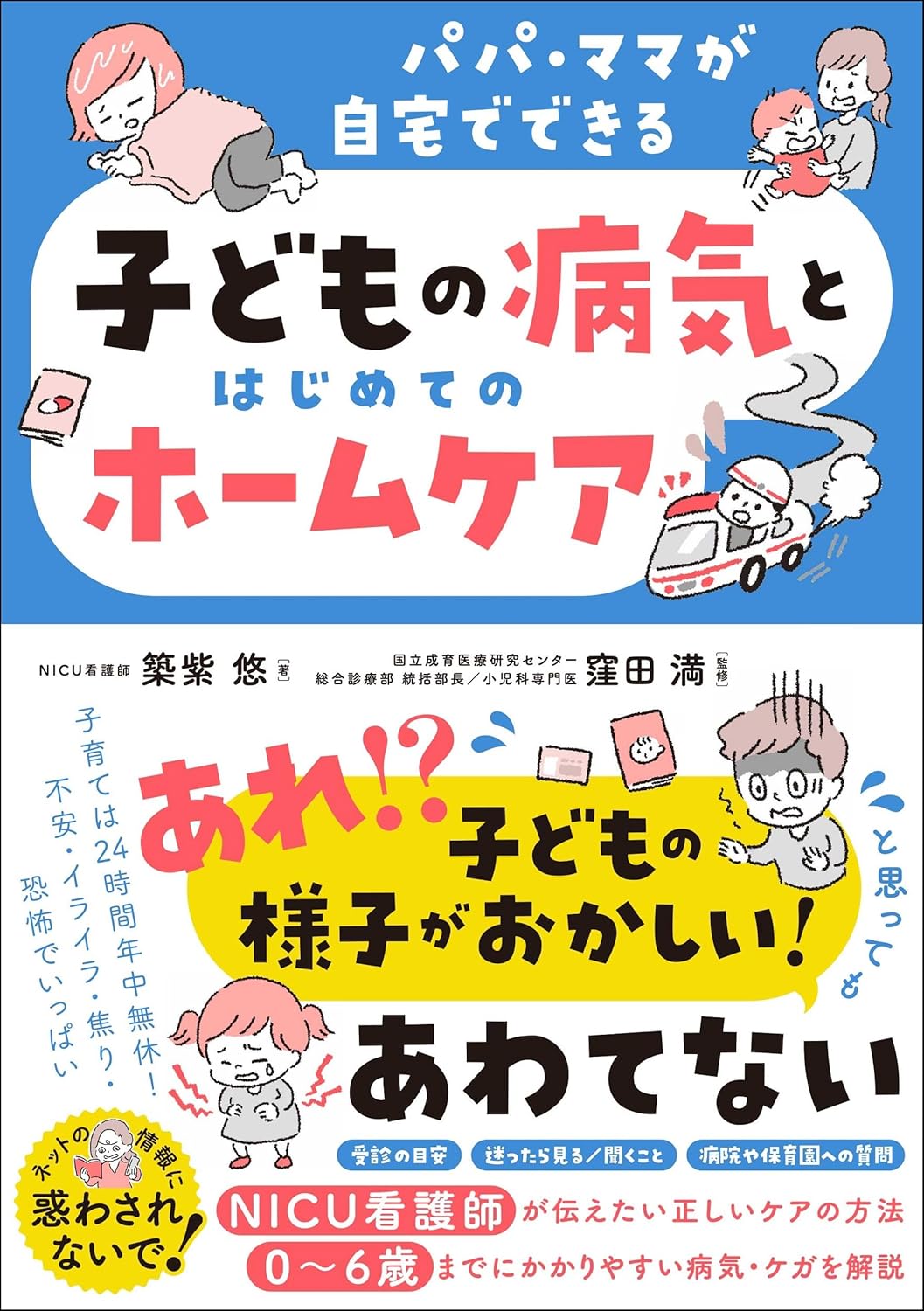休日に子どもが発熱! 病院が休みでも慌てない「ホームケア」の基本

病院がやっていないときに限って子どもが突然発熱…そんな経験はありませんか?
「温めるべき?冷やすべき?」「救急に行くべきか悩む…」そんな親の戸惑いに応える、“正しいホームケア”の基本を、看護師・築紫悠さんの著書より紹介します。
※本稿は、築紫悠(著),窪田満(監修)『子どもの病気とはじめてのホームケア』(総合法令出版)より一部抜粋・編集したものです。
OK:熱を測って、時間と体温を記録する
汗をかいたまま計測しても正しい体温はわかりません。わきの下の汗を拭いてから体温計を挟み、子どものわきをしっかりとしめるようお手伝いしましょう。
OK:手足が冷たい場合は体全体を温める
この「寒気のサイン」を感じたら軽く1 枚羽織らせるか、毛布をかけて体全体を温めてあげましょう。
「熱がある」=「冷やしたほうがいい」と考えがちですが、乳幼児期の子どもは体温調節が未熟。寒さを感じにくいうえ、ガタガタと体を震えさせる力が弱いため、体全体を温めてあげることが寒さを和らげ、適切な体温調整のサポートになります。
OK:顔が赤い、汗ばんでいれば薄着させる
熱が上がりきると、顔が赤くなり汗をかき始めます。
これらは、体が熱を逃がそうとしているサインです。
汗をかいてびしょびしょになった衣類を着たままにしていると、体温を奪われて症状が悪化することがあります。温かいタオルでさっと体を拭いて着替えをさせましょう。
※発熱は、子どもの体がウイルスや病原体と闘うための自然な反応です。無理に汗をかかせたり、過度に冷やしたりしても熱が下がるわけではありません。
NG:赤ちゃんのおでこに冷却シートを貼る
実は、冷却シートに熱を下げる効果はあまり期待できません。赤ちゃん(特に1 歳以下の子ども)には使用を控えてください。
赤ちゃんは自分で冷却シートを外すことができないので、冷却シートがずれて鼻や口を覆ってしまい、呼吸を妨げる危険があるためです。
NG:無理やり汗をかかせる・保冷剤で冷やしすぎる
「汗をかけば熱が下がる」というのは誤解です。着こませたり、布団をかけすぎたりすると、子どもは重苦しさを感じ、不快で疲れてしまいます。発汗目的に温めすぎると、かえって体力を消耗させてしまうので注意が必要です。
一方で、わきの下や足の付け根に保冷剤を当てて冷やすと一時的な快適さを与えることがあります。しかしながら、冷やしすぎると体温が必要以上に下がり、かえって病気を長引かせることがあります。保冷剤を使うときは、タオルで包んで、短時間だけ使うようにしましょう。
NG:無理にお風呂やシャワーをあびる
ぐったりしているときや寒気を感じているときに、無理してお風呂やシャワーに入れるのは避けましょう。体温が上がり始めた段階で無理に入浴させると、体に負担がかかります。温かいお湯に浸したタオルを固く絞って、体を軽く拭いてあげるだけで十分清潔を保てます。特にお尻や股のまわりの拭き取りを心がければ、無理にお風呂に入れなくても大丈夫です。
※「熱があるときにお風呂やシャワーが絶対にダメ」ということはありません。熱の上昇が治まって元気そうにしているのであれば、さっとシャワーを浴びて汗を流すのも子どもにとっては心地よいものですから。
緊急度
けいれんした(★★★★)
救急車をすぐに呼び、即受診する
子どもは発熱にともなって、けいれんを起こすことがあります。はじめてのけいれんのときは、落ち着いてすみやかに救急車を呼びましょう。
0〜3カ月未満で38 度以上の発熱(★★★☆)
診療時間外でも受診。タクシーか自家用車で病院へ
3 カ月未満の赤ちゃんは、たとえ元気であったとしても、急激に体調が悪化することがあるので、注意が必要です。
元気がない、ぐったりしている(★★★☆)
診療時間外でも受診。タクシーか自家用車で病院へ
呼びかけないとウトウトしてしまう、笑顔がない、お気に入りのおもちゃに興味
を示さないといった状態は要注意。
水分、母乳やミルクが飲めない(★★★☆)
診療時間外でも受診。タクシーか自家用車で病院へ
食事は無理に取る必要はありませんが、水分や母乳・ミルクが飲めずに、だんだん元気がなくなってきたときには受診が必要です
3〜4日熱が続いている(★★☆☆)
ホームケアをしながら、日中の診療時間に受診
元気そうにしていても、38 度以上の熱が丸3日間続いていたり、37.5 度あたりの微熱が続いているときは、何か病気が隠れていることがも考えられます。
明らかな風邪症状がない(★☆☆☆)
ホームケアをしながら、自宅で様子を見る
子どもは新陳代謝が活発なので、病気ではないのに熱が上がることがあります。熱以外の症状(鼻水や咳など)がなければ、ホームケアで様子を見ましょう。
発熱時の食事
食欲があれば、ふだん通りの食事で問題ありません。嘔吐や下痢症状がある場合には、おかゆやうどんなどの消化の良いものがおすすめです。
体力をつけようと無理に食べる必要はなく、食べられる量を食べられる範囲で大丈夫。ただし、水分はこまめに与えてあげましょう。
症状の掛け合わせ
・ 発熱×咳(風邪症候群、インフルエンザ、はしか、RS ウイルス感染症、クループ症候群、気管支炎、肺炎、新型コロナ)
・発熱×鼻水(風邪症候群、RS ウイルス感染症、副鼻腔炎)
・発熱×嘔吐(ウイルス性胃腸炎、食中毒、新型コロナ、髄膜炎)
・発熱×下痢(ウイルス性胃腸炎、食中毒、新型コロナ)
・発熱×不機嫌(インフルエンザ、髄膜炎、川崎病)
【著者紹介】
築紫悠
看護師/寄り添い疲れの人専門コーチ
北海道在住。看護専門学校卒業後、JA北海道厚生連帯広厚生病院に入職し産婦人科、新生児集中治療室(NICU)を経験。
退職後、内科、整形外科に勤務。看護師として13年、延べ2万人以上の患者と家族に寄り添ってきた。
20代でがんと診断された夫を12年間支え続けるうちに、自己犠牲による心身の消耗を痛感。自身の「寄り添い疲れ」をきっかけに、患者本人に「寄り添う言葉」が自分自身を守るものでもあるべきだと気づく。
現在は、病気の家族や介護に寄り添い続けて疲れた人に向けに、本当の自分を取り戻し、再び自分らしい人生を歩めるようフルサポートするサービスを提供中。
オンラインサロン「リトリートスペース」主宰。働きながら娘を育てる母。
窪田満(監修)
国立成育医療研究センター 総合診療部 統括部長
小児科専門医。医学博士。北海道大学医学部卒業後、埼玉県立小児医療センターなどを経て、2018年より現職。
専門は、先天代謝異常症、小児消化器病、小児総合診療(成人移行支援や小児在宅医療など)。
日本小児科学会、日本先天代謝異常学会、日本マススクリーニング学会の理事、日本小児突然死予防医学会 評議員も務める。
『パパ・ママが自宅でできる 子どもの病気とはじめてのホームケア』(築紫悠著,窪田満監修/総合法令出版)
本書は、子どもの病気やケガ・気持ちに悩まされるパパ・ママに向けて、NICU(新生児集中治療室)看護師で一児の母である著者が正しいホームケアの方法を解説します。
さらに、病院に行くか判断するために子どもの「どこ」を見るのか・「何」を聞くのか、病院や薬局で話す・聞くべき項目も掲載。
病院に行くか悩んで検索・自己判断する前に、「こんなとき、どうしたら?」と思ったら本書を見てください。