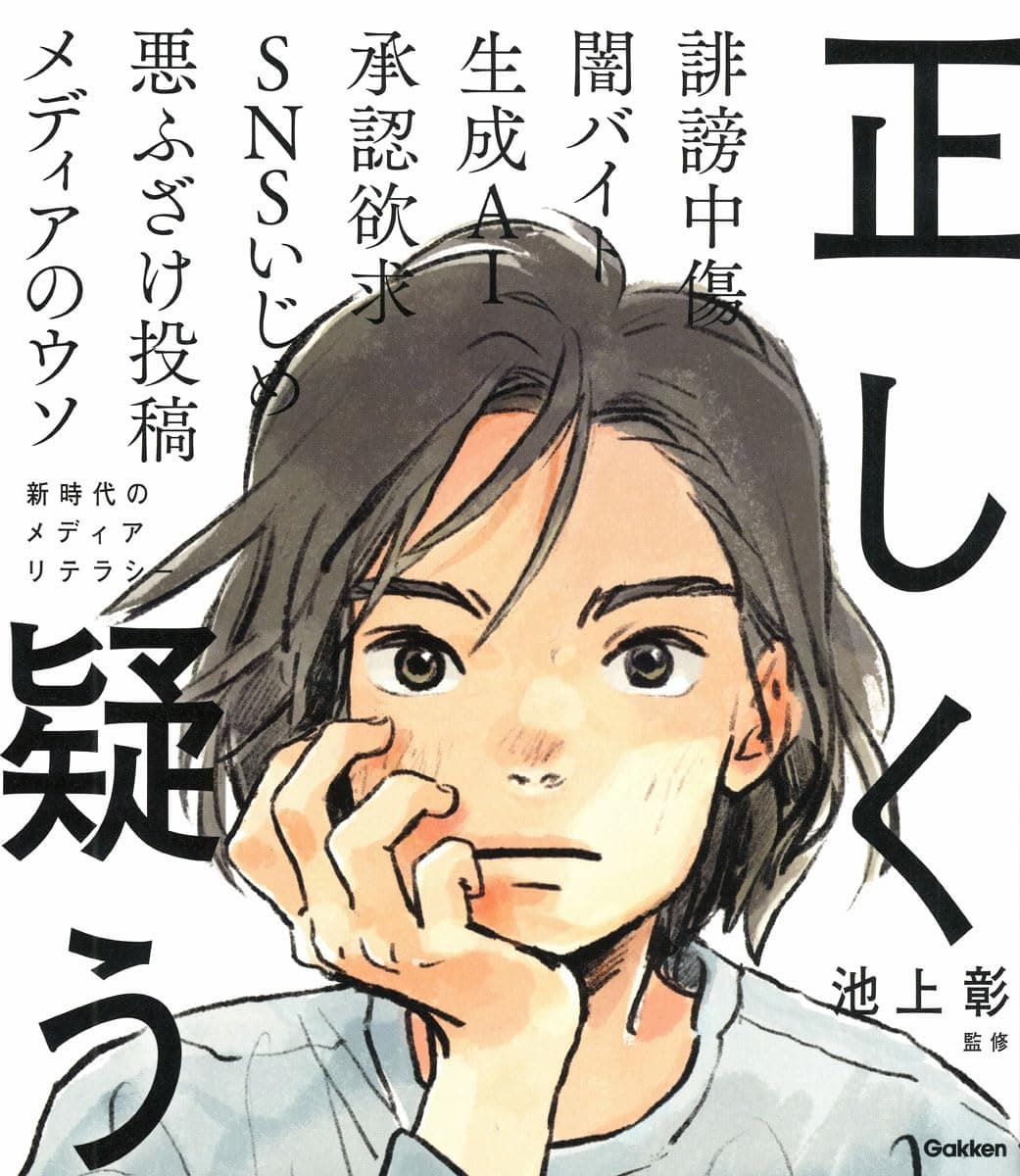SNSに疲れる子どもたち 「いいね」に振り回されないための付き合い方は?
SNSは、現代を生きる子どもたちにとって大切なコミュニケーションツール。しかし、「いいね」の数にとらわれ、自身の承認欲求に振り回されたり、SNS依存に陥ってしまう子も少なくありません。
今こそ親子で考えたいSNSとの向き合い方について、池上彰さん監修『正しく疑う 新時代のメディアリテラシー』より抜粋してご紹介します。
※本稿は池上彰監修『正しく疑う 新時代のメディアリテラシー』(Gakken)より一部抜粋、編集したものです。
SNS依存と承認欲求
SNSは非常に便利ですが、ときにはあなたを疲れさせることもありますよね。SNSとの上手な付き合い方について、さまざまな問題点を見ながら考えましょう。
あなたもそうかも?SNS依存
SNSはスマホやタブレットさえあれば、いつでもどこでも世界中の人とつながることができます。チャットしたり、写真を送り合ったり、情報を交換したりと、さまざまなコミュニケーションが取れるので、とても便利で楽しいツールです。
でも、SNSをずっとやっていると疲れませんか?
そもそもスマホやタブレットをずっと見ていると、目が疲れたり姿勢が悪くなったりして体に負担がかかります。このような身体的な疲れはもちろん、「早く返信しなきゃ」「いいね!がたくさんついてほしい」などと、ネットの向こう側の人たちとのコミュニケーションに対する精神的な疲れを感じる人も多いでしょう。
これらのように、SNSをずっと使い続けていると疲れてしまう、でもやめられず、ずっとSNSを見続けてしまう。そういう状況になっている人はもしかするとSNS依存かもしれません。あなたにも思い当たるふしはありますか?
SNS依存になると“脳過労”になる!?
私たちはSNSに限らず、スマホなどからかなりの量の情報を受け取っています。研究者のある報告によると、脳に情報がたくさん入りすぎるとストレスがかかり、記憶や判断力をつかさどる前頭葉という脳の一部の機能が低下するといわれています。
そうした状態を「脳過労」と呼び、疲れが取れない、イライラが収まらない、眠れなくなるなどの症状が出ることがあるようです。症状を改善するには、スマホを使わない時間を確保してストレスを減らし、人とのリアルな交流や自然との触れ合いを増やすことが必要だといわれています。
「承認欲求」ってどんなもの?
SNS依存について学びましたが、SNSには私たちを夢中にさせる魅力、いや魔力のようなものがあります。それは私たちの「承認欲求」を満たしてくれるからです。
「承認欲求」は他人から認められたいという気持ちのことで、誰もが持っている感情です。まわりに認められたいと思い、頑張るときの活力になるので、人間にとって承認欲求はとても大切な感情だといえるでしょう。
現在の私たちは、SNSで自分の意見や作品を世界中の人に届けることができます。しかも、自分や自分の作品を、実際より良く見せることができます。
たとえばカメラの機能を駆使して自分が撮った写真を素敵に加工することもできます。そうした写真を投稿して何千、何万の「いいね」がつくとうれしくなるので、あなたの承認欲求は大いに満たされることでしょう。
だからといって、やみくもに自分を良く見せようとするのも考えものです。みんなからの反応が活力になる以上に、つらい気分が増してくるようなら、一度自分とSNSの関係を見直したほうがいいかもしれません。例を見て考えてみてください。
SNSで友だちと遊んだ写真を投稿するとき
●Aさんの場合
楽しそうにみんなで遊んでいる写真をいつも投稿しているAさん。
でも実はAさんは友だちが少なく、妹やいとこたちを無理やり遊びに誘って、そのようすを撮っています。
いとこたちもうんざりして、Aさんの誘いに乗らなくなってきました。
写真を投稿したいAさんはクラスメートを誘ったのですが、一緒に遊んでくれず困っています。
Check!
Aさんは、「友だちが多くていいな」と思われることで承認欲求を満たしています。
ウソをずっとつき続けるのは大変ですし、SNSで自慢するための遊びに付き合おうと思うクラスメートもいないでしょう。
●Bさんの場合
BさんもAさんと同じく、友だちと遊んでいる写真をSNSに投稿しています。
ですが、そうした投稿を頻繁にするわけではなく、友だち同士で集まったときにたまたま撮った写真を上げているだけです。
Aさんの投稿のようないかにも「盛り上がっている」感じがなく、ごく自然なようすの写真がけっこう多くの「いいね」を得ています。
Check!
みんなで遊んでいるときの写真をSNSに投稿するのが好きなBさんですが、必ずしも盛り上がっている写真だけでなく、見てほっこりするような写真が撮れたときに投稿するようにしています。
「いいね」がつくより、いい感じの写真が撮れたかどうかに興味があるBさんです。
SNSで新しく買ったフィギュアの写真を投稿するとき
●Cさんの場合
とても人気のあるフィギュアの写真を投稿したところ、「いいね」の数がそれまでの何十倍となりました。
そのうれしさが忘れられず、新たに買ったフィギュアの写真を頻繁に上げるようになりました。
しかしフィギュアは高価なのでお金が足らず、こっそりお母さんの財布からお金をぬき取ろうとしてしまい、見つかってこっぴどく怒られてしまいました……。
Check!
Cさんはレアなフィギュアを手に入れたことがうれしいというより、その投稿で「注目」されることがうれしくなってきて、限度を超えた行動を取ってしまいました。
●Dさんの場合
Cさんと同じく、人気のフィギュアを手に入れたDさん。
たくさんの「いいね」がつきましたが、そのあとの投稿では、このフィギュアのどこがすごいかについて書いたり、つくった人(原型師)のことや、欲しがっている人のために、自分はどこの店で買ったかなどの情報を投稿して、さらに多くの「いいね」がついたのです。
Check!
Dさんはフィギュアが大好きで、そのことについていくらでも書くことができるほどです。
とにかく自分の好きなことを投稿したいという気持ちが強いので、「いいね」がつくのはうれしいとは思いますが、その数が多いとか少ないとかで、気持ちが左右されることはあまりありません。
「自分軸」と「他人軸」
AさんとCさんは、他人が自分のことをどう思うかという「他人軸」で生きるタイプです。BさんとDさんは、自分が思うことややりたいことを優先する「自分軸」で生きるタイプといえるでしょう。
どちらがいい、悪いではありませんが、他人は自分の思いどおりにはならないので、あまりに「他人軸」を頼りに承認欲求を満たそうとすると、疲れてしまうことがあります。ふだんの考え方が「他人軸」に寄りすぎていないかどうか考えてみましょう。
『正しく疑う 新時代のメディアリテラシー』(池上彰(監修)/Gakken)
悪ふざけ投稿、誹謗中傷、炎上…。いまや誰もが発信者、気を付けないと自分が加害者になることもあります。また、フェイクニュースやデマも多く情報の受け取り方にもコツが必要です。情報との向き合い方、発し方を池上彰がわかりやすくナビゲートします。