「スマホで動画」が歯並びを乱す? 子どもの口への意外なリスク
笑った時に綺麗にそろった白い歯を子どもが見せれるように! そう気遣い、子どもを歯医者さんに通わせる親御さんも多いことでしょう。
子どもの口の危険信号に早く気づくためにも、子どもの「かみ合わせ」や「歯並び」で日頃から気をつけておきたいこととは? 歯科医・生澤右子さんの著書(医師・脳生理学者の有田秀穂さん監修)より紹介します。
※本稿は、生澤右子(著)有田秀穂(監修)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)から一部抜粋・編集したものです。
「い」の口で"かみ合わせ”をチェック!
一見、歯並びが整っていても注意が必要な場合もあります。
奥歯をかみ合わせて「い」の形の口をしてもらうと、下の前歯が全く見えないのです。
正常では、かみ合わせると、上の前歯がかぶさっていて、少し下の前歯も見えます。
また、子どもの歯では、上と下の前歯が重ならないでかんでいてもOKです。
子どもの歯で、下の前歯が見えないくらい、上の前歯が覆いかぶさっているということは、深すぎるかみ合わせか過蓋咬合(がいこうごう)です。
深すぎるかみ合わせでは、上のあごに対して下のあごが小さく、後ろに下がってしまってます。
下のあごが小さく、後ろに下がっているため、鳥にたとえられるような横顔が特徴的で、まるであごがないかのように、なだらかなカーブで口元から首へとつながっていきます。
子どもの歯が重なり合って生えてしまうのは、本来、隙間があるはずの子どもの口であることを考えると、あごが相当小さいと説明しました。
これに加えて、さらに下のあごの位置が後ろに下がっているという場合は、下のあごが小さい人たちの中でもさらに小さいということになります。
さて、きれいに子どもの歯が並んでいても、下のあごが小さく、後ろに下がっていると何が困るのか。
まず口の問題を挙げてみましょう。
下の前歯は上の前歯の裏をかんでおらず、歯ぐきをかんでいる場合があります。これでは、前歯でしっかりとかみ切ることができません。食事の効率が悪いですね。
また、食べにくいものを嫌がったり、丸呑みになってしまったりします。
かむといつもあたるので、上の前歯の裏の歯ぐきが常に腫れている状態になることもあります。
そして、歯の生え替わりの時期になると、下のあごの大人の歯が高確率で重なりあって生えてきてしまうという問題へとつながっていきます。
下のあごはもちろん、上のあごも、きれいに並びきらないこともあるでしょう。
大人の歯が生えるために、あごも成長していますが、正常なあごの大きさに追いつきません。
スマホ育児が「かみ合わせ」や「歯並び」に与える影響
これに関連して私が街で気になっているのは、ベビーカーのお子さんにスマートフォンを見せることです。小さなお子さんが胸やおなかのあたりでスマホをじっと見ている、あの光景です。
お子さんの退屈しのぎやご機嫌とりとして持たせているのだと思うのですが……。
スマホが育児界隈に登場してきたのは、そんなに昔のことではありません。
大人が使うのが当たり前になり、子どもにもそれを渡すということで、まだ便利な部分しか見えてきていないと思うのです。
スマホの大人への影響を調べた研究は、「姿勢」に関するものでは2010年に初めて登場して、現在は年々右肩上がりで増えています。
その結果、多くの人が考えていたことが科学的に検証されました。
スマホをうつむいて使うと、頭を支えようと首や背中の筋肉が姿勢のいいときよりも緊張します。そして、首に対して頭が曲がる角度が大きくなり、頭も前に移動します。
立っているよりも座ってスマホを見るというのは、さらに負担がかかる姿勢です。
そこで考えていただきたいのが、首の上にのっている頭、の下にぶら下がっている下のあごです。
正常な頭の位置より前下方に出てしまっている頭の下側に位置するのが上のあごで、それとかみ合って使うのが、ぶら下がっている下のあごです。はたして正常に働くでしょうか?
大人を集めたスマホを使った研究では、無意識に歯の食いしばりが増え、かみ合わせに負担をかけていることが明らかになりました。
また、かみ合わせが不安定なときにうまく調整する適応力も下がる可能性が指摘されています。
スマホが子どもの歯並びにどんな影響があるかという研究は、残念ながら、まだ進んでいません。
さらに、それを継続したときに、今までの「クセ」の話のように、歯並びや、あごの成長にどんな影響があるのかということもわかっていません。
大人の結果をそのまま子どもに当てはめることはできませんが、私はやはり悪影響があるのではないかと考えています。
成長段階の子どもの方がかみ合わせが不安定ですし、子どものときからスマホを使うと大人より時間の積み重ねが多くなります。
大人の研究から想像するに、正常なかみ合わせの子どもでスマホによって歯ぎしりが増え、かみ合わせが低くなったり、下のあごが押し込められたりするのではないかという心配があります(子どもに時々見られる歯ぎしりは異常ではありません)。
他のタイプのかみ合わせでも、「傾いた頭にぶら下がっている下のあご」についている筋肉の影響や、子どもの成長もあわせると、複雑な問題が起きる可能性は十分あります。
ですから、子どもと一緒の外出のときの苦労を知っているだけに大変申し上げにくいのですが、無理のない姿勢を作ってあげられる自宅で、スマホを見せるくらいがよいのではないでしょうか。
スマホの他にも、下のあごの正常な成長を邪魔する可能性があるのが、頬杖(ほおづえ)をつくことです。続けていくと、かみ合わせが悪化していきます。片方の頬杖では、さらに顔がゆがむこともあるのでご注意ください!
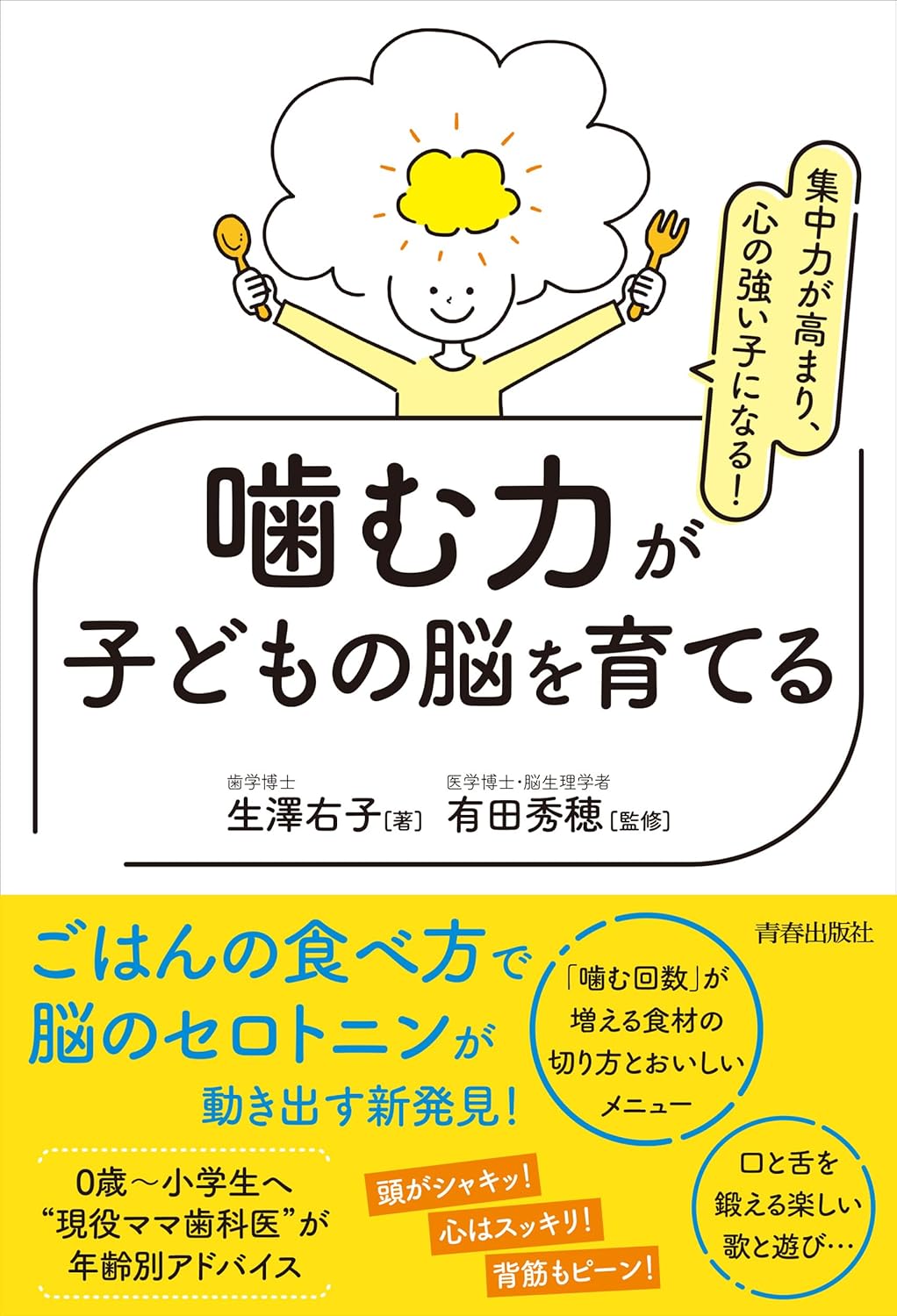
生澤右子/有田秀穂(著)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)
「かむ」から始める「食育」といつもの「生活習慣」をちょっと変えれば、幸せホルモン・セロトニンがどんどん脳で作られるという新発見 !
「噛む回数」が増える食材の切り方とおいしいメニュー 、口と舌を鍛える楽しい歌と遊び……など、0歳~小学生へ 歯と口のママドクターが年齢別にアドバイス。子どもの脳がぐんぐん育つ食育と生活習慣を伝授する一冊。