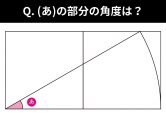歯科医が教えるやってはいけない歯磨きとは? 気をつけたい3つのポイント

ちゃんとした歯磨きを子どもに教えるとなると、技術的な面ばかりに気を取られがちになる親御さんも多いかもしれません。
でも、重要なのは「歯磨き・歯医者に悪いイメージをつけないようにする」こと、と歯科医師の生澤右子さんはいいます。「やってはいけない歯磨き」とは? 親が気をつけるべき3つのポイントを紹介します。
※本稿は、生澤右子(著)有田秀穂(監修)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)から一部抜粋・編集したものです。
「やってはいけない歯磨き」をしない

「やってはいけない」というと、「私は歯磨きをちゃんと習ったことないから……」と心配になってしまう方もいるかもしれませんね。でも、これは歯磨きの技術的な問題ではありません。
ここで注目していただきたいたったひとつのポイントは、「歯磨き・歯医者に悪いイメージをつけないようにする」ということなのです。
それでは具体的に3つ挙げましょう。
1.「歯磨きしなきゃダメ」と子どもに迫る
子どもに歯磨きをさせたいがあまり、ダメな理由を「歯磨きしないと、むし歯になって歯医者さんに行かなきゃいけなくなっちゃうよ」と話していないでしょうか。
とはいっても、日本のアニメに出てくる歯医者は、みんな「怖くて痛いことをしてくる人」として描かれているので、そのアニメを見て育った大人がそう言ってしまうのも無理はないのですけれど……。
しかし、それは負の連鎖です!!
これでは、歯医者は悪いイメージになってしまいます。怖い・痛いなど嫌なイメージと歯医者を結びつけると、最終的にお子さんを含めて、みんなが困りますよね。
歯医者さんに行くのはいいこと、歯をピカピカにしてくれるところというポジティブなイメージをつけるように常に意識をして言葉がけをしましょう。
2.歯磨き習慣をつけようとして、寝る前に必ず歯磨き
「絶対にむし歯にしたくない」「私はこのタスクを完遂しないとダメなんだ!」とばかりに必ず歯磨きをするというのは、時に逆効果になってしまうかもしれません。
夜寝る前、お互いに疲れはピークです。このときに無理しすぎて歯磨きが嫌いになってしまっては一番まずいわけです。
お伝えしたいのは、正しい歯磨きと、第1章の食育編で出てきた正しい食習慣を実践していれば、そうそう簡単にむし歯にはなりません、ということ。
逆に、正しくない歯磨きと食習慣では、すぐにむし歯になります。
ですから、読者のみなさんは少しどっしりと構えて、「今日はできそうにないから、しょうがないね」と潔くあきらめる勇気を持って大丈夫です。
その代わり、正しい歯磨きと使うべき道具はこのあと解説しますので、しっかり頭に入れましょう。
少しでも歯磨きできそうなら、「奥だけ」「フロスだけ」と区切って終わらせます。そして、機嫌がよくて、こちらも時間と気持ちに余裕があるとき、昼の別の時間帯などに残りをやってしまってもいいのです。
その別のときに、歯の絵本を見せて、歯の話ができるといいですね。
もちろん、理想は寝る前に歯磨きをきっちりとすることですが、現実は、そんなに簡単ではありません。特に夜の眠い時間帯はギャン泣きされて、これは何かの修業か!? と思う場合もありますから(トホホ)。
3.子どもの歯磨きにダメ出しする
お子さんがやる気になって歯磨きをしているときに、横で「そうじゃなくて、こうだよ」と言ってしまうこと、ありますよね。
でも、そうなると一気にお子さんのテンションが下がってしまいます。
危なくない限りは、見守るようにしてください。そして、「上手にできて、すごいね!」
「歯がピカピカになってるね」といっぱい褒めてあげてください。
そもそも(?)お子さんの歯磨きでは不十分という目で見ていてください。仕上げ磨きが大前提です。
私もオンラインの歯磨きクラスでは、「みぎこ先生(私)も一番奥の歯の後ろは見えないよ。だから誰か見える人に磨いてほしい」と言っています。
「みんなは仕上げ磨きをしてくれるおうちの人がいて、ラッキーだね」と。
お子さんの歯磨きを見ていて、何かアドバイスしたい場合は、「〇〇すれば、もっといいね」くらいにしておきましょう。また、お子さんと一緒に歯を磨いて歯磨きを見せてあげれば、コメントしやすくなります。
どうぞ、くれぐれも、お子さんのやる気の芽(モチベーション)をザザッと摘まないようにお気をつけください。
まだ弱々しい芽がしっかりと育つまで、気長に見守りましょう。
いかがでしょうか。
「やってはいけない歯磨き」で身に覚えがあるものはありましたか?
もし、「やってました……」というものがあったら、「歯の遊び」のほうで挽回すればいいので、これから気をつけてみてください。
ここで、「歯の遊び」と「やってはいけない歯磨き」を心理学的に考察してみましょう。
〝自己決定理論〞によると、自分の意思で決定できたり(自律性)、スキルを向上させたり(有能性)、他者と結びつく(関係性)ことで、自発的に喜びや満足感を持って行動するようになります。
「歯の遊び」をたくさんすると、お子さんの中で歯に対するモチベーションが高まり望ましい行動をします。つまり、内発的動機づけがされています。園児さんや生徒さんの見違えるような変化は、歯の遊びを通して、この理論で説明できます。
そして、内発的動機づけの反対は、外発的動機づけといいます。これは、報酬や評価、罰で行動させることです。
例えば、「〇〇をしたら、これをあげる」「〇〇したら、こんな困ったことになるよ」
ということなど、お子さんを動かすために結構言ってしまいますよね。
けれども、みなさん経験済みかもしれませんが、だんだん効果がなくなってきて、こちらも困ってしまいます。
「やってはいけない歯磨き」は外発的動機づけにあたります。正しい歯磨きを身につけてほしいという親心であっても、お子さんは望ましい行動をとってくれないのです。
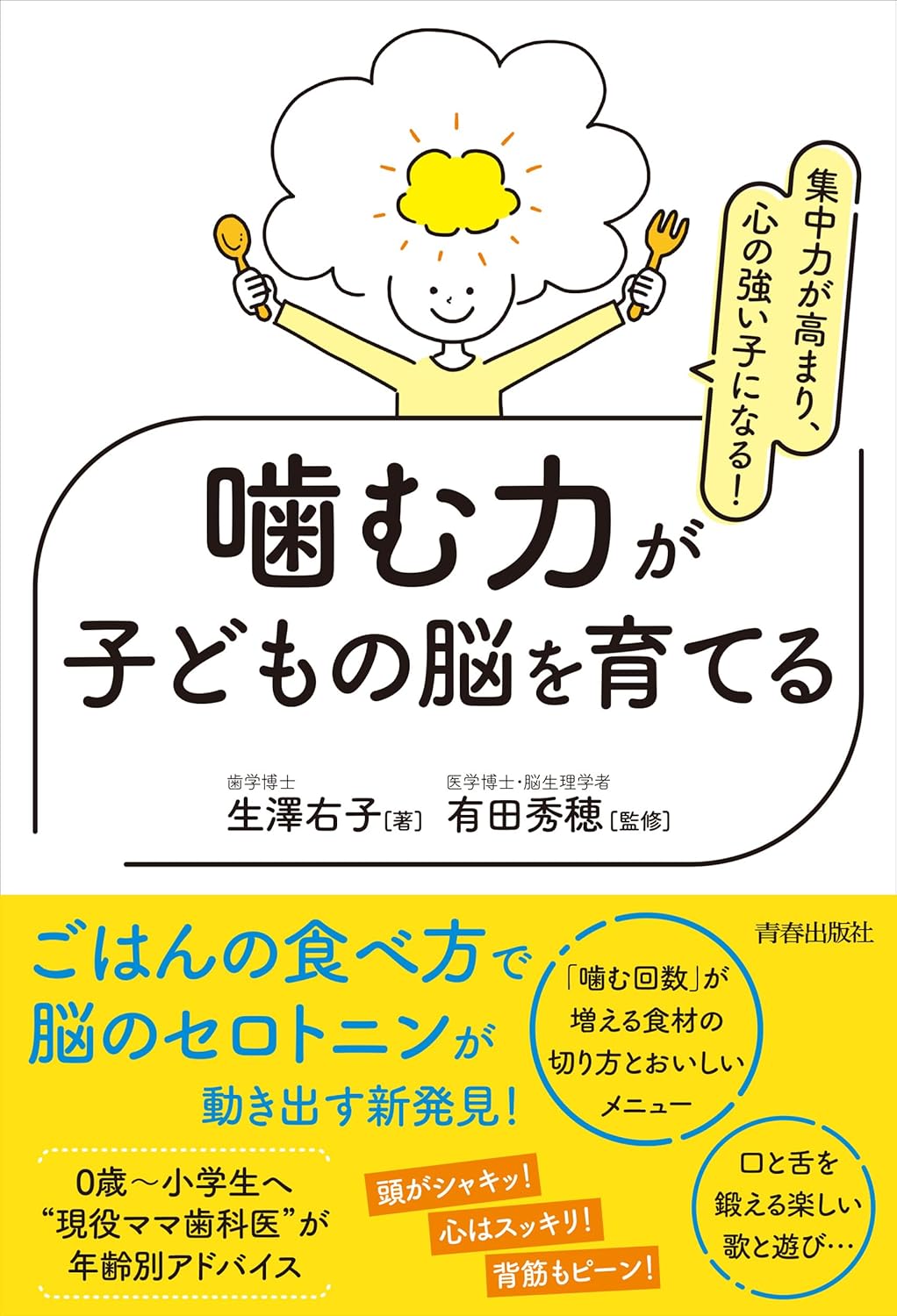
生澤右子/有田秀穂(著)『集中力が高まり、心の強い子になる! 噛む力が子どもの脳を育てる』(青春出版社)
「かむ」から始める「食育」といつもの「生活習慣」をちょっと変えれば、幸せホルモン・セロトニンがどんどん脳で作られるという新発見 !
「噛む回数」が増える食材の切り方とおいしいメニュー 、口と舌を鍛える楽しい歌と遊び……など、0歳~小学生へ 歯と口のママドクターが年齢別にアドバイス。子どもの脳がぐんぐん育つ食育と生活習慣を伝授する一冊。