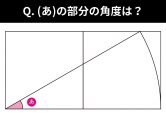「私なんて」「どうせ」の口癖を変えるには? 子どもの自信を引き出す方法

「すぐ『私なんて』『どうせ』と言います。自信がないの?」と悩む親御さん。子どもに自信をつけさせたいという悩みに、親子でできる意外なアプローチ方法を提案。その答えとは?
非認知能力育成のパイオニアとして知られるボーク重子さんの回答をご紹介します。
※本稿は、ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)から一部抜粋・編集したものです。
Q:すぐ「私なんて」「どうせ」と言います。自信がないの?
→ 周りになんでも、早く、上手にできちゃう人がいるのかも…

そんな発言があると心配しちゃいますよね。子どもが小さければ小さいほど「どうしてこんなに自信がないんだろう?」って不安になるし、自分の子育てのどこがダメだったんだろうって悩んだり、そんなわが子にちょっと不甲斐ない思いもしたりして、「親として失格じゃん」なんて思ったりもする。
本当に子育てって自分に向き合うことの連続ですよね。どうやったらもっと自信を持ってくれるのかな。
そこでおすすめなのは「親子で一緒に新しいことに挑戦する」ことです。このとき重要なのは「子どもが興味を示すこと、かつ親もやったことがないこと」。
大人は子どもに比べて絶対的に経験値が高いので子どもよりも早く、上手にいろんなことができちゃいます。そんな姿を見て「私なんて」と思うこともあるでしょう。
親が苦手で子どもが得意そうなことだと最高によいかも。
わが家で試したのはスケート。運動神経のよい娘はすぐに滑れるようになったけど、ツルツル系が全部ダメな私はいつまでも壁につかまり立ち状態。「ムリ」と思った私に娘から「ママがんばって!」「大丈夫、転んでも怖くないよ」なんて声がたくさん聞こえてきて、嬉しかったのを覚えています。
こんなふうにしてお互いに「うわー、できた!」「やったね」「もう1回やってみよう」「次はできるかも」「前よりできるようになってるね」という言葉のシャワーを浴びられるような機会を作り出してみませんか?
そうやって「私なんて」「どうせ」を上書きしていく。スポーツ、音楽、語学、アート、ぜひ何か一緒に試してみてね。
A:親子一緒に新しいことに挑戦してみてね。
Q:「ムリ」「別にいい」と言ってチャレンジしません。
→ 自分を守っているのかも…

子どもが「ムリ」「別にいい」と言うときは、大きく2つのケースがあるかと思います。
1つは単に興味がないとき。自分にとって意味がないことだからどんなに親が「やったほうがいい」と言っても「別にいい」。
特に思春期はこのケースが多いんじゃないかな。自分のアイデンティティを作っていく過程で親と子どもの認識がずれていく。子どもからすればそれほど大きな意味はなくても、
親にとってはそれまでとは違う反応にモヤモヤして、この発言が余計に気になるのかもしれませんよね。この場合は無理強いするのでも、「やる気ない!」と判断するのでもなく、「そんなものか」と深読みしないのが一番かな。
もう1つのケースは自分を守るとき。たとえば前にやってできなくて恥をかいたとか、今の自分の能力じゃ到底無理だと思うなど、「どうせできない」と思わせる何かがあったとします。
そんなときは「また恥をかくかもしれない」「できないって証明されちゃうかもしれない」「親をがっかりさせるかも」と思って「ムリ」「別にいい」、という発言になることもあるでしょう。
それって年齢に関係ないと思う。大人の私たちにもそんなときってあるものね。
そんな自分を守るための「ムリ」「別にいい」への対処法は「小さな成功を積み上げる」。
求める結果のハードルを下げたり、そもそものタスクのレベルを下げる。そうやってコツコツと「できた!」事実を積み上げていく。
振り返ってみたら「ムリ」と思っていたことができるようになっている。自信の特効薬は即効性ではなく、地味な作業の積み重ねです。
地味な作業の1つひとつが確実に「ムリじゃない!」自分を作っていきます。
A:自信の特効薬は「小さな成功の積み重ね」という地味な作業。
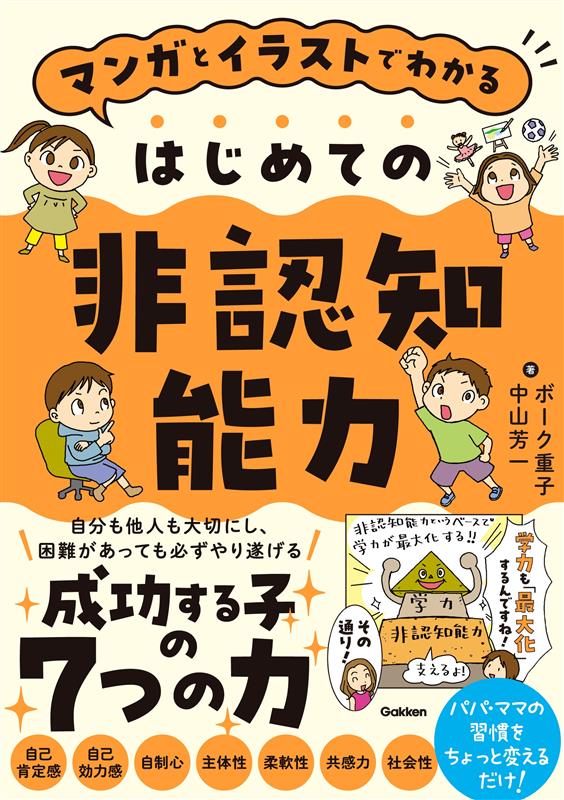
ボーク重子(著)中山芳一(著)『マンガとイラストでわかる はじめての非認知能力』(Gakken)
AIの進化や不透明な未来。そんなこれからの時代を生き抜くためには、学力だけではなく、目に見えない力「非認知能力」を身につける必要があります。力強くはばたいていく子どもを育てたい! という親必見。全米優秀女子高生を育てたボーク式&大学教授の理論を取り入れた、最も新しい「子どもの非認知能力」の育て方が学べます。