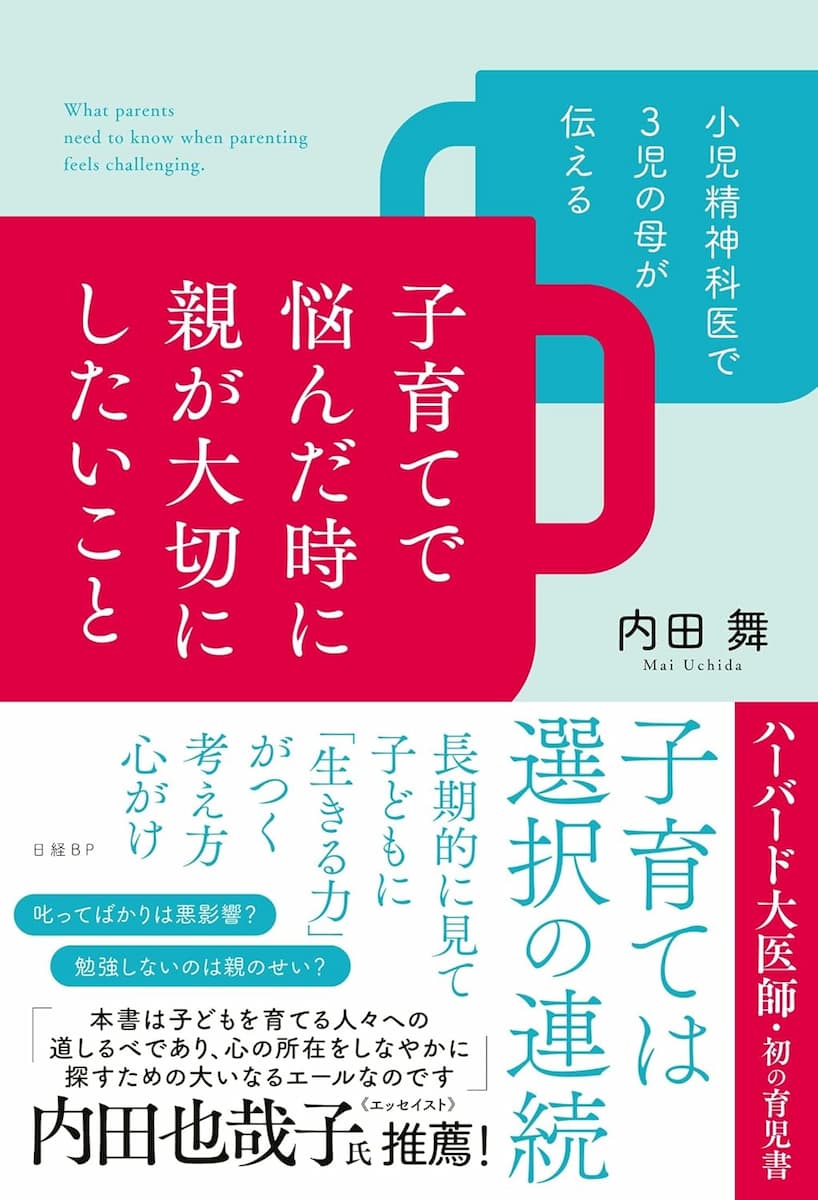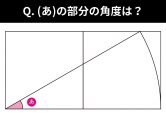「習い事やめたい」はどこまで本気?子どもの本音と親の葛藤の向き合い方

子どもから「習い事をやめたい」と言われたとき、親としてどのように対応すればよいのでしょうか。本当に辞めたいのか、ただ面倒なだけなのかわからず、判断に困ることもあると思います。
児童精神科医であり3児の母でもある内田先生の経験をもとに、子どもと親が共に納得できる対話のヒントをご紹介します。
※本稿は内田舞『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)より一部抜粋・編集したものです。
子どもが習い事を「やめたい」と言った時は

子どもの「NO」に関連する悩みでよく挙がるのが、「習い事をいつまで続けさせるか」「子どもが『辞めたい』と言った時、すぐにやめさせてもいいのか」という問題です。
これは私にも経験があって、子どもから「この習い事にはもう行きたくない」と言われた時にどうしたらいいかについては、毎回本当に悩みます。単に、今日は疲れていて行くのが面倒でそう言っているのか、行ってしまえば楽しんで参加できるのか、それとも、本当にその習い事が苦痛なのかがわからないこともあります。また、本人の意向以外に、「将来のことを考えるとぜひ続けてほしい」という親の願いなども関係してくるでしょう。
私の長男も今、チェロ、SASUKEなどの習い事をしています。今のところ一番好きなのはSASUKEで、その練習のためなら休みの日でも早起きをして楽しそうに参加しています。しかし、これも成長するに従って変わる可能性もあるでしょう。チェロは、本人はそれほど熱心ではないのですが、夫がチェロ奏者ということもあって続けています。楽器というのはすぐに好きな曲が弾けるようになるわけではなく、最初は音を出すのも大変なので、長い積み重ねが必要です。そこを越えた時に素晴らしい世界が広がるということを夫自身が経験しているので、夫は、「たとえ『やりたくない』と思うことがあっても続けてほしい」と考えているようです。
ただそれでも、もしも本人がどうしてもやりたくなくなり、心身の状態に悪影響が出るようになったり、家族の関係性が悪くなったりするようなことがあれば、やめさせると思います。
少し前には日本語も習わせていたのですが、これは比較的早いタイミングでやめています。日本にルーツのある子どもですし、日本語を書いたり話したりできてほしいと思っていたのですが、本人はいやがっていて、毎回日本語教室に向かう際に大げんかをして行っていました。これ以上無理に続けさせても親子の関係性を壊すだけだと考えて、やめさせる判断をしました。しかし、日本語教室をやめさせてみると、子どもも日本語に興味がないわけではないことも明確になり、その後は語学アプリだけは毎日続けることにしています。子どもの成長とともにまた変わるかもしれないので、子どもがまた「やりたい」と言った時にはまた違う機会を用意できたらと思っています。
本当にケースバイケースで、難しいのですが、習い事を続けさせることの先に何を求めるのか、親がしっかりと考えておくことが必要なのではないかと思います。「将来どんな大人になってほしいのか」、その姿につながるかを考えながら判断するしかありませんが、やはり本人のNOも尊重すべきですし、親子・家族関係を悪化させるようなら、そこまでこだわらずにやめさせた方がいいのではないでしょうか。
特に、「勝手な未来予知(fortune telling)」に影響されすぎていないか、考えてみるといいかもしれません。子どもの将来を予測して心配や不安を膨らませ、受験で英語が重視されるから、プログラミングの授業があるから「早いうちに習っておかないと落ちこぼれるのではないか」「受験で苦労するのではないか」といった理由の場合は、将来どんな大人になってほしいのかという姿がなかなか描けません。すると、子どもがその習い事に行き渋った時に、どうしたらいいか、なかなか判断がつかなくなりそうな気がします。
不安を感じるのは悪いことではありませんし、大切な子どもを守りたいという自然な反応です。ただ、だからこそ、子どもに関する不安は行き過ぎてしまいやすいことも、心に留めておいた方が良いと思います。
大好きだったSASUKEを「やめたい」と言い出した息子

SASUKEに熱中していた長男ですが、実は数カ月ほど前に「やめたいんだ」と言い出し、私も夫も大変驚きました。まずはじっくり話を聞かなくてはと思い、「どうしてやめたいの?」と聞いたところ、「SASUKEをやめると言ったら、ママとダディががっかりするんじゃないかと思ってなかなか言えなかったんだ」と言って、なぜやめたいと思うのか、一生懸命話してくれました。
そのしばらく前に、みんなの前で本番さながらの障害物に挑戦する公開練習があったのですが、そこでいろいろな事情が重なって、あまりいいパフォーマンスができなかったことがきっかけだったようです。「練習しても成長を感じられないし、大会に出た時のプレッシャーも大きくて、『もうやりたくない』と思うようになった」と言っていました。SASUKEの大会は、盛り上がる観客を前に、たった1人でコースに挑まなくてはなりませんし、チーム戦もあるので、自分が結果を出さなければチームの足を引っ張ることにもなってしまいます。そうした重圧もつらいと話していました。
夫も私も、それを聞いて、「せっかくずっと頑張ってきたのに」「ほかの子たちにはできないような、すごい技も持っているのに」と、残念に思いました。でも、その気持ちも本人に伝えたうえで、2人とも「やめてもいいよ」と伝えました。
そして私たちは、プレッシャーの大きさや、練習してもなかなか上達が感じられない時のもどかしさもよくわかる、と共感する気持ちを伝えました。そのうえで、「いつやめてもいいから、とりあえずシーズンの終わりまでやろうか」と話したところ、息子は「そうする」と言って、あと数カ月だけ続けることになりました。
「今シーズンが終わるまで」と、ゴール地点が見えたことで、本人の気持ちは少し軽くなったようです。そのせいか、当初は「もう出たくない」と渋っていた大会にも、「今シーズンで最後だから」と二つ出場して、悪くない成績を残すことができました。
するとシーズンの終わりに近づいたころ、この数カ月で自分がどれだけ成長していたか、息子自身が気付き始めたのです。今までは「ケガをするんじゃないか」と怖くて挑戦できなかった障害物にも挑むことができるようになり、完全攻略とまではいかなくても、それに近いところまでできるようになったといいます。
そんなことを話していた練習からの帰りの車の中で、「もう少し続けてみてもいいかな?」と言い出しました。
「攻略したいと思う障害物がいくつかあるから、その目標を達成するために、『1年間通しで続ける』とは決めない感じで続けてみてもいいかな? 大会には出てもいいけど、そこでいい成績を取るために出場するわけじゃない。○○や××を攻略するという目的を達成するために成長することの方が、今の僕には大事なんだ」
私は「もちろんいいよ。『やらなきゃいけないから』という親やコーチからのプレッシャーのためでもなく、大会でいい成績を取るといった結果のためでもなく、あなたの内側から『自分が成長したい』という気持ちが湧いてきて、続けたいと思えたのはすごいね!その気持ち、聞かせてくれてどうもありがとう」と話したのでした。
振り返ると、最初に息子から「やめたい」と聞いた時に、息子の気持ちに共感しながら「やめてもいいよ」と言ってあげられたことが、大きかったのではないかと思います。それで息子は、「2人とも僕のつらさをわかってくれている」という安心感を持ちながら、自分自身と話し、オーナーシップを持って決断することができたのでしょう。
内田舞(著)『小児精神科医で3児の母が伝える子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと』(日経BP)
ハーバード大小児精神科医で3児の母でもある内田舞さん、初の育児書!
内田也哉子氏(エッセイスト)推薦
「子育てを見つめると、多様な世の中が見えてくる。
本書は、こどもを育てる人々への道しるべであり、心の所在をしなやかに探すための大いなるエールなのです」
子育ては選択の連続。
長期的に見て子どもに「生きる力」がつく親の考え方、心がけとは――。
「子どもが勉強できないのは自分のせい?」「一緒にいる時間が短くて申し訳ない」・・・
いろんな思いを抱えながら子育てに向き合う親へ向けて、【専門性】×【育児の実体験】でアドバイスとエールを送ります。