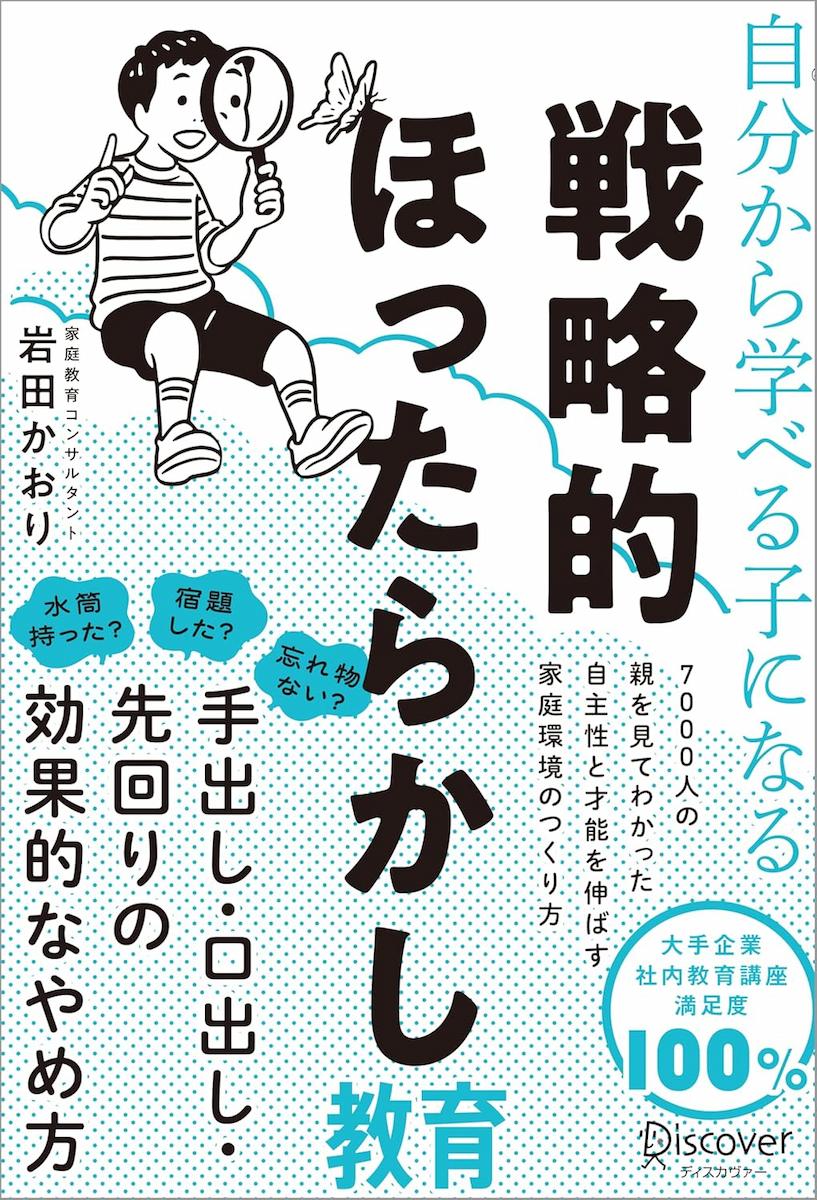学びは「好き」が原動力! 子どもの探究心を育てる“天才ノート”とは

子どもにはそれぞれ、夢中になれる「好き」があります。そんな「好き」を肯定し、探究心を育てるツールが「天才ノート」です。
特別な準備も不要、短時間で取り組めるという、「天才ノート」のつくり方とは? 岩田かおり著『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』から紹介します。
※本稿は、『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から一部抜粋・編集したものです。
「天才ノート」をつくる

探究心を深めていくために私が推奨しているのは「天才ノート」です。
ここでいう「天才」とは、アーティストになったりオリンピック選手になったりするような、他者と比べて特別に秀でた才能を持っていることを指すわけではありません。
すべての子どもは、なんらかの才能を持って生まれてきています。
「虫が好き」「恐竜についてずっと話をしている」「絵を描くときの集中力がすごい」「食べ物への執着にはいつも驚く」「なぜかずっと走っている」などなど、その子ならではの特徴がありますよね。これこそが才能です。
この才能とは、興味関心や得意と言い換えてもいいかもしれませんね。
つまり、子どもは全員天才! そんな思いから名づけた教育アプローチが「天才ノート」です。「天才ノート」は、子どもの「好き」を承認することで、主体的に学びを進めて探究心を育てるツールです。
用意するものと取り組む時間
「天才ノート」はツールといっても、特別なものは何も必要ありません。
用意するのは、この2つだけ。
① 方眼ノート(5ミリ方眼推奨)
② 赤ペン
両方とも100円ショップですぐに買えます。
「天才ノート」に取り組む時間は、「年齢×1分」で十分です。
3歳であれば3分、6歳であれば6分。どんなに慌ただしい日々でも、「年齢×1分」であれば取り組みやすいのではないでしょうか。
そして、「天才ノート」を実践する際のポイントは3つあります。
ポイント① 子どもの関心のあること・好きなテーマを探す
テーマはアニメ、バス、電車、スポーツ、料理、お菓子、ゲーム、歴史、科学、昆虫、動物、恐竜、妖怪、自然など、どんなものでも大丈夫です。
子どもの日頃の様子から、何に興味がありそうか推測したり、子どもに聞いてみたりしてテーマを決めましょう。勉強に関する事柄にとらわれずに幅広く探すことが重要です。
ポイント② 好きなテーマから親が問題(今日のテーマ)を設定
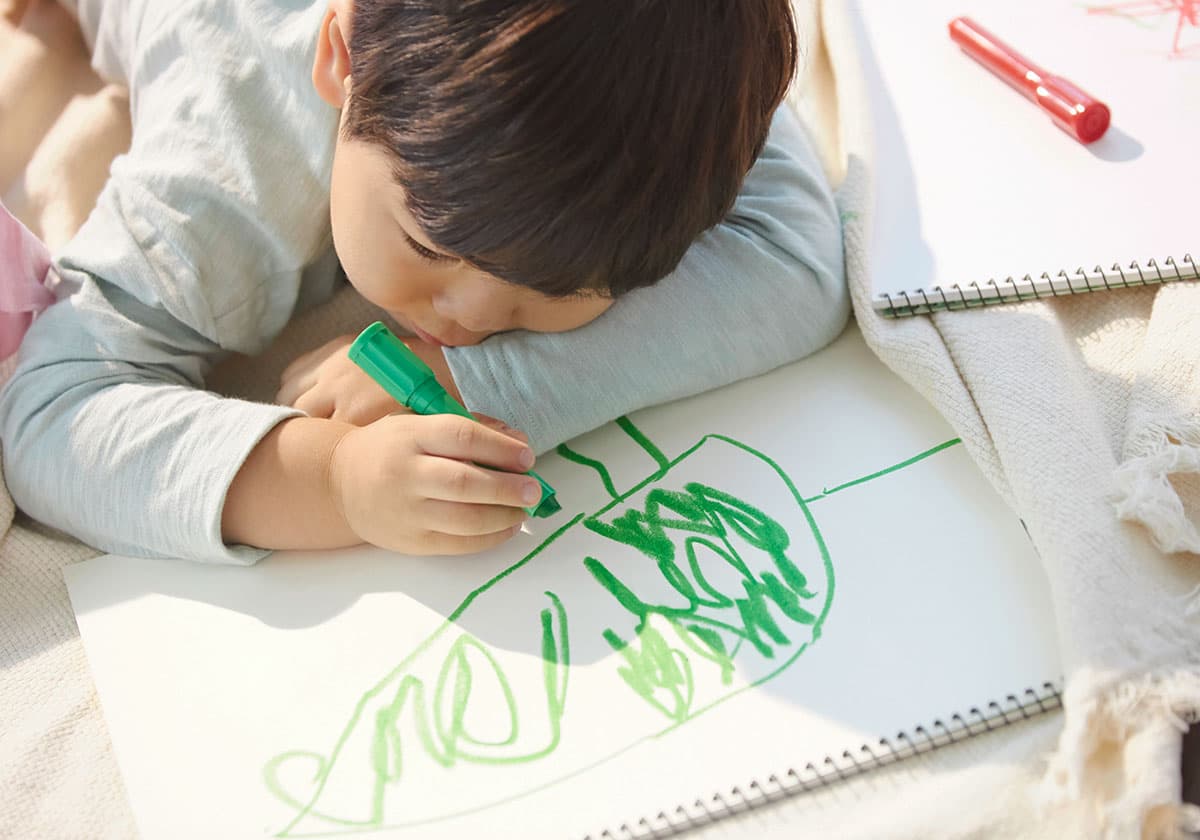
ノート1〜2ページ分で親が問題を出します。多すぎると持続しないので最大でも2ページまでにとどめましょう。
問題といっても難しく考える必要はありません。「好きなポケモンの名前を3つ書きましょう」や「世界で一番強いと思う虫を描いてみよう」「ほしいドラえもんの道具とその理由は?」といった質問で大丈夫です。
ポイント③ 子どもが問題を解いたら、「よくできたね!」と承認して花丸をする
子どもが問題を解けたら、そこに大きく花丸を描いて、「こんなポケモンよく知っているね!」とか「たしかに、この虫はめちゃくちゃ強そう(笑)」など、いいところを探して褒めます。
子どもは好きなことであれば一人でどんどん進めていける

「こんなに短時間でいいの?」「勉強に関係なさそうだけど大丈夫?」、そんな疑問を抱くかもしれませんが、まずは数分試してみてください。
おそらく、子どもは好きなことであれば一人でどんどん進めていけることを、親は改めて実感するはずです。
また、自分の「好き」を軸にしながら、駅名を書くために漢字を覚えたり、恐竜が全長何メートルかを調べる中で単位に触れたりすることにもつながります。
つまり、子ども自身の関心からスタートし、結果的にはいわゆる従来の勉強にたどりつきます。ここでは漢字も計算も、子どもたちの関心を深めるツールにすぎないのです。
次第に、ポイント② の親からの出題がなくても、自分自身で疑問を持って探究したり、気になることを見つけてどんどんまとめていったりするようになります。そうなれば、親の役割はポイント③ のみ! できたことを承認して、子どもがやる気を出せるようにサポートすることこそ、親の役割の本丸です。
『自分から学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』(岩田かおり/ディスカヴァー・トゥエンティワン)
「夏休みの宿題、どれからやればいい?」とお子さんに聞かれたら、なんと答えますか?
答え① 一番時間のかかりそうな宿題からやるといいんじゃない?
答え② 自分の勉強だから、自分で考えてみたら?
答え③ トマトを口にいっぱい入れることじゃん?
……じつは、この答えは③です。
「え? なんで?」と思われた人も多いのではないでしょうか。
その理由が気になる方は、本書の「はじめに」で解説しているので、ぜひお手に取って確認してみてください。