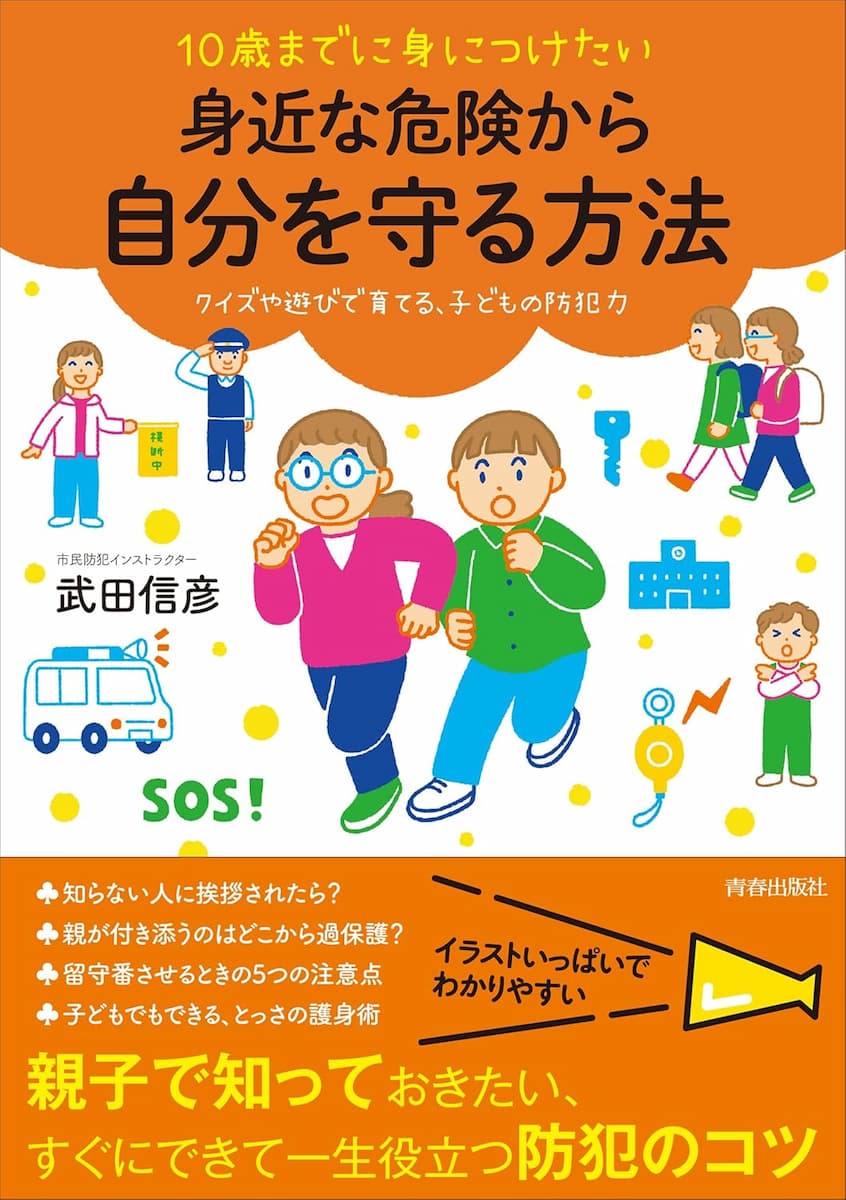「危険な場所」を避ければOK? 犯罪者が子どもを狙う時の“条件”とは
「危険な場所」を思い浮かべる時、暗い道や人気のない公園を思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、防犯の専門家・武田信彦さんは、「ここは危険!と言い切れる特定の場所はない」と解説します。
では、子どもが犯罪に巻き込まれるリスクが高まる場面とは?
防犯の基本を、武田さんの著書から抜粋してご紹介します。
※本稿は武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)より一部抜粋・編集したものです。
Q危険な場所ってどこ?暗い道とか危ないの!?
A 注意すべきは「場所」ではなく「子どもだけになる瞬間」!
「危険な場所は、どこですか?」。
ゴミが散乱し、落書きが放置されているような道は危ない印象を受けますよね。たしかに、不法投棄などの犯罪が発生するかもしれません。
駐輪場や駐車場では、自転車泥棒や車上荒らしも想定されます。
しかし、子どもの防犯対策上、「ここは危険!と言い切れる」特定の場所はありません。また、昔から、「暗い道に気をつけて!」といった注意喚起はありますが、明るい・暗いも関係なし。朝や日中の時間帯にも、子どもが巻き込まれる犯罪は発生しているのです。
子どもの防犯対策で重要な視点は、「場所」ではなくて、「瞬間」です。子どもを狙う犯罪の多くが「子どもだけになる瞬間」に発生しています。
警察庁が作成した防犯啓発資料「みんなで守ろう! 子供の安全!」でも、とくに注意すべき場所として、道路、駐車場、駐輪場、公園、集合住宅の共用部(自宅の周り)が紹介されています。
これは特定の場所を指しているのではなく、子どもだけの状況で犯罪被害リスクが高まる場面として紹介されているところがポイントです。
このように、子どもの防犯対策の基礎は、「子どもだけになる瞬間」を減らすこと。そのため、⾒守りや防犯ボランティアを通じ、⼤⼈が地域で「姿を⾒せる」ことが防犯効果を⾼めます。
また、休⽇や⻑期休みには、防犯活動が休⽌になるうえ、⼦どもだけで外に出る機会が増えるので、⼦ども⾃⾝の「⾃分を守る⼒」も欠かせません。
なお、「子どもだけになる瞬間」は、家族とのお出かけ先であるショッピングモールやレジャー施設でも起こりえます。
「最も注意したいのが、トイレに⾏く瞬間」です。トイレは、ひとりになりやすく、個室もあるため、悪意や犯罪をもつ⼈が犯罪を⾏いやすい環境。
⼤⼈が付き添う、トイレの外から「⼿を洗いなさいよ︕」などと声をかけると効果的です。
さらに、ご⾃宅で家族が顔をそろえていても、「子どもだけになる瞬間」が存在します。お⼦さんが眺めているスマホ……ネット空間には家族はおらず、そこには「⼦どもひとり」。悪意や犯罪をもつ⼈が忍び寄る危険性があるのです。
武田信彦著『身近な危険から自分を守る方法』(青春出版社)
学校・塾・習い事・スポーツ活動など、親の手から離れる時間が増えてくると、子どもがひとりで行動する場面も広がっていきます。 家族と一緒に出掛けた場所でも、家の中でも、じつは「ひとり」のシーンは案外多いもの。
だからこそ、子ども自らが「自分の身を守る」力を育ててあげましょう。クイズやゲーム感覚でできる防犯力の高め方を中央省庁をはじめ、自治体や教育委員会、警察等からの信任も厚い子どもの防犯のスペシャリスト・武田信彦先生が徹底解説。
家庭はもちろん、教育関係者や自治体まで、子どもの防犯に取り組む方々には必携の一冊です。