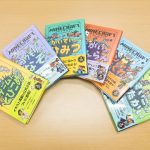難聴の息子の才能どう伸ばした? 水泳ジュニア選手の母に聞いた「好きが未来を変えた瞬間」
生まれてすぐの頃から水が大好きだったという、水泳ジュニア選手の玉造珠宇さん。1歳で聴覚障害がわかり生活は一変しましたが、「好きなことに挑戦してほしい」というご両親の思いから、珠宇さんは水泳の道に足を踏み入れることになります。
「好き」が才能につながった経緯や、ハンデがあるからこその苦労などについて、珠宇さんの母・美穂さんにお話しいただきました。
水が好きで水泳の道へ
──珠宇さんは3歳半から水泳を始められたと聞きましたが、ご両親はどのように珠宇さんの才能を見いだされたのでしょうか。
生後数か月の時、 旅行先で珠宇をプールに連れていったら、本当に楽しそうにしていたんです。水遊び用のオムツをはいた状態で、ずっとはしゃいでいて。 保育園でも水遊びがとにかく好きで、一度水に入るとずっと出てきませんでした。 ああ、この子は本当に水が好きなんだなぁと思っていました。
しかし、1才4カ月の時、珠宇の聴覚障害がわかりました。
それまでは聞こえないと知らずに育てていたのですが、ある時、お姉ちゃんが中耳炎にかかり、一時的に聞こえがちょっと落ちたんです。そこでふと、「あれ、珠宇はどうなんだろう? 」と調べたら、全く聞こえてないってわかって。そこから生活もガラっと一変しました。
2歳前に右耳、3歳前に左耳の人工内耳の手術をして、ハンデはあるものの、なんとか聞こえが整った状態になりました。そこで、スイミングスクールに通わせてみようかなと思い立ったんです。
でも、周りの人たちからは、「耳が聞こえないと断られるよ」と言われましたね。命の安全を保証できないので、実際に聴覚障害を理由に断られたという話もたくさん聞いていて。どうなんだろうとは思いつつ、スクールに相談してみることにしたんです。「耳と頭に聞こえをサポートする装置を付けていますが、水泳用の防水カバーがあります」「この程度は聞こえています」と説明をしたら、予想外に「いいですよ」と許可が出たので、水泳を始めることになりました。
選手を目指すことは考えておらず、ただ好きそうだからやらせてみたんです。
──本格的に選手を目指すことになったきっかけは何でしたか?
最初レッスンは週1回だったのですが、珠宇が「もっとやりたい」というので、週2回に増やしました。そうして練習を重ねる中、5歳の時に、当時のコーチから幼児選手育成コースの推薦をいただいたんです。「聞こえないのに、大丈夫ですか?」と、当時は驚きましたね。
そこからレッスンが週4回になり、その後小2ごろにクラスのレベルがさらに上りました。なので、コーチから声をかけていただいた事が、本格的に競泳をやっていくことになったきっかけです。
──子どもの「好き」が才能につながったのですね。
本当に水に恐怖心がなかったんですよ。 顔に水をつけるのを全く嫌がらなくて。平気で頭からざっぷーんって飛び込む子で(笑)。
本人の好きなものと得意分野が、たまたまカチッとはまったのかなと感じますね。
水泳をサボったことはない
──低学年の頃からハードな環境だったと思いますが、水泳をやめようと思ったことは?
クラスが上がるにつれて練習量も増え、大変そうでしたね。
小さいうちに選手の育成コースに選ばれたこともあり、周りは年上ばかりで。身体もひと回り大きい子たちの中で、珠宇は一番後ろをなんとかついていくような状態でした。
そんな中、小学3年のときに、すごくいい記録がポンと出たんです。そこで本人の気持ちにも、本格的に火が付いたのかなと思います。
すごい世界に足を踏み入れてしまったな、と感じることもありますが、「今日は嫌だからサボる」というようなことは今までありませんでした。休むのは、せいぜい感染症にかかったときくらい。
「行ったふりをして、実は行っていなかった」というようなこともありませんね。まあ、塾はサボったことがあるんですが(笑)。
聞こえにくさからの苦労も
──水泳において、障害があるからこその難しさは感じますか?
スタートの合図が、音ではなく光になるんです。
ピストルの先がピカッと光るのを目で確認してからスタートしますが、この「見てから動く」という動作は、0.01秒を争う世界ではどうしても遅れにつながってしまいます。
距離が長くなれば、スタートの差はレースの中で埋められますが、短距離では、そのわずかな差が命取りになります。特に50メートルでは、出遅れると挽回が難しいですね。
競技だけでなく、招集のときにも難しさがあります。
大会では、次に出場する選手の名前が呼ばれ、待機場所まで移動するのですが、その案内が音声のみです。聞こえる選手なら「そろそろかな」と見計らって移動できますが、珠宇は招集員のすぐそばで、かなり前から待たなければなりません。ずっと「いつ呼ばれるのか」と集中して待っていなければならないので、大変ですよね。
また、珠宇が聞こえないことを知らない人も多くいます。見た目ですぐ分かる障害ではないため、気づかれにくいのです。
──なかなか気づかれないからこその苦労もありそうですね。
声での会話はできますし、静かな環境であれば話も聞き取れますからね。
学校生活では、教室に入ると30人ほどの子どもたちの声が重なり、全く聞き取れないことがあるようです。担任の先生にはマイクをつけてもらい、声や指示が耳に入るようにしていますが、それでも、友達が盛り上がる瞬間などは分からず、少ししょんぼりしてしまうこともあります。
それでも珠宇は、聴、難聴、デフの世界に身を置きながら、自分が聞こえないことをある程度受容できているんですね。だから、そんな自分に自信を持って、頑張っていってほしいと思います。
(取材・文:nobico編集部)