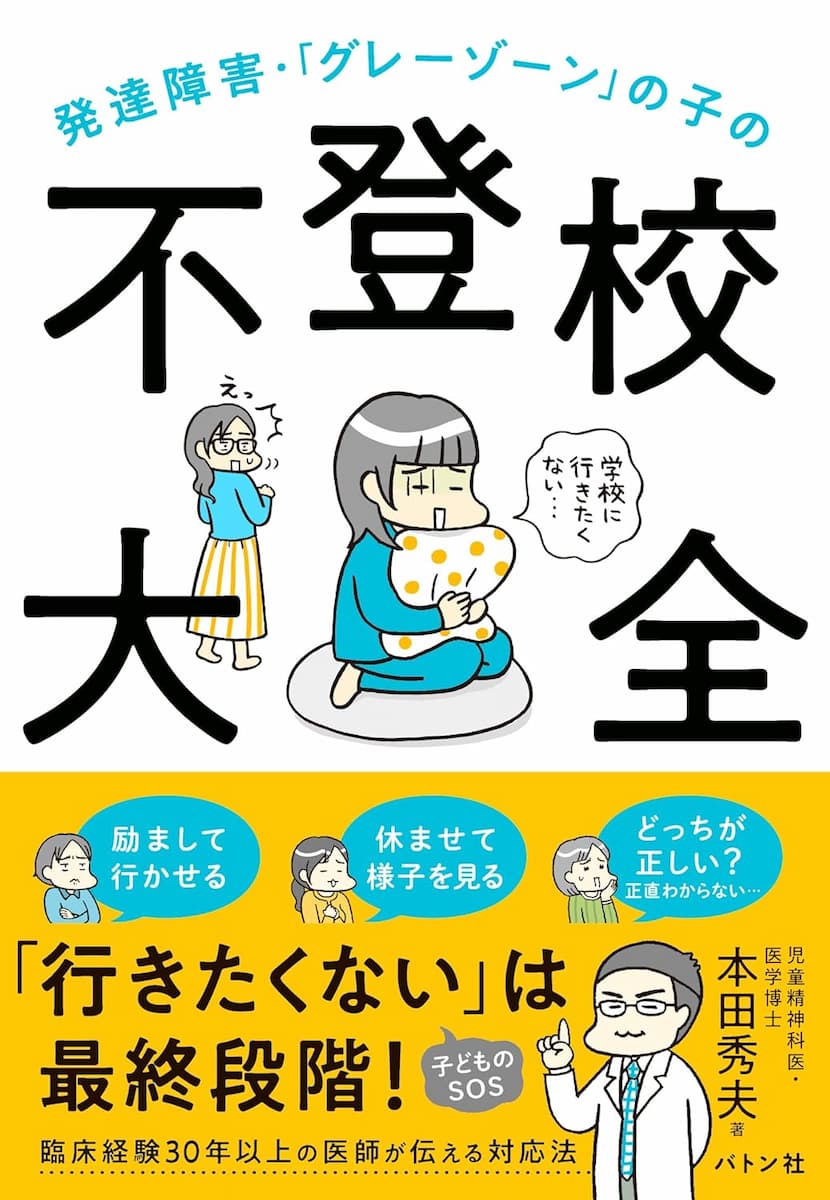今の子どもは期待されすぎ? ノルマとダメ出しが不登校につながる理由
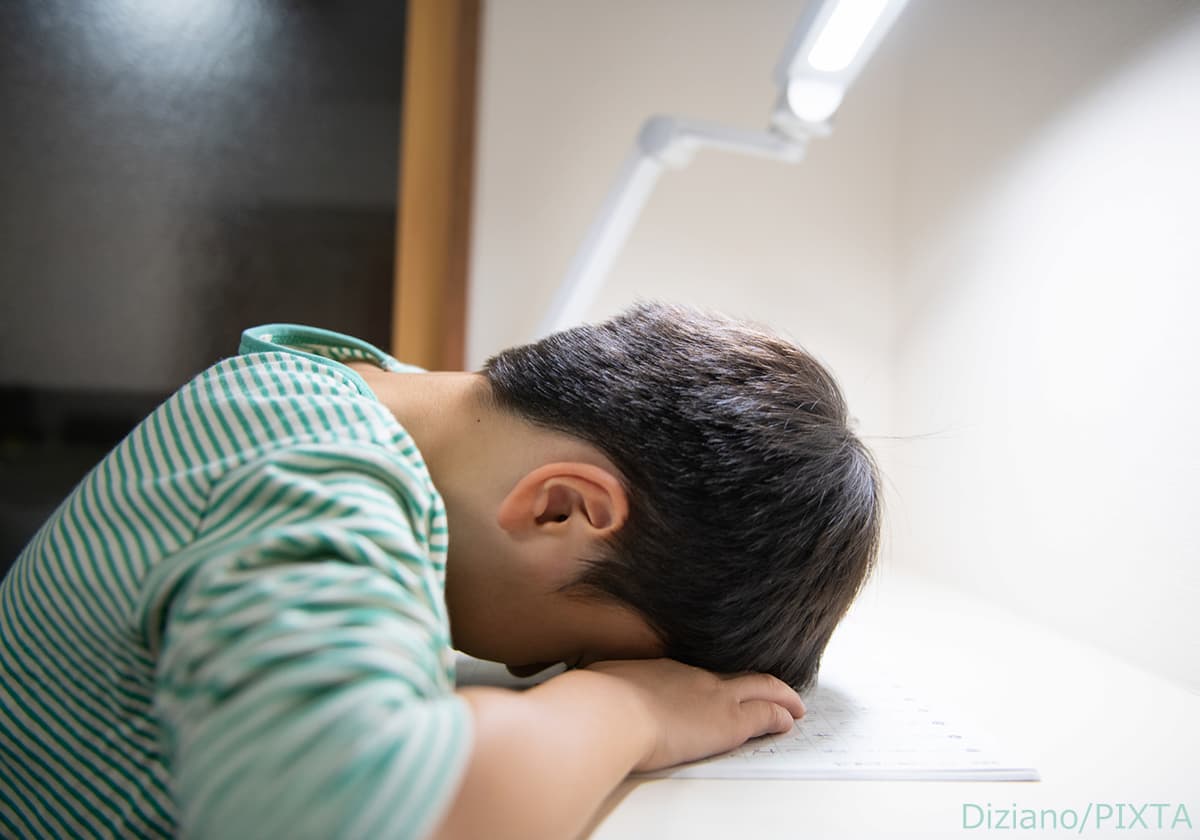
今の学校は「ノルマ化とダメ出しが多すぎる」と語る、精神科医の本田秀夫先生。平均的な子どもにも「背伸び」が求められる環境が、子どもたち、特に発達に特性のある子に負担を与えていると解説します。
今の子どもたちを取り巻くプレッシャーと不登校との関係とは?本田先生の著書からその解説をご紹介します。
※本稿は本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)より一部抜粋、編集したものです。
なんで不登校が増えているの?
不登校の原因は一つではなく、学校や家庭の悩みなど複数の要因が関わっています。不登校への対応では、子どもの状況を理解することが大切ですが、一方で、急増する不登校という全体的な傾向については、環境的な要因も考える必要があります。
学校にはノルマ化とダメ出しが多すぎる
不登校の背景は、子どもによって異なります。多くの場合、原因は一つではなく、学校での悩みごと、学校以外での悩みごとなど、さまざまな要因が関わっています。子どもの不登校に対応するときには、その子がどのような状況にあるのかを理解していくことが大切なわけですが、一方で、不登校になる子どもが急増しているという全体的な傾向について、環境的な要因を考えていく必要もあります。
私は、学校生活にノルマ化とダメ出しが多すぎることが、不登校の環境的な要因になっていると考えています。
「入学のしおり」が厳しすぎる

小学校の「入学のしおり」で、新入生に身につけてほしいこととして、次のような項目が挙げられているのを見かけたことがあります。
・人に呼ばれたとき、「はい」とはっきりと返事ができる
・人の話をしっかり聞ける
・自分の名前や家族の名前が言える
・自分の名前(ひらがな)を読むことができる
・自分で身の回りの始末をすることができる
・自分で洋服を脱いだり着たりすることや、脱いだものをたたむことができる
このような行動を、入学するまでに家庭で教えておいてほしいという話なのですが、そう言われても、できない子もいます。大人にだって、人の話をよく聞いていない人や、脱いだ服をきちんとたたまない人がいるでしょう。小学1年生向けの「入学のしおり」にしては、基準が厳しすぎます。
ここで挙げた項目はあくまでも一例ですが、最近の学校ではこのような行動がノルマ化していて、それができない子どもはダメ出しされることがあります。苦手なことは克服するように目標設定され、できなければダメ出しされるのです。いまの子どもたちは、早い時期からさまざまなことのハードルをやや高めに設定されて、そこに届かないと認めてもらえない雰囲気のなかで過ごしていることがあります。最近では、学校や学級にそのような雰囲気があり、不登校の環境的な要因となっている場合があるのです。
学校のカリキュラムは平均的な子ども向けにつくられていると言われますが、こういった例をみていると、いまの学校は平均的な子どもであっても、少し背伸びをしないと標準に到達できない環境になってきているように感じます。
勉強面でも過度の期待をかけられる
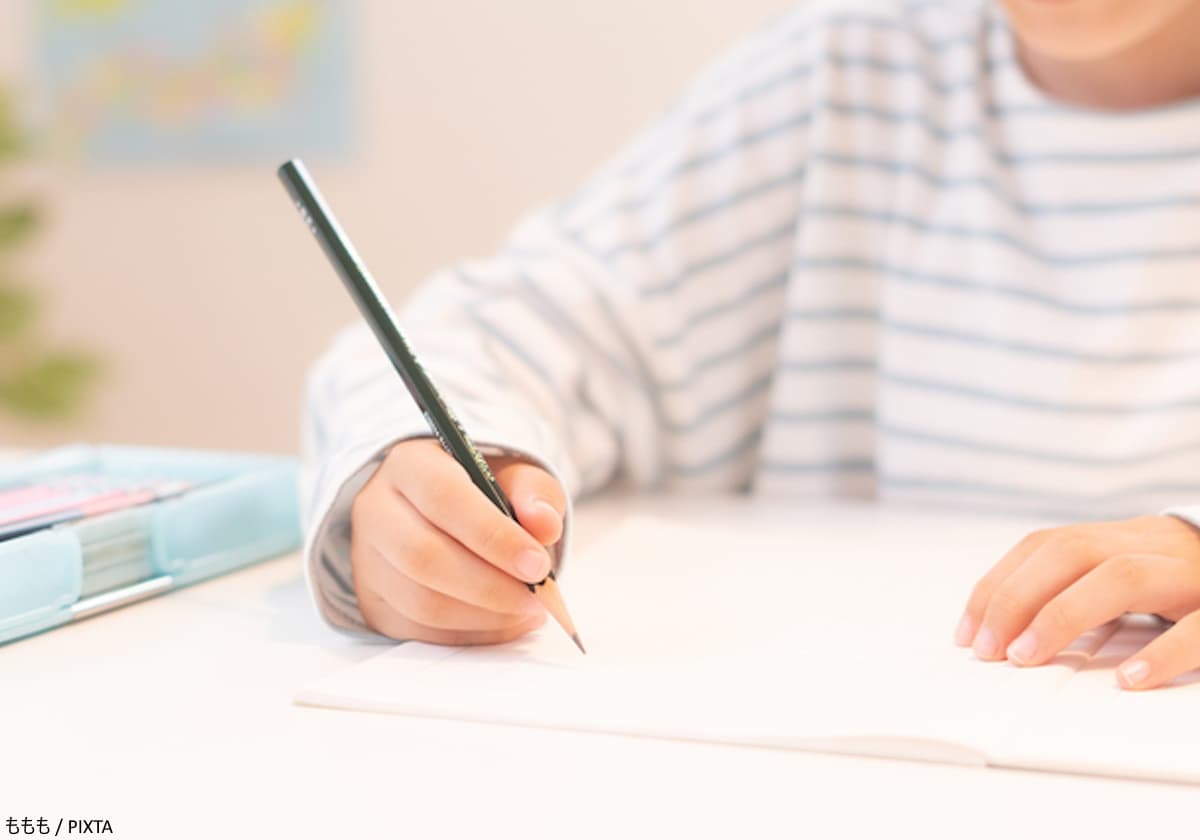
「入学のしおり」は主に生活面の話でしたが、勉強の面でもノルマ化とダメ出しがみられます。いまの子どもたちは、勉強面でも過度の期待をかけられていることがあります。年々出生数が減っているなか、高等教育を受ける学生の割合は次のように増えています。
・1990年度:18歳人口が約201万人、大学進学率24.6%、大学進学者約49万人
・2023年度:18歳人口が約110万人、大学進学率57.7%、大学進学者約63万人
※文部科学省の「学校基本調査」
出生数が減って少子化しているにもかかわらず、高等教育に進学する層は拡大していて、大学生の人数は増えています。その結果として、勉強の苦手な子が、無理な学習を強いられる場面が増えているように感じます。勉強ができなくて困っていても、高校や大学への進学を期待され、成績が上がらないと叱られてしまう。そのような状況で、子どもが学校に行く意欲を失っていくこともあります。これもノルマ化やダメ出しの一つの例です。
受験して中高一貫校に入学し、不登校になった子

中学1年生 男子の場合
勉強面で無理をして、不登校になったケースを紹介しましょう。このお子さんは中学1年生の男子です。彼の場合、勉強が苦手ということではないのですが、両親から私立の中高一貫校を目指してほしいという期待をかけられ、受験勉強で無理をしていました。
彼は小学3年生の頃から、学習塾に通うようになりました。夏休みなどの長期休みにも毎日のように塾へ行って、講習を受けていました。その努力の甲斐あって、志望校に合格。そのときは本人も両親も大喜びしたそうです。
ところが中学に入ってから、授業やテストの内容が難しくて、ひどく苦労するようになりました。彼は時間をかけて勉強し、背伸びをして学力レベルの高い中学に入ったので、同じように勉強を続けなければ、ほかの子どもたちについていけなかったのです。その結果、1学期の途中から登校をしぶるようになり、夏休み明けの2学期には学校に行けなくなりました。
親や先生の期待が高すぎると不登校になる可能性も
このお子さんは、平均的な子どもよりも勉強がよくできます。それでも目標を高くしすぎると、ノルマ化やダメ出しが本人の負担となるのです。親や先生の期待していることが
子どもに合っていない場合には、たとえ勉強が得意な子でも不登校になることがあります。
そして、学校生活にノルマが多くなると、子どもだけではなく先生も苦労します。先生の「教えるノルマ」も増えてしまいます。昭和40年代、小学生だった私の学校では、1年間の授業で教科書を最後まで読み終わらないことが珍しくありませんでした。教え方のペースは先生によって違い、勉強の「教えるノルマ」はいまよりゆるやかだったと思います。
最近では、教科書を終わらないという話は聞きません。先生方が教科書の内容を律儀に全部教えようとしているようです。地域差はありますが、先生の「教えるノルマ」は増えている印象です。現在の学校は「子どもも先生もつらい」という状況かもしれません。
まとめ
いまの学校にはノルマ化とダメ出しが多すぎて、子どもたちも先生も苦労しています。平均的な子どもであっても、少し背伸びをしないと標準に到達できない環境になってきているように感じます。ノルマ化とダメ出しの多さが不登校の環境的な要因になっていると考えられます。
本田秀夫著『発達障害・「グレーゾーン」の子の不登校大全』(バトン社/フォレスト出版)
「発達特性を持つ子どもの不登校」に焦点を当てた初の書籍
子どもが「学校に行きたくない」と言ったら、大人はどうすればいいのでしょうか。
休ませて様子を見たほうがいいのか。
それとも、励まして登校させたほうがいいのか。
保護者の方からそのように聞かれることがあります。
学校の先生方から「どう対応すればいいのか」と質問されることもあります。
この本では、そのような悩みにお答えして保護者や学校の先生をしっかりサポートしていきたいと思います。
<中略>
私は、不登校になっているお子さんもみてきましたが、発達障害や知的障害があっても登校できているお子さんもみてきました。ですから「学校に行けるお子さんは、どうして行けているのか」を知っています。何がポイントなのかをお伝えすることができます。
主には発達特性がある子を対象とする話ですが、この本の内容の多くは、特性が目立たない子にも通用します。お子さんの不登校に悩んでいる保護者の方や学校の先生方、子育て・教育に関わっている支援者の方々に、ぜひ読んでいただきたいと思います。
(「はじめに」より)