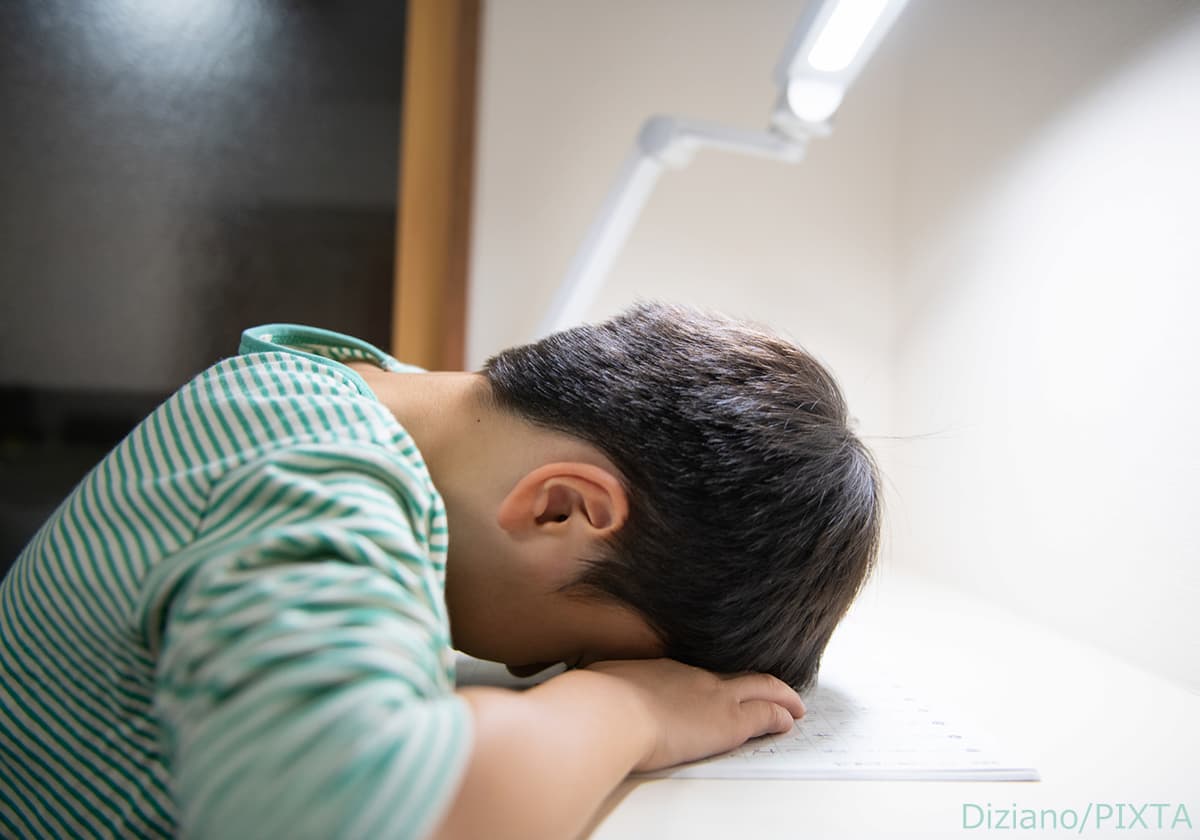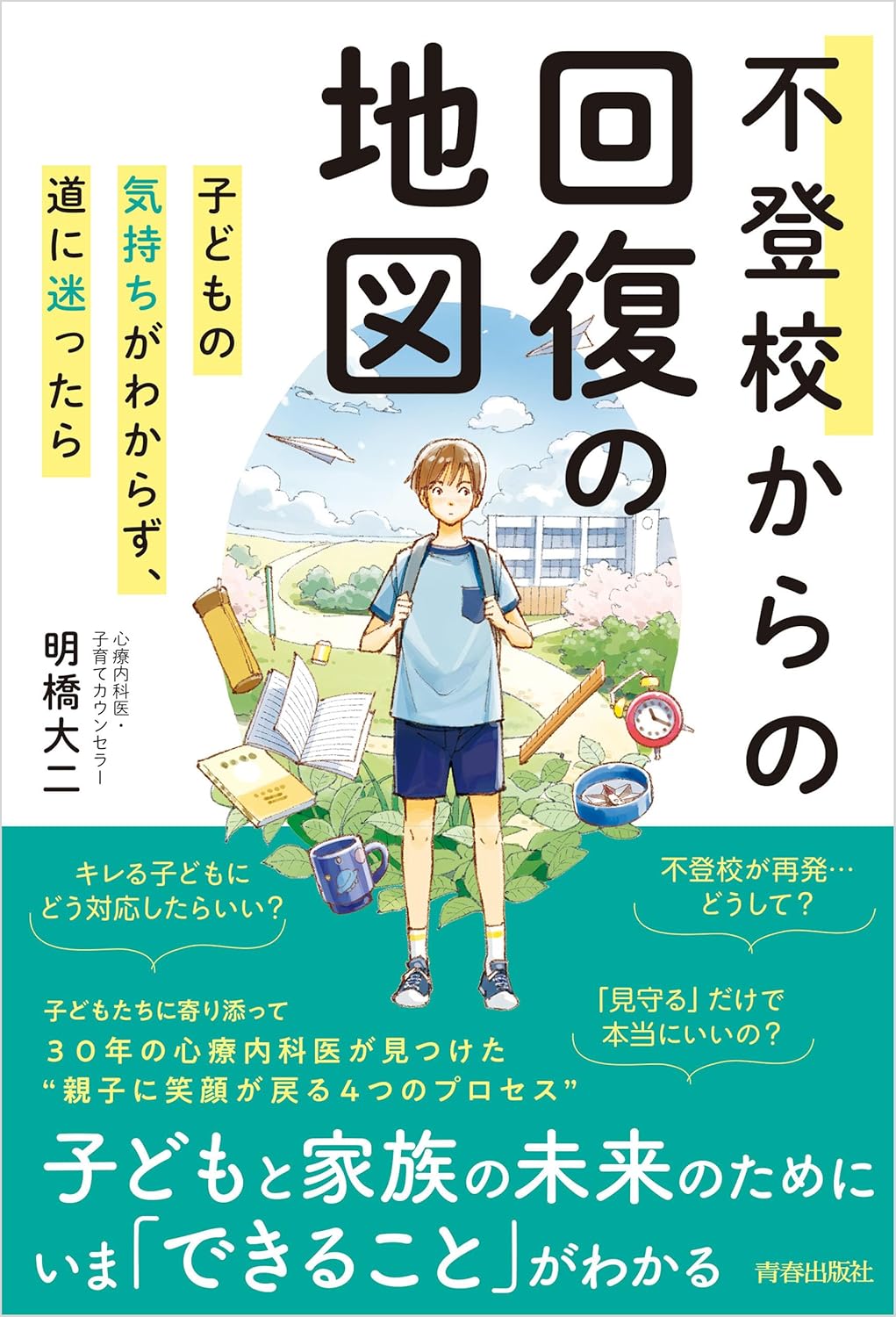子どもが学校に行けない本当の理由…見逃してはいけない2つのサイン
学校に行けないわが子を前にすると、親は「どうすれば行けるようになるのか?」と考えてしまいがちです。しかしその前に必要なのは不登校の子どもが発する心と身体のサインに目を向けること。
「不登校の子どもの心と身体では、オーバーヒートや凍りつき反応が起きている」と語るのは、心療内科医で子育てカウンセラーの明橋大二さん。この2つのそれぞれの特徴とは?明橋先生の著書『不登校からの回復の地図』から紹介します。
※本稿は、明橋大二著『不登校からの回復の地図』(青春出版社)より一部抜粋、編集したものです。
子どもの心の中で起こっていること
不登校状態をどのように理解するのか、不登校の子どもの心と身体に何が起きているのか、少し掘り下げて考えてみたいと思います。不登校の状態には、大きく分けて2パターンあると、私は考えています。
ひとつは、オーバーヒート。この特徴は、疲労です。もうひとつは、凍りつき反応。この特徴は、不安と恐怖です。 場合によっては、この2つが重なっていることもあります。それぞれについて説明してゆきたいと思います。
まず1つ目のオーバーヒートですが、これは、心身の疲れが限度を超して、いわばオーバーヒートして、学校に行けなくなる、というものです。
たとえば、電気ごたつなどだと、温度が上がりすぎると、サーモスタットが作動して、スイッチを切ります。それと同じように、私たちの心と身体にも、サーモスタットのようなものがあって、心身の疲労が限度を超すと、そのサーモスタットが作動して、スイッチを切る。それが子どもの場合、不登校だ、ということです。
ですから、これはある意味、きわめて自然な生理的な現象であって、むしろ生体の自己回復力のあらわれです。電気ごたつでは、温度が下がればまた回路はつながるように、不登校も、疲労が取れれば、元気は回復してきます。
もし、サーモスタットが作動しなかったら、電気器具はどうなるでしょうか。オーバーヒートして、壊れてしまったり、最悪、火事になったりしてしまいます。人間の心身もそうで、もしサーモスタットが働かなかったら、逆に本当の精神的な病気になってしまったり、自殺をしたり、ということにもなりかねません。
私の経験した事例では、20歳を過ぎてから精神疾患になった人が、後になって「実は、学校でずっといじめを受けていた。しかし親が暴力的な人で、学校に行きたくないなどと言えなかった。だからずっといじめに耐えるしかなかった。だから不登校の子がうらやましい。自分は不登校さえもできなかった」と語った例がありました。
あるいは別の患者さんは、高校の卒業式の晩から、家庭内で激しく暴力を振るうようになり、同時に摂食障害を発症しました。その人も、学校で中学校・高校とずっといじめを受け続けていたのですが、家では虐待を受けていたのです。
ですから学校に行きたくない、などと言おうものなら、殴る蹴るなど何をされるか分からない。家にいるよりは、学校でいじめられているほうがまだましだ、と学校に行き続けていたのです。
そして高校3年生の卒業式の晩、というのは、もう学校に行かなくてもいい、という日。その日にとうとう今までため込んできた心の苦しさが爆発して、精神疾患を発症した、ということです。
その人が回復するのに、その後、10年の歳月が必要でした。もしその人が不登校になって、学校に行かずに済めば、心の傷もそこまで深くならなかったのではないかと思えてなりません。
さらに深刻なケースに、いじめ自殺というものもあります。いじめ自殺というのは、もしその人たちが不登校になっていたら、死ななくて済んだ人かもしれません。
いじめを受けているのに、それでも学校に行き続けたために、自殺まで追い込まれてしまったと言える場合もあると思います。もちろん何より優先すべきは、いじめ行為をやめさせ、被害者をしっかり守る、ということですが、それがどうしてもなされない場合は、学校を休んで、いじめの現場から離れるということもあっていいと思います。
そういう意味で、学校に楽しく行けたなら、もちろんそれに越したことはないかもしれませんが、どうしてもつらい場合は、命を犠牲にしてまで行かねばならないところでは決してない、ということです。
ですから学校に行けない状態なのに、無理やり学校に行かせようとすることは、例えて言えば、電気器具がオーバーヒートして、サーモスタットが作動してスイッチが切れたのに、「なんでスイッチが切れたんだ!」と怒って、無理やり回路をつなげようとする努力だとも言えるでしょう。
いかにむちゃなことか分かっていただけると思います。実際、学校に行けない子どもを無理やり学校に行かせようとすると、子どもは激しく泣き叫んで「そんなら自分が死ねばいいんだろう!」と言ったりします。
どうしても学校に行けない、しかし家で休むことも許されないとすれば、子どもは、死を考えるしかなくなってしまいます。それは決して、親も望んでいることではないはずです。
外に出られないのは「凍りつき反応」のせいかもしれない
2つ目に、不登校の子どもが学校に行けない理由として、疲労というよりも不安や恐怖を訴える場合も少なくありません。オーバーヒートという考え方では、この不安や恐怖を訴える不登校をうまく説明できないと感じていました。
そんなとき、この状態をとてもよく解き明かす、新たな理論に出合ったのです。それがポリヴェーガル理論です。
ポリヴェーガル理論とは、アメリカの神経生理学者、ステファン・W・ポージェスによって、1994年に提唱された、自律神経系についての新しい理論です。
現在、これは、トラウマやPTSDの理解や治療に広く用いられ、その有用性が証明されています。一方で、この理論は不登校の理解にも役立つ、ということで、最近、不登校状態をこのポリヴェーガル理論で説明する人も増えてきました。
ポリヴェーガル理論では、人間が脅威にさらされたとき、2種類の防衛反応を取る、と言います。ちなみにこの「脅威」ということですが、何を「脅威」と感ずるかは人それぞれで異なります。
2種類の防衛反応というのは、ひとつは、「闘争/逃走反応」と言われるものです。逃げるか戦うか、という反応です。山で熊に出合ったとき、ふつうは逃げると思いますが、中には戦う人もあります。そのときに活性化するのは、交感神経系です。
心臓は激しく高鳴り、呼吸は荒くなります。逃げたり戦ったりしやすくするためです。末梢血管は収縮します。攻撃されても出血しにくくするためです。このような反応は、皆さんもよく経験して知っていると思います。
しかし脅威の中には、戦うことも逃げることもできないときがあります。このときに発動するのがもう1つの防衛反応、凍りつき反応です。ここで働くのは、背側迷走神経系です
迷走神経とは、副交感神経の一部で、延髄(えんずい)から出ている神経ですが、延髄の背中側の核から出ている迷走神経を背側迷走神経と言い、腹側〈前方〉の核から出ている迷走神経を、腹側迷走神経と言います。
この反応が起きると、まず身体が動かなくなります。また意欲や思考力も損なわれます。そして自律神経系の反応ですから、自分の意志ではどうすることもできません。またいったんこの凍りつき反応が起きると、回復には長い時間がかかります。
動物でも大変な脅威に面したとき、「死んだふり」をして難を逃れたり、人間でも強いショックを受けると、意識を失ったり、腰が抜けたりすることはよく知られる事実でしょう。
しかしこのような反応は、実は不登校の子どもにもよく見られる現象です。不登校の子どもは、戦うことも逃げることもできません。学校に行かねば、というプレッシャーは世の中に非常に根強いですから、そんな簡単に学校から逃げることはできないし、学校と戦う、なんてこともできません。
夜には「明日は学校へ行く」と言いますが、朝起こそうとすると、布団から出てきません。また意欲や思考力も失われ、ぼーっとしていたり、家でごろごろしているだけになったりします。
自分の意志ではどうにもならないので「頭では行かなきゃと思うけど、身体が動かない」と言います。そして回復には数ヶ月から数年という長い時間がかかります。
要するに、不登校状態というのは、ポリヴェーガル理論でいう、一種の凍りつき反応であり、何らかの脅威に出合ったときの防衛反応と考えられるのです。
ただここで疑問に思う人もあるかもしれません。確かに、猛獣に出合うとか、凶悪犯に襲われるなどの、命の危険にさらされたときに凍りつき反応が起きるのは分かるが、学校にそれほどの脅威があるとは思えない。なのになぜ凍りつき反応が起きるのかと。
そこでヒントになるのが、HSCについての知識です。HSC は、先ほど述べたようにひといちばい敏感なことから、先生の叱り声や友達の暴言、喧嘩、人前での発表などが苦手です。
それが積み重なると、本人には大きな脅威として認知されます。それが結果として凍りつき反応を惹じゃっき起するきっかけとなることがあるのです。
たとえ典型的なHSCでなくても、脅威の感じ方は人それぞれです。その子にとって、学校にいくのがつらい、教室が怖い、と感じるなら、それはやはりその子にとっては脅威なのだと思いますし、闘うことも逃げることもできない状況の中で凍りつき反応が起こっても不思議はないと思われます。
心療内科医・子育てカウンセラー明橋大二著『不登校からの回復の地図』(青春出版社)
不登校児童が増える今、「最近、子どもが学校に行きたがらなくて…」「朝、子どもを起こそうとしても、ちっとも布団から出てこないんです」「このまま、ひきこもってしまうのではと不安です」などの相談を30年以上受けてきた心療内科医が、「これだけは伝えたい」と思ったことをまとめた一冊。