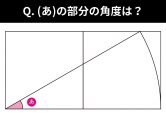子どもはなぜ柵を乗り越える? ベランダ転落事故を専門家が解説

過ごしやすい季節に注意したいのが、子どものベランダ転落事故。
10月は、5月に次いで2番目に事故の発生件数が多いという調査結果もあり、東京都生活文化局消費生活部も注意情報を発信しています。
「親がしっかり見ていれば防げる」と思われがちなベランダ転落事故すが、それだけでは限界があるのが現状です。
子どもの命を守るために大切な事とは?子どもの安全対策について研究する、専門家の大野美喜子先生にお話をうかがいました。
※この記事は前編です
子どもはなぜ危険な行動をする?

─そもそも、子どもはなぜベランダの柵をのりこえてしまうのでしょうか。
正確な理由はわかりませんが、好奇心が旺盛な時期なので、つい柵に登ってみたくなった、あるいは外の景色や物に興味をもったのかもしれません。
また、子どもには、“穴があれば指を突っ込んでみたくなる“、“ソファがあれば登ってみたくなる“といった「試してみたくなる」という特徴があります。
子どもが「やってみたい」と思うこと、チャレンジすることは、発達の過程においては大切な姿のひとつでもあります。
─「ここは高いから危険だ」ということが、子どもにはピンとこないんでしょうか。
「高い」ということは理解できるのかもしれませんが、例えば「落ちるかもしれない」と予測したり、落ちた後に重症になるリスクを判断する力はまだ未熟だと思います。子どもたちが自分でリスクを判断して、「やりたい」と思う行動を抑えるということは、まだできないのではないでしょうか。
―事故に遭いやすい子に共通する特徴はありますか?
転落事故に限らず、統計的には男の子の方が事故に遭う率が高く、また発達障害のある子や多動傾向のある子は事故に遭いやすいという調査もあります。しかし、実際には子どもの特徴だけで、事故のリスクが大きく変わるわけではありません。
「うちの子はおとなしいので大丈夫」とおっしゃる親御さんもいますが、おとなしい子だからといって事故に遭わないわけではありません。こうした保護者の認識に関係なく、子どもが安全に過ごせる環境や対策の仕組みを整えることが大切です。
―転落による死亡事故の数は多いのでしょうか。
子どもの数が減っていることもありますが、いわゆる事故による子どもの死亡は、この10年で大きく減っています。
ただ、その一方で「事故そのものの件数」はほとんど減っていないんです。死亡事故は確かに一番重症な結果ですが、亡くならなくても後遺症が残ったり、その後ずっと医療的ケアが必要になるケースがあります。
ですから、今は、死亡事故だけでなく、重い後遺症につながった事故の方にもっと目を向ける必要があると思います。
保護者ができる対策は

―小さい子どもに対して事故の危険性を上手に伝えるにはどうしたらいいのでしょうか。
ベランダや遊具など転落リスクのある場所で、「ここは高いから危ないね」と声をかけ、普段の生活の中で危険を教えていくことは大事です。ただし、子どもへの教育だけでは転落を予防することはできません。転落の予防対策と、子どもにリスクを教えることは、切り離して考える必要があります。
―予防に関しては、大人が対策していくしかないということですね。
そうですね。中学生くらいになれば、ある程度リスクを自分で判断できるようになりますが、未就学児や小学生は、転落のリスクを判断する能力がまだ未熟です。だからといって、「小さい子はリスクの判断ができないから、転落しても仕方ない」ということにはなりません。危険を判断する能力が未熟な時期には、大人がきちんと対応する必要があります。子どもが安全に生活できるよう、大人が環境を整えることが大事だと思います。
―実際の事故がどういう状況で起きていたのか、共通する特徴があれば教えていただけますか?
室外機など、柵の近くに足がかりがあると転落するリスクが高まります。実際に事故が起こった状況でも、足がかりがあったことが報告されています。
ただし、実際にどのような状況で子どもが転落しているのか、詳細がわからないことも多いのが現状です。転落事故が起きた場合、特に死亡事故の場合は、警察が現場検証を行いますが、その調査結果が公表されるわけではありません。実際にどんな状況だったのかは、記者の取材によって断片的に報道されるだけで、全容を把握することは難しいのです。こうした情報の不足は、社会の仕組みとして大きな課題だと思います。
―室外機など、足がかりにになりそうなものの置き場所を見直すほかに、やるべきことは何でしょうか。
今、優先的に行うべきとされているのは、補助錠の設置です。子どもがベランダに一人で出たり、窓を開けたりできないように、クレセント(窓についている鍵)以外に、子どもの手が届かない場所に補助錠をつけることが推奨されています。まずは子どもが鍵を開けられない環境を作ることが、現時点では優先すべき対策だと考えられています。
賃貸の場合も、不要になったら取り外せるタイプの補助錠があります。使い勝手は製品によりますが、対策は可能です。やらないよりは、やった方が安心ですね。
ただ、転落事故は、どんな対策をしても起こる可能性があります。
現在、保護者ひとりひとりの対策に頼っていますが、事故は起こり続けているので、これからは、社会の仕組みとして対策を普及させる方法を確立することが大切だと感じています。
【東京都 WEBサイト】
■ベランダからの子供の転落に注意!(東京くらしWEB)
■こどもが住宅等の窓・ベランダから墜落する事故に注意!(東京消防庁)