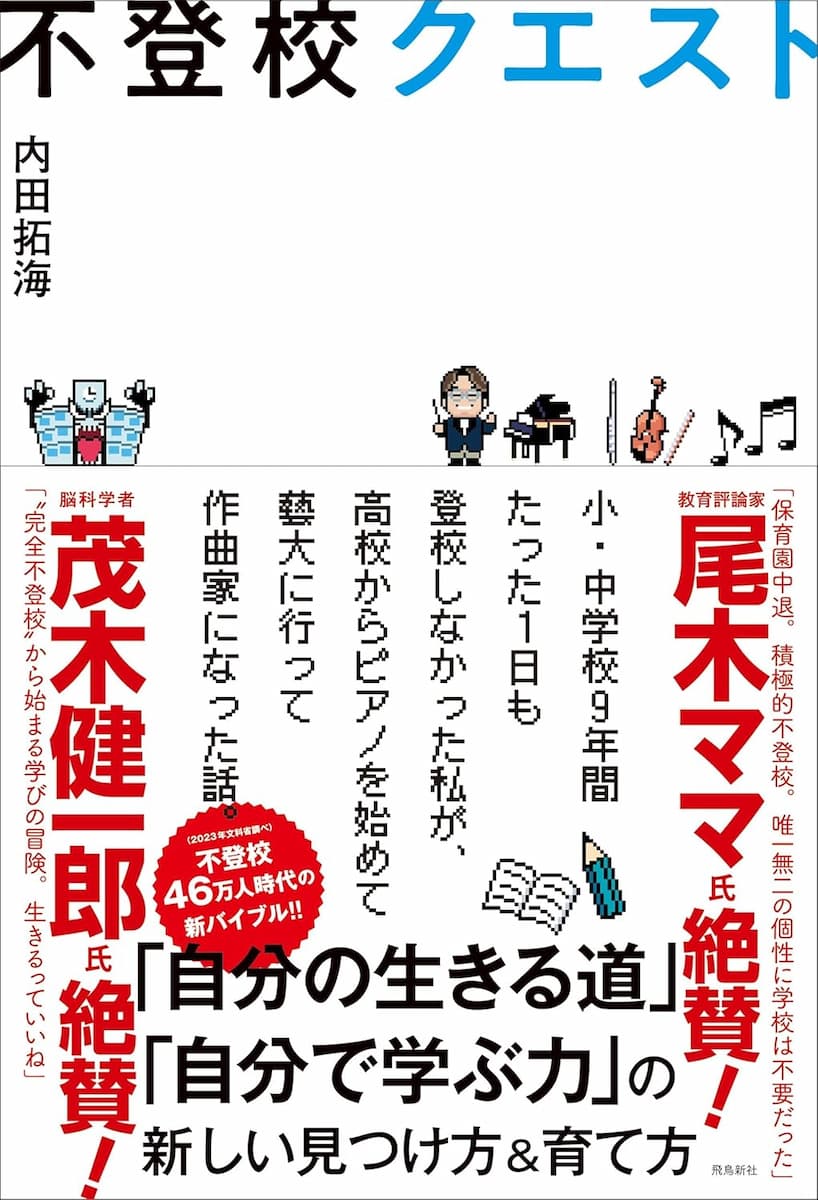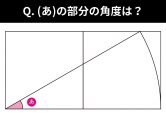6歳で「学校には行かない」と不登校宣言 両親が子どもの意見を尊重した理由は

藝大の音楽学部を卒業し、現在作曲家として活躍する内田拓海さんは、小・中学校の9年間、1日も学校へ行かなかった過去を持っています。
内田さんが6歳にして「学校には行かない」と決心したいきさつ、そしてその時のご両親の反応とは?
ご自身の不登校を振り返る著書『不登校クエスト』から、一部を抜粋してご紹介します。
※本稿は内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)より一部抜粋、編集したものです。
不登校だけれどコミュニケーションは「大好き」

私の家はトラック運転手の父と母、妹2人の5人家族。幼少期はどちらかと言えば、生活を切り詰めるような貧しい時期もありましたが、それ以外はごくごく一般的な家庭だったと思います。
父も母も、普通に義務教育を受けて育ってきていますから、そんな家庭で「学校に行かない」という選択をすることは、大きなチャレンジだったかもしれません。「9年間ただの1日も学校に通わなかった」と聞くと、たいていの人は私に対してこう思うかもしれません。
「さぞや人嫌いで“コミュ障“なんだろうな」
「周囲や社会から離れて、引きこもって生きてきたんだろうな」
たしかに同世代の子どもとの関りは極端に少なかったので、半分は当たっていますが、私自身は人嫌いやコミュ障ではまったくありません。むしろどちらかといえば、幼い頃から人とのコミュニケーションが大好きでした。1人で遊ぶだけでなく、近所の子どもや身近にいる大人と遊んでいることも多かったと思います。
「人とコミュニケーションをとることが大好き」という部分は、1人で作業を進めることが多い作曲家になった今も、変わっていません。
保育園で理不尽な大事件

そんな私が、なぜ小・中学校に「行かない」と決めて、それを頑なに実行したのか?不登校を始めるきっかけは、それより前の保育園時代にさかのぼります。今もはっきりと覚えている、明確なきっかけがありました。
母も働いていて共働きだったので、私は保育園に預けられるようになったのですが、通い始めて少しも経たないうちに、“事件“がその保育園で起きました。
その頃の私は絵を描くことが大好き。その日も、保育園にあるクレヨンで楽しく絵を描いていました。みんなでシェアしながらクレヨンを使っていたのですが、突然、そのうちの1人が、私がまだ使っている途中のクレヨンを奪い取ってしまいました。急な出来事にびっくりしたのですが、私がすぐにその子からクレヨンを取り返すと、その子は泣き出してしまいました。
すると、保育園の先生は私を叱りました。
「違うよ! 最初に取ったのはあの子だよ!」
そう訴えたのですが、先生は聞く耳を持たず相手にしてくれません。悔しさのあまり、私も大号泣してしまいました。
「もう、あんなところには行きたくない」
涙ながらにそう訴える私に、思うところがあったのでしょう。このようなトラブルがほかにも立て続けに起こったこともあって、母は保育園に私を預けることをやめました。
この事件の頃からかもしれません。
自分以外の誰かが決めたこと――「行かなければならない」場所や「しなければならない」ことに対して、私が不信感や違和感を持つようになったのは。
6歳で確信した「小学校には行かないほうがいい」

保育園に行かなくなった私は、自宅で絵を描いたり公園に遊びに行ったり……と自由に楽しく生活をしていました。そんな6歳の冬のある日だったと思います。
「こういうのが来たよ?」
母はそう言いながら、私に1通のハガキを見せてくれました。市役所から送られてきた入学通知書でした。
《ご入学おめでとうございます!》と、お祝いの言葉が添えられていたのを、よく覚えています。
「来年から小学生だって。どうする?」
「どうする?」というのは、言うまでもなく「小学校、行く?」という意味です。一般的に考えれば、小学校に行くも行かないもありません。基本的には誰もが行くものであり、親が子どもにわざわざ意思確認すること自体、なかなかないでしょう。
でも母は、こだわりが人一倍強く、頑固で、保育園をすぐに辞めたりしてしまった息子に何か思うところがあったのかもしれません。入学通知書には入学予定の公立小学校が記載されていて、決められた期日までに必要事項を記入して、その指定小学校に提出しなければいけないことになっていました。
「どうする? 行く?」
「いや、行かないよ」
私は、一切迷うことなく即答しました。
「小学校には行きたくない」
私は、まったく迷うことなく即答しました。
「えっ! 本当に行かないの?」
私の言葉に母は少し驚きながらも、その後、「小学校に行かせる」か「本人の意思を尊重する」か、父と話し合ったそうです。母に当時の話を聞くと、「“学校に行かない“というかもしれない」という予感はあったと言います。
当時、私は6歳。世の中のことを何ひとつ知らない子どもでしたが、「行かない」と断言できるくらい、私の中には確信めいたものがありました。
「小学校は行かないほうがいいだろうな」
「自分にとっては、行かないほうがいいところだ」
保育園での出来事も、少なからず影響していたとは思います。
不登校宣言を尊重してくれた両親
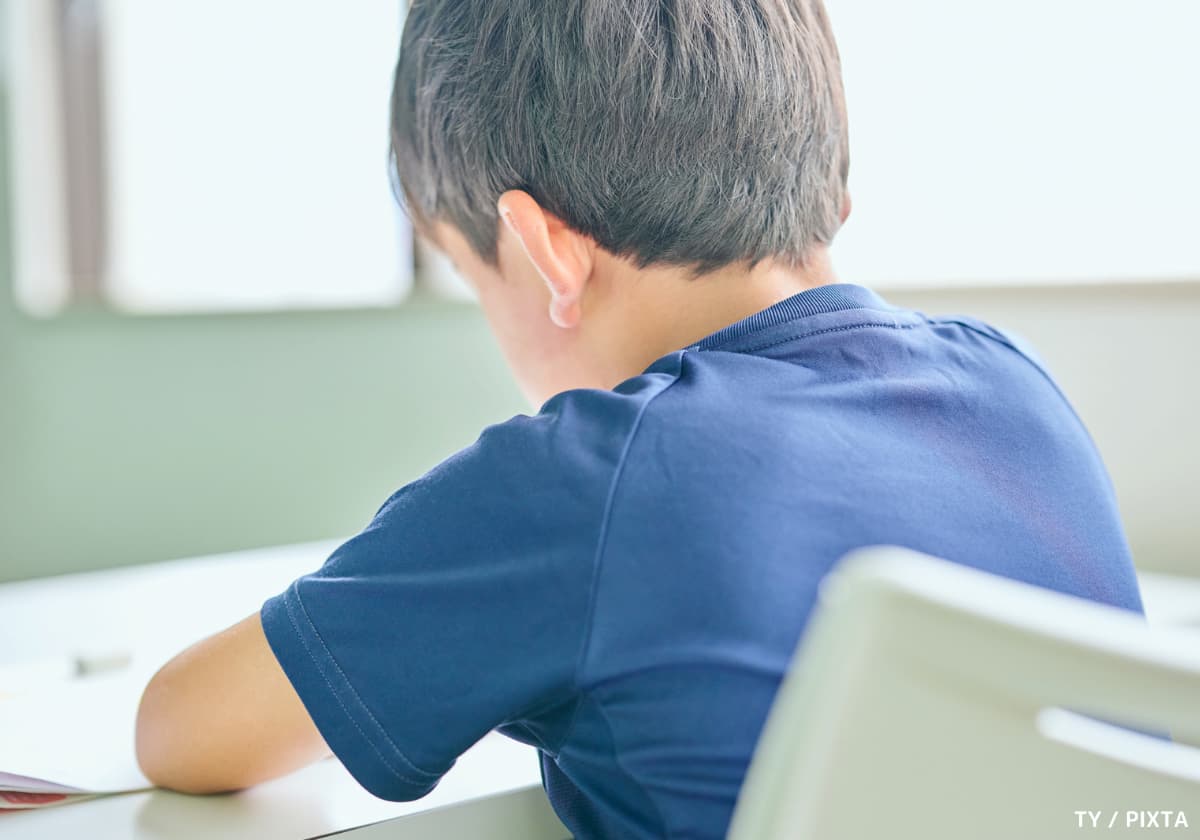
もうひとつ、身近な存在として「ホームスクーリング」をしていた知り合いがいたことも、私にとって大きかったと思います。外国人のお父さんと日本人のお母さんを持つ年上の友人がいたのです。
ホームスクーリングとは、学校に通学せず、自宅を拠点として学習を行う教育形式のこと。日本では、現在もそこまで浸透したスタイルではなく、海外でもその受け入れられ方は国によって様々です。アメリカなどホームスクーリングが広く認知されている国では、法律的にも権利を認められています。
ホームスクーリングの方法は様々ですが、自宅で親が先生となる場合もあれば、インターネットを使って授業を受けたり、単に主要な教科の勉強という範疇だけでなく、子どもの自主性や興味・関心に沿って学校では学べないようなテーマを深く学ぶスタイルもあります。
私よりひと回り上のその子も、学校に通わずにホームスクーリングをしていました。当時、家族ぐるみで付き合いがあったので、幼かった私もホームスクーリングというスタイルを何となく知っていたわけです。私の決断にどれくらい影響したのかは、わかりませんが少なくとも、彼の存在によって、
「学校に行かなくても勉強も生活もできる」
という感覚が、私の中にあったことはたしかです。
息子が学校に行かないという選択をしたことに対して、両親は少し心配はあったのかもしれませんが、大反対することも叱りつけることもなく、私の意思を尊重してくれました。
私の父や母が、ホームスクーリングなどの先進的な教育に特別理解があったわけではないと思います。逆に教育にまったく無関心の放任主義だったというわけでもありません。ただ、父は幼い頃に両親が離婚した関係で、一時的に学校に通えない時期があったそうです。だから、学校に行かないということに少しは考えがあったかもしれません。母は、もちろん小学校に通っていましたし、ごくごく普通に義務教育を受けてきましたが、「子どもの意思を尊重しましょう」という考えを持っていました。もしも両親のこの決断が違うものだったら、私はまったく違った人生を送っていたのだろうと思います。
内田拓海『不登校クエスト』(飛鳥新社)
教育&学びの第一人者、大絶賛!!
「保育園中退。積極的不登校。唯一無二の個性に学校は不要だった」
――教育評論家・尾木ママ
「“完全不登校“から始まる学びの冒険。生きるっていいね」
――脳科学者・茂木健一郎
小・中学校9年間、たったの1日も通学せず、高校からピアノを始めて藝大に入った26歳作曲家が考える「自分で学ぶ力」「自分の生きる道」の新しい見つけ方&育て方!!
6歳で自ら「学校に行かない!」と宣言し、ホームスクーラーとなった作曲家…内田拓海さんによる自伝的エッセイ。生きづらさに苦しむ子ども自身はもちろん、子どもの教育、学校との向き合い方に悩む親の背中を押してくれる「人生を切り拓くヒント」満載の一冊。不登校46万人時代の新バイブルです。