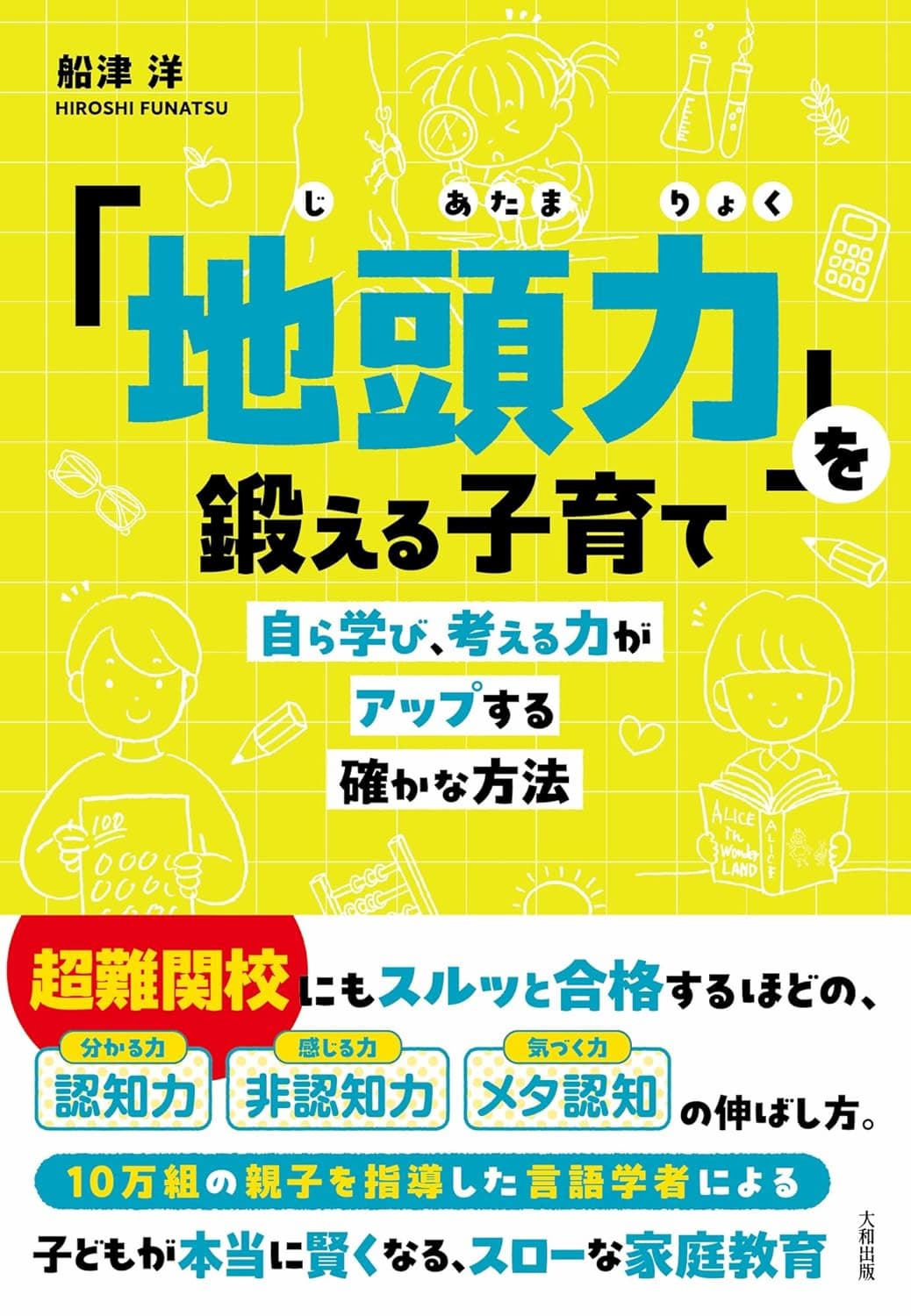言葉の遅れも改善! 子どもの論理性高める「ごっこ遊び」のすごさ
子どもたちが大好きなごっこ遊び。実は、子どもの論理的な思考を高めるすごい効果があります。ごっご遊びを通して、子どもの力を伸ばすためのコツとは?、言語学学者の船津洋先生の解説を、著書より抜粋してご紹介します。
※本稿は船津洋著『「地頭力」を鍛える子育て』(大和出版)より、一部編集、抜粋したものです。
論理性を高める「ごっこ遊び」
「ごっこ遊び」の指導を通して言語発達が遅滞気味の「気になる子ども」の言語能力やコミュニケーション能力などを伸ばす試みが行われています。
とある研究報告では、生活年齢の60ヶ月(5歳0ヶ月)に対して、語彙年齢が36ヶ月(3歳0ヶ月)と、24ヶ月の遅滞があった子を対象として行われました。
そうした遅れのある子どもに、定期的にレストランのごっこ遊び続けた結果、なんと5ヶ月間で20ヶ月分の発達の上昇が見られたそうです。
つまり65ヶ月(5歳5ヶ月)の段階で、56ヶ月(4歳8ヶ月)の発達まで急速に発達を取り戻したのです。
また、他の研究では幼稚園の5歳児クラスに、八百屋で稼いだお金の使い方に関する、子どもたち同志あるいは子どもと教師との会話を観察しました。
そこでは、子どもたちに論理的思考と直感的思考の間で「ゆらぎ」があることを報告しています。
「畑で採れたメロンをどうするか?」という設定において、「売る」「食べる」などさまざまな意見が交わされます。
「いくらで売るのか」という問に対しては「100万円」と言う子もいれば、「食べる」と言う子もいました。5歳児ですので100万円の具体的な価値は理解があるのではなく、「100」と「万」という多くを表す数字を使い高い価値を表現しようとしていたのでしょう。
「100億万円」などという存在しない単位が飛び出すのも、この時期の子どもたちの特徴です。このように現実的な論理世界での単位を使いながら、直感的な価値を表現しようとしているのです。
また、メロンを「食べる」という発言に続いて「みんなで食べたい」「半分こで食べる」「みんなと」などの意見が出ます。
とある子は「小さくてみんなの分がないんじゃない」と発言しましたが、この発言の背景には論理的な思考作業とその結果として得られた、かさの理解が見て取れます。子どもたちは直感的ではありながら、思いの外、論理的に物事を考えているのです。
ごっこ遊びといって馬鹿にしてはいけません。会話の型、手続きの型を身につけるとてもいい機会です。このあたりができていないので、企業も新入社員の教育に苦労するのです。
ごっこ遊びは型の習得と同時に、なぜこうなるのか、次に何が起きるのか、など論理的な思考を促すいい機会にもなります。
論理性がみるみる身につく「ごっこ遊び」
●レストランごっこ
入店に際しての店側の発言は、「こんにちは」「いらっしゃいませ」「何名様ですか?」「ご注文はお決まりですか」などなど型は決まっています。
それに対して、「これはからいですか?」「氷なしでください」「持ち帰りできますか?」など客側には比較的自由な発言が許されています。
子どもにも、お客さん役をやってもらいましょう。
最後には、「お会計お願いします」「おいくらですか?」「3000円です」「クレジットカードは使えますか?」「こちらに暗証番号をお願いします」「ごちそうさまでした」「ありがとうございました」などある程度型決まってはいますがいろいろなパターンでやりましょう。
●デパート、スーパー、コンビニなど
デパートなどでは「いらっしゃいませ」から始まり、「何かお探しですか?」「ギフト包装しますか?」、あるいは客側からは「いつまで保ちますか」など商品を決定するまでの会話が想定されます。
また、スーパーやコンビニではレジにて「袋はご利用ですか?」「ポイントカードはお持ちですか?」などのレジ係のセリフから、「カードでお願いします」など支払い方法に関する客側のセリフなどが考えられます。
●バスの案内、電車の案内
電車やバス、タクシーなどの乗り物が好きな子は喜んでやってくれます。
それらのおもちゃも持っているでしょうから、より具体的に彼らの中でイメージを膨らませることができます。
最近は便利になったもので、「電車名・駅名・アナウンス」などのワードで検索すると、実際の音声の録音されたものを、パソコンやスマホで何度でも再生することができます。これらには英語のアナウンスもついているので、英語も一緒に覚えてしまいましょう。
「次は○○」などバス停の名前なども正確に取り入れると、具体的な道のりも想像できるので楽しめます。
●宅配便や、出前の受け取り
家で玄関のベルが鳴るシチュエーションも頻繁に起こりますが、こちらも、宅配便、出前などある程度パターンが決まっています。
「あ、お客さんだ。誰だろう」「どちら様ですか?」「はい、今開けます」、あるいは「ヤマトです」「ウォルトです」など配送業者側を演ずることもできるでしょう。
●旅行予約、飛行機予約、レンタカー
旅行に関する電話でのやりとりも、子どもたちの想像力を刺激します。飛行機の手配では、行き先、日時、人数、席の並びの希望、会員番号、氏名、電話番号、料金の支払い方法など、宿泊やレンタカーに関しても、より具体的にやりとりを再現するといいでしょう。
大切なのは「心内表象化」です。形式のみのやり取りではなく、より具体的な内容に掘り下げることが大切です。和室・ベッドの大きさなど部屋についての希望や、レンタカーの車種なども、とにかくできる限り具体的に下位概念で再現することが、子どもの論理性を伸ばすことになります。
家族での旅行計画、夕食時に目の前の料理の調理方法を想像させて説明させるなど、いくらでも論理性を高める取り組みは親子の会話の中で行うことができます。
これらを積極的に日常生活に取り入れるように心がけましょう。
船津洋著『「地頭力」を鍛える子育て』(大和出版)
テストでいつも高得点、何事も論理的に思考し、好きな分野で才能を伸ばせる! 気鋭の言語学者が、子どもの「知識・理解力・共感力・メタ認知」が伸びる方法をワークとともに紹介。この一冊で「一流の賢さ」の育み方が分かる!