繊細な子が挑戦するために必要な5つの力 ストレスに強い脳をつくる親子関係とは?

「やってみたい気持ちはあるのに、行動にうつせない」。そんな繊細な子どもの“心の中”はどうなっているのでしょうか。
『発達科学コミュニケーション』マスタートレーナーのむらかみりりかさんは、「感情は脳を動かす原動力」とし、挑戦できる脳を育てるカギは「5つの心の力」にあると考えます。繊細な子どもが前向きに成長していくための理想的な親子関係とは?
※本稿は、『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(むらかみりりか/パステル出版)から一部抜粋・編集したものです。
5つの心の力で「挑戦できる脳」を育てる

人が行動を起こそうとするとき、欠かせないのが心です。「知りたい!」「やってみたい!」「できそう!」「面白そう!」「楽しそう!」「ワクワクする!」―。そんな気持ちが行動の原動力となり、人は挑戦を始めます。
では、行動を起こすときに働く「脳の機能」とはなんでしょう?
私は「心」にあたる脳の機能を5つの力にカテゴライズし、それぞれが安定しているか、それとも不安定な状態かというコンディションを知ることで、繊細な子どもたちの発達をサポートしやすくなると考えました。
その5つの力とは、①親子の愛着、②ストレスコントロール、③心のブレーキ、④心のアクセル、⑤適応力です。
この5つの力を数値に置き換えて見える化したのが『ココロファインダー』です。『発達科学コミュニケーション』の創始者である吉野加容子(よしのかよこ)さん監修のもと、私が独自に開発したもので、どの力をどう伸ばせば行動できるようになるかを考えるための材料になります。これにより1人1人に合った脳の育て方がわかるのです。
これまでに400名を超える繊細な子どもたちの親御さんに子どもとの接し方を教える中で、どのようにアプローチすればこの子たちが育っていくのかを記録してきました。
400名の子どもたちが証明してくれたのは、『ココロファインダー』の5つの力は上の表の〝左から順番に伸びていく〟という法則です。「親子の愛着」が安定すると、次に「ストレスコントロール」が安定していき、「ストレスコントロール」が安定すると、その次には「心のブレーキ」も安定していく、という具合です。
この順番が違っていたり、アンバランスだったりするときは、成長しづらいコンディションだといえます。5つの力のひとつである「親子の愛着」について、さらに詳しく解説していきましょう。
親子の愛着
「親子の愛着」とは、子どもにとって最も身近であるお母さんやお父さんとの間に築かれる〝心の絆〟です。親子の間で安心と信頼の絆が築かれると、子どもの自己肯定感や自己効力感が育ちやすくなるだけでなく、子どもの脳がストレスにも強くなることをご存じでしたか?
お母さんやお父さんとの愛着形成がうまくいっていると、子どもは安心と安全を感じ取ることができ、「何があっても自分は大丈夫」という自信が持てます。お母さんやお父さんの存在が、いつでも自分らしさを取り戻せる安全基地になるのです。
この親子の愛着こそが、脳の成長に深く関わっています。愛着は、子どもが外の世界で挑戦していくために必要な「心の土台」となるからです。
「心の土台」が確かであるほど、自信を持って行動できるようになるため、子どもの脳は成長します。
また、「親子の愛着」は必ずしも愛情の量や寄り添いの度合いで測れるものではありません。
英語では愛着を「アタッチメント(attachment)」といい、相互の結びつきを意味しています。つまり、愛着は親から子、子から親への一方通行では不十分で、双方向の結びつきが不可欠。
親が子に無条件の愛情を持つと同時に、子が親に対してゆるがない安心と信頼を確信したきに、ようやく成立します。
繊細な子どもたちの中には、親子関係も含め、人との愛着関係を築くことが苦手な子もいます。
例えば、お母さんが漏らしたため息ひとつでさえも敏感に感じ取り、さらにネガティブな認知を働かせてしまうと、「ママは私のことが嫌いなんじゃないか」と捉えてしまったりします。
お母さんはただ疲れてため息をついただけだったとしても、繊細な子の脳が持つ敏感すぎるセンサーが悪いほうに働いてしまうと、子どもの親との愛着形成はゆらぎ、不安定になってしまうのです。
それは、実際にお母さんやお父さんがきょうだいの区別なく同じように愛情を注いでいたとしても起こりえます。お母さんやお父さんにしてみれば、「むしろあなたのほうに寄り添ってるのに……」という場合さえあるのに、愛情や寄り添いの度合いと愛着関係は比例しないのです。
また、愛着は強く根を張るまでに時間がかかります。まるで植物が成長するのと同じように、しっかり水やりをしてあげる必要がある一方で、水を与えすぎても根を張れずに弱ってしまいます。
繊細なわが子に寄り添い続けてきたのに、わが子が外の世界で挑戦できないのはどうして―?
もしそう感じているとしたら、過度に子どもを守ろうとして外からの刺激を避け、おうちでたっぷりの水を与えて、おうちの中でしか根を張れないようになってしまっているかもしれません。
「親子の愛着」とは、「お母さんやお父さんは必要なときに自分を助けてくれる」「お母さんやお父さんならわかってくれる」「お母さんやお父さんはそばにいなくても心がつながってる、だから私は大丈夫」という実感です。
「親子の愛着」は、子どものストレスをコントロールする力に大きな影響を与えるといわれています。「親子の愛着」が安定していれば、子どもは外からのストレスに過剰反応することなく、ストレスにさらされても短期的に回復できると考えられています。
逆に、親子の愛着が不安定であれば、子どもは外からのストレスに「怖い」「イヤだ」「行きたくない」「おうちにいたい」と消極的な行動が目立つようになったり、ストレス症状が身体に現れたりと、脳のストレス状態が長期化してしまいやすいのです。
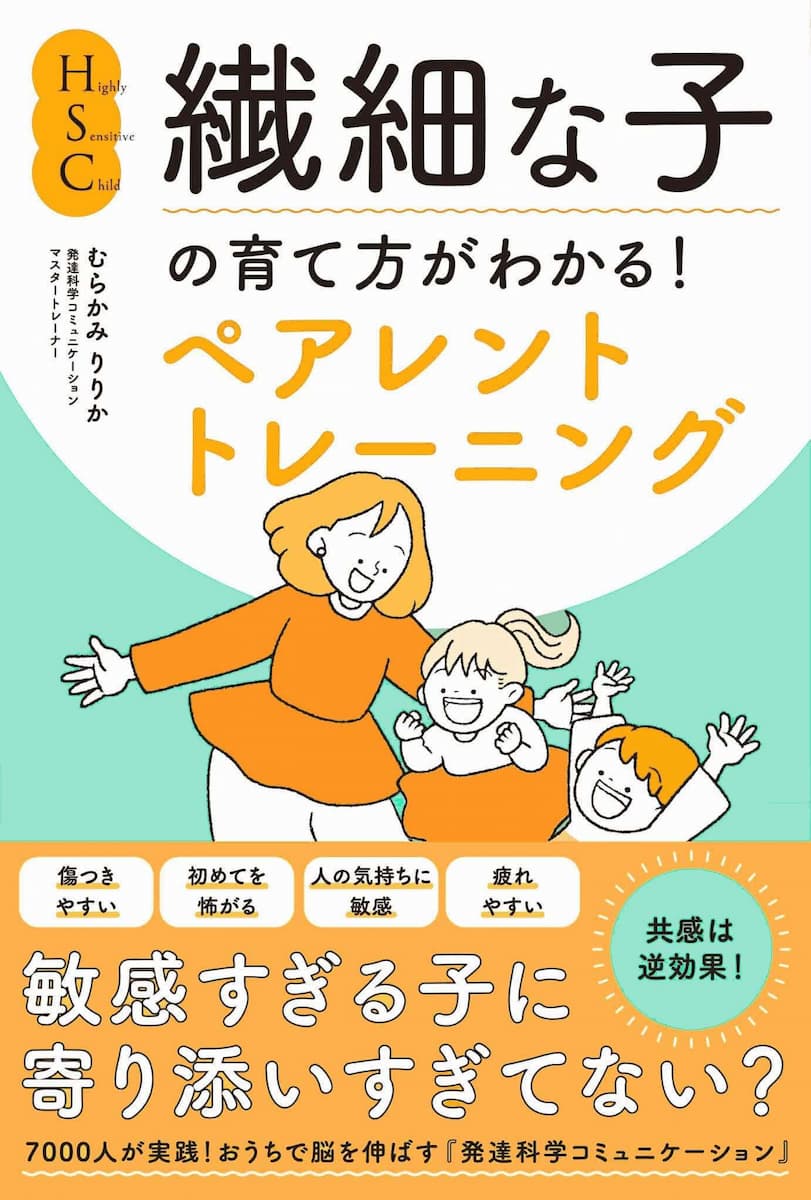
むらかみりりか『HSC・繊細な子の育て方がわかる!ペアレントトレーニング』(パステル出版)
「共感は逆効果だった――」
「初めてのことが苦手」「学校に行くのがつらい」「すぐ傷つく」そんな繊細な子が、わずか3カ月で笑顔で挑戦できる子に変わった!繊細な子の脳を発達させる、親子のコミュニケーションの新常識がわかります。
本書は、脳科学に基づいたペアレントトレーニングを通じて、親の関わり方を変えるだけで子どもが大きく変わった理由と解決策を、親子の実話とともにまとめた一冊です。































