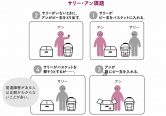習い事は子どもの才能・自信を伸ばす?逆効果になる“親の熱心さ“の落とし穴

子どもの自己肯定感や才能を伸ばしてあげたい。そんな理由から、子どもに習い事をさせる親御さんも多いのではないでしょうか。
しかし、その親の想いが、時に逆効果になってしまうこともあります。子どもの“本心”を置き去りにしないために、親が知っておきたいこととは?
潜在意識の専門家、谷原由美さんの著書から紹介します。
※本稿は、谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)より一部抜粋、編集したものです。
楽しくないものを強いられるのはイヤ

子どものためを思い、小さい頃から幼児教育に熱心なご家庭も多いと思います。でも、子どもの才能を伸ばすためにあれもこれもと習い事をやらせることで、かえって子どもの才能をつぶしてしまうことがあります。
たとえば、小さい頃から子どもに英語を習わせている場合、100%親から仕掛けていますよね。小さい子どもが「英語が好きだから、英語を習いたい」とは言わないはずです。ほかの習い事でも、きっかけは親であることがほとんどです。
もちろん、習い事にはいいこともたくさんありますから、それ自体が悪いわけではあり
ません。
子どもに悪影響を及ぼすのは、子どもに対して「強いる」ことです。
子どもが本当はやりたいと思っていないのに、無理に強いるようなことをすると、悪い意味での思い込みが生まれます。
多くの親御さんは習い事をさせることで「私(ぼく)はこれができるんだ!」といった子どもの自信につながることを期待しています。でも、子どもの自信につながるケースばかりではありません。
私はかつてピアノを教えていた経験があります。ピアノ業界には英才教育を受けてきた人たちもたくさんいて、何人もの挫折した人たちを見てきました。
実力があり、有名な音楽大学に進んでも、「もう二度とピアノは見たくない」という人もいました。もちろん、その親御さんは良かれと思って小さい頃からピアノを習わせています。でもその結果、ピアノを嫌いにさせてしまっては、誰も幸せではありません。
何かの才能を伸ばしてあげたいと親は思うものです。でも子どもの才能を伸ばすことは、親の仕事ではないのです。

ピアノを教えていたこともあり、わが家の3人の子ども(長男、次男、長女)も、ピアノを習っていました。でも、高校生になるまで続けていたのは長女だけ。息子2人は、全然興味がないのがわかったため、早々にやめさせました。
習い事に関しては、親としていろいろと思うところがあるでしょう。
大切なのは、子どもが本当に心から楽しんでやっているかどうかです。そうでない場合、潜在意識の中では「親を喜ばせたい」あるいは「親をがっかりさせたくない」という思い込みがあることが多いようです。一見、楽しんでやっているようでも、習い事をさせているお母さんやお父さんの機嫌をとるためにやっているのです。
つまり、子ども側に「自分のため」がどこにもないのです。
「○○しなきゃ」という気持ちや、「やらされている感」があると、人生は面白くなくなっていきます。
「心から楽しんでいるか」と、文字にするのは簡単ですが、別の言い方をすれば、「情熱
を傾けられているか」「能動的にやっているか」ということに近いでしょう。
情熱を傾けられないことに対して、それを強いられると、身体も心も病み、才能が壊れていきます。
大げさに聞こえるかもしれませんが、子どもにとって「楽しくないものは、楽しくない」のです。楽しくないことを強いられる人生は、子どもにとってとてもつまらない、残念な人生です。
「自分の情熱のために頑張る子に育てるには、親の意向を押し付けない」、これが重要です。
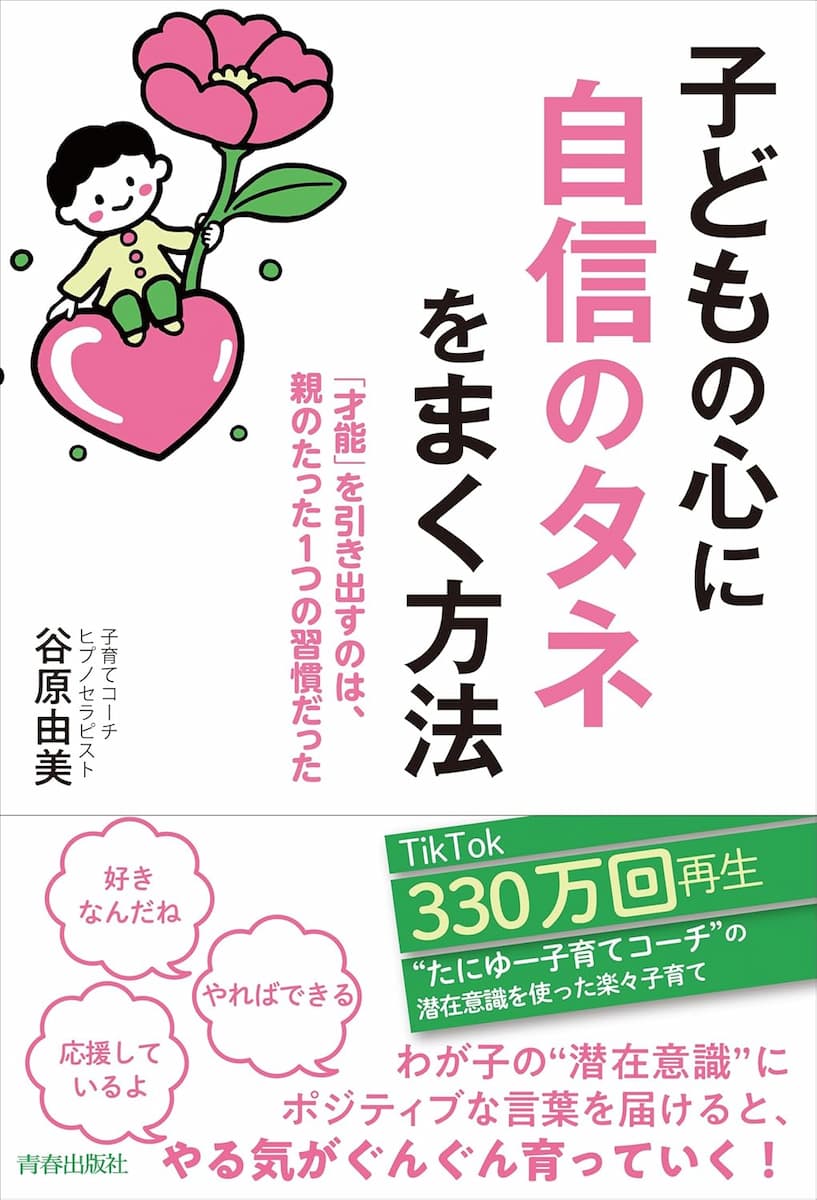
谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)
10歳までで決まる!子どもの隠れた才能を引き出す親のたった1つの習慣とは?TikTok330万回再生の人気子育てコーチたにゆーが教える、潜在意識を味方につけて子どものやる気と才能を伸ばす子育て。