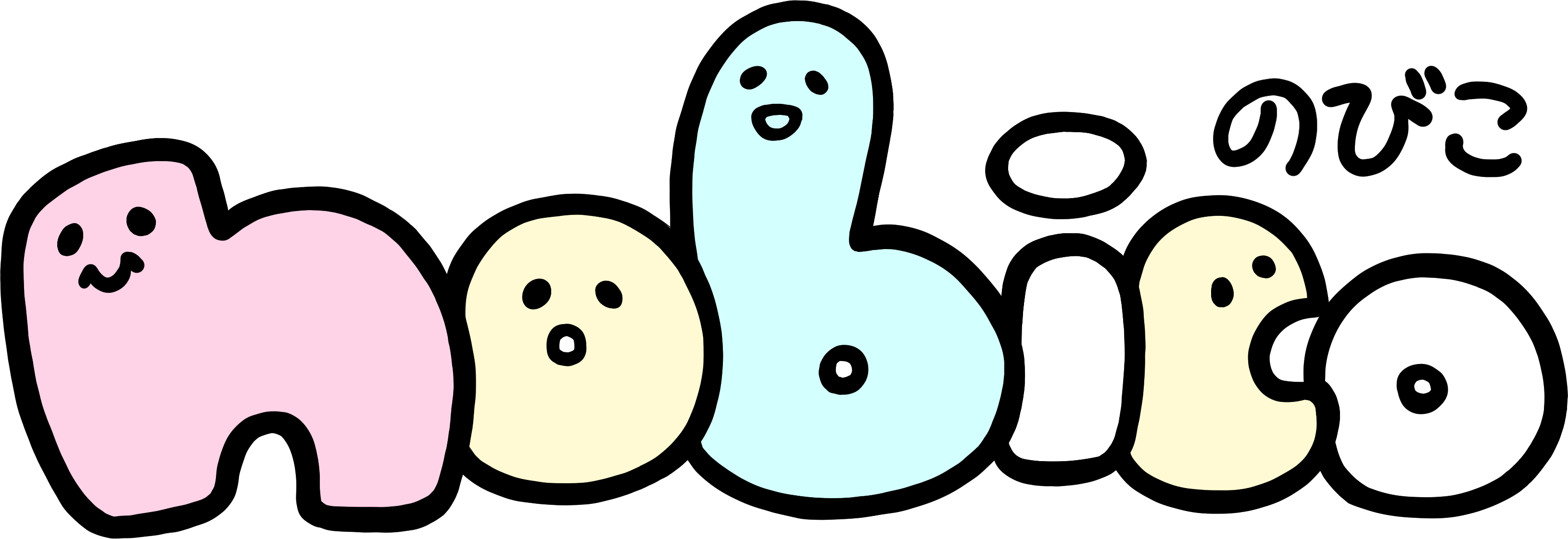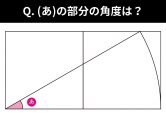字が読めなかった少女が偏差値69の高校へ 心のささえは父の言葉「お前は頭がいいはずだ」

小学6年生まで、まともに文字が読めなかったという谷原由美さん。
先生から露骨にバカにされ、悔しい思いを重ねる日々の中で、谷原さんの心を支えていたのは、親からかけられた一つの「暗示の言葉」でした。
ご自身の体験を、著書から抜粋して紹介します。
※本稿は、谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)より一部抜粋、編集したものです。
「勉強ができない私」を変えた言葉の力

私は、子どもの頃、おそらく「識字障害」だったのだと思います。今でこそそうした言葉がありますが、当時はそんな概念は知られておらず、ただ「頭の悪い子」と見なされていたように思います。
文字がなかなか読めず、指でなぞりながらひとつひとつ音読しても、結局全体の意味がつかめない。漢字は、何度書いてもまったく覚えられない。そんな子どもでした。
両親は、なぜ自分の子がこんなにも勉強ができないのか、理解できなかったはずです。実際に成績はひどく、小学3年生のときには担任の先生が家に来て、こう言いました。
「お母さん、本気で娘さんの将来を考えていますか? このままでは本当に危ないですよ」
そんな私に、父はいつも同じ言葉をかけてくれました。
「お前は頭がいいはずだ。やればできるようになる」
私は、その言葉を、ただまっすぐに信じていました。
「私は頭がいい。やればできるようになる」―それが、私の記憶にある最初の「親からの暗示」です。
どれだけ私がこの言葉を大切にしていたか、想像できるでしょうか。
学校でうまくいかないたびに、私はこの言葉を心の中で何度も繰り返しました。
昭和時代の学校は、今よりずっと厳しかったので、先生たちはできない子には露骨に冷たく当たることもありました。
みんなの前でバカにされたり、点数の悪いテストを「こんなひどい点を取る人がいます」と黒板に貼られたりすることもありました。
どれだけ恥ずかしかったでしょう。
それでも私は、いつも思い出していました。
「私は頭がいい。やればできるようになる」
その言葉は、次第に私の中で本当の力となっていきました。
まともに文字が読めるようになったのは、小学6年生になってからでした。
それでも、私はあきらめませんでした。そしてその後、偏差値69の高校に合格することができたのです。
小学生時代の私を知る人たちは皆、驚きました。何しろ、クラスで一番成績が悪かった私が、そこまで変わったのですから。

そして、この体験は私の子どもたちにも受け継がれました。
高校2年生のときに偏差値42だった長男は、最終的に東京大学大学院に進みました。同じく偏差値42だった娘も、都内の有名私大に合格しています。
私は、彼らにもかつて父が私にしてくれたように、ただこう伝え続けてきました。
「あなたはいつか素晴らしい人になるよ。きっとそのうち、ものすごくできるようになるよ」
勉強しなさい、とは言いませんでした。ただ、可能性を信じて言葉をかけ続けたのです。
この「言葉の力」こそが、勉強しろと言うよりも、はるかに強い影響を与えるのだということを、ぜひ多くの方に知っていただきたいと思います。

谷原由美著『子どもの心に自信のタネをまく方法』(青春出版)
10歳までで決まる!子どもの隠れた才能を引き出す親のたった1つの習慣とは?TikTok330万回再生の人気子育てコーチたにゆーが教える、潜在意識を味方につけて子どものやる気と才能を伸ばす子育て。