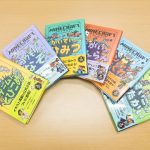「宿題したの?」と聞くと、子どもはもっと宿題をしなくなる

ダラダラするわが子に、つい小言を言ってしまう…。そんなお母さんは要注意です! 家庭教育支援センター・ペアレンツキャンプ代表理事の水野達朗氏が、宿題をやらない子どもに言ってはいけない言葉を紹介します。
※本稿は水野達朗著『子どもには、どんどん失敗させなさい』(PHP研究所)から一部抜粋・編集したものです。
水野達朗(家庭教育アドバイザー、不登校復学支援専門のカウンセラー)
不登校専門の訪問カウンセラーとして多くの不登校の子どもたちと関わり復学へと導く。不登校の解決法として家族内コミュニケーションの在り方に着目し、水野式の家庭教育メソッドである「PCM(=ParentsCounselingMind)」を構築。家族と子どもの自立を第一に考え、全国の親と子をサポート。
ちょっと待って、それはNGワード

宿題があるはずなのに、寝転がってマンガを読んだり、ゲームをしてケラケラ笑っているわが子を見て、お母さん大爆発という場面はよくありますよね。そんな感情的になっている時に親の口から出る言葉のほとんどにプラスの効果がありません。
「宿題したの?(イライラ)」「さっさと先に終わらせなさい!」
このあたりの言葉で口火が切られて、そこからはとどまることのない怒りの言葉があふれ出るようです。
私もその言葉をいわれた後の何千人という子どもの様子を見ていますが、そのようなことをいわれて「ハイ。かしこまりましたママ。すぐやります」という子を見たことがありません。
親自身も「こんな言葉はいいたくないけれどウチの子が全くやらないからいってしまいます」とお悩みの方が多いです。
ここでいったん冷静になって考えてみましょう。いって効果がないならいわないでおきませんか。そしてなぜ子どもが主体的に宿題をしないのかを考えてみませんか。