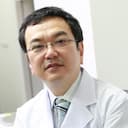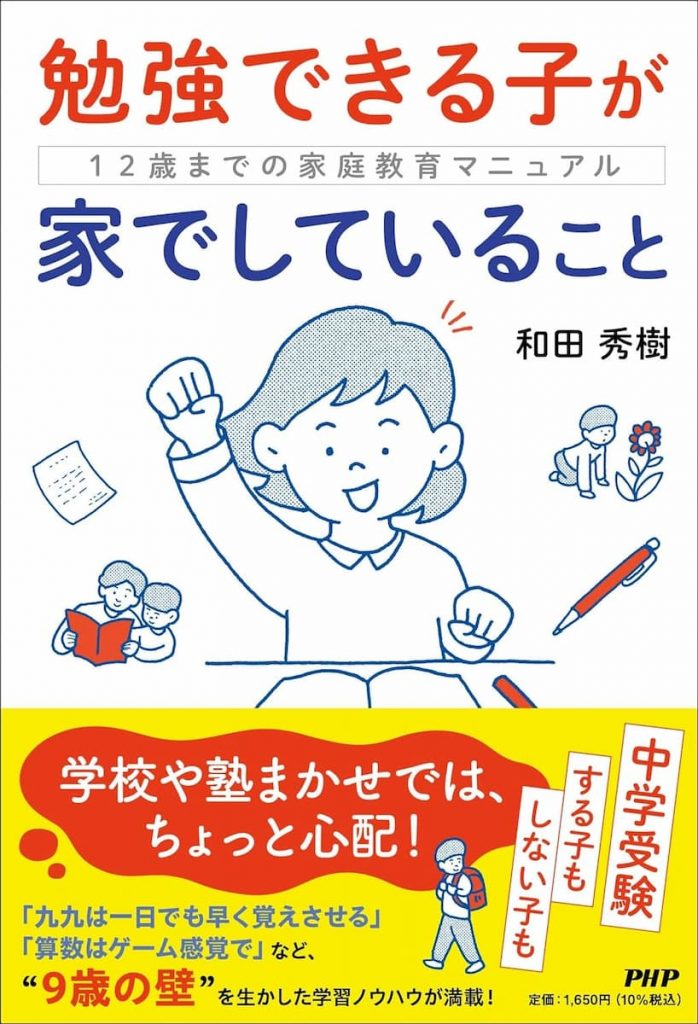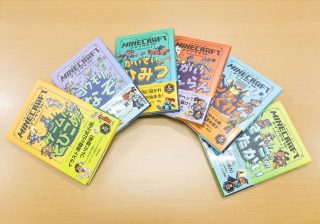東大合格者に「早生まれ」が少ないのは本当? 子どもの発達にあわせて親がサポートできること
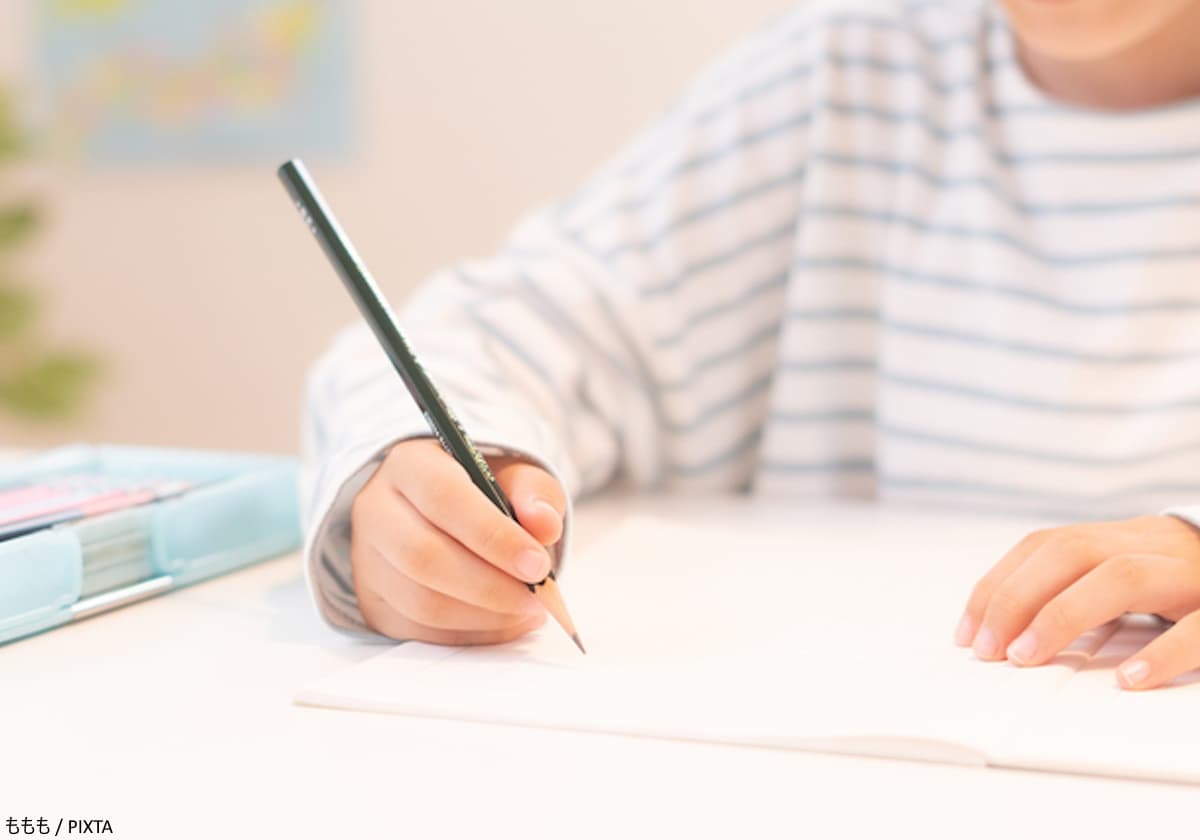
「うちの子は発達が遅い?」そんな不安を抱えた親御さん、多いのではないでしょうか?
しかし、子どもの発達はそれぞれ違うということを忘れてはいけません。学校や塾のカリキュラムは画一的であり、すべての子どもに合うわけではありません。大切なのは、子どもの発達段階に合わせたサポートをすることです。精神科医の和田秀樹さんが語ります。
※本稿は和田秀樹著『勉強できる子が家でしていること』(PHP研究所)より一部抜粋・編集したものです
学校へ行かないエジソンにお母さんが勉強を教えた

発明王で名を馳せるエジソンは、学校へ行かなかったということでも有名です。しかし、エジソンが勉強していなかったのかというと、そういうわけではありません。エジソンは、お母さんから学校の勉強やその他いろいろなことを教えてもらっていたのです。お母さんに勉強を教えてもらい、自分でも努力した結果、あの数々の偉大な発明が生まれました。
このエジソンのお母さんの熱意ある教育は、いまでも多くの教育学者たちが敬意を払っています。本当は、エジソンに限らず、小さな子どもにとって一番よい先生になれる可能性があるのは親なのです。
言葉も世の中のルールも、みなお母さん、お父さんから教えてもらえば、素直に受け入れていくはずです。そして、そのときに、親から何を教えてもらったのかによって、子どもの成長は変わります。
学校に入るころになると、勉強を含め、いろいろなことを教えてくれるのは学校の先生というようなイメージに変わりますが、それでも、本質的には家庭での先生としての親の役割が終わるわけではありません。親が子どもに何かを教えるということは、子どもが何歳になってもとても重要なことなのです。
子どもの発達の早い・遅いは、家庭でしっかりと認識する

就学前の子どもの様子を思い出してみてください。「おかあさんへ、おとうさんへ」と、手紙を一生懸命に書いてくれた姿。一から百まで一緒に数えられた日。虫や鳥や、はたらくくるまなど、大好きなものの名前を覚えられたとき…。何かができるたびに、うれしそうな姿を見せてくれたのではないでしょうか。
本来、子どもにとって知らないことを覚えること、すなわち学びは大好きで楽しい体験のはずです。ところが、学校へ通うようになると、多くの子どもが「勉強嫌い」になっていきます。なぜでしょうか。
これは、学校で学ぶようになって初めて、「先生の言っていることがわからない」という体験を味わうからといえるでしょう。問題は、「わからない」ことではなく、「まわりのお友だちがみんなわかっているのに、自分だけわからない」という点にあります。
でも、どうして同じ授業を受けているのに、わかる子と、わからない子が出てきてしまうのでしょう。
確かなことは、子どもたちの発達には差があるということです。子どもの発達は、それぞれ違います。ところが、学校や塾のカリキュラムは、個々の能力に合わせて作られていません。そのため、発達の遅い子はもちろん、発達が早い子にとっても、最適な学習内容とは言えないのです。

「発達の早い・遅い」とは、何か——。小学一年生の発達を例に、具体的に説明していきましょう。4月生まれの子と3月生まれの子がいたとします。学年は同じでも、およそ1年の月齢の違いがあるため、身体的にも精神的にも、その成長の程度には大きな差が出てしまいます。
4月生まれの子は発達が早い分、比較的身体は大きく足も速い、学校の勉強も理解ができて「自分はできる」と思いながら成長していきます。一方、3月生まれの子は発達が追いついていないわけですから、まわりの友だちと比べても身体は小さく、運動能力も理解力も劣りがちです。「自分はできない」という劣等感が植え付けられてしまうこともあるでしょう。
月齢による能力差は成長とともに縮まっていくものなので、焦らずに成長を待ってほしいと思いますが、一方で東大合格者には、4月・5月・6月生まれが多いとも言われます。早生まれと遅生まれで、もともとの能力に差があるわけではないのに、「東大合格」というはっきりとした知的能力の差が生じているのはなぜなのでしょう。
これには、子どものころの自己肯定感が関係していると考えられます。ですから、子どもに「自分はできない」と思わせては、絶対にいけないのです。「どうせ何をやって無駄」と考えるようになってしまうと、勉強嫌いになるだけでなく、自己肯定感の低いまま成長していくことになってしまいます。
子どものころに育くまれた自己肯定感は、大学受験や社会に出てからも、その子を力強く支えてくれる土台となります。子どもには、「必ずわかるようになるから大丈夫」と伝えてあげましょう。無用な劣等感を払しょくしてあげることが、勉強嫌いにならず、自信をもって人生を歩んでいくためにも必要なことといえます。
「9歳の壁」を理解し、効果的に利用する

「9歳の壁」という言葉をご存じでしょうか。子どもの発達は、学童期に入ってから小学校低学年と高学年(9歳以降)と2つの時期に分けられるというものです。
高学年になると、物事をある程度対象化して認識できるようになり、自分のことも客観的に捉えられるようになるとともに、発達の個人差が顕著になります。自己肯定感を持つようになる一方で、勉強ができないことなどが原因で、劣等感を持ちやすくもなります。9歳の壁とは、この段階にあることを意味します。
9歳の壁を越えるまでは、抽象的思考が必要な課題を解くのが難しいといわれています。算数の帯分数や、あまりのある割り算、文章問題、複雑な図形の問題、国語の長文読解問題などは、9歳の壁を越えていない子どもにとっては、ほとんど歯が立たない課題といえるでしょう。
一方で9歳の壁を越える前、小学校低学年までは記憶力に長けているので、その記憶力のよさを生かすことができる課題を与えましょう。漢字であれば、小学校の低学年のうちに、6年で習う範囲までやらせてしまうことも可能でしょうし、それでも余裕がありそうでしたら、中学1年で習う英単語を覚えさせてもいいかもしれません。その子が「できる」課題であれば、どんどん先に進めてしまっていいと、私は考えています。
9歳の壁といっても、小学校低学年ですでにその壁を越えている子もいれば、高学年になってもまだ越えられていない子もいるように、発達はそれぞれです。大切なことは、その子どもの発達段階に応じた課題を与えることです。
本人の自己肯定感を失わせてしまうようであれば、無理にレベルの高い課題を与える必要はありません。子どものうちは、できることを積極的にやらせてあげましょう。
また、発達のスピードには性差もあり、一般的に女の子のほうが脳も身体も発達が早いといわれています。女の子の親が、将来、性差を超えて活躍できるようにと「先取り学習」に積極的になる気持ちはわかります。英才教育は、発達が早い女の子のほうが向いているともいわれますし、子どもにとって無理のない形であれば、先に先にと学習を進めていくことはよいことでしょう。
親が自分の子どもに教える最大のメリットは、一般に「よい」とされている勉強法でも、その子に「合わない」と判断したときに、ほかの勉強法に変えてみることができるという点です。
個人差に合わせた指導は、学校や塾は無理でも、親ならできる

PISA(国際学力調査)で常にトップクラスの成績を誇るフィンランドでは、一クラス16~20人ほどの少人数制が基本です。授業ではさらに、4、5人ずつのグループに分け、教師はそれぞれに教え方を変えながら指導します。学力に差のある子どもたちを同時に教えるのですから、本来、これくらいのきめ細やかさがあって当然です。
ところが日本は、一クラスの人数が35~40人もいるため教師の負担が大きいうえに、残念ながら、個々に合った指導が行われているとは言えないのが実情です。
改正義務教育標準法が可決され、2021年度から一クラス35人制が段階的に導入されてきているものの、全学年35人学級が実現するのは、2025年度と、まだ時間がかかります。学校のシステムが変わるのを待つより、いま、親としてできることをしていくべきでしょう。子どもの発達に合わせて、「いつ」「何をさせるか」を考えてあげましょう。
また、「中学受験のために塾に通わせたい」と思っても、子どもによっては成績が上がるどころか、逆効果となってしまうことがあります。できる(発達の早い)子にとっては、学校の授業が物足りなくて飽きてしまっている可能性がありますから、楽しく勉強を続けさせるという意味では有益かもしれません。
しかし、できない(発達の遅い)子にとっては、学校の授業だけでも辛いのに、レベルの高い中学受験塾にまで行かされるとなったら、みじめな思いが強化されてがんばる気力さえも奪ってしまいかねません。
もはや「学校や塾に頼っていれば安心」という時代は終わりました。家庭こそ教育の最後の砦といえるのです。
『勉強できる子が家でしていること 12歳までの家庭教育マニュアル』(和田秀樹 著、PHP研究所刊)
著者は学生時代、「勉強は素質だ」とあきらめていたところ、勉強法を変えることで成績が伸びて、東京大学に合格した経験があります。「子どもに合わない勉強法で劣等感を持たせるよりも、子どもに合ったやり方を見出して勉強をさせれば必ず伸びる」というのが、著者の強い信念です。それができるのは、家庭の働きかけがあってこそ。
中学受験する子も、しない子も! 子どもにとって“最後の砦”といえる、家庭で心得ておきたい「令和版・和田式勉強法」をお届けします。