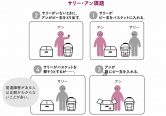志望校全落ちのあとに見えた希望とは? シンママが「中受を後悔していない」と語る理由【後編】

2月5日に受験したのは、杉並区にある佼成学園中学校・高等学校だった。受験当日、
「わかっていたのは学校の名前くらいでした」
と順子さん。とにかく、合格体験をという一心で学校に向かうと、そこには、
「よく来てくれたなー!」
と手を広げて一人ひとりにあいさつをする男性が待っていた。
同校の校長だった。
「息子も私もこれだけで涙が出ました」
その後、伸也君は試験会場へ。保護者の控え室では、まさかの学校説明会が始まった。
出願校に「全落ち」して初めてこの学校を知って来る親子も多い。それを学校側もわかっているのだろう。最終日の控え室の雰囲気は独特だ。ここにいるのは、どこからもまだ合格をもらえていないとう家庭がほとんどだ。保護者控室は、どうか、お願い!今度こそは!と、祈る気持ちであふれている。
そんな中、学校紹介の映像と共に流れてきたのは、Mr.Childrenの「GIFT」だった。
白と黒のその間に 無限の色が広がってる
君に似合う色探して やさしい名前をつけたなら
ほら一番きれいな色 今君に贈るよ
会場の至るところからすすり泣きが聞こえた。
伸也君の試験結果は合格。
入学説明会での説明と、温かく迎えてくれた学校に感激し、入学を決意した。

「塾で勧められるのは、ほとんどが偏差値50以上の学校でした」
順子さんは、選択肢を狭めた中から学校を選んでいたことを反省した。
「偏差値的には名前が挙がらないけど、いい学校はいっぱいある。この受験でそのことを知りました」
当初受験を予定していた学校には受からなかった中村家だが、親子とも、受験にチャレンジしたことに後悔はない。
「今、息子は“受験部“という部活に入っていたのだと思えます。部活なら、一生懸命に頑張って、都大会出場ができなかったとしても“よく頑張った“と頑張りを素直に褒めてあげると思う。受験も一緒で、全力で勉強に向き合った3年間です。望む結果は残せなかったけれど、あの頑張りは無駄ではないとたたえてあげたい。何より今の息子の楽しそうな様子を見て、つらかったけれど、やってみてよかったと思っているんです」
この母子の事例からわかるように、中学受験は多くの家庭にとって決してたやすいものではないだろう。それがわかっていて、なお挑んだ親子の一つの着地点として、またそれまでの軌跡に、学ぶことは多いのではないだろうか。
あの取材からしばらくたった2024年、母親に連絡をしてみると、伸也君はすでに大学生になっていた。そして、母親も中高6年間の学校生活に満足していると言う。一番の理由は、本人が好きなことを見つけて自分で道を切り開いたことだ。本人の希望で入学したものの、入学後は滑り止めに入ったという気持ちが拭えなかったのか、周りを少し下に見るようなところもあった。しかし、こうした様子もしばらくするとなくなった。この中学校ではテストで順位が出る。自分は上位だろうと思っていたら、意外にも自分の順位はそれほど高くなかったため、「なんだ、みんな同じくらいの力があるんだ」と認識するようになった。
中高一貫校に入ったことで、親の気持ちも変化していった。初めは本人の成績が気になり、面談で勉強のことばかり相談していた。担任は、この学校に入る子は比較的ゆっくりタイプの子が多いこと、男子は土台さえできていれば、1、2年で学力はすぐに伸び、やる気になるのはだいたい高校2年生あたりからだと教えてくれた。最低限の勉強は必要なものの、中学時代は友達を大切にすることなど、心の成長の部分を大事にしたいと説明を受けた。
「勉強についてはまだあまりご家庭で言わなくても大丈夫、本人をそのまま受け止めてあげてくれたらそれでいいですと言っていただけたことで、こちらも気持ちがすごく楽になりました」
それからは、成績が落ちてもおおらかな気持ちで見ていられるようになった。そのうちに、伸也君はファッションに興味をもつようになり、おしゃれな店が集まることで有名な裏原エリアへ足繁く通うように。好きなブランドが見つかると、自らそのブランドのコンセプトやデザイナーのルーツを調べるようになっていた。そして、進路選択にもこの「好き」が繫がっていった。現在は美術大学に進学し、テキスタイルなどを学んでいる。 母親は言う。
「今だから言えることかもしれないですが、勉強ができることがそんなにいいことかなという考えにもなりました。それよりも、何か熱中できるものを見つけられることのほうが本人の幸せに繫がるんじゃないかなと思うようになりました」
学力が必要ないとは言わない。だが、子どもは熱中できるものを見つければ、それに向かって自ら学ぶようになっていく。自走する力をつけた子どもは自ら将来の道を切り開いていく強さを手にする。親すべきなのは本人が自分の道を見つけるための地図を見せることであり、いつまでもわが子の手を引き、道を一緒に進むことではない。自走できる力をつけるよう見守ることが一番大事なのではないだろうか。「全落ち」を経験した伸也君は、中高の6年間でしっかりと自走する力をつけていた。

宮本さおり著『中学受験のリアル』(集英社インターナショナル)
急増する中学受験生、「全落ち」などの厳しい現実…。
「合格体験記」には書かれないドラマを追って、15組の親子を取材したノンフィクション。
首都圏の中学受験者数は2023年、過去最高を記録した。東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県では、18パーセントの子どもたちが受験を経験し、熱は地方にも波及している。中・高一貫校への人気が高まり、子どものために移住するケースもみられる。一方、第一志望校に合格する子どもの数はわずか3割。負け戦とわかっていても中学受験へと向かわずにはいられない親子。まだ幼さの残る小学生の彼らが立ち向かう受験という魔物。
「全落ち」を経験する子どもは立ち直れるのか? 親のエゴや塾の実績づくりで志望校を決めていいのか? 偏差値では測れない、子どもに合った学校とは? 中学受験に挑んだ親子を5年間追い続けたルポルタージュには、きれい事では終わらない中学受験のリアルがある。