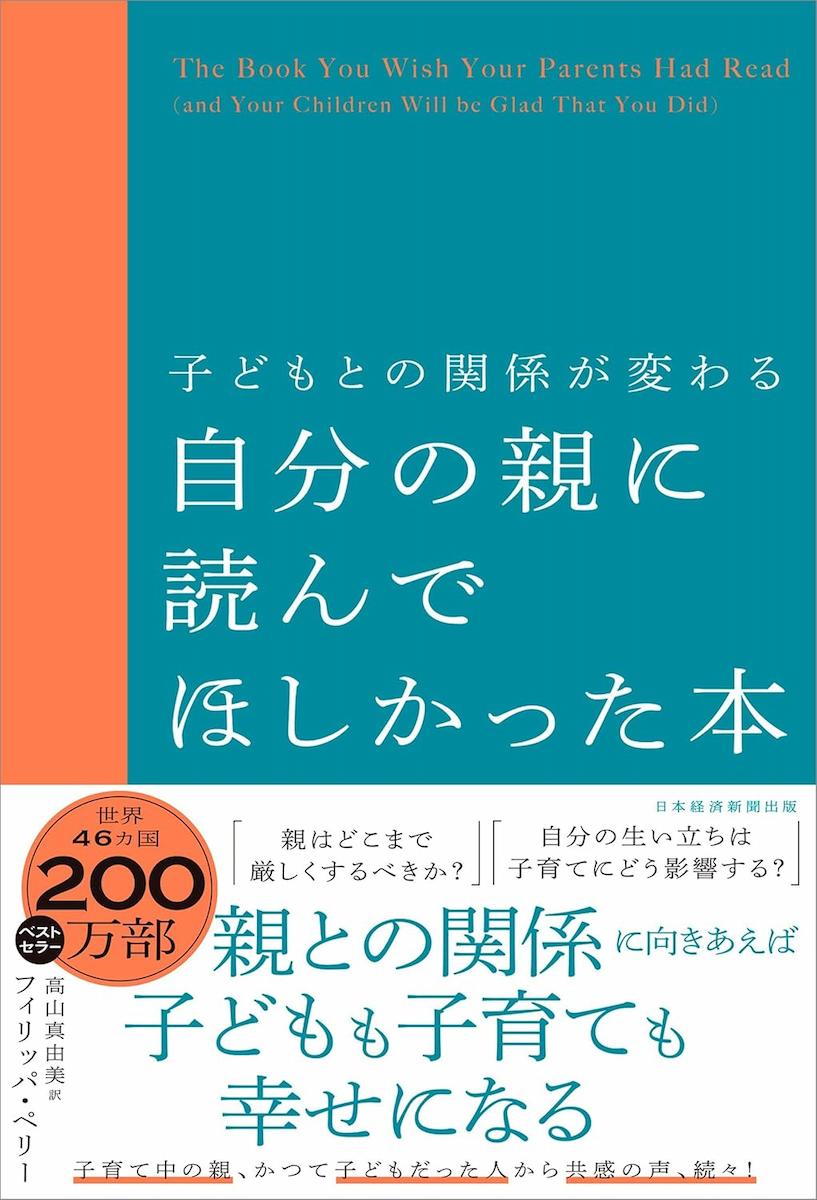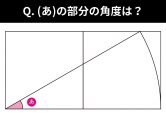親の行動は子どものふるまいにどう影響を与えるのか?

子どもはいつも「良い」行動を取るとはかぎりません。子どもが周りの人々にとって都合の悪い行動をしたとき、親はどのようにすればいいのでしょうか?
子どもの行動に対して一番大きな影響力を持つ親の行動について、『子どもとの関係が変わる 自分の親に読んでほしかった本』よりご紹介します。
※本稿は、フィリッパ・ペリー(著), 高山真由美(訳)『子どもとの関係が変わる 自分の親に読んでほしかった本』(日本経済新聞出版)から一部抜粋・編集したものです。
手本となる人物(ロールモデル)

子どもはあなたの真似をします。いまはそうでなくても、いずれそうなります。以前出会ったクライアントのなかに、「私の父親は巨大な営利企業のワンマン経営者なんですが、私は父とは似ても似つかないんですよ」と言う人がいました。確かに、そのクライアントが働いていたのはチャリティ部門でしたが、彼が自分の部署を運営する姿はワンマン経営者そのものでした。
子どもの行動に対して一番大きな影響力を持つのは、おそらく親である私たち自身の行動です。私たちは一人ひとり異なる人間ですが、お互いに影響しあっています。みな社会というシステムの一部であり、個人として引き受ける役割は周りの人々の役割の影響を受けています。だから、あなたや子どもがどうふるまおうと、それは孤立した行動ではなく、周りの人々や文化によってつくりだされたものでもあるのです。
子どもがいつも「良い」行動を取るとはかぎらない

あなたは自分の行動をどう説明しますか? いつも他人に敬意を払っているでしょうか? 他人の感情を思いやることができますか? あなたの「良いおこない」は心からのものですか、それともただマナーを守っているだけでしょうか? 表面上は人あたりがいいのに、陰で悪口を言ったりしていませんか? 厳しい競争社会で行き詰まっていませんか? どんな行動であれ、あなたは同じ行動を取るようにと子どもに教えているのです。
あなたが周囲の人々に常に思いやりをもって接していれば、おそらく子どももそうなるでしょう。しかし子どもはいつも「良い」行動を取るとはかぎりません。言葉が発達するまでは、自分に何が起こっているかを伝える手段が行動しかないからです。じつはこれは、言葉をうまく使えるようになってからも続きます。自分がどう感じているか言葉にして必要なものを引きだせるようになるには、ある程度の実践を通じてスキルを磨く必要があるからです。大人でさえ、ふさわしい言葉で表現するのが難しいこともあります。
完全な善人や完全な悪人は存在しません。もっと言えば、「良い」とか「悪い」という考え方は役に立たないのです。確かに、ごく稀ではありますが、どんなに人に教えられても生まれつき共感能力がない人もいます。しかし脳の配線が人と異なるからといって、それが「悪い」ということにはなりません。私がこうした議論を多少なりとも許容できるのは、ある人の行動がほかの人々にとって「不都合である」とか、「害がある」といった言い方をするときだけです。生まれつき悪い人間などいないのです。人の行動に「良い」「悪い」というラベルを貼るよりは、「都合が良い」「都合が悪い」と表現したいのはそのためです。
親の行動が子どものふるまいにどう影響を与えたのか自問する

すでに述べたとおり、行動とはコミュニケーションそのものです。子どもが不適切なふるまいをするのは、それに代わるもっと効果的な方法で感情やニーズを表現することができないからです。周りの人々にとって都合の悪い行動をする子どももいますが、その子が「悪い」わけではないのです。
親であるあなたの仕事は、子どもの行動を読み解くことです。子どもたちを「良い」グループと「悪い」グループに分けるのではなく、次のように自問する必要があります。
この子の行動は何を伝えようとしているのか? もっと良いやり方でコミュニケーションが取れるように、手を貸せないだろうか? 子どもが自分の体や、騒音や、自分なりに選んだ言葉を使って、本当に伝えようとしていることは何なのか? そして、一番きつい疑問はこれです――この子のふるまいに、私の行動はどう影響を与えたのだろう?
『子どもとの関係が変わる 自分の親に読んでほしかった本』(フィリッパ・ペリー(著), 高山真由美(訳)/日本経済新聞出版)
「心を揺さぶられた」「涙なしで読めない」「子育て全般が変わった」……
世界中から共感の声、続々! 世界46カ国200万部のベストセラー。
自分の親との関係を見つめ直し、感情を受け止めれば見えてくる
子どもが幸せになるための心がけ