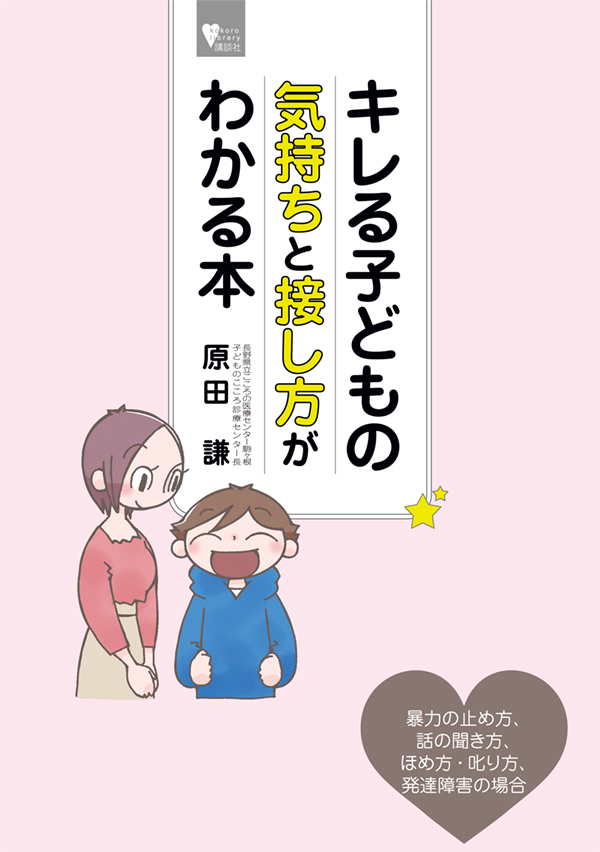「些細なことでキレる子」なぜ増えた? 児童精神科医が解説
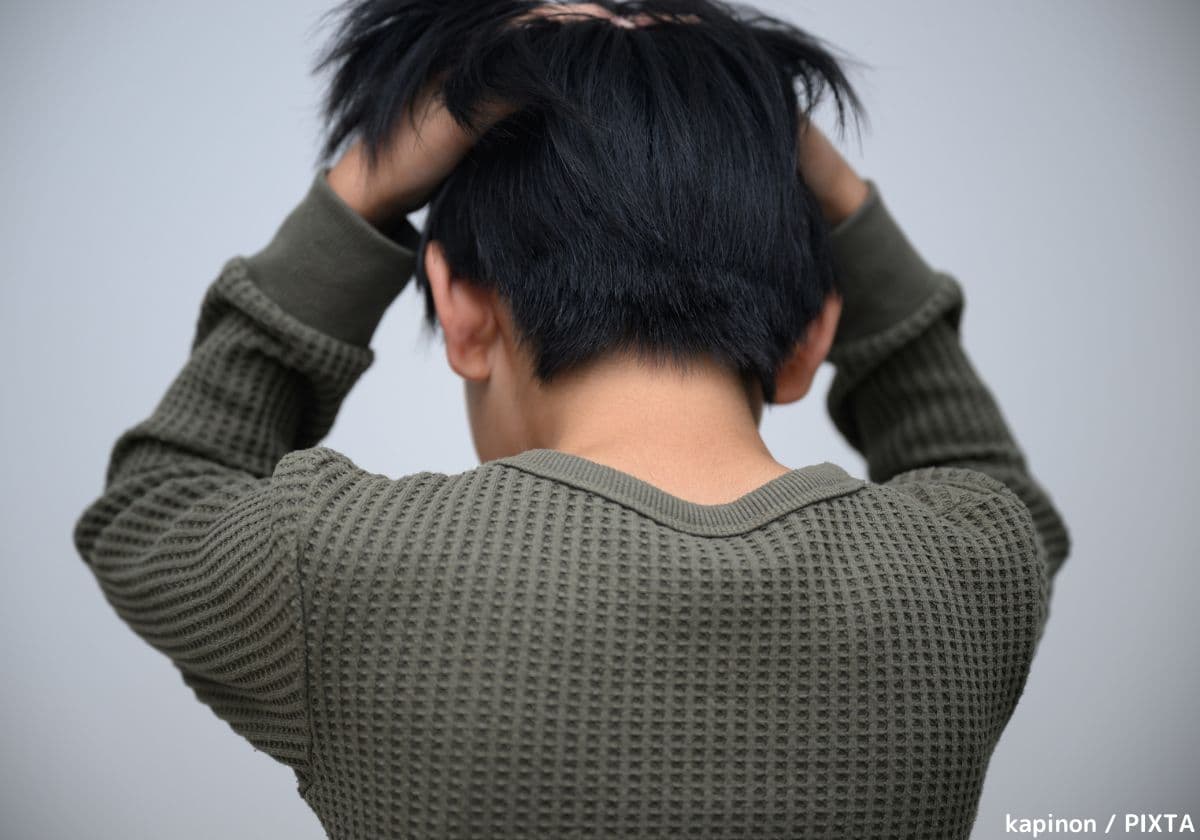
思い通りにならないと感情を爆発させ、周囲に当たる「キレる子」。そんなキレる子たちに、共通する特徴はあるのでしょうか。
『キレる子どもの気持ちと接し方がわかる本』(講談社)を執筆した児童精神科医の原田謙先生に話を伺いました。
「キレる子」が増えているのはなぜ?

――親御さんの相談を受ける中で、具体的にどういうキレ方をするお子さんが多いと感じますか?
自分の思い通りにならないとイライラして、周囲に当たり散らすパターンが多いと感じます。
例えばゲームがうまくいかないと親に当たるなどですね。きょうだいがいると、下の子にイライラをぶつける場合も多いと思います。
学校でキレてしまう子も、基本的には同じです。自分の思い通りにいかなかったり、自分の主張が通らない時に、怒りが爆発してしまうことが多いです。
――年齢層によってキレる原因や、キレ方に違いはあるのでしょうか。
些細なことでキレるという点では、年齢による違いはあまりないと思います。違うのは、暴れ方ですね。体が大きくなるので、行動が派手になることがあります。ただ、根本的な部分は年齢が上がったからといってあまり変わらない印象です。
中学生になると社会性がついてくるので、学校でキレる子は少なくなりますが、家庭内ではあまり変わらないと思います。
――先生は著書の中で、「現在はキレる子が増えている」と解説されていました。子どもたちは以前と比べて、どのような社会的な影響をうけているのでしょうか。
自分は社会学者ではないので印象でしか語れないのですが、子ども同士で「群れる」機会が減ったことが原因の一つではないかと考えています。
金沢工業大学の長尾隆司教授の研究からうまれた、「インターネットコオロギ」という言葉をご存じでしょうか?
コオロギは通常、群れで飼うのが一般的ですが、1匹ずつ別々に飼うと、体が大きく育つのだそうです。オスのコオロギは、ヒエラルキー(上下関係)を決めるためにぶつかり合うのですが、群れの中で育ったコオロギ同士だと、優劣がついた後はそれ以上争いません。
一方で、単独で育ったコオロギを群れに入れると、相手が死ぬまで攻撃し続けるという研究結果が出たそうです。
また、単独で飼われたオスのコオロギは、気に入ったメスを見つけると、そのメスが逃げても追いかけ回し、最終的にうまくいかないと殺してしまうことがあるようです。
長尾教授は、このようなコオロギの行動を、インターネット環境で育った人々に例えて「インターネットコオロギ」と呼びました。これはあくまでコオロギの実験の話ではありますが、群れの中で育たなかった個体が集団に加わると、他の個体を必要以上に攻撃してしまう、という結果が出たんです。
昔は、公園に行くといろんな年齢の子どもたちがあつまっていて、皆で一緒に遊ぶのが当たり前でしたが、特にコロナ禍以降は家の中でゲームやインターネットを使う時間が増え、そのような機会が減ったと感じます。これにより、他人の気持ちを察する能力や思いやりの心が育つ機会も、以前より少なくなっているのではないでしょうか。
とはいえ、今の時代、ゲームやインターネットは切り離せない存在になっているので、ただ禁止するのは現実的ではありません。節度を持って付き合っていくことがポイントですね。例えば時間を決めて使うなど、「そればっかり」にならないように気をつける。リアルな友達との付き合いや、他の活動とのバランスを取ることが大事だと思います。
大事なのは「一人で抱え込まないこと」

――キレやすい子たちに共通する特徴はありますか?
自己評価が低い子が多いように感じます。自分の存在価値を認められず、「自分が生きている意味がないのではないか」と感じていることが多いです。
原因としては、発達障害を含む自分の特性や性格と、その子がいるの環境とのミスマッチが原因のことが多いと感じています。自分が理解されていない、気持ちやつらさが大人に伝わっていないと感じている子が多いです。
――家庭での親の関わり方も、子どものキレやすさに影響を与えているのでしょうか?
この点は非常に難しい問題ですね。どうしても親の接し方や育て方に注目が集まりがちですが、どの親もそれぞれ一生懸命に子どもを育てています。それでも、うまくかみ合わないことはあるんですね。要するに、ミスマッチが起きているのだと思います。
例えば、キレやすい子どもが外来に来た場合、その子の兄弟全員が同じようにキレやすいわけではありません。
親が同じように関わっていても、うまくいく子どももいれば、うまくいかない子どももいます。うまくいかない子は、しつけがうまくかみ合っていない。つまり、親の関わり方が良いか悪いかではなく、その子に合っていないということです。
なので、キレやすいお子さんに悩む親御さんに伝えたいのは、「自分を責めないでほしい」ということです。そのためには、相談できる相手や愚痴を言える相手が大切です。必ずしも適切なアドバイスを求める必要はなく、まずは「つらい」「大変だ」と感じている気持ちを理解してくれる人がいるといいですね。
一番大事なのは、親御さんが一人で抱え込まないことです。
(取材・文:nobico編集部 中野セコリ)