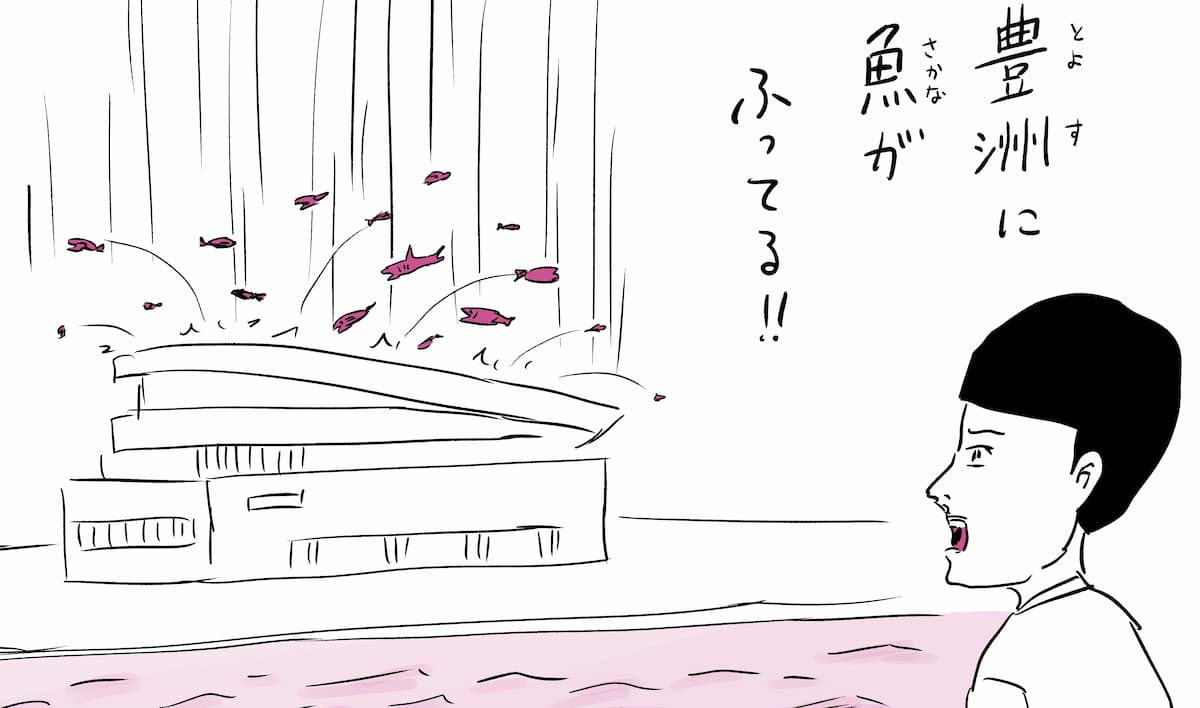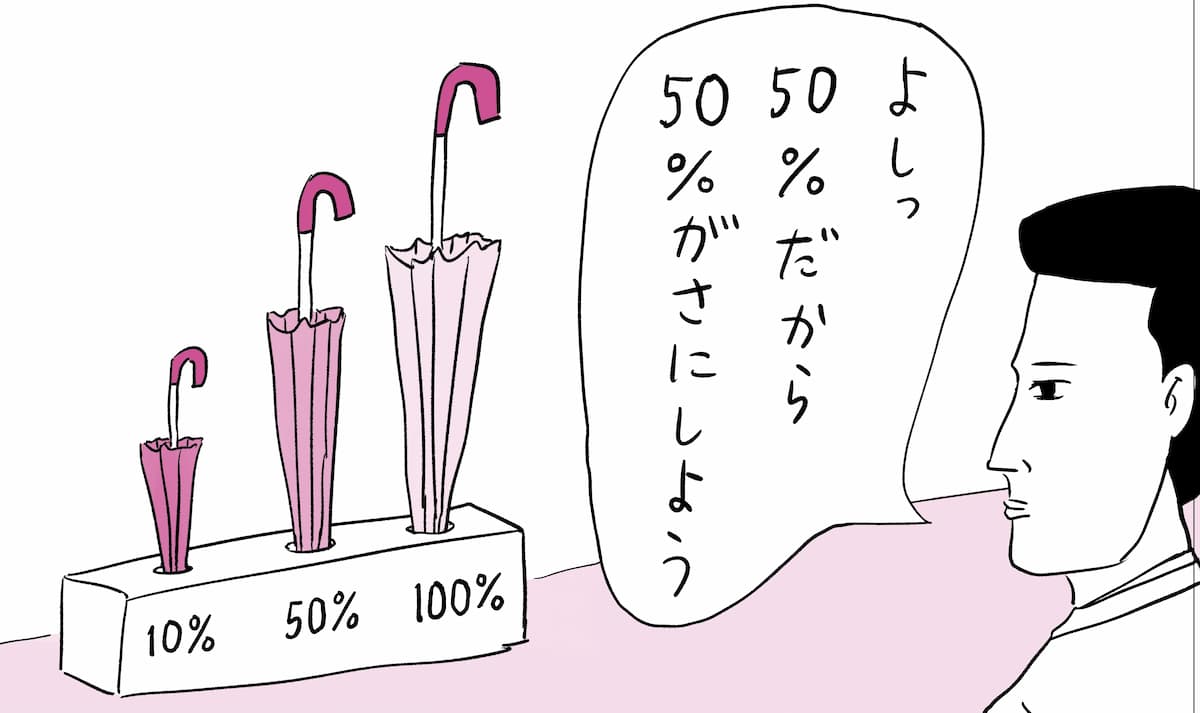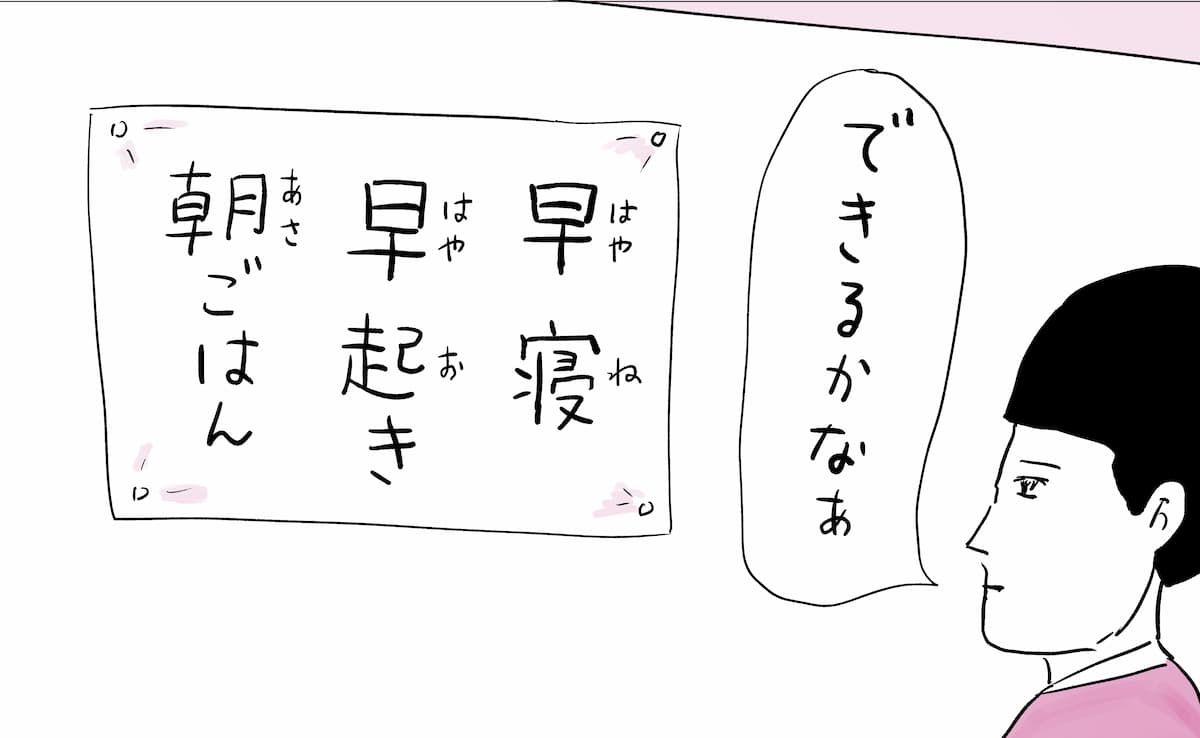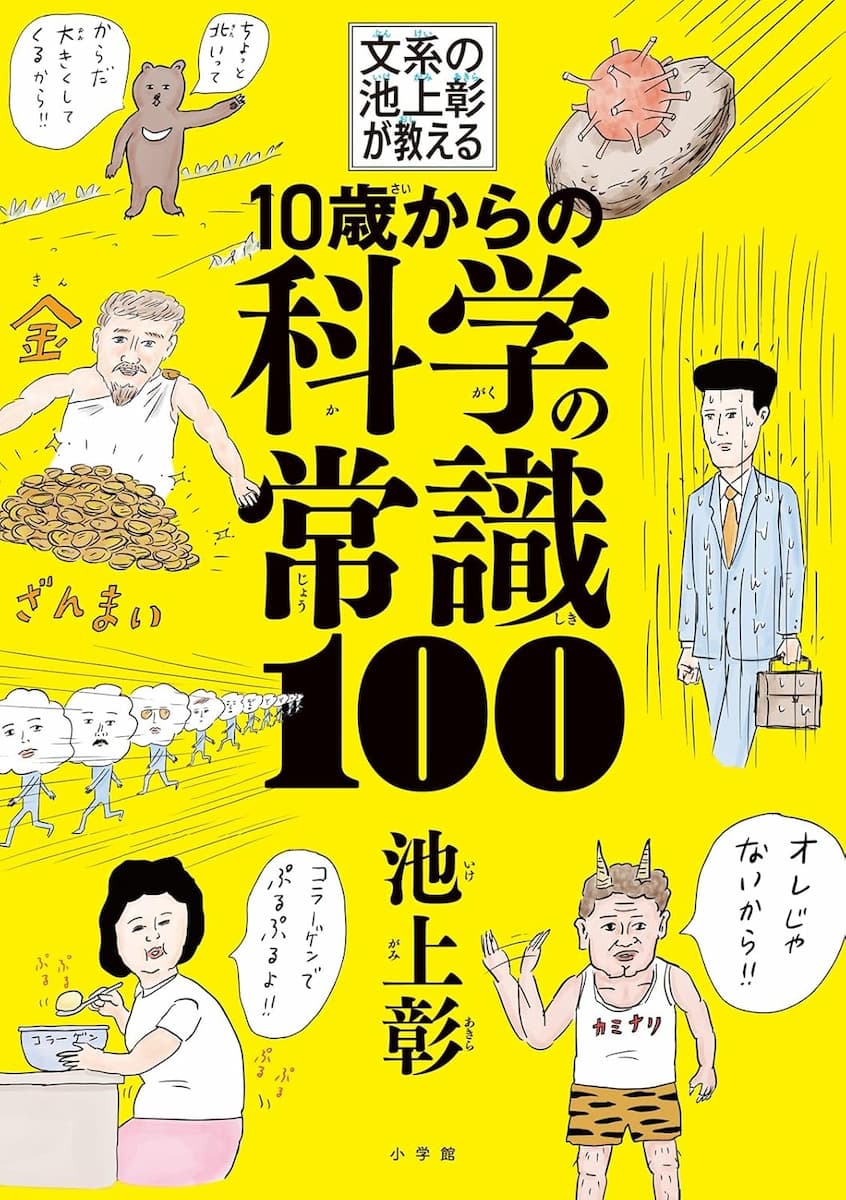「地震雲」「人工降雨」「空から魚」・・・子どもが夢中になり、学力向上にもつながる科学の話
「『地震雲』は本当にある?」「人が雨を降らせることはできる?」「空から魚が降る?」──普段何気なく耳にする話の中には、科学的根拠があるものと、そうでないものが混ざっています。私たちの常識は、思い込みや勘違いによるところも多いのです。子どものころから科学的な視点で考えるクセをつけると、自分で考える力が養われます。身近な疑問をきっかけに科学的思考を身につけると、子どもの学力向上にもつながるのです。楽しく学びながら、知識と考える力を育ててみませんか?
※本稿は、池上彰・著『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(小学館)から一部抜粋・編集したものです。
イラスト/和田ラヂヲ
気象クイズ1:「地震雲」は科学的根拠がある。本当? うそ?
「地震雲」というと、不吉なことが起こりそうな、変わった形や色の雲を想像するでしょう。
「地震」は地中で起こる現象で、「雲」は大気の変化による現象。地震と雲はまったく別の現象です。ですので、基本的に地震雲はありません。よって、答えは「うそ」です。
ただ、地震雲が絶対にないとはいいきれません。現時点で、雲と地震を関連づける科学的根拠はないということです。
そもそも「地震雲」の存在自体があやしいといえます。人々が「地震雲」と呼ぶものの多くは、変わった形の飛行機雲など自然現象です。雲はそのときどきの大気の状態や地形の関係で、不思議な色や形になることがあります。
また、日本では、震度1以上を観測した地震が年間約2000回あり、平均すると1日5 回も起こっています。
地震が多い国なので、雲と地震という関係のない現象を結びつけ、地震が起こった後で「そういえば、変な雲が……」と後付けしているように感じます。
地震の予知は研究者たちの長年の課題です。2024年3月、京都大学大学院の研究グループが、大地震の発生直前に震源地近くの上空(地上60〜1000㎞の電離層)に異常が生じるメカニズムを国際的な学術誌に報告しました。
この研究の実証が進むことで、もしかしたら地震の予知が実現するかもしれません。そうすれば、効果的な防災対策ができるでしょうし、被害を最小限にくいとめることができるようになるかもしれないですね。
気象クイズ2:人工的に「雨」を降らせられる。本当? うそ?
遠足や運動会の日を晴れにしたり、水不足の地域に雨を降らせたり、天気を自由に変か えられたらいいですよね。
実は、実験段階ではありますが、世界では人工的に雨を降らせることができています。なので、「本当」です。
では、どうやって雨を降らせると思いますか?
雲は、あたためられた海水が水蒸気となり、水蒸気が冷やされてできます。雲の中では、冷やされた水蒸気が集まって氷の粒ができ、それがくっついて大きく重くなって下(地上)に落ち、途中でとけて雨になります。つまり、雲の中に氷の粒がたくさんあれば、それだけ雨が降る確率が高くなる。そのため、雲の中に氷の結晶と似た「ヨウ化銀」という物質(医療用のX線フィルムなどに使われます)や「ドライアイス(二酸化炭素がこおったもの)」をまくことで、人工的に雨を降らせる(= 降りやすくする)ことができるのです。
飛行機からドライアイスをまく、地上でヨウ化銀を燃やしたけむりを発生させて、雲の中にヨウ化銀の粒子を入れるなどの方法があります。2008年の北京オリンピックでは、開会式を晴れにするために、ヨウ化銀をまく方法を使うことで前もって雨を降らせることに成功しています。
もともとは水不足解消のための研究ですが、特定の地域に雨を降らせることで、まわりの地域や世界の気象に影響を及ぼすことが心配されています。
また、ヨウ化銀が人体に与える影響もわかっていません。日本でも東京の奥多摩町に人工降雨の施設がありますが、実用化のハードルは高いでしょう。
気象クイズ3:空から魚が降ってくることがある。本当? うそ?
「そんなことあるわけない!」と思ったあなた。思いもよらないことが起こるから、世界はおもしろいんですよ。
ということで、答えは「本当」です。空から魚が降るのは「ファフロツキーズ現象」といい、小さい魚やカエルなどが降ってくることを表します。
これは、竜巻が原因という説が有力です。強い上昇気流によって積乱雲ができたときに、その上昇気流の回転がさらに強まると、積乱雲の下に空気のうず、つまり竜巻ができます。
竜巻が、地表の木や家などを巻き上げている映像を見たことがあるでしょう。竜巻が海の上で起こると、海水と海の中の生きものを一緒に巻き上げます。巻き上げられた魚が落ちてくるのを見て、「空から魚が降ってきた!」とびっくりするんですね。
実際、2023年2月には、オーストラリア北部の街ラジャマヌで空からたくさんの魚が降ってきました。日本では、さかのぼること270年あまり、1752年に現在の鳥取県東部でドジョウが降ってきたという記録があります。
アメリカの中南部で発生する激しい竜巻は、「トルネード」といいます。アメリカでは竜巻から避難するためのシェルター、地下室をつくっている家が多くあります。家が竜巻でふき飛ばされても、地下室なら安全ですからね。
一つの積乱雲の中で上昇気流と下降気流があちこちで発生すると、雲も竜巻もぐんぐん成長し続けて巨大化します。このようにして大きくなった積乱雲を「スーパーセル」と呼んでいます。
気象クイズ4:降水確率50%のとき、かさをもっていく? もっていかない?
朝、天気予報を見て、かさをもっていくかはあなたも迷うところでしょう。私も、毎日降水確率はチェックしています。天気予報で「何%以上ならかさが必要です」と明言することはできません。なぜなら、あくまで「確率」であって「確信」ではないからです。ですが、私は50%だったら絶対にかさをもっていきます。なので、答えは「(私なら)もっていく」になります。
では、「今日の降水確率50%」とは具体的にどういうことでしょう?
これは、今日と同じような気象条件が10回あったとしたら、そのうち5回雨が降るだろう、ということ。下の図のように、過去の大量の天気データと、天気予報・観測データから確率を割り出しています。降ることもあるし降らないこともある。つまり、確率は50%になるのです。
気象庁で働く人に「何%だったらかさをもっていきますか?」と聞いたところ、「30%です」といっていました。理由を聞くと、「確率が低くても、万が一、雨が降ったときにかさをもっていなかったら、職業的に立場がないので……」とのこと。そのため、その気象庁の人は「置きがさ」をしているそうです。
降水確率とは、ある時間内に1㎜以上の雨や雪が降る確率のこと。過去のデータから気象庁が算出し、1986年から全国的に発表されています。
ちなみに、これは雨の降りやすさを表すもので、雨の量や強さを表すものではありません。「10%だから小雨」「100%だから大雨」ではなく、10%でザーザー降りのこともありますし、100%でポツポツと降ることもあります。
科学的考え方クイズ5:朝食を食べる子は学力が高い。本当? うそ?
こういわれると、確かにそんな気がしますよね。「朝ごはんを食べなさい!」と、おうちの方にも先生にもいわれたことがあるでしょう。朝食を食べるのが体にいいというのはまちがいありませんが、「朝食を食べる子は学力が高い」を「科学的考え方」という視点からいえば、答えは「うそ」です。「じゃあ、朝食を食べない方が学力が高くなる?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
ここでの問題は、「相関関係」と「因果関係」を取りちがえてしまうことにあるのです。「相関関係」とは、二つのものごとに関わりがあること(いいかえれば、ただ関わりがあるだけ)。「因果関係」とは、二つのものごとが原因→ 結果の関係にあることです。「朝食を食べる子は学力が高い」ならば、これは因果関係にあるはずです。因果関係にあるならば、「朝食を食べたから学力が高い」ことが証明されなければなりません。
そもそも「朝食を食べる子は学力が高い」というのは、2003年の国立教育政策研究所による研究結果で、ペーパーテストの成績がよかった子どもの多くが朝食を食べていたことが背景にあります。
それを受けて文部科学省が「早寝 早起き 朝ごはん」というスローガンを掲げたのです。早起きすれば朝食をしっかりとる、そうすれば脳にエネルギーが回って学校で授業に集中できる、だから学力が上がる、というわけ。ですが、朝食をとるのは親が規則正しい生活をさせているからかもしれませんし、学力が高いのは親が教育熱心だからかもしれません。そうなると、朝食→学力に直接的な因果関係があるとはいえないんですね。
『文系の池上彰が教える 10歳からの科学の常識100』(池上彰 著/小学館)
「朝食を食べる子は学力が高い?」「南海トラフ地震は30年以内に起こる?」「地震雲は科学的根拠がある?」「コラーゲンを食べると肌がぷるぷるに?」
――気になる現代の科学知識を池上彰がスッキリ解説!
文系出身ながら、科学にも強い池上彰が、理系の「むずかしい」を文系にも「わかる!」に変換します。科学的考え方、気象、地学、物理、化学、生物、環境問題…子どもが興味をもつ現代的な7つの科学ジャンルをクイズ形式で楽しく紹介。読むことで、理系ジャンルに強くなるだけでなく、論理的思考も養われ、国際情勢や国内ニュースに対して、自分の頭で深くで考える力が身につきます。