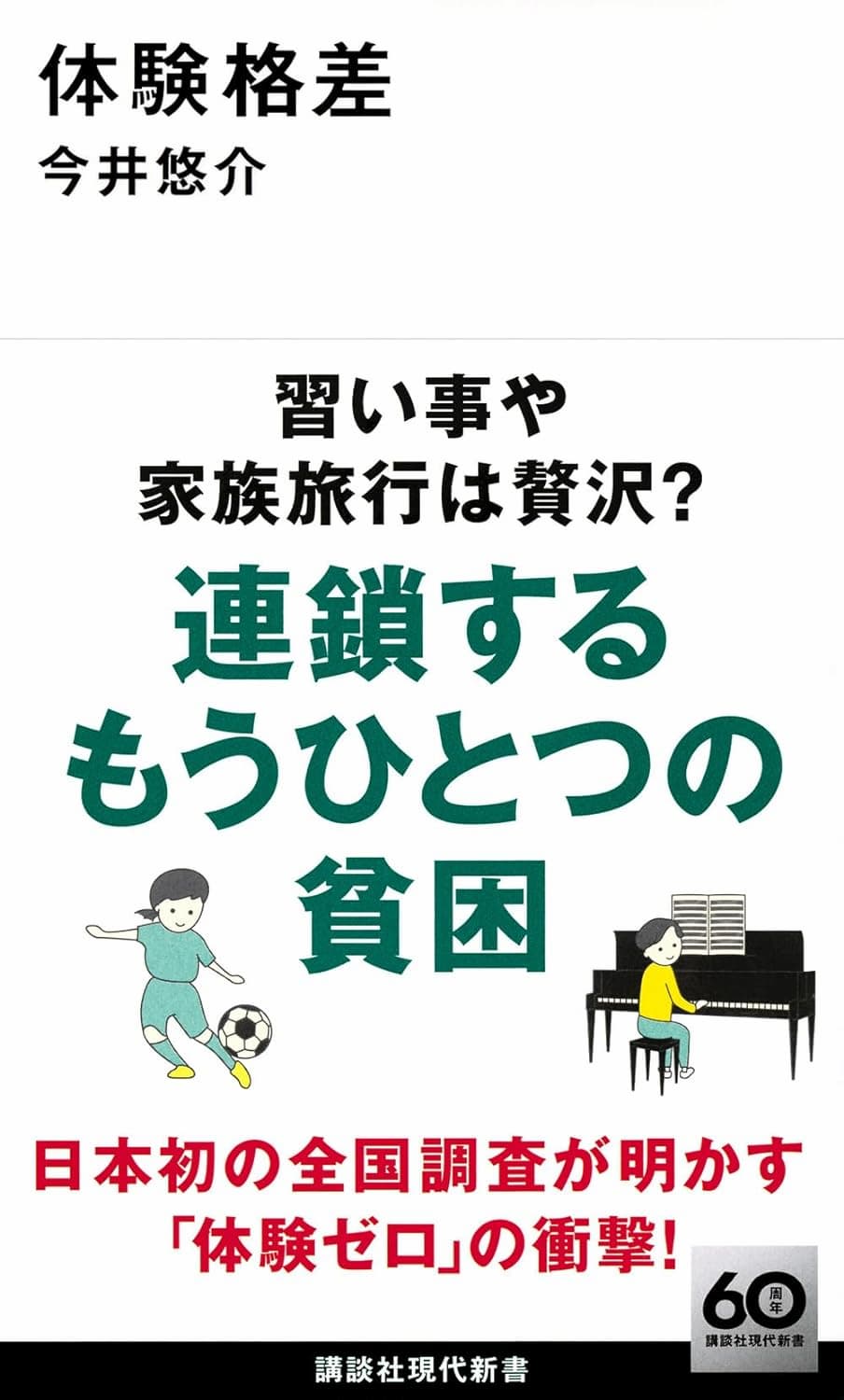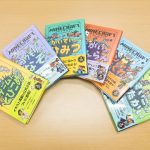体験は必需品? 日本の子ども達が直面する「体験格差」とは

習い事や旅行、レジャーなど、子どもには様々な体験をさせてあげたいもの。しかし、これらの体験は「できればさせてあげたいもの」であって、子どもにとっての「必需品」と考える人は少ないのではないでしょうか。
しかし、イギリスではこのようなレジャー活動を、「子どもたちにとって必要なもの」だと考える大人が大多数なのだそう。
そんな日本社会の価値観の中で、子どもたちが直面しているのが「体験格差」。
この問題に向き合うのが、チャンス・フォー・チルドレンの今井悠介さんです。
今回は、今井さんの著書から一部を抜粋し、私たちが今、目を向けるべき現状をお伝えします。
※本稿は今井悠介著『体験格差』(講談社)から一部抜粋・編集したものです。
「サッカーがしたい」と泣いたシングルマザーの息子

昨年の夏、あるシングルマザーの方から、こんなお話を聞いた。
息子が突然正座になって、泣きながら「サッカーがしたいです」と言ったんです。
それは、まだ小学生の一人息子が、幼いなりに自分の家庭の状況を理解し、ようやく口にできた願いだった。たった一人で悩んだ末、正座をして、涙を流しながら。私が本書で考えたい「体験格差」というテーマが、この場面に凝縮しているように思える。
私たちが暮らす日本社会には、様々なスポーツや文化的な活動、休日の旅行や楽しいアクティビティなど、子どもの成長に大きな影響を与え得る多種多様な「体験」を、「したいと思えば自由にできる(させてもらえる)子どもたち」と、「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」がいる。そこには明らかに大きな「格差」がある。
その格差は、直接的には「生まれ」に、特に親の経済的な状況に関係している。年齢を重ねるにつれ、大人に近づくにつれ、低所得家庭の子どもたちは、してみたいと思ったこと、やってみたいと思ったことを、そのまままっすぐには言えなくなっていく。
私たちは、数多くの子どもたちが直面してきたこうした「体験」の格差について、どれほど真剣に考えてきただろうか。「サッカーがしたいです」と声をしぼり出す子どもたちの姿を、どれくらい想像し、理解し、対策を考え、実行してきただろうか。
子どもの必需品とは何か

社会政策学者の阿部彩氏は、2008年の著書『子どもの貧困』の中で、日本の一般市民においては、イギリスやオーストラリアといったほかの社会に比べて、「子どもが最低限にこれだけは享受するべきであるという生活の期待値が低い」と述べている。
阿部氏が紹介するイギリスの調査では、「趣味やレジャー活動」(90%)、「水泳(1ヵ月に1回)」(78%)、「1週間以上の旅行(1年に1回)」(71%)など、子どもたちの様々な「体験」に関わる項目について、大多数の大人が、子どもたちにとって必要なものであると回答している。
その一方、阿部氏自身が2015年に日本の大人を対象に行った調査では、「1年に1回の家族旅行(最低1泊)」(30.5%)や「スポーツ・チーム(野球、サッカー等)や音楽活動への参加」(20.0%)などの項目について、必要であり、すべての子どもが持つことができるべきであるとする回答が、相対的にかなり低い割合にとどまっていた。
ここからわかるのは、子どもにとって何が「必需品」であるのか? という問い、つまり、「たまたま恵まれた家庭に生まれた一部の子ども」だけではなく、「その社会に生まれたすべての子ども」が享受できて然るべきものは何か? という問いに対する答えや考え方が、それぞれの社会によってかなり違うということだ。ある社会にとっての当たり前が、別の社会にとっても同じであるわけではない。
私たち、日本社会で生きる大人たちの多くは、子どもたちにとっての「体験」の機会を、いまだ「必需品」だとは見なしていないのだろう。阿部氏の調査では、泊まりの旅行、スポーツ、音楽活動への参加などについて、「あったほうがよいが、持てなくても、いたしかたがない」、「必要ではない」という回答が大多数を占めている。
もちろん日本でも、自分自身の子どもに対して様々な「体験」を与えたいと願い、実際にその機会を与える親は数多く存在する。だが、それがあくまで個々の家庭ごとの話にとどまっている限り、裕福な家庭に生まれた子どもたちはともかく、低所得家庭の子どもたち、あるいはその他のハンディキャップを抱えている家庭の子どもたちは、誰からのサポートも得られずに置き去りにされるだろう。そして、実際に置き去りにされてきたのだ。
重要な分岐点は、この社会で生きる大人たちが、「私の子ども」だけではなく、「すべての子ども」に対して、「体験」の機会を届けようとするかどうかにある。「体験格差」をなくそうという意思を、社会全体として持つかどうかにある。
そもそも、日本社会が「子どもの貧困」という課題に向き合い始めたこと自体、それほど昔の話ではない。「子どもの貧困対策法」が施行されたのは、ようやく2014年になってからのことだ。そこから今年(※2024年時点)でちょうど10年が経つが、社会の課題認識という意味でも、必要な対策が十分に立てられているかという意味でも、まだまだ道なかばだろう。
その中でも、「体験格差」への関心や取り組みは、特に不十分だと言える。
見過ごされてきた「体験格差」

東日本大震災を契機に、私は当時勤めていた会社を辞め、学生時代の仲間とともに、被災した子どもたちの支援に取り組み始めた。宮城県の仙台で事務所を立ち上げ、子どもたちが直面する現実と向き合い始めた。2011年6月のことだ。
「チャンス・フォー・チルドレン」という私たちの団体名には、「たまたま生まれ育った環境によって、子どもたちが得られる人生の機会に格差があってはいけない」という思いが込められている。
私たちは、主に寄付金を原資とする「スタディクーポン」という仕組みをつくり、これまで日本中の様々な地域で、低所得家庭の子どもたちに対する学校外教育費用の支援をしてきた。過去に支給したクーポンの総額は13億円を超え、さらに一部の自治体には私たちの取り組みが波及して、公的な資金を用いた同様の支援もなされ始めている。
たまたま被災したから、たまたま低所得の家庭に生まれたから。そうでない子どもと違って、十分に勉強する機会が得られない、通いたい学習塾に通えない、あるいは進学したい学校を目指せない。そういう子どもたちとたくさん出会ってきた。
私たちの10年を超える活動を通じて、そのうちの幾分かの子どもたちには、「スタディクーポン」を届けることができたかもしれない。また、子どもたちの「学習」には大きな機会格差があり、それを社会的に埋める必要があるという認識も、少しずつ広がりを持ってきたように思える。
だが、だからこそ、同じ「子どもの貧困」という問題の中でも、「体験」の格差や貧困が(例えば「食事」や「学習」の格差や貧困に比べて)後回しになっている状況について、そして自分たち自身もその問題に気づいていながらなかなか真正面から取り組めずにいることについて、何かしなければとずっと感じていた。
子どもたちにとって、「食事」や「学習」はもちろん重要だ。同時に、それら以外の場面で生じている格差についても、見過ごすことはできない。私たちは子どもたちの「体験格差」をも直視し、その解消に向けた取り組みを始める必要がある。
『体験格差』(今井悠介著/講談社)
習い事や家族旅行は贅沢?
子どもたちから何が奪われているのか?
この社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態とは?
日本初の全国調査が明かす「体験ゼロ」の衝撃!