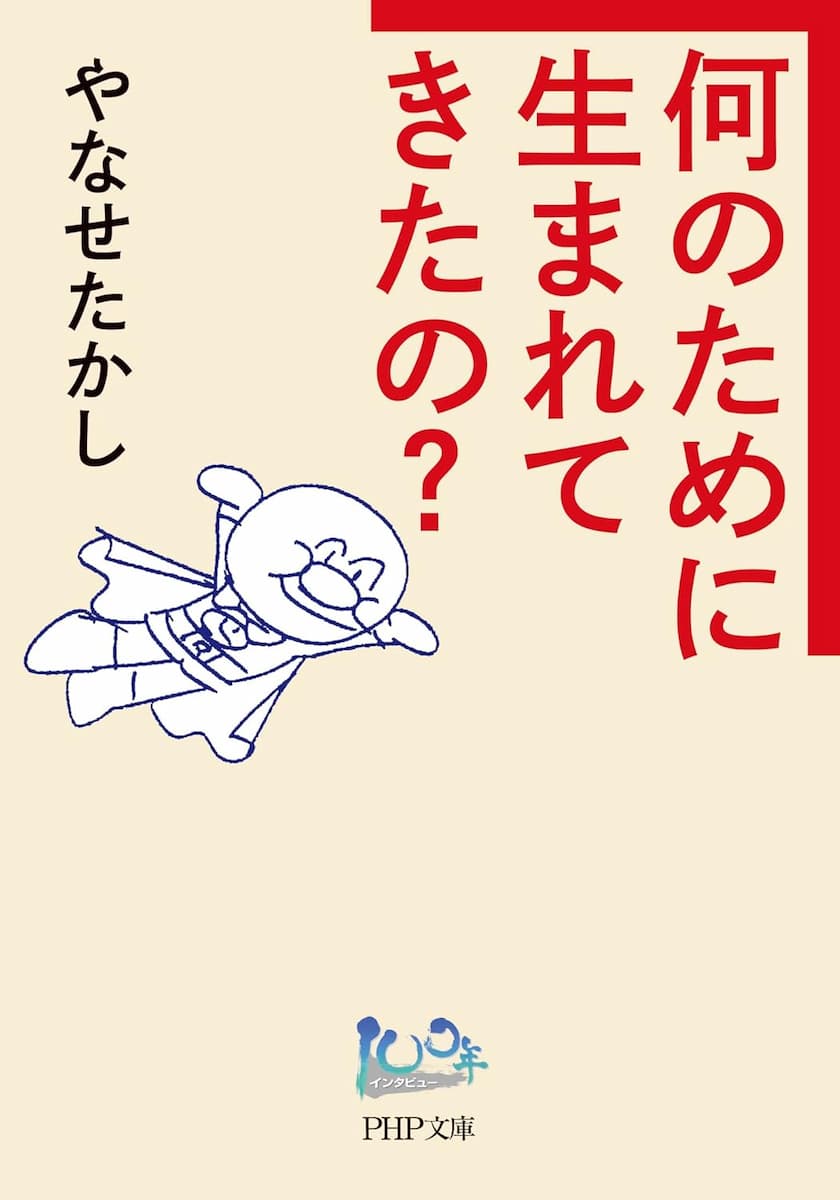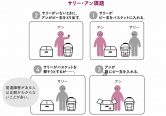アンパンマンマーチが「哲学的」なのはなぜ? やなせたかしが明かす“子ども向けにしなかった”理由

「なんのために生まれて、何をして生きるのか」──子ども向けとは思えないとしばしば話題になる、アンパンマンの主題歌。
作者のやなせたかしさんは、物語や歌を作る際に「子ども向け」「大人向け」といった区別をしたことはないそうです。その理由とは?
やなせさん自身が語った、アンパンマンの創作哲学をご紹介します。
※本稿は、やなせたかし著 『何のために生まれてきたの?』(PHP研究所)から一部抜粋・編集したものです。
子どもこそ理解者だった
――アンパンマンは自分の顔を食べさせますよね。この発想はどこからきたんですか。
アンパンマンも、自分が傷つくということですね。相手を助けるということを、ごく単純に、シンボリックにやっているわけで。他のヒーローと違い、いつも傷つく。バイキンマンに押しつぶされたり、ジャムおじさんに、「助けて」と弱音を吐いたり。で、顔をつくり直してもらうと、元気に飛び立っていく。苦しくても、傷ついても、ヒーローは人を助けるために飛び立つんです。
あんまり難しいことを言おうとしているわけじゃないんです。ただそういうことを物語の中に、自分が気分として入れているだけなんですけど、それを受け止めたのが、幼い子どもだったんだね。いやあ、これには驚きますね。けっして大人ではなかった。評論家には全部けなされて。ところが、幼い子どもには文句なしに受けてしまったから。
――絵本『あんぱんまん』は当初、大人向けに描かれたというふうに伺いましたけれど。
ええ、大人に向けて。それで最初のアンパンマンは”人間”でした。世界中の飢えた子に、あんパンを届けるちょっと太ったヒーロー。最後は許可なく国境を越えたため撃ち落とされてしまうという物語で。誰にも理解されませんでした。
「やなせさんね、こんな馬鹿馬鹿しいものを描いても、読者には喜ばれません。もうちょっとショッキングなもの、そういうものでないと。こんな、自分の顔を食べさせてやっていくような生ぬるい話では……」と、出版社の人に言われたんですよ。僕も、その通りだと思いましたけど。
でも、受けないだろうけど、僕はこの話は描き続けるって言ったんです。ところが、大人の考えとは別に、子どもには受けてしまって。
いま、大学生や社会人になっている人が「幼稚園の頃にアンパンマンを読んでました」と言うので、どこが面白かったかを聞くと「アンパンマンが自分の顔をあげるところです。すごいショックを受けて、それがずっと心に残っていて、非常にひきつけられました」って、ほとんどの人はそう言ってくれます。
当時、「顔を削るのはやめてください。残酷です」という抗議をもらいましてね。「あんパンが食べられなかったら、それはまずいパンです。あんパンが食べられることは当然のことです、少しも残酷なことではありません」と、すぐに手紙を書いて出しました。いまはそういうことを言う人はいませんけど、始めの頃はそういう反応でした。
――アンパンマンの元祖となる絵本の登場は、やなせさんが54歳の時。やがてシリーズ化され、テレビでアニメが放映されたのは69歳の時だったそうですね。
最初の絵本を描いてから、ずっと後のことです。
ある日、テレビのディレクターが自分の子どもが通う幼稚園に行ったら、一冊の本がボロボロになっている。気になったので「なぜ、この本だけボロボロになっているんですか?」と先生に聞くと、この本ばっかり子どもたちが読むので、いくら買い替えてもすぐボロボロになってしまうと。で、その本を見たら『あんぱんまん』だったというわけです。まあ、これが放映されるひとつのきっかけにもなったと。
僕は大人向けの詩集や本を書く作家だったんですけど、不思議なことに、いつのまにやら子どもに向けた本ばかり描くようになってしまって。これには自分がびっくりで。『あんぱんまん』を描いたために、僕は児童書の出版社の仕事をするようになったんですね。「児童書の仕事はできないぜ」と言っていたんですけど、仕方なく児童書のほうに入っていったんです。
ところが、この児童書というのが大変なんですよ。幼い子どもは、気に入る作品と気に入らない作品を、ハッキリと分ける。気に入らない場合はバーッと捨てる。ところが気に入った作品は、何度も何度も繰り返して読む。そういう現象があるんですね。
それと児童書の仕事をするようになってわかったことは、幼児向けの作品は、幼児用だというのでグレードをうんと落とそう、というふうに考えるんですね。そうして文章も非常に短くする。僕もそれを要求されたけど、それは違うんです。不思議なことに、幼児というのは話のホントの部分がなぜかわかってしまう。難しいことばとか、そういうこととは無関係なんです。
僕は物語をつくる時も、歌をつくる時も、子ども向け、大人向けとかを区別したことはなくて。子どもも大人も、一緒に感動しなくちゃいけないと思っているから。だから歌詞が子ども向けにしては難しいと指摘されるのかもしれません。
例えば、アンパンマンのテーマソングの歌詞は「なんのために生まれて なにをして生きるのか」というものなんですが、これは幼稚園で歌うような歌詞じゃないんですよ。だから難しいと指摘されることもありますが、幼稚園の子どもは平気で歌っている。
面白い話があるんですよ。ある哲学者が、孫と一緒に新幹線に乗って、向こう側の席に4歳の孫が、おじいちゃんはこっち側に座った。それでおじいちゃんがじっと本を読んでいると、孫が退屈だからいつのまにか歌を歌い始めた。「なんのために生まれて なにをして生きるのか」と歌うと、哲学者であるおじいちゃんは「何なんだ、これは!」と驚いた。4歳の子どもがこんなことを歌っているのは、いったいどういうことだと。うちへ帰って調べてみたら、それは『それいけ! アンパンマン』というテレビ番組のテーマソングだったということがわかった。それで、非常にびっくりしましたという手紙を、私にくださったんですよ。
おじいちゃんはびっくりしたんだけど、子どもはなんの苦もなく歌っているんですねえ、永遠の命題を。
「なんのために生まれてきたか」って、わからないまま人生を終えるのは残念ですね。この歌を子どもの頃からずっと歌っていると、考えることが自然と身に付くような気がするんだ。もっとも僕にそれがわかったのは、60歳を過ぎてからのことで、ずいぶん遅いんですがね。
『何のために生まれてきたの?』(やなせたかし著 /PHP研究所)
25年春スタートのNHK連続テレビ小説「あんぱん」のモデル!
脚本家・中園ミホさん(「あんぱん」作者)、推薦!
「69歳でアンパンマンが大ヒット。愛と勇気にみちた生き方が素敵です!」
本書は、大反響を呼んだNHK「100年インタビュー」のやなせたかし氏の回を書籍化。
苦しい時もユーモアと好奇心を忘れなかった著者が、半生を振り返りつつ前向きに生きる秘訣を語ります。波瀾の人生を乗り越えて綴った、痛快人生論。
読むだけで元気が出る1冊です。